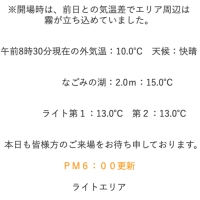まずTV
画面の巨大化と高精細化の両立にメドが立ったようだ。つまり数年後には100inch 8K/4Kが可能になる。
これがどういう状況かというと・・・。
100inch=2.54m対角の長方形。画像規格から横/縦が16/9となるため、
iPhone 5s Ratinaの仕様は
Ratinaまであと4倍。
100inchで32k/16kになるとRatina TVとなる。
(これが必要かどうかは置いといて)写真並みの表示になる。
そうなると、もはや情報の窓ではない。
TVのコンテンツは大きく変わる。顔のアップなんかつかえない。
32inchで顔のアップを100 inchでやると・・・
例を示そう。

多分、少女時代と思うがフリー素材からピックアップ。たくさんいるからちょうどいい。
100inchで横幅2.2m,縦1.2mの窓にみなさんが並んで映っていると言う感じだ。

この解像度のまま、32inchで一部を表示する。
このように真ん中の3人だけを映しだすことが出来る。
今迄のTVは基本的にこういう写し方だ。
多分、違和感無くアップになったという感じだろう。
これをそのまま100inchにすると下の様になる。

PCの画面でみているから拡大されただけと思うだろうが、100inch(横幅2.2m、高さ1.2m)で表示されているわけだから、右端の女性の顔は幅30cm、高さ42cmの楕円の大きさとなる。
そう、本来よりもドアップで虫眼鏡で見ている世界になる訳だ。
スクリーンサイズと見やすい距離があるというが、100inchだと2.5mから3.0mらしい。
6畳間だと長軸が3.6m短軸が2.7mだから6畳間の長い壁を背中に見る100inchのTVを見るといい感じだろ。
そうすると、始めの100inchで紹介した画面でも臨場感が溢れる。32inchの窓から見ている感覚が無くなる。
だが、32inchの画像を拡大すると(下の3人だけの画像)でかすぎて鬱陶しくなるとおもう。
臨場感は溢れるが、強調され過ぎかもしれない。
バラエティ番組でもニュースでもそうだが、少々遠い目からパンするというか、そういう風に全体像を映像として配信することになると思う。アナウンサーの顔のドアップは不要。
今はコンテンツがその辺をまだ考えていない様なので、これから写し方撮り方が大きく変わるんだろうと思う。
ビデオファインダーで覗く世界では無くなる。
次に、大画面TVでできる技を考えた。
マルチチャンネルビュー。

メイン画面が高野山の大塔とする。左に半透明で見えているのが他のチャンネル。
上から鹿と子供、簡易SL、明石大橋、どこかのショー、女性、食べ物(焼肉)、欧州の街、飛行機。
6-7inch程度の画面で横にアイコン風に表示しているわけだ。
あくまでも一例。
次にメカトロニクス
これはデッドコピーしにくいというかしても当初の性能が出ない。
なぜここにこの板バネがあるのか?このバネを止めているねじの締め付けトルクは?そしてなぜトルク管理が必要なのだ?
この辺のノウハウは設計思想に取り込まれている。
メカトロニクスってあるの?と思うだろうが、洗濯機、空気清浄機、掃除機、複写機、プリンター、ミラー付きデジカメ...これらがメカトロニクスだ。比較的古くて、回転速度が小さいものは代替が進み易いが、高速回転を担うものや、極薄ものを扱う機器は職人の技が生きている。
これはデジタル技術ではカバーできない。
デジタル技術は何と言っても補正技術。CDから始まった。上のTVなんかまさにそういうもので、稼動部が無いから、メモリーにどういう風に情報を配置するかという考えになる。ミスったら次のタイミングでピックアップすればいい。
アナログ技術はそうはならない。回転軸のぶれが生じるとそれは本体のぶれや騒音、引いては自己故障となる。
それをどう防ぐかが、アナログ技術者の強みである。
この辺、経験がかなりモノを言う。廃れてしまったビデオデッキなんかメカトロニクスの塊りだったと思う。
日本が、腕時計のスイスの様に高付加価値で行くためにはメカトロニクスの充実が鍵となる。
自動巻100万円⇒クォーツ機械式10万円⇒クォーツデジタル1万円という大まかな価格帯を考えると、
クォーツ機械式と自動巻が狙い所なんだろうね。
いうれ騙しが聞かないところだから、デザインセンスが鍵になる。
そのためには経営/デザイン/技術が「本物」に触れる必要がある。そうでないと笑い物しか作れない。
画面の巨大化と高精細化の両立にメドが立ったようだ。つまり数年後には100inch 8K/4Kが可能になる。
これがどういう状況かというと・・・。
100inch=2.54m対角の長方形。画像規格から横/縦が16/9となるため、
縦1.2m、横2.2m
となる。8Kということは2.2m (=2,200mm)に8,000個の画素(pixel)があるということ。0.275mm/pixelとなる。92pixel/inch (=ppi)になる。
スマホの解像度は・・・iPhone 5s Ratinaの仕様は
1,136*640 pixels, 4inch, 89mm*50mm,
89mm/1136pixel= 0.078mm/pixel =326ppi
89mm/1136pixel= 0.078mm/pixel =326ppi
Ratinaまであと4倍。
100inchで32k/16kになるとRatina TVとなる。
(これが必要かどうかは置いといて)写真並みの表示になる。
そうなると、もはや情報の窓ではない。
TVのコンテンツは大きく変わる。顔のアップなんかつかえない。
32inchで顔のアップを100 inchでやると・・・
例を示そう。

多分、少女時代と思うがフリー素材からピックアップ。たくさんいるからちょうどいい。
100inchで横幅2.2m,縦1.2mの窓にみなさんが並んで映っていると言う感じだ。

この解像度のまま、32inchで一部を表示する。
このように真ん中の3人だけを映しだすことが出来る。
今迄のTVは基本的にこういう写し方だ。
多分、違和感無くアップになったという感じだろう。
これをそのまま100inchにすると下の様になる。

PCの画面でみているから拡大されただけと思うだろうが、100inch(横幅2.2m、高さ1.2m)で表示されているわけだから、右端の女性の顔は幅30cm、高さ42cmの楕円の大きさとなる。
そう、本来よりもドアップで虫眼鏡で見ている世界になる訳だ。
スクリーンサイズと見やすい距離があるというが、100inchだと2.5mから3.0mらしい。
6畳間だと長軸が3.6m短軸が2.7mだから6畳間の長い壁を背中に見る100inchのTVを見るといい感じだろ。
そうすると、始めの100inchで紹介した画面でも臨場感が溢れる。32inchの窓から見ている感覚が無くなる。
だが、32inchの画像を拡大すると(下の3人だけの画像)でかすぎて鬱陶しくなるとおもう。
臨場感は溢れるが、強調され過ぎかもしれない。
バラエティ番組でもニュースでもそうだが、少々遠い目からパンするというか、そういう風に全体像を映像として配信することになると思う。アナウンサーの顔のドアップは不要。
今はコンテンツがその辺をまだ考えていない様なので、これから写し方撮り方が大きく変わるんだろうと思う。
ビデオファインダーで覗く世界では無くなる。
次に、大画面TVでできる技を考えた。
マルチチャンネルビュー。

メイン画面が高野山の大塔とする。左に半透明で見えているのが他のチャンネル。
上から鹿と子供、簡易SL、明石大橋、どこかのショー、女性、食べ物(焼肉)、欧州の街、飛行機。
6-7inch程度の画面で横にアイコン風に表示しているわけだ。
デジタルチューナーの切替速度を0.1msで出来たとする。画面のリフレッシュレートを仮に500Hzとする。これは1/500秒=2ms毎に画面が切り替わる事を意味する。
0.0-0.1ms (main Channel) 大塔
0.1-0.2ms (change)
0.2-0.3ms (Sub Channel A) 鹿と子供
0.3-0.4ms (change)
0.4-0.5ms (Sub Channel B) 簡易SL
...
0.8-0.9ms (Sub Channel D) どこかのショー
...
1.8-1.9ms (Sub Channel i) 空欄
1.9-2.0ms (change)
2.0-2.1ms (main Channel)
という風に各チャンネルの画面情報を時分割してメモリーに取り込む事が可能だ。
そしてその情報を合成してモニターに供給する。そうするとマルチチャンネル表示が可能となる。
メモリー節約のため、マルチチャンネル表示でサブ画面の取り込み周期は長くても言いだろう。
これによって、メイン画面の横で裏番組を確認できる。
半透明にするのではなく、横から(あるいうは下からWindowsのバーの様に)出てきてもいい。
100inch画面を94inchに縮小して外郭を6inchパネルで埋め尽くすのもよいだろう。
これはチャンネル変更のインターフェイスを換えるものだ。
リモコンは少なくともWiiのリモコン並の反応があって、矢印でも◎でもいいが、レーザーポインターで選択している様に画面にマウスのポインタ見たいに選択できる。
ここで明石大橋の画面が大きくなっているのは、ポインタで選択された映像を少し大きく表示する事で、OS Xのジーニアスアクションを彷彿させる。いずれにせよ今の使いにくいリモコンを簡単にする。
いずれにせよ、メニュー選択とリモコンの考え方を根本的に換えないとあかんだろうね。IR送受信がいいのか、青歯にするのか、Wifiにするのかは判らんが。
0.0-0.1ms (main Channel) 大塔
0.1-0.2ms (change)
0.2-0.3ms (Sub Channel A) 鹿と子供
0.3-0.4ms (change)
0.4-0.5ms (Sub Channel B) 簡易SL
...
0.8-0.9ms (Sub Channel D) どこかのショー
...
1.8-1.9ms (Sub Channel i) 空欄
1.9-2.0ms (change)
2.0-2.1ms (main Channel)
という風に各チャンネルの画面情報を時分割してメモリーに取り込む事が可能だ。
そしてその情報を合成してモニターに供給する。そうするとマルチチャンネル表示が可能となる。
メモリー節約のため、マルチチャンネル表示でサブ画面の取り込み周期は長くても言いだろう。
これによって、メイン画面の横で裏番組を確認できる。
半透明にするのではなく、横から(あるいうは下からWindowsのバーの様に)出てきてもいい。
100inch画面を94inchに縮小して外郭を6inchパネルで埋め尽くすのもよいだろう。
これはチャンネル変更のインターフェイスを換えるものだ。
リモコンは少なくともWiiのリモコン並の反応があって、矢印でも◎でもいいが、レーザーポインターで選択している様に画面にマウスのポインタ見たいに選択できる。
ここで明石大橋の画面が大きくなっているのは、ポインタで選択された映像を少し大きく表示する事で、OS Xのジーニアスアクションを彷彿させる。いずれにせよ今の使いにくいリモコンを簡単にする。
On/Off, 音量、10キー、選択(OK)ボタンのみ
10キーを押すと画面に半透明で表示してくれたらいい。
スマホやタブレットと連携するとなおいいが。
10キーを押すと画面に半透明で表示してくれたらいい。
スマホやタブレットと連携するとなおいいが。
いずれにせよ、メニュー選択とリモコンの考え方を根本的に換えないとあかんだろうね。IR送受信がいいのか、青歯にするのか、Wifiにするのかは判らんが。
あくまでも一例。
次にメカトロニクス
これはデッドコピーしにくいというかしても当初の性能が出ない。
なぜここにこの板バネがあるのか?このバネを止めているねじの締め付けトルクは?そしてなぜトルク管理が必要なのだ?
この辺のノウハウは設計思想に取り込まれている。
メカトロニクスってあるの?と思うだろうが、洗濯機、空気清浄機、掃除機、複写機、プリンター、ミラー付きデジカメ...これらがメカトロニクスだ。比較的古くて、回転速度が小さいものは代替が進み易いが、高速回転を担うものや、極薄ものを扱う機器は職人の技が生きている。
これはデジタル技術ではカバーできない。
デジタル技術は何と言っても補正技術。CDから始まった。上のTVなんかまさにそういうもので、稼動部が無いから、メモリーにどういう風に情報を配置するかという考えになる。ミスったら次のタイミングでピックアップすればいい。
アナログ技術はそうはならない。回転軸のぶれが生じるとそれは本体のぶれや騒音、引いては自己故障となる。
それをどう防ぐかが、アナログ技術者の強みである。
この辺、経験がかなりモノを言う。廃れてしまったビデオデッキなんかメカトロニクスの塊りだったと思う。
日本が、腕時計のスイスの様に高付加価値で行くためにはメカトロニクスの充実が鍵となる。
自動巻100万円⇒クォーツ機械式10万円⇒クォーツデジタル1万円という大まかな価格帯を考えると、
クォーツ機械式と自動巻が狙い所なんだろうね。
いうれ騙しが聞かないところだから、デザインセンスが鍵になる。
そのためには経営/デザイン/技術が「本物」に触れる必要がある。そうでないと笑い物しか作れない。