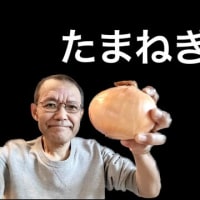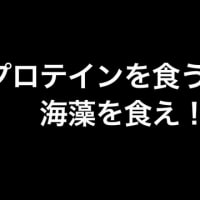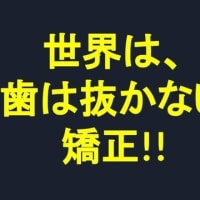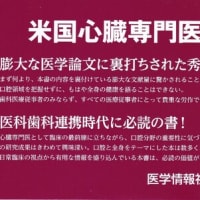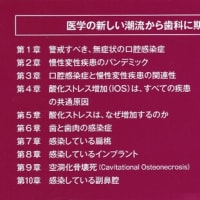キシリトールは、多くの果物や野菜にも含まれる甘味炭水化物の一種です。
キシリトールは、多くの果物や野菜にも含まれる甘味炭水化物の一種です。 安全性について
安全性について1983年国連食料農業機関(FAO)と世界保健機構(WHO)の食品添加物専門家共同委員会(JECFA)で
「キシリトールは、1日の許容摂取量を特定しない」と評価しています。これは、キシリトールは、最も安全な食品のカテゴリーに含まれ、キシリトールについては、中毒的研究を行う必要が無い事を意味しています。もちろん、日本の厚生省もキシリトールの使用を許可しています。
 虫歯予防とキシリトール
虫歯予防とキシリトール人の歯垢(プラーク)中では、発酵されず乳酸や多糖類を産成しない(歯を溶かさない、細菌の餌を作らない)
除去が容易な歯垢(プラーク)ができる
歯垢(プラーク)の量が減少
虫歯菌(S.mutans)の付着減少
虫歯菌の数の減少
などの働きがあります
 ミュータンスコントロール
ミュータンスコントロール虫歯の原因菌であるミュータンス菌の感染を防ぎ、たとえ感染してもミュータンス菌の質の改善と数の減少により虫歯発生を抑制する事をいう。
 キシリトールとミュータンスコントロール
キシリトールとミュータンスコントロールキシリトール摂取期間による影響
1)短期摂取ではミュータンス菌の数の抑制
2)長期摂取(1日3回3ヶ月以上)ではミュータンス菌の質が変化し、虫歯発生しにくいミュータンス菌の増加となる。よって、虫歯発生が抑制される。
 母子感染予防とキシリトール
母子感染予防とキシリトール虫歯菌は、主として母親から子供へ感染することから母子感染と呼ばれている。(母親が子供と同じスプーンなど使用するため)
最近の研究では,母親へのキシリトール摂取が母子感染の予防に有効であると報告している。つまり、母親がキシリトールを摂取する事で子供への虫歯菌感染を防いでいる。
 キシリトールの商品
キシリトールの商品キシリトールの割合が、100%が理想。現状では,50%以上含有するものを勧めます。
 キシリトールの使用法とその効果
キシリトールの使用法とその効果1日3回100%キシリトールガムを摂取して歯垢(プラーク)が減るのは、1~2週間です。さらに、3ヶ月間摂取すると虫歯になりにくい状態になります。その後3ヶ月くらい摂取を止めても効果は持続するようです。ただし、キシリトールを使った虫歯予防法は追加型と呼ばれ、現状の虫歯予防法(歯ブラシ、フッ化物、正しい食生活、歯科定期検診など)に代わるものではないことを、理解しておいてください。
 参考文献
参考文献鈴木 章:キシリトールの意義と価値,歯科衛生士、VOL.24、7、46~53、2000
鈴木 章:キシリトールと歯科臨床、日本歯科医師会誌、VOL.50 No.8 712~722