「言いたくねぇけど ばいばい」
そんなアオリ文句。
2002年1月期のドラマだった「木更津キャッツアイ」。
2003年の今頃の時期に公開されたその続編映画「木更津キャッツアイ日本シリーズ」。
ドラマのラストにも一度、ぶっさんは死んだ(かのように見えた)。この時は死ななかったわけだけれど。
「日本シリーズ」のラストには、淡々とぶっさんが遂に本当に死を迎えたということが『報告』された。
ぶっさんは、2003年に死んだのだ。最初に余命半年と宣告されながらしぶとく生きていたけれど、ぶっさんは死んだのだ。
だから、「ワールドシリーズ」をやると聞いた時、最初に思ったのは…
「何で今更?ぶっさんは本当に死んだんでしょ?」
ということだった。
ここ数年、時折見かける「奇跡もの」の感動ストーリー。
亡くなった人が期間限定であるいは霊として戻ってきたり、何かに姿を変えて残された人に思いを伝えるために留まったり……。
私は実はこういう系統の物語を見るのはあまり好きではなくて。
いや、正確にいうと「好きじゃない」わけじゃないのだ。
ただ、最近のように「今はこういうのが流行り」みたいに濫立されると、「大事な人と永遠に別れてしまう悲しみ」軽く扱われ安売りされてる気がして。
「いくらキャッツでも」そんな風にされてしまったら嫌だったから、どんな話になるのか不安だった。
だって、宮藤官九郎の書いた「木更津キャッツアイ」は、どんなに荒唐無稽でバカバカしくて笑わせる中にも、ぶっさんが目前に見ている「死」だけは真摯に描いていたと思うから。
クドカンだから大丈夫だろうと思う気持ちと不安とがあった。
「日本シリーズ」が荒唐無稽に過ぎる感じがしたから余計に不安が大きかったのかもしれない。
そして、見て、思ったこと。
「何故今更」じゃなかった。
3年経った今だからこそ、意味のある話だったのだと思う。
───永遠に別れなければならない人に、きちんと「ばいばい」が言えますか?
木更津キャッツアイ ワールドシリーズ
【以下ネタバレ。もう終わりかけですがネタバレを嫌う人はここで引き返しましょう】
「フィールド・オブ・ドリームス」という映画を見た人は多いだろう。
実は、私はこの映画は見ていない。
どういう物語か、というのはあらすじ程度には知っているけれど、これを見ておけば良かったと初めて思った。
つまるところ、「木更津キャッツアイ・ワールドシリーズ」は乱暴に言ってしまえば「フィールド・オブ・ドリームス」のパロディと言っていいだろう。
こういう時にはパロディのネタ元を知っていた方が確実に面白い。
仕方ないので、後日ネタ元映画を見て逆パロディとしても楽しむことにするか。
ぶっさんが死んで3年。
木更津で公務員になったバンビ。
東京でIT関連の仕事をしてる?(←怪しい)アニ。
大阪でたこ焼きを売ってるマスター。
何故か自衛隊に入ってしまったうっちー(!)
何故か市長選に出馬している美礼先生。
何故か猫田と結婚することになってるモー子(!!)
千葉ロッテマリーンズのエースになっているらしい(!!!)アニの弟・純くんww(←出番は無い)
それぞれに、それぞれの3年が経っている。
もちろんスクリーンのこちら側にいる私たちにも、同じ年月が流れた。
開発予定地の広大な空き地で、バンビが不思議な声を聞いたところから物語は転がり始める。
すっかりばらばらになってしまった仲間たちを集めようと奔走するバンビ。
その度にぶっさんの思い出話になる。
そして、多分全員が漠然と感じていたことが形になっていく。
「俺たち、ぶっさんにちゃんと『ばいばい』言ってねえじゃん」
テレビシリーズでも「日本シリーズ」でも、ぶっさんが『死んだ?』と思わせる場面が出てきてはその度に皆で号泣して、でもぶっさんは死ななくて。
実際に病気の進行とともに衰えてゆくぶっさんを見ていられなくて、少しずつ足が遠のいて………
本当にぶっさんがいってしまった時、4人は泣くことも出来なかった。
それから3年、その間に一度は「俺たちはぶっさんがいなきゃ何も出来ないのか?」と一念発起、キャッツアイ復活を図ったこともあったけど大失敗。それがもとでアニとマスターは断絶してしまって、本当にバラバラになってしまった。「ぶっさんがいない」ことに慣れて、それぞれの暮らしをしている4人。
もう、昼間っからビールを飲んで野球して遊びまわってた「コドモ」では無くなってしまった………
「フィールド・オブ・ドリームス」そのままに、
「それを作れば彼はやってくる」
という不思議な声に導かれるまま、どうせ開発されてしまう広大な空き地を切り開き野球場を作るキャッツたち。
間のドタバタをすっ飛ばして言ってしまうと、物語も後半に入ってからぶっさんは
「本当に復活」
してしまう。
「死んだ人が帰ってくる」安易な感動モノは嫌と言いながら、もうこの時点で「ぶっさん」が戻ってきたことにあんまり疑問を持たなくなっている私がいる。キャッツの持つ「なんでもアリ」な空気をすっかり思い出しているからだろう。
だって、50年前の高校野球全米代表選手たちがゾンビとなって出てくるくらいだから、3年前に死んだぶっさんが戻ってくるくらいなんてこたーないのだ。
でも、ぶっさんが戻ってきて、ばらばらになってた仲間たちがまたもとのようにわいわいと集まって、「やっぱ仲間はいいなあ」みたいな話にはならない。
これだけ、「なんでもアリ」なくせして、
これだけ、荒唐無稽でムチャクチャなくせして、
なんでそういうトコだけは、この上なくリアルなんだろう………。
最初はぶっさんが戻ってきてはしゃいでいたキャッツたち。
『木更津キャッツアイ』を復活したり。
野球の試合に臨んだり。
「ぶっさん変わんねーな」
そんな風にぶっさんを見つめる4人。
当然だ。
4人に、そのほかの人たちに、均等に流れた「3年」は、ぶっさんにだけ流れていないのだから。
ぶっさんは、死んだ22歳の時のままなのだから。
土壇場で4-4に追いつき延長戦に突入した試合。
先頭打者は敵の女子野球チームのキャプテンにして主砲の自衛官(うっちーの上司)。
マウンド上に集まって先頭打者を歩かせる相談をする。
「普通ここは敬遠でしょ」
「なに普通のこと言ってんだよ!」
生前は、「普通」がいいよといつも言っていたぶっさんが、あまりにも「普通」な仲間たちにキレる。
だって、俺たちもう25だもん。
ぶっさんみたいにいつまでも22歳じゃいられない。
それでも、生きてかなきゃなんねーんだよ。
俺たち、もう大丈夫だから。
もう合わせてらんねーっつうか。
呼んどいて悪いんだけど、ぶっさんもう帰ってくんね?
「ばいばい」
「ばいばい」
「ばいばい」
「ばいばい」
ぶっさんが寂しそうに微笑む。
やっと言えたじゃん、って顔に書いてある。
それでも、「22歳」のぶっさんが意地を通してど真ん中にミットを構える。それを目掛けて投げるバンビ。
打球は高々と舞い上がった。
オーライオーライと叫びながら打球を追うぶっさん。
それはキャッチャーの守備範囲ではない。
外野の向こうの、ホームランの打球を追ってぶっさんは草むらに消えていった。
そして二度と帰ってこなかった。
その「別れ」は、ぶっさんという仲間を失った悲しみの焼き直しではなく。
ただバカみたいにはしゃいでた楽しい日々に告げる別れ。
期限が来たとかいう受動的に訪れる「二度目の別れ」ではなく、自分たちから「帰ってくれ」と言うことの勇気。
否が応でも流れていく年月。
おとなになる痛み。
後ろを振り返ってあの頃は良かったつまらない大人になってしまったと嘆くことではなく、きちんと前を向いて生きてゆくために。
この物語を、たとえばテレビシリーズの直後、あるいは「日本シリーズ」とさほど間をおかずにただテロップで「3年後」みたいにして出されていたらどうだっただろうとふと思う。
たぶん、この物語を素直に受け止めて、ああ、本当に「ばいばい」なんだ…と思えるためには、スクリーンのこちら側にもバンビたちと同じ年月が流れている必要があったのだ。
だからこそ、時の止まってしまったぶっさんの「取り残された」ような孤独感をも感じることが出来る。
だから、この映画は「今更」じゃなかった。「今」が必要だったんだ。
映画であることに浮かれたように「お祭り」っぽかった「日本シリーズ」とは違って、どこをどう切り取ってもキャッツそのものだった。
だから、バカバカしいし、さりげないシーンに「裏」のためのネタがいっぱい仕込んであるし、目まぐるしいし忙しいし、しょっちゅう大笑い。
謎の韓国映画「釜山死ね死ね団」とか
たこ焼き屋の客が中川家礼二だったとか
実体化する前のぶっさんがあちこちでイタズラしてたりとか
うっちーが自衛隊で矯正されて「普通」の喋り方してるとか
ミー子が色白というだけでロシアンパブに紛れ込んでたりとか
アニが秋葉原の店頭でやってた野球ゲームはマリーンズ対ベイスターズで、ピッチャーは弟・佐々木純だったとか(そして打たれたとか)
ゾンビ選手のフォームは種田っぽかったりとか
ミニミニオジーはオジーとよく似てるとか
何故か下半身がマネキンだったりとか
………なんだけど。
私は途中からちょっとしたことですぐに涙ぐんだりしてたのだった。
たとえば、最初たった3人で作り始めたキャッツスタジアム。気づいたらどんどんみんな集まってきてあっというまに完成するとことか。
たとえば、沈没船のお宝を取りに行くのは無理そうじゃない?という場面でバンビが
「すげーこと言っていい?………野球、やろうよ」
って言った時とか。
あと、最初誰も見物客のいなかった試合に、いつの間にか大勢集まってたりとか。
オジーがホームランを打ったのに消えてしまってホームに帰ってこなかったとか。
悲しい場面じゃないとこでこみ上げてくるっていうのは………トシですか?w
そして。
ぶっさんが消えようとしている時。
父親の公助は、息子が息をひきとった時のことを思い出してた。
ずっとぶっさんは、自分の父親のことを「公助」と名前で呼んでいた。
もう意識が朦朧としていたぶっさんは、小さく呟く。
「おとうさん」
閉じた目から涙が滲んでいる。
「ありがとう」
父親は、優しく微笑んで息子の髪を撫でた。
「公平くん、『普通』だね」
戻ってきたぶっさんの姿を、父親の公助だけが見ることが出来なかった。
きっと「公平」は父親に対して思い残すことがなかったんだろう。
「お父さん」って、呼ぶことができたから。
ちゃんと───「お別れ」が出来ていたから。
これまで、避けるようにぶっさんの本当の死を描かなかったクドカンも、こうやってきちんと「ぶっさんの最期」を描くことで「木更津キャッツアイ」という作品に「ばいばい」を言おうとしているのだろう。
打球を追って草むらに消えたぶっさんを探し草むらの向こうの森にまで行ってみると、ただぶっさんのキャチャーミットだけが遺されていた。
その中にはボール。
「ばいばい」
と一言書かれたボール。
大好きな仲間に、自分から「ばいばい」なんて言いたいわけがない。
でも、言わなくちゃ前に進めない時もある。
遺された者たちが、これからも生きてゆくために。
そんなアオリ文句。
2002年1月期のドラマだった「木更津キャッツアイ」。
2003年の今頃の時期に公開されたその続編映画「木更津キャッツアイ日本シリーズ」。
 | 木更津キャッツアイ 5巻BOXメディアファクトリーこのアイテムの詳細を見る |
 | 木更津キャッツアイ 日本シリーズメディアファクトリーこのアイテムの詳細を見る |
ドラマのラストにも一度、ぶっさんは死んだ(かのように見えた)。この時は死ななかったわけだけれど。
「日本シリーズ」のラストには、淡々とぶっさんが遂に本当に死を迎えたということが『報告』された。
ぶっさんは、2003年に死んだのだ。最初に余命半年と宣告されながらしぶとく生きていたけれど、ぶっさんは死んだのだ。
だから、「ワールドシリーズ」をやると聞いた時、最初に思ったのは…
「何で今更?ぶっさんは本当に死んだんでしょ?」
ということだった。
ここ数年、時折見かける「奇跡もの」の感動ストーリー。
亡くなった人が期間限定であるいは霊として戻ってきたり、何かに姿を変えて残された人に思いを伝えるために留まったり……。
私は実はこういう系統の物語を見るのはあまり好きではなくて。
いや、正確にいうと「好きじゃない」わけじゃないのだ。
ただ、最近のように「今はこういうのが流行り」みたいに濫立されると、「大事な人と永遠に別れてしまう悲しみ」軽く扱われ安売りされてる気がして。
「いくらキャッツでも」そんな風にされてしまったら嫌だったから、どんな話になるのか不安だった。
だって、宮藤官九郎の書いた「木更津キャッツアイ」は、どんなに荒唐無稽でバカバカしくて笑わせる中にも、ぶっさんが目前に見ている「死」だけは真摯に描いていたと思うから。
クドカンだから大丈夫だろうと思う気持ちと不安とがあった。
「日本シリーズ」が荒唐無稽に過ぎる感じがしたから余計に不安が大きかったのかもしれない。
そして、見て、思ったこと。
「何故今更」じゃなかった。
3年経った今だからこそ、意味のある話だったのだと思う。
───永遠に別れなければならない人に、きちんと「ばいばい」が言えますか?
木更津キャッツアイ ワールドシリーズ
【以下ネタバレ。もう終わりかけですがネタバレを嫌う人はここで引き返しましょう】
「フィールド・オブ・ドリームス」という映画を見た人は多いだろう。
 | フィールド・オブ・ドリームス ― コレクターズ・エディションソニー・ピクチャーズエンタテインメントこのアイテムの詳細を見る |
実は、私はこの映画は見ていない。
どういう物語か、というのはあらすじ程度には知っているけれど、これを見ておけば良かったと初めて思った。
つまるところ、「木更津キャッツアイ・ワールドシリーズ」は乱暴に言ってしまえば「フィールド・オブ・ドリームス」のパロディと言っていいだろう。
こういう時にはパロディのネタ元を知っていた方が確実に面白い。
仕方ないので、後日ネタ元映画を見て逆パロディとしても楽しむことにするか。
ぶっさんが死んで3年。
木更津で公務員になったバンビ。
東京でIT関連の仕事をしてる?(←怪しい)アニ。
大阪でたこ焼きを売ってるマスター。
何故か自衛隊に入ってしまったうっちー(!)
何故か市長選に出馬している美礼先生。
何故か猫田と結婚することになってるモー子(!!)
千葉ロッテマリーンズのエースになっているらしい(!!!)アニの弟・純くんww(←出番は無い)
それぞれに、それぞれの3年が経っている。
もちろんスクリーンのこちら側にいる私たちにも、同じ年月が流れた。
開発予定地の広大な空き地で、バンビが不思議な声を聞いたところから物語は転がり始める。
すっかりばらばらになってしまった仲間たちを集めようと奔走するバンビ。
その度にぶっさんの思い出話になる。
そして、多分全員が漠然と感じていたことが形になっていく。
「俺たち、ぶっさんにちゃんと『ばいばい』言ってねえじゃん」
テレビシリーズでも「日本シリーズ」でも、ぶっさんが『死んだ?』と思わせる場面が出てきてはその度に皆で号泣して、でもぶっさんは死ななくて。
実際に病気の進行とともに衰えてゆくぶっさんを見ていられなくて、少しずつ足が遠のいて………
本当にぶっさんがいってしまった時、4人は泣くことも出来なかった。
それから3年、その間に一度は「俺たちはぶっさんがいなきゃ何も出来ないのか?」と一念発起、キャッツアイ復活を図ったこともあったけど大失敗。それがもとでアニとマスターは断絶してしまって、本当にバラバラになってしまった。「ぶっさんがいない」ことに慣れて、それぞれの暮らしをしている4人。
もう、昼間っからビールを飲んで野球して遊びまわってた「コドモ」では無くなってしまった………
「フィールド・オブ・ドリームス」そのままに、
「それを作れば彼はやってくる」
という不思議な声に導かれるまま、どうせ開発されてしまう広大な空き地を切り開き野球場を作るキャッツたち。
間のドタバタをすっ飛ばして言ってしまうと、物語も後半に入ってからぶっさんは
「本当に復活」
してしまう。
「死んだ人が帰ってくる」安易な感動モノは嫌と言いながら、もうこの時点で「ぶっさん」が戻ってきたことにあんまり疑問を持たなくなっている私がいる。キャッツの持つ「なんでもアリ」な空気をすっかり思い出しているからだろう。
だって、50年前の高校野球全米代表選手たちがゾンビとなって出てくるくらいだから、3年前に死んだぶっさんが戻ってくるくらいなんてこたーないのだ。
でも、ぶっさんが戻ってきて、ばらばらになってた仲間たちがまたもとのようにわいわいと集まって、「やっぱ仲間はいいなあ」みたいな話にはならない。
これだけ、「なんでもアリ」なくせして、
これだけ、荒唐無稽でムチャクチャなくせして、
なんでそういうトコだけは、この上なくリアルなんだろう………。
最初はぶっさんが戻ってきてはしゃいでいたキャッツたち。
『木更津キャッツアイ』を復活したり。
野球の試合に臨んだり。
「ぶっさん変わんねーな」
そんな風にぶっさんを見つめる4人。
当然だ。
4人に、そのほかの人たちに、均等に流れた「3年」は、ぶっさんにだけ流れていないのだから。
ぶっさんは、死んだ22歳の時のままなのだから。
土壇場で4-4に追いつき延長戦に突入した試合。
先頭打者は敵の女子野球チームのキャプテンにして主砲の自衛官(うっちーの上司)。
マウンド上に集まって先頭打者を歩かせる相談をする。
「普通ここは敬遠でしょ」
「なに普通のこと言ってんだよ!」
生前は、「普通」がいいよといつも言っていたぶっさんが、あまりにも「普通」な仲間たちにキレる。
だって、俺たちもう25だもん。
ぶっさんみたいにいつまでも22歳じゃいられない。
それでも、生きてかなきゃなんねーんだよ。
俺たち、もう大丈夫だから。
もう合わせてらんねーっつうか。
呼んどいて悪いんだけど、ぶっさんもう帰ってくんね?
「ばいばい」
「ばいばい」
「ばいばい」
「ばいばい」
ぶっさんが寂しそうに微笑む。
やっと言えたじゃん、って顔に書いてある。
それでも、「22歳」のぶっさんが意地を通してど真ん中にミットを構える。それを目掛けて投げるバンビ。
打球は高々と舞い上がった。
オーライオーライと叫びながら打球を追うぶっさん。
それはキャッチャーの守備範囲ではない。
外野の向こうの、ホームランの打球を追ってぶっさんは草むらに消えていった。
そして二度と帰ってこなかった。
その「別れ」は、ぶっさんという仲間を失った悲しみの焼き直しではなく。
ただバカみたいにはしゃいでた楽しい日々に告げる別れ。
期限が来たとかいう受動的に訪れる「二度目の別れ」ではなく、自分たちから「帰ってくれ」と言うことの勇気。
否が応でも流れていく年月。
おとなになる痛み。
後ろを振り返ってあの頃は良かったつまらない大人になってしまったと嘆くことではなく、きちんと前を向いて生きてゆくために。
この物語を、たとえばテレビシリーズの直後、あるいは「日本シリーズ」とさほど間をおかずにただテロップで「3年後」みたいにして出されていたらどうだっただろうとふと思う。
たぶん、この物語を素直に受け止めて、ああ、本当に「ばいばい」なんだ…と思えるためには、スクリーンのこちら側にもバンビたちと同じ年月が流れている必要があったのだ。
だからこそ、時の止まってしまったぶっさんの「取り残された」ような孤独感をも感じることが出来る。
だから、この映画は「今更」じゃなかった。「今」が必要だったんだ。
映画であることに浮かれたように「お祭り」っぽかった「日本シリーズ」とは違って、どこをどう切り取ってもキャッツそのものだった。
だから、バカバカしいし、さりげないシーンに「裏」のためのネタがいっぱい仕込んであるし、目まぐるしいし忙しいし、しょっちゅう大笑い。
謎の韓国映画「釜山死ね死ね団」とか
たこ焼き屋の客が中川家礼二だったとか
実体化する前のぶっさんがあちこちでイタズラしてたりとか
うっちーが自衛隊で矯正されて「普通」の喋り方してるとか
ミー子が色白というだけでロシアンパブに紛れ込んでたりとか
アニが秋葉原の店頭でやってた野球ゲームはマリーンズ対ベイスターズで、ピッチャーは弟・佐々木純だったとか(そして打たれたとか)
ゾンビ選手のフォームは種田っぽかったりとか
ミニミニオジーはオジーとよく似てるとか
何故か下半身がマネキンだったりとか
………なんだけど。
私は途中からちょっとしたことですぐに涙ぐんだりしてたのだった。
たとえば、最初たった3人で作り始めたキャッツスタジアム。気づいたらどんどんみんな集まってきてあっというまに完成するとことか。
たとえば、沈没船のお宝を取りに行くのは無理そうじゃない?という場面でバンビが
「すげーこと言っていい?………野球、やろうよ」
って言った時とか。
あと、最初誰も見物客のいなかった試合に、いつの間にか大勢集まってたりとか。
オジーがホームランを打ったのに消えてしまってホームに帰ってこなかったとか。
悲しい場面じゃないとこでこみ上げてくるっていうのは………トシですか?w
そして。
ぶっさんが消えようとしている時。
父親の公助は、息子が息をひきとった時のことを思い出してた。
ずっとぶっさんは、自分の父親のことを「公助」と名前で呼んでいた。
もう意識が朦朧としていたぶっさんは、小さく呟く。
「おとうさん」
閉じた目から涙が滲んでいる。
「ありがとう」
父親は、優しく微笑んで息子の髪を撫でた。
「公平くん、『普通』だね」
戻ってきたぶっさんの姿を、父親の公助だけが見ることが出来なかった。
きっと「公平」は父親に対して思い残すことがなかったんだろう。
「お父さん」って、呼ぶことができたから。
ちゃんと───「お別れ」が出来ていたから。
これまで、避けるようにぶっさんの本当の死を描かなかったクドカンも、こうやってきちんと「ぶっさんの最期」を描くことで「木更津キャッツアイ」という作品に「ばいばい」を言おうとしているのだろう。
打球を追って草むらに消えたぶっさんを探し草むらの向こうの森にまで行ってみると、ただぶっさんのキャチャーミットだけが遺されていた。
その中にはボール。
「ばいばい」
と一言書かれたボール。
大好きな仲間に、自分から「ばいばい」なんて言いたいわけがない。
でも、言わなくちゃ前に進めない時もある。
遺された者たちが、これからも生きてゆくために。













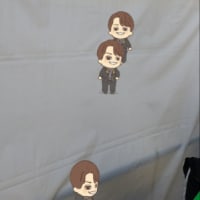






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます