
11月のとある金曜日、京都・先斗町で深夜まで飲んで祇園のスパで風呂入ってひと眠りした私は(おっさんやがな)実家に帰る前にふと思い立ってバスに乗りました。
約20年前(うわぁ…)には毎日乗っていた路線のバス。
長い月日を経て、バスの番号「37」は変わってないけど、行き先は変わってました。
昔は「上賀茂神社」行きだったのになー。
今は「西賀茂車庫」行きになってて、御薗橋を渡らずに曲がってしまう…。

と、いうわけで御薗橋は歩いて渡ってみる。
付近も随分変わっていました。
御薗橋から下流を望むとその風景は変わってない気がする。

橋を渡りきると、そこは上賀茂神社。
そして「神馬堂」の看板。

「神馬堂」のやきもち。
上賀茂の名物といってもいいでしょう。
たっぷりの粒餡をお餅で包んで焼いたもの。
焼いた皮が香ばしく、とっても美味しいのです。
…が非常に人気があり、売り切れれば閉店。
学生時代から、よく売り切れの憂き目にあいました。
この日は昼過ぎだったので「もしや」と淡い期待を寄せて店を覗いてみるとすでにおばちゃんが店の前を掃除していて、
「すんまへん、今日はもう終わったんどすわ」
………orz
悔しいから近くのもう一軒、「葵屋」のやきもちを買っていったのですがやはり神馬堂の焼きたてには勝てまい…。
気を取り直して上賀茂神社を散策。
上賀茂神社公式HP
正式には賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)と言います。
祭神は賀茂別雷大神。
雷の神様ですね。
京の都の鬼門を守る神社のひとつでもあります。

一の鳥居。

一の鳥居からニの鳥居までの参道の両脇は広々とした芝生になっていて、学生時代に時間空き(ニ講めが空いちゃったとか)にはここまで下山(笑)してきて芝生に座り、延々と落ち葉の散るのを眺めたりしていました。
この日は雨が降っていたので残念ながら芝生に座ることは断念…。

ニの鳥居をくぐると、拝殿とその前に「立砂」と言われる美しい三角錐の盛った砂山があります。
これは社の北西にある神山(こうやま)を形どったもので、神が降りる憑代なのだそうです。
神山っちゅーと、まさしく私の母校のあるとこあたりです。

11月ということもあり、七五三のお参りに来ている子供達もたくさんいました。
あと、結婚式もあったみたい。
花嫁さんがずっと記念撮影をしていました。

4月に行われる「曲水の宴」はこの曲水で行われます。

裏道をずっと行くと、稲荷社がありました。
「二葉姫稲荷」
石段をずっと登っていくと、寂しいのだか賑やかなのだか判らないようなお社が二つ。
どうもちょっと調べてみたら、この神様は参拝する人を選ぶみたいで、石段が登れなかった人もいるみたいです。
私はひとまず大丈夫でした(苦笑)。
登りきってお参りして、反対側の石段を降りて帰りました。
天気がよければもう少しゆっくりしたかったのですが、雨も降るのに傘を持っていなかったので散策もそこそこに。
御薗橋を再び渡り、随分変わったような気がする辺りを見回すと、昔もあった「餃子の王将」が健在だったのでそこで懐かしく思いながらお昼ご飯。

御薗橋から今度は上流を望んでみる。
少し天気の良くない日に、向こう側の山が霞んでいる風景が私は好きでした。
光原くんや平野佳くん(ともに檻)もこの風景を見てただろうな。
私がこの風景を毎日見てた頃には、うちの大学からプロ野球選手が出るなんてこれっぽっちも思ってなかったよ(笑)
ここまで来たなら学校(京都産業大学)まで行ってみても良かったんだけど…。
なんとなく、そのまま引き返しました。
さて再びバスに乗って、三条京阪に戻ってきましたよ。

やじさんきたさんが迎えてくれます(笑)
おまけ。

京都の子(特に京阪沿線の子)にはおなじみ、待ち合わせの定番、「土下座おじさん」高山彦九郎様。
御所に向かって手をついているんですが、たいてい
「ほな土下座前なー」とか「おっちゃんとこにいるわー」とか、散々な言われ方だと思う…。
約20年前(うわぁ…)には毎日乗っていた路線のバス。
長い月日を経て、バスの番号「37」は変わってないけど、行き先は変わってました。
昔は「上賀茂神社」行きだったのになー。
今は「西賀茂車庫」行きになってて、御薗橋を渡らずに曲がってしまう…。

と、いうわけで御薗橋は歩いて渡ってみる。
付近も随分変わっていました。
御薗橋から下流を望むとその風景は変わってない気がする。

橋を渡りきると、そこは上賀茂神社。
そして「神馬堂」の看板。

「神馬堂」のやきもち。
上賀茂の名物といってもいいでしょう。
たっぷりの粒餡をお餅で包んで焼いたもの。
焼いた皮が香ばしく、とっても美味しいのです。
…が非常に人気があり、売り切れれば閉店。
学生時代から、よく売り切れの憂き目にあいました。
この日は昼過ぎだったので「もしや」と淡い期待を寄せて店を覗いてみるとすでにおばちゃんが店の前を掃除していて、
「すんまへん、今日はもう終わったんどすわ」
………orz
悔しいから近くのもう一軒、「葵屋」のやきもちを買っていったのですがやはり神馬堂の焼きたてには勝てまい…。
気を取り直して上賀茂神社を散策。
上賀茂神社公式HP
正式には賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)と言います。
祭神は賀茂別雷大神。
雷の神様ですね。
京の都の鬼門を守る神社のひとつでもあります。

一の鳥居。

一の鳥居からニの鳥居までの参道の両脇は広々とした芝生になっていて、学生時代に時間空き(ニ講めが空いちゃったとか)にはここまで下山(笑)してきて芝生に座り、延々と落ち葉の散るのを眺めたりしていました。
この日は雨が降っていたので残念ながら芝生に座ることは断念…。

ニの鳥居をくぐると、拝殿とその前に「立砂」と言われる美しい三角錐の盛った砂山があります。
これは社の北西にある神山(こうやま)を形どったもので、神が降りる憑代なのだそうです。
神山っちゅーと、まさしく私の母校のあるとこあたりです。

11月ということもあり、七五三のお参りに来ている子供達もたくさんいました。
あと、結婚式もあったみたい。
花嫁さんがずっと記念撮影をしていました。

4月に行われる「曲水の宴」はこの曲水で行われます。

裏道をずっと行くと、稲荷社がありました。
「二葉姫稲荷」
石段をずっと登っていくと、寂しいのだか賑やかなのだか判らないようなお社が二つ。
どうもちょっと調べてみたら、この神様は参拝する人を選ぶみたいで、石段が登れなかった人もいるみたいです。
私はひとまず大丈夫でした(苦笑)。
登りきってお参りして、反対側の石段を降りて帰りました。
天気がよければもう少しゆっくりしたかったのですが、雨も降るのに傘を持っていなかったので散策もそこそこに。
御薗橋を再び渡り、随分変わったような気がする辺りを見回すと、昔もあった「餃子の王将」が健在だったのでそこで懐かしく思いながらお昼ご飯。

御薗橋から今度は上流を望んでみる。
少し天気の良くない日に、向こう側の山が霞んでいる風景が私は好きでした。
光原くんや平野佳くん(ともに檻)もこの風景を見てただろうな。
私がこの風景を毎日見てた頃には、うちの大学からプロ野球選手が出るなんてこれっぽっちも思ってなかったよ(笑)
ここまで来たなら学校(京都産業大学)まで行ってみても良かったんだけど…。
なんとなく、そのまま引き返しました。
さて再びバスに乗って、三条京阪に戻ってきましたよ。

やじさんきたさんが迎えてくれます(笑)
おまけ。

京都の子(特に京阪沿線の子)にはおなじみ、待ち合わせの定番、「土下座おじさん」高山彦九郎様。
御所に向かって手をついているんですが、たいてい
「ほな土下座前なー」とか「おっちゃんとこにいるわー」とか、散々な言われ方だと思う…。













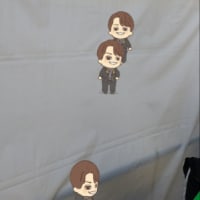












「葵祭り」と縁が深いところですね。
やはり歴史の重さを感じさせますよ。
神奈川を始めとする相模の国は頼朝が幕府を
開くまでは歴史にあまり出てくることはなかった
ですし、横浜に至っては幕末まで寂れた漁村です。
そんなこともあるのでしょうか、横浜そごうの
屋上に伏見稲荷が祭られていたり横浜松坂屋では
豊川稲荷が祭られていたりもしています。
いずれも正式に手続きを経て行われていますが。
最近乱視が更にひどくなってきたんでしょうか?
一瞬「やじさんきたさん」がやしきたかじんに
見えてしまいました、私の年のせいでしょうね...
最近はBomBerSの方もえらいことになってますよ...
葵祭(京都三大祭のひとつ)は学生時代ここで何度か見ましたね。人が多くなってバスに乗れず困りました(笑)
京都にはそのまま残っているものでないものは多いのですがやはり史跡は多いですね。建都1212年ですから(笑)
ビルの屋上のお稲荷さんは屋敷神として祀られていることが多いので歴史とはあまり関係ないのかもしれません。
>やじきた
やしきたかじんに迎えられてもあんまり嬉しくないなぁww
>BomBers
管理が行き届かないので一旦閉鎖を考えてますorz