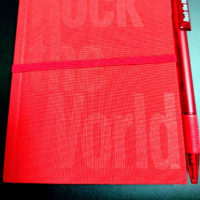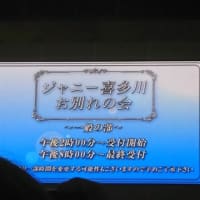出羽の国への旅は災難続きだったのですね。
関所で不審人物扱いされたり、
山賊が出るという山を越えたり……。
その後に、出会った紅花を扱う地元の豪商、
清風に強く勧められ向かったのが立石寺。山寺なのですね。
◎山寺◎
『おくのほそ道』を朗読する翔くん。
翔くんの声の持つ低音の魅力がいかんなく発揮されてます。
めちゃめちゃ渋くて素敵っ。
もっと年を重ねたら、もっと渋くなるのかなぁ。
いやー。今から楽しみだなぁ♪
翔「山形県、立石寺にある登山口にやってきました。
この立石寺は標高およそ380メートルある岩山に様々な
お堂がある寺院なんですね」
登山口の場所も既に結構高いのかしら?
翔くんの声と一緒に風の音がヒューって
大きな音で収録されちゃってます。
単に風の強い日だったのかな?
翔「上まで上がった景色はどうなんでしょうか?」
ザクザクという足音と、軽めにあがる息の音。
翔「狭いなぁ」
足音だけでなく、荷物の音なのかな、
いろいろな音に混ざって、
翔さんの息が少しずつ乱れて大きくなって。
翔「これは……はぁ、はぁ、はぁ、はぁ」
く、苦しそうな翔さん(きゃ )
)
翔「ここは展望台と言うか、絶景だなぁ」
えー。もう着いちゃったの~。
荒い息づかいがめっちゃ可愛かったのにな。
詰まんないの。←コラ。
翔「綺麗だな~。あ、気持ちいい!
風が、吹いて。ちょっと蝉の声が遠くから
若干聴こえるかな?」
凄く見晴らしが良くって綺麗だったんだろうな~って、
声からわかるの。
パっと光が差す様な明るいトーンで話す翔くんの声で
あぁ、今見てる景色は凄く綺麗なんだろうなって
ちゃんとわかる。
蝉の声、しっかり録れてるよ。聴こえて来たよ。
翔「辺りが一望出きる。自分が見てる目の前を
まさに現世が広がってるけど、横から見ると
お堂とお寺が立ち並んでる景色が、何て言うんだろう、
神聖さを醸し出してる気がします」
翔「ふーー(大きく息を吐いたので、有声音なの。
こんな素直な翔くんが可愛くって好き)
すぅ(吐ききって吸ったので、吸う音も音が出た♪)
うぅーん、本当に今日、ここ来て、想像以上でした。
あのぉー何か見たことのない景色と、んー、
見た事のない不思議なアンバランスさが詰まっていて
んー、まさに絶景と言う感じでしたね」
翔「ふっ(息を吸いました)
ただ、あそこの雰囲気、空気、景色を五七五、
その短い言葉に綺麗に収める芭蕉と言う人の凄さを
また改めて実感する場所でもありました」
翔「と言う訳で。え、僭越ながらちょっと叩きで
書いてみたんで詠ませて頂きます」
ノートなのかな?レポート用紙なのかな?
金色堂では句を詠む時に聴こえてこなかった、
紙の音が山寺ではしていました。
遠くから 秋の入り口 蝉ひとり
翔「何か遠くから登山口の入り口の方から蝉の声が
一匹だけ聴こえたのがなんかこう、秋の入り口を
感じさせる別れの声にも聴こえたのでこんな風に
詠んでみました」
金色堂では、ひねった句の説明とかなかったのに、
山寺ではどういう気持ちを込めたかを説明してくれて。
金色堂も素敵だったと思うのですが、
何だか根が素直なのでしょうね。
景色を見て、グッとくる気持ちと重なるように、
創作心も刺激される翔くんなんだなぁと。
当たり前っちゃー当たり前なのですが。
ね、一応、プライベートじゃないし、ラジオだし。
優劣ではけしてなく、好みの問題、
または気分の問題なのだと思いますが、
翔さんの心の琴線に触れた場所に立つと、
浮かぶ言葉も熱を帯びてくるのですね。
確実に、あぁ、この場所、気に入ったんだなぁ~。
今、目にしてる景色、すんごい綺麗なんだろうな~。
って、わかっちゃう翔くんはやっぱり可愛くって
チャーミングなのです。
山寺で詠んだ句も、翔さんの言葉のエッセンスが
ギュっと詰まって素敵でした。
ちなみに。ボツねたも2つあったそうです。
翔「秋の風 芭蕉と同じ 景色かな。
これ、ボツ第一ですね。
時を経て 変わらぬ景色 ここにあり。
え、いずれもなんか、ふぅーーー(息吸った)
ホーム降りた時に書いてあった言葉だったので、
ボツにさせて頂きました。ハハハ(笑)」
翔「という事で有名な蝉が登場したので、ここでお次は
『クイズショウ・音で読み解くマツオバショー』」
↑オーケストラのBGMに翔さんの声はエコー付き(笑)
こういうエネルギーの傾け方、大好きです>J-WAVE様
翔「嵐のラップ詞担当・櫻井翔です。
芭蕉の俳句を幾つか口ずさんでいてふと、思いつきました。
芭蕉の俳句をローマ字で書き起こしてみるとどうだろう?
しずかさや いわにしみいる せみのこえ
ん?ラジオじゃわかんない?
えー、では。では、皆さん!お手元に書くものがあったら
ちょっと書いてみてください」
はーい!
メモ用紙、メモ用紙と…。ちょっと待ってね。
翔「いいですか?
しずかさや いわにしみいる せみのこえ
SHIZUKASAYA IWANISHIMIIRU SEMINOKOE
どうですか?おわかりになりましたか?
し、い、に、し、み、い、み。
なんと「イ」の音が七つも使われてますね。
し、い、に、し、み、い、み。ね?
これって何か、まるで蝉の鳴き声の様なリズムですよね。
イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ。そうです。
これはにーにー蝉です。
シャワシャワシャワシャワと鳴くあぶら蝉でもなければ、
カナカナカナカナカナカナと鳴く蜩でもない。
まさにこれはにーにー蝉の鳴き声です」
蝉の声。
あ、ホントだ!すっごーい。
目のつけ所がめちゃめちゃ面白い。
翔「長年、岩に染み入るこの蝉は何蝉なんだと言う事が
論争されてきました。あぶら蝉派とにーにー蝉派が
熾烈な戦いをしたそうです。
その激しさ蝉の鳴き声より凄まじく、
でも、蜩こそ相応しいでしょうと主張する声も。
現在では、にーにー蝉であるという結論に
落ち着いてるそうです。
リスナーの皆さんはどう思いますか?」
にーにー蝉に一票な気持ちです。
翔「で、次です。これも皆さん、
ローマ字で書いてみてください」
はーい!今回はリスナー参加型ですね。
面白い趣向です。
翔「いいですか?
なつくさや つわものどもが ゆめのあと
NATSUKUSAYA TSUWAMONODOMOGA YUMENOATO」
も、の、ど、も、の、と。
「オ」の音が6つも出てきますね。
「オ」の音は哀しみの音。
言葉の意味とは別に音が人に訴える音です。
果たして芭蕉先生、この事を知っていてやったのか?
それとも、知らないでいてやったのか?
無論、元禄時代の芭蕉がローマ字など、
知る訳もありません。
天才は「言葉の力」その効果について
知っていたのでしょうか?
うん。知っていたんですね、きっと。
僕、櫻井翔もこんな「言葉の力」
マジックをもっと学んで、
もっと上手く使いこなしたいと思うのです」
なるほど~。何だか俳句を音で分析するなんて、
目からウロコだったのですが。
詩と考えれば共通する部分も多いのかも…。
翔さんのご講義、とっても面白かったです。
◎最上川◎
山の旅の次は川の旅。
水音と船のエンジンなのかな。
モーターの音が聞こえてきます。
それと、先頭さんのお声と手拍子の音も。
手拍子をもんで頂くと、という船頭さんのご説明に。
HPにお名前ありますが、船頭さんは女性の方です。
翔「へぇ~。(手拍子してる感じです)
最上川舟歌、お願いします」
♪歌う船頭さん。
調子の良い歌声と、手拍子。
川の水の音が激しくて急流感がライブに伝わってきます。
何か、涼しくなる気持ちです。
お、手拍子、だんだん揃ってきた!
翔「や~。ありがとうございます。(拍手)」
目、キラキラしちゃってるんだろうな~って感じ。
可愛い!←見てないけど(笑)
翔「手拍子が一回、ブレイクするのが良いですねぇ」
船頭さん「ブレイクですか(笑)」
翔「一度止んで、また、鳴り出す感じが凄い。
やー、カッコ良かったです。何を歌ってるんですか?」
船頭さん「これは船頭さんが家族に向けて、
俺は酒田の港に行って来るから、
皆風邪なんかひかないように元気でいるんだぞーと」
翔「へぇぇぇ~~~」
船頭さん「後半の方は船頭さんの生活ぶりを歌ってまして。
まっかんだいこというのは売り物にならない大根の事で、
二股にも三股にも分かれた所謂くず大根ですよね。
それを、自分たちの小屋で潮汁作ったんだけど、
男ばっかりの船旅なものですから、
なかなか作り慣れてなくて塩加減に失敗して、
しょっぱくて食べられないという素朴な生活を歌ってます」
『おくのほそ道』を朗読する翔くん。
超シブい声です。
コーナーによって全然違う声出すんだもんなー。
ドキドキしちゃうじゃないか~。
船頭さん「俳句は季語とか五七五とか様々な決まりが
ありますが、芭蕉さんが大切になさった事は
挨拶と言う意味合いで新しい土地に対して、
「はじめまして」という感謝の気持ちをこめて
歌を詠むというのが一番大事なんだそうです」
翔「へぇぇっ!ふぅぅん。その土地土地への感謝。
旅してないと、強く感じる事は出来ないんでしょうね」
『おくのほそ道』現代語訳。
パキパキっとした声で読み上げる翔くん。
鳥の鳴き声と水の音が聞こえてくる中、
最上川ロケのまとめコメントを話す翔くん。
翔「てわけで、最上川、川を下ってきましたが、
夕焼けと伸びる最上川と左右囲まれる山々と
いろんな表情、景色を短い時間で感じる事が出来ました。
えー、ここで、では。この1時間ほどで考えた一句なので
ちょっと恥ずかしいですけども、ここは最後の滝が
あまりにドラマチックだったので、そこに引っ掛けて
詠んでみたいと思います。
山を焼き 水面に伸びる 滝の白
何か、徐々に聴こえる滝の音がドンドン近づく滝の音と
現れた時にスっと白く伸びる滝の景色が
あまりに綺麗だったので、こう詠んでみました」
一幅の絵が目に浮かぶ様な句ですね。
このままずっと、翔くんの詠む俳句を
聴いていたいなぁと思わせるような。
芭蕉一行は修験道の聖地、出羽三山を抜けて
酒田へ辿り着いたのですね。
松島でもそうでしたが、絶景を女性に喩えるなんて、
松尾さん、ロマンチストなのですねぇ。
松島は笑っているようで、
象潟は憂いてるようなのですね。
『おくのほそ道』の現代語訳を朗読する翔くんの声は
またもや、悩ましげで困ります。
痔の痛みに耐える声すら、妙に可愛らしくって。
佐渡の島を見て、奈良の時代から時の権力に
抗い流された人の心情に思いを馳せ、
七夕の夜に胸を締め付けられてる松尾さん。
その感じ入りやすさが創作の源だったのでしょうか。
翔「今回のART OF WORDSの旅に出るまで、
『おくのほそ道』は芭蕉の旅日記のようなものだろうと
僕、櫻井翔は考えていました。でも、
少しずつ調べていくと「え?」と驚かされる事、
ばかりなのです」
◎立松和平氏との対談その2◎
翔「芭蕉は『おくのほそ道』書き上げるまで5年の月日を
費やしてる訳ですが、こういった事は紀行文の執筆には
よくある事なんでしょうか?」
立松氏「滅多にないんじゃないですか。
僕なんかすぐ書いちゃうけどね」
翔「あはははは(笑)」
立松氏「これは僕らの感覚とは違いますよ。
発表して原稿料を貰うとかそういうのじゃないんですよね。
伊賀・上野のお兄さんに、ずっと自分を庇護してくれた
お兄さんに捧げたって言うかね。
それをお兄さんが弟子たちに渡して筆写して
流布していった訳です」
翔「これだけ5年かけると言うのはそれなりの
試行錯誤の上『おくのほそ道』というフィクションと
呼んでいいのか分からないですけど、
作品に時間をかけて丁寧に作っていった」
立松氏「蕉風を確立した過程をきちっと
残したかったんだと思う。推敲に推敲を重ねて。
俳句の中もどんどん入れ替わって。
推敲を重ねて5年かかってしまったんじゃないですかね。
芭蕉としてみたら、人生をかけた完成品というかね。
蕉風に到達したぞという強い自覚が
あったんじゃないですかね」
翔「150日間を旅した記録を収めた
『おくのほそ道』ですけれども、物凄く短い文章で
簡潔にまとめられてますよね。何か、こう、
今、仰っていた様に言葉を変えて、どんどん、
いらない言葉をそぎ落としていくような。
ま、短い文章、短い言葉で相手に物事を伝える、
表現する、この術というのはどういった物なんでしょうか?」
立松氏「筆で書いて削ぎ落としてくのが俳句ですから。
17文字しかない所に宇宙を表現しちゃうから。
そうする事で世界が広がると言うか。
俳句と言うか、文学の宿命ですね。
削ぎ落として、削ぎ落として。
だから、芭蕉の散文というのは、
散文というか、全部、詩の文章ですね。
蕉風に辿り着いた芭蕉の喜びを感じますね。
一字、一点さえも無駄にしないという」
翔「芭蕉の様な俳句の神様でも悩みに悩み、
推敲に推敲を重ね、ひとつの俳句を完成させるのに
労を惜しまなかった。僕も良い詩が出来る様に
励みにします」
芭蕉の旅も終盤へ。
体調を崩した曾良と別れて、
途中からひとりぼっちの旅になるのですね。
詠む歌も死や別れをテーマにした句が増えたそうですが、
別れてから、再び巡り会い、喜びを噛み締めて、
旅の終着地、大垣では大団円が待っていたと。
翔「旅のスタート、この番組の冒頭、千住を旅立つ時に
芭蕉が詠んだ句を覚えていますか?
ゆく春や とりなき魚の よは涙
そして、この大垣で最後に詠んだ句は
蛤の 二身に別れ ゆく秋ぞ
ゆく春とゆく秋が対称となる実に見事な結びになっています」
旅に病んで 夢は枯野を 駆けめぐる
翔「元禄7年10月12日、午前4時。奇しくも今日です。
松尾芭蕉は波乱に飛んだ生涯に筆を起きます。
享年51歳でした。
体が動く限り旅をする。体が動かなければ夢で旅をする。
最後の瞬間まで旅する事を止めなかった芭蕉。
漂泊の詩人でした」
◎立松氏との対談その3◎
翔「立松さんの著書を拝見する中で
僕が理解出来なかったのは『言葉が時代を旅をする』
という中で、芭蕉は私たちをつないでくれる、
一方で私たちの言葉も芭蕉の世界を
つなげてるんだという事が書かれていたんですけれども、
これはどういう事なんでしょうか?
私たちから芭蕉へというのは、
ちょっとわからなかったんですけれども」
立松氏「芭蕉の時代の旅と今の時代の旅は
違ってますでしょ。芭蕉の旅は求道の旅。
道を究める旅ですね。我々は快楽の旅ですよね。」
旅の仕方としては変わっているけども、
四国八十八箇所を巡ろうとか、奥の細道でもいいですよ、
そういう旅の形を時代、時代にある訳ですよね。
例えば、奥の細道を周ってる外国人も結構います。
彼等がどういう風に読んでるかわからないけども、
今の時代を芭蕉に向ける事も出来るんですね。
これだけ、芭蕉に想いを持って奥の細道を旅する人が
後から後からいるという事は。
我々は今の時代に芭蕉に捧げていて、
もし芭蕉が生きていたら、恥ずかしくて
解釈出来ないかもしれないけど、
いないのを幸いに好きな事言ってるんだけど。
僕等はあの時代を背負わなくちゃしょうがないですね。
時代を芭蕉をささげないと」
翔「最後に、この番組では言葉の力について
探っているんですけれども、
立松さんご自身がお考えになる言葉の力というのは
ずばり何でしょう?」
立松氏「魂に入るって事かな」
翔「魂に入る。は~。というと?」
立松氏「心を動かす。
その人の人生を変える、大きくはね」
◎最後に◎
翔「そろそろ、お別れの時間が近づいて来ました。
J-WAVE SPECIAL ART OF WORDS 櫻井翔の『おくのほそ道』
今回、番組全体を通して感じた事なんですけども。
まず、僕は『おくのほそ道』にこれだけこう、
どっぷりと、しっかりと向き合うのは
初めてだったんですけれども、
いろいろな発見がありました。
まずその、今で言うサンプリングといいましょうか、
その、先人達の言葉を使ってみたり、また、
別のアプローチでその先人達の言葉を表現してみたり、
んー、サンプリングの様な物もあったり。
また、この番組の話にもありましたが、
ダブルミーニング、トリプルミーニング、
いろんな言葉の意味を重ねて、重ねて、作っていく。
凄く面白かったですね。
そしてまた今回『おくのほそ道』の場所に
実際に行って見た訳ですけれど、
そこで俳句を素人ながらひねってみる、
またその作業と言うのが、僕のラップ詞を書く作業に
凄く似ていました。
と言うのは、僕もラップ詞を書く時に、
リリックを書く時に何か1枚の画、
景色の様な物が頭に浮かんで、
それを文字に書き落としていく作業をする事が
あるんですけれど、まさに景色が目の前に広がっている
今見ている物を、文字に、言葉に
落としていく作業と言うのは少し
僕のラップを作る作業に似ていました。
ただ、それを五七五、わずか17文字に、
どんどん削ぎ落としてわずか17文字に書き落とす、
ひっじっよーに難しかったですね。
改めてその、俳句の難しさ、
また、その奥の深さ感じました。
立松さんも仰ってましたけれども、
これから言葉と向き合う上で、
言葉を生み出してく上で魂を揺さぶる。
うん、そんな言葉の力を感じる瞬間が
沢山あると良いなと思いました。
これから魂を揺さぶる言葉とどれだけ出会い、
また、多くの人たちの魂を揺さぶる事が出来る様な
言葉を生み出せる様、伝える様、
これからも言葉の力を探って行きたいと思いました。
以上、櫻井翔でした」
関所で不審人物扱いされたり、
山賊が出るという山を越えたり……。
その後に、出会った紅花を扱う地元の豪商、
清風に強く勧められ向かったのが立石寺。山寺なのですね。
◎山寺◎
『おくのほそ道』を朗読する翔くん。
翔くんの声の持つ低音の魅力がいかんなく発揮されてます。
めちゃめちゃ渋くて素敵っ。
もっと年を重ねたら、もっと渋くなるのかなぁ。
いやー。今から楽しみだなぁ♪
翔「山形県、立石寺にある登山口にやってきました。
この立石寺は標高およそ380メートルある岩山に様々な
お堂がある寺院なんですね」
登山口の場所も既に結構高いのかしら?
翔くんの声と一緒に風の音がヒューって
大きな音で収録されちゃってます。
単に風の強い日だったのかな?
翔「上まで上がった景色はどうなんでしょうか?」
ザクザクという足音と、軽めにあがる息の音。
翔「狭いなぁ」
足音だけでなく、荷物の音なのかな、
いろいろな音に混ざって、
翔さんの息が少しずつ乱れて大きくなって。
翔「これは……はぁ、はぁ、はぁ、はぁ」
く、苦しそうな翔さん(きゃ
 )
)翔「ここは展望台と言うか、絶景だなぁ」
えー。もう着いちゃったの~。
荒い息づかいがめっちゃ可愛かったのにな。
詰まんないの。←コラ。
翔「綺麗だな~。あ、気持ちいい!
風が、吹いて。ちょっと蝉の声が遠くから
若干聴こえるかな?」
凄く見晴らしが良くって綺麗だったんだろうな~って、
声からわかるの。
パっと光が差す様な明るいトーンで話す翔くんの声で
あぁ、今見てる景色は凄く綺麗なんだろうなって
ちゃんとわかる。
蝉の声、しっかり録れてるよ。聴こえて来たよ。
翔「辺りが一望出きる。自分が見てる目の前を
まさに現世が広がってるけど、横から見ると
お堂とお寺が立ち並んでる景色が、何て言うんだろう、
神聖さを醸し出してる気がします」
翔「ふーー(大きく息を吐いたので、有声音なの。
こんな素直な翔くんが可愛くって好き)
すぅ(吐ききって吸ったので、吸う音も音が出た♪)
うぅーん、本当に今日、ここ来て、想像以上でした。
あのぉー何か見たことのない景色と、んー、
見た事のない不思議なアンバランスさが詰まっていて
んー、まさに絶景と言う感じでしたね」
翔「ふっ(息を吸いました)
ただ、あそこの雰囲気、空気、景色を五七五、
その短い言葉に綺麗に収める芭蕉と言う人の凄さを
また改めて実感する場所でもありました」
翔「と言う訳で。え、僭越ながらちょっと叩きで
書いてみたんで詠ませて頂きます」
ノートなのかな?レポート用紙なのかな?
金色堂では句を詠む時に聴こえてこなかった、
紙の音が山寺ではしていました。
遠くから 秋の入り口 蝉ひとり
翔「何か遠くから登山口の入り口の方から蝉の声が
一匹だけ聴こえたのがなんかこう、秋の入り口を
感じさせる別れの声にも聴こえたのでこんな風に
詠んでみました」
金色堂では、ひねった句の説明とかなかったのに、
山寺ではどういう気持ちを込めたかを説明してくれて。
金色堂も素敵だったと思うのですが、
何だか根が素直なのでしょうね。
景色を見て、グッとくる気持ちと重なるように、
創作心も刺激される翔くんなんだなぁと。
当たり前っちゃー当たり前なのですが。
ね、一応、プライベートじゃないし、ラジオだし。
優劣ではけしてなく、好みの問題、
または気分の問題なのだと思いますが、
翔さんの心の琴線に触れた場所に立つと、
浮かぶ言葉も熱を帯びてくるのですね。
確実に、あぁ、この場所、気に入ったんだなぁ~。
今、目にしてる景色、すんごい綺麗なんだろうな~。
って、わかっちゃう翔くんはやっぱり可愛くって
チャーミングなのです。
山寺で詠んだ句も、翔さんの言葉のエッセンスが
ギュっと詰まって素敵でした。
ちなみに。ボツねたも2つあったそうです。
翔「秋の風 芭蕉と同じ 景色かな。
これ、ボツ第一ですね。
時を経て 変わらぬ景色 ここにあり。
え、いずれもなんか、ふぅーーー(息吸った)
ホーム降りた時に書いてあった言葉だったので、
ボツにさせて頂きました。ハハハ(笑)」
翔「という事で有名な蝉が登場したので、ここでお次は
『クイズショウ・音で読み解くマツオバショー』」
↑オーケストラのBGMに翔さんの声はエコー付き(笑)
こういうエネルギーの傾け方、大好きです>J-WAVE様
翔「嵐のラップ詞担当・櫻井翔です。
芭蕉の俳句を幾つか口ずさんでいてふと、思いつきました。
芭蕉の俳句をローマ字で書き起こしてみるとどうだろう?
しずかさや いわにしみいる せみのこえ
ん?ラジオじゃわかんない?
えー、では。では、皆さん!お手元に書くものがあったら
ちょっと書いてみてください」
はーい!
メモ用紙、メモ用紙と…。ちょっと待ってね。
翔「いいですか?
しずかさや いわにしみいる せみのこえ
SHIZUKASAYA IWANISHIMIIRU SEMINOKOE
どうですか?おわかりになりましたか?
し、い、に、し、み、い、み。
なんと「イ」の音が七つも使われてますね。
し、い、に、し、み、い、み。ね?
これって何か、まるで蝉の鳴き声の様なリズムですよね。
イ、イ、イ、イ、イ、イ、イ。そうです。
これはにーにー蝉です。
シャワシャワシャワシャワと鳴くあぶら蝉でもなければ、
カナカナカナカナカナカナと鳴く蜩でもない。
まさにこれはにーにー蝉の鳴き声です」
蝉の声。
あ、ホントだ!すっごーい。
目のつけ所がめちゃめちゃ面白い。
翔「長年、岩に染み入るこの蝉は何蝉なんだと言う事が
論争されてきました。あぶら蝉派とにーにー蝉派が
熾烈な戦いをしたそうです。
その激しさ蝉の鳴き声より凄まじく、
でも、蜩こそ相応しいでしょうと主張する声も。
現在では、にーにー蝉であるという結論に
落ち着いてるそうです。
リスナーの皆さんはどう思いますか?」
にーにー蝉に一票な気持ちです。
翔「で、次です。これも皆さん、
ローマ字で書いてみてください」
はーい!今回はリスナー参加型ですね。
面白い趣向です。
翔「いいですか?
なつくさや つわものどもが ゆめのあと
NATSUKUSAYA TSUWAMONODOMOGA YUMENOATO」
も、の、ど、も、の、と。
「オ」の音が6つも出てきますね。
「オ」の音は哀しみの音。
言葉の意味とは別に音が人に訴える音です。
果たして芭蕉先生、この事を知っていてやったのか?
それとも、知らないでいてやったのか?
無論、元禄時代の芭蕉がローマ字など、
知る訳もありません。
天才は「言葉の力」その効果について
知っていたのでしょうか?
うん。知っていたんですね、きっと。
僕、櫻井翔もこんな「言葉の力」
マジックをもっと学んで、
もっと上手く使いこなしたいと思うのです」
なるほど~。何だか俳句を音で分析するなんて、
目からウロコだったのですが。
詩と考えれば共通する部分も多いのかも…。
翔さんのご講義、とっても面白かったです。
◎最上川◎
山の旅の次は川の旅。
水音と船のエンジンなのかな。
モーターの音が聞こえてきます。
それと、先頭さんのお声と手拍子の音も。
手拍子をもんで頂くと、という船頭さんのご説明に。
HPにお名前ありますが、船頭さんは女性の方です。
翔「へぇ~。(手拍子してる感じです)
最上川舟歌、お願いします」
♪歌う船頭さん。
調子の良い歌声と、手拍子。
川の水の音が激しくて急流感がライブに伝わってきます。
何か、涼しくなる気持ちです。
お、手拍子、だんだん揃ってきた!
翔「や~。ありがとうございます。(拍手)」
目、キラキラしちゃってるんだろうな~って感じ。
可愛い!←見てないけど(笑)
翔「手拍子が一回、ブレイクするのが良いですねぇ」
船頭さん「ブレイクですか(笑)」
翔「一度止んで、また、鳴り出す感じが凄い。
やー、カッコ良かったです。何を歌ってるんですか?」
船頭さん「これは船頭さんが家族に向けて、
俺は酒田の港に行って来るから、
皆風邪なんかひかないように元気でいるんだぞーと」
翔「へぇぇぇ~~~」
船頭さん「後半の方は船頭さんの生活ぶりを歌ってまして。
まっかんだいこというのは売り物にならない大根の事で、
二股にも三股にも分かれた所謂くず大根ですよね。
それを、自分たちの小屋で潮汁作ったんだけど、
男ばっかりの船旅なものですから、
なかなか作り慣れてなくて塩加減に失敗して、
しょっぱくて食べられないという素朴な生活を歌ってます」
『おくのほそ道』を朗読する翔くん。
超シブい声です。
コーナーによって全然違う声出すんだもんなー。
ドキドキしちゃうじゃないか~。
船頭さん「俳句は季語とか五七五とか様々な決まりが
ありますが、芭蕉さんが大切になさった事は
挨拶と言う意味合いで新しい土地に対して、
「はじめまして」という感謝の気持ちをこめて
歌を詠むというのが一番大事なんだそうです」
翔「へぇぇっ!ふぅぅん。その土地土地への感謝。
旅してないと、強く感じる事は出来ないんでしょうね」
『おくのほそ道』現代語訳。
パキパキっとした声で読み上げる翔くん。
鳥の鳴き声と水の音が聞こえてくる中、
最上川ロケのまとめコメントを話す翔くん。
翔「てわけで、最上川、川を下ってきましたが、
夕焼けと伸びる最上川と左右囲まれる山々と
いろんな表情、景色を短い時間で感じる事が出来ました。
えー、ここで、では。この1時間ほどで考えた一句なので
ちょっと恥ずかしいですけども、ここは最後の滝が
あまりにドラマチックだったので、そこに引っ掛けて
詠んでみたいと思います。
山を焼き 水面に伸びる 滝の白
何か、徐々に聴こえる滝の音がドンドン近づく滝の音と
現れた時にスっと白く伸びる滝の景色が
あまりに綺麗だったので、こう詠んでみました」
一幅の絵が目に浮かぶ様な句ですね。
このままずっと、翔くんの詠む俳句を
聴いていたいなぁと思わせるような。
芭蕉一行は修験道の聖地、出羽三山を抜けて
酒田へ辿り着いたのですね。
松島でもそうでしたが、絶景を女性に喩えるなんて、
松尾さん、ロマンチストなのですねぇ。
松島は笑っているようで、
象潟は憂いてるようなのですね。
『おくのほそ道』の現代語訳を朗読する翔くんの声は
またもや、悩ましげで困ります。
痔の痛みに耐える声すら、妙に可愛らしくって。
佐渡の島を見て、奈良の時代から時の権力に
抗い流された人の心情に思いを馳せ、
七夕の夜に胸を締め付けられてる松尾さん。
その感じ入りやすさが創作の源だったのでしょうか。
翔「今回のART OF WORDSの旅に出るまで、
『おくのほそ道』は芭蕉の旅日記のようなものだろうと
僕、櫻井翔は考えていました。でも、
少しずつ調べていくと「え?」と驚かされる事、
ばかりなのです」
◎立松和平氏との対談その2◎
翔「芭蕉は『おくのほそ道』書き上げるまで5年の月日を
費やしてる訳ですが、こういった事は紀行文の執筆には
よくある事なんでしょうか?」
立松氏「滅多にないんじゃないですか。
僕なんかすぐ書いちゃうけどね」
翔「あはははは(笑)」
立松氏「これは僕らの感覚とは違いますよ。
発表して原稿料を貰うとかそういうのじゃないんですよね。
伊賀・上野のお兄さんに、ずっと自分を庇護してくれた
お兄さんに捧げたって言うかね。
それをお兄さんが弟子たちに渡して筆写して
流布していった訳です」
翔「これだけ5年かけると言うのはそれなりの
試行錯誤の上『おくのほそ道』というフィクションと
呼んでいいのか分からないですけど、
作品に時間をかけて丁寧に作っていった」
立松氏「蕉風を確立した過程をきちっと
残したかったんだと思う。推敲に推敲を重ねて。
俳句の中もどんどん入れ替わって。
推敲を重ねて5年かかってしまったんじゃないですかね。
芭蕉としてみたら、人生をかけた完成品というかね。
蕉風に到達したぞという強い自覚が
あったんじゃないですかね」
翔「150日間を旅した記録を収めた
『おくのほそ道』ですけれども、物凄く短い文章で
簡潔にまとめられてますよね。何か、こう、
今、仰っていた様に言葉を変えて、どんどん、
いらない言葉をそぎ落としていくような。
ま、短い文章、短い言葉で相手に物事を伝える、
表現する、この術というのはどういった物なんでしょうか?」
立松氏「筆で書いて削ぎ落としてくのが俳句ですから。
17文字しかない所に宇宙を表現しちゃうから。
そうする事で世界が広がると言うか。
俳句と言うか、文学の宿命ですね。
削ぎ落として、削ぎ落として。
だから、芭蕉の散文というのは、
散文というか、全部、詩の文章ですね。
蕉風に辿り着いた芭蕉の喜びを感じますね。
一字、一点さえも無駄にしないという」
翔「芭蕉の様な俳句の神様でも悩みに悩み、
推敲に推敲を重ね、ひとつの俳句を完成させるのに
労を惜しまなかった。僕も良い詩が出来る様に
励みにします」
芭蕉の旅も終盤へ。
体調を崩した曾良と別れて、
途中からひとりぼっちの旅になるのですね。
詠む歌も死や別れをテーマにした句が増えたそうですが、
別れてから、再び巡り会い、喜びを噛み締めて、
旅の終着地、大垣では大団円が待っていたと。
翔「旅のスタート、この番組の冒頭、千住を旅立つ時に
芭蕉が詠んだ句を覚えていますか?
ゆく春や とりなき魚の よは涙
そして、この大垣で最後に詠んだ句は
蛤の 二身に別れ ゆく秋ぞ
ゆく春とゆく秋が対称となる実に見事な結びになっています」
旅に病んで 夢は枯野を 駆けめぐる
翔「元禄7年10月12日、午前4時。奇しくも今日です。
松尾芭蕉は波乱に飛んだ生涯に筆を起きます。
享年51歳でした。
体が動く限り旅をする。体が動かなければ夢で旅をする。
最後の瞬間まで旅する事を止めなかった芭蕉。
漂泊の詩人でした」
◎立松氏との対談その3◎
翔「立松さんの著書を拝見する中で
僕が理解出来なかったのは『言葉が時代を旅をする』
という中で、芭蕉は私たちをつないでくれる、
一方で私たちの言葉も芭蕉の世界を
つなげてるんだという事が書かれていたんですけれども、
これはどういう事なんでしょうか?
私たちから芭蕉へというのは、
ちょっとわからなかったんですけれども」
立松氏「芭蕉の時代の旅と今の時代の旅は
違ってますでしょ。芭蕉の旅は求道の旅。
道を究める旅ですね。我々は快楽の旅ですよね。」
旅の仕方としては変わっているけども、
四国八十八箇所を巡ろうとか、奥の細道でもいいですよ、
そういう旅の形を時代、時代にある訳ですよね。
例えば、奥の細道を周ってる外国人も結構います。
彼等がどういう風に読んでるかわからないけども、
今の時代を芭蕉に向ける事も出来るんですね。
これだけ、芭蕉に想いを持って奥の細道を旅する人が
後から後からいるという事は。
我々は今の時代に芭蕉に捧げていて、
もし芭蕉が生きていたら、恥ずかしくて
解釈出来ないかもしれないけど、
いないのを幸いに好きな事言ってるんだけど。
僕等はあの時代を背負わなくちゃしょうがないですね。
時代を芭蕉をささげないと」
翔「最後に、この番組では言葉の力について
探っているんですけれども、
立松さんご自身がお考えになる言葉の力というのは
ずばり何でしょう?」
立松氏「魂に入るって事かな」
翔「魂に入る。は~。というと?」
立松氏「心を動かす。
その人の人生を変える、大きくはね」
◎最後に◎
翔「そろそろ、お別れの時間が近づいて来ました。
J-WAVE SPECIAL ART OF WORDS 櫻井翔の『おくのほそ道』
今回、番組全体を通して感じた事なんですけども。
まず、僕は『おくのほそ道』にこれだけこう、
どっぷりと、しっかりと向き合うのは
初めてだったんですけれども、
いろいろな発見がありました。
まずその、今で言うサンプリングといいましょうか、
その、先人達の言葉を使ってみたり、また、
別のアプローチでその先人達の言葉を表現してみたり、
んー、サンプリングの様な物もあったり。
また、この番組の話にもありましたが、
ダブルミーニング、トリプルミーニング、
いろんな言葉の意味を重ねて、重ねて、作っていく。
凄く面白かったですね。
そしてまた今回『おくのほそ道』の場所に
実際に行って見た訳ですけれど、
そこで俳句を素人ながらひねってみる、
またその作業と言うのが、僕のラップ詞を書く作業に
凄く似ていました。
と言うのは、僕もラップ詞を書く時に、
リリックを書く時に何か1枚の画、
景色の様な物が頭に浮かんで、
それを文字に書き落としていく作業をする事が
あるんですけれど、まさに景色が目の前に広がっている
今見ている物を、文字に、言葉に
落としていく作業と言うのは少し
僕のラップを作る作業に似ていました。
ただ、それを五七五、わずか17文字に、
どんどん削ぎ落としてわずか17文字に書き落とす、
ひっじっよーに難しかったですね。
改めてその、俳句の難しさ、
また、その奥の深さ感じました。
立松さんも仰ってましたけれども、
これから言葉と向き合う上で、
言葉を生み出してく上で魂を揺さぶる。
うん、そんな言葉の力を感じる瞬間が
沢山あると良いなと思いました。
これから魂を揺さぶる言葉とどれだけ出会い、
また、多くの人たちの魂を揺さぶる事が出来る様な
言葉を生み出せる様、伝える様、
これからも言葉の力を探って行きたいと思いました。
以上、櫻井翔でした」