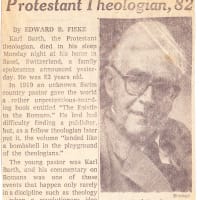藤本満先生から、貴重な原稿をいただきました。
日本基督教学会から書評の依頼があった際に、お書きになったものだそうです。
評者ご本人からのお知らせで、今頃になってこの書評の存在を知った次第です。
掲載の許可を藤本先生からいただきました。
***
野呂芳男『ジョン・ウェスレー』(松鶴亭、二〇〇五年)、三四二頁
藤本満(インマヌエル高津教会牧師)
これまでウェスレー研究には二つの大きな波があった。かつて一九五〇~七〇年代に、聖書論、義認論、キリスト論、聖霊論、聖化論、教会論、聖餐論、またウェスレーとカルヴァン、ルター、英国国教会、モラビア派、ピューリタン、神秘主義との関係、と主要題目は博士論文や研究書で扱われてきた。野呂が七五年に出版した『ウェスレーの生涯と神学』は、それらの研究成果を踏まえ、かつ独自の実存的視点や教理史の知識を縦横無尽に用いてウェスレー像を集大成したものであり、もし英訳されていたら、世界におけるウェスレー研究のスタンダードとなっていた。大著の発行から三〇年経過して、ウェスレーに対する熱い思いを再び著されたことは、日本のウェスレー研究を鼓舞することとなった。
第二の波は、一九八〇年代後半から始まった。『二百年記念ウェスレー全集』(刊行中)の膨大な資料に後押しされ、コンピュータによるデータベースが可能になり、新しい展望が開けてきた。また、この時期に、神学的アイデンティティーを失った合同メソジスト教会が、ウェスレー回帰を打ち出したことも、第二波の一因となった。もっとも回帰の流れに乗って、神学者たちが自分の主義主張の「拠り所」をウェスレーに求める傾向もあり、ウェスレーが面白くもなり、また歪みもした。本書九~十章で、著者は最近の動向との対話を試みている。
本書は、三つの部門に別れる。一章でウェスレーの生涯をわかりやすく要約し、二~八章でウェスレー神学を各論的に分析し、九~十章で最近のウェスレー研究の動向と問題点を指摘する。
Ⅰ. 実存主義的解釈
各論において、著者は前作よりも明確に、ウェスレー神学を実存的視点から描くことに努めている。義認の章は、ことさら興味深かった。野呂は、ウェスレーによる「この点(義認)に関して私は、彼(カルヴァン)から髪の毛ひと筋ほども違っていない」との言葉を評して、「おそらくウェスレーは、自分がどれほどカルヴァンから遠くに立っていたかを認識していなかったのではないだろうか」(一五一頁)と解説を始める。
野呂は、宗教改革者たちが義認を「言わばその信者の全生涯を無差別に内に複妙に永遠の面から考える」、客観主義に立っていたのに対して、ウェスレーが義認を「聖化という過程の中の出発点として、その中に含ませ」ることで、「信者が絶えず罪と闘いつつあり、その信者の生活の支配的原則が神の意志に服従しようとの意欲」「主体的な決断」を強調していると説明する。つまり、ウェスレーは、神と信者との関係を「動的な、緊張をもったとらえ方」で考えている。予定論者ならば、「自分の決断とは無関係に設定された必然性の中に、信仰者の安心を見いだそうとするであろう」。しかし、「ここにウェスレー神学の実存的な厳しさがあると言っても良い。これを捨てたならば、ウェスレー神学の持ち味は薄められてしまう」(以上、一五四~六五頁)。また野呂は「ほんとうのキリスト教的な慰めは、神とのきびしい対面そのもののなかからわき出てくるのではないだろうか」(二一六頁)と実存主義的色合いをあざやかに描く。
聖化についても、ウェスレー自身は、それが漸次的に上昇する一つの直線であるかのように教えていた。ウェスレーと聖化の研究で著名なリントシュトレームも、ウェスレーの言葉をそのまま受けて直線的に聖化を説く。だが、野呂は、ウェスレーにとって「上昇する聖化の直線は、手際よくきちんと引かれうるようなものではなく、破れを内包し」、ウェスレーにとって人生の初段階の理解は、「キルケゴールと同じような、きわめて実存的なもの」(一七〇頁)であると指摘している。
時に単純すぎるウェスレーの言葉を鵜呑みにしないで、その全体像からウェスレー神学の「持ち味」を描き、ウェスレー神学の至らなかった点を配慮して解説するところは、研究者の「応用編」らしく、多くを学ばされる。評者は、実存主義のカテゴリーを使わないし、また使えない。このカテゴリーを使うとき、ウェスレー神学の「持ち味」が生かされることは確かである。――著者にとっての実存主義は、「自分を、自分の根底としてすでに与えられてしまっている神の秩序から理解し、そこに生きようとすること」であり、「自分の生形成さえも自分から根拠づけようとする意味での自由な決断ではない」(二〇四頁)。――だが、このカテゴリーを理解しない人には、それはかえって難解な解釈になり得るし、本書に出てくる「前理解」「非神話化」という用語でさえ、次の世代の神学にどの程度通用するのかも考えさせられる。
「キリスト者の完全」の教理においては、もしユングの深層心理学的分析やマルクスの階級分析が当時存在したなら、十八世紀の「ウェスレーが気づいていないような、魂の事情が明るみに出されてくるであろう」と著者は述べる。だが、この教理の核心において、ウェスレーが教えたことは神学的に妥当性があると野呂は記す。ウェスレーは「動機における純粋」「意思の統合性」を語ったが、野呂は、それを「決断という人間の実存的次元の視角」に置き換え、その視角から人間の罪を理解するとき、すなわち、もし「私たちがこの地上の生において、ある瞬間以降、決断をし続けるその方向が、いつも絶えず神に向けられているなら……私たちの決断のすべてが、過ちを除いて汚れのないものになる状態」(一八八頁)が生じてくる。
教理の重要性・正当性をこのように養護しておいて、野呂は反面、ウェスレーの完全論の欠点をも指摘する。それは、上述のような深層心理の角度からの追求ではなく、ウェスレーの完全論が「平盤」であり、「個人差を顧慮していない」という点である。キリスト者の体験を、神の恵みの大海に飛び込み、できる限り潜っていくことにたとえれば(ウェスレー自身もこのたとえを使う)、これ以上深くは潜れないというところに行き着く。その時点で、上を見れば、そこには聖化の始まりであり、下を見れば、それ以上潜れないという完全がある、と野呂は説明する。だが、この距離は、水面から測ってみれば、人によって異なっていて当然であり、また同一個人においてさえ、その深みは徐々に増し加わるはずが、ウェスレーの説明にはそうしたことへの配慮が欠けているという。評者にとっては、これはウェスレーの完全論批判として実に新鮮であった。
Ⅱ. 他のウェスレー研究者との対話
評者にとって最も読み応えがあったのは、第九章に見る、野呂と他のウェスレー研究者たちとの対話であった。氏が対話の相手として選んだのは、
①初代教会史を専門にしながら、六〇年代にウェスレーと東方教父との関連に着目し、その後、ウェスレー研究「第一人者」の立場を譲ることはなかった教会史家アウトラー
②ウェスレーと解放の神学の関連づけからウェスレー研究に着手し、一九九八年に『新創造――今日におけるウェスレー神学』を著したランヨン(米国ドルー神学校で野呂の三年後輩、その後ゲッチンゲンでゴーガルテンとティリッヒの研究で博士号を取得)
③そして、世界的に著名なプロセス神学者カブによる『恵みと責任――今日のためのウェスレー神学』(一九九五年)である。
この二書は、ランヨンが「新創造」、カブが「神の恵みに応答する人間」という、共にウェスレー神学に特徴的なテーマを軸に、その全体像をとりまとめ、なおかつ人権・貧困・女性・環境問題といった現代の諸問題からウェスレー神学の意義を浮き彫りにする、意欲的な取り組みである。アウトラーは別としても、野呂は、ランヨンやカブよりもウェスレー研究・教理史全体に深い造詣を誇る。その彼が二者をどう評価するか。評者は多大な関心をもって読んだ。
カブは、ウェスレーの「先行の恵み」の教理に注目する。堕罪以来、生まれながらの人間には善を選ぶ自由意思も良心もなくなってしまったのであるが、神は先行の恵みとしてそれらを部分的に回復させ、恵みに応答できる存在として、人間をこの世に生かしている。「先行の恵み」こそ、ルターやカルヴァンのように、救いを与える神とそれを信じる人間の関係を排他的に・予定論的には考えなかったウェスレー神学の特徴であり、それが故にカブは自著に『恵みと責任』という題名をつけたことを、野呂は的確に指摘する(二四一頁)。だが、カブは神が聖霊によってすべての人に理性や良心を与えているというウェスレー考えの中に、プロセス思想から来る「神の内在」を巧みに織り交ぜてくる。野呂は、カブの背後にあるホワイトヘッド哲学にまで遡り、カブの解釈が歪んでいく過程を説明する。「カブによると、ウェスレーはちょうどホワイトヘッドと同じように、人間の自由意思を損なわずに完全の聖化まで人間を導いていく、時間の中に内在する神を強く主張した神学者になる」(二四四頁)。
ランヨンは、ウェスレーの救済論が個人だけでなく、社会的視野、さらには宇宙的な次元までも含んでいることを強調した。そもそも、救いは罪の赦しの宣言だけではなく、破壊された人間の中の「神の像」の回復過程であることは、ウェスレーの聖化論に顕著である。そして、これに東方教会との関連づけを与えたのはアウトラーであった。だが、アウトラーが「新創造」を主に個人の聖化に集中させて理解したのに対して、ランヨンは社会的次元に重きを置いているという印象を野呂は抱く(二三四頁)。評者も同感である。当然、ここで聖化論は終末論と結びついている。すなわち、人間の歴史の流れの中で、将来から現在に攻めって来る神の国こそが、聖化を実現していく神の力である。ここで野呂のランヨン評は、評者もまたランヨンを読んで漠然と疑念を抱いていた印象を明確に論理化してくれた。すなわち、ランヨンが終末と結びつけて聖化を語るとき、あたかも「人間の持つ宿命成就的主体性がまるで存在しないかのように、それとは無縁であるかのように、神学において向こう側から人間を捕らえてくる神の働き」(二五七頁)として描いている感が強い。そういう主体的な生き方の選択なしに、信仰義認、そして個人と社会との次元における聖化を語ることは、カルヴァン主義者たちの路線であり、「現代神学の分野で言えば、バルトを延長したモルトマンの路線によるウェスレー解釈と言っても良いかも知れない」(二五九頁)。ランヨンは解放の神学を通してモルトマンとの親交があり、後者は前者を通してウェスレーの聖化を高く評価するようになった(参・『いのちの御霊-総体的聖霊論』)。
野呂のランヨン批判に、実存的思考が反映されていることも事実である。だが、ウェスレーの場合には、終末から社会を変革する神の働き以上に、「個人の信仰体験が深まり、ひとりひとりの完全の追求によって、その人びとのいる社会全体が大きく変化し、そこにこれまでにない宗教的な雰囲気が作り出されることを認め、かつ喜んでいるふしがある」(二七一頁)との野呂の観察は妥当であり、こちらが正統なウェスレー論であると評者は考える。
Ⅲ. 現在のウェスレー研究を二分する論争
最終章に至って、察しの悪い評者は、野呂が近年のウェスレー研究を二分する大きな問題に積極的に関わっていることに気がついた。それは、ウェスレーの福音的回心、アルダスゲイト体験をどう解釈するかである。
ウェスレーは、一七二五年のオックスフォード時代、ア・ケンピスやJ・テイラーなどに触れて、生涯と心を神にささげ、「第一の回心」を体験した。神聖クラブを率い、ジョージアに宣教に赴き、聖くあろうとする自分に絶望し、帰英する。その彼は、入植地でモラビア派から信仰義認を学び、アルダスゲイト街でもたれた集会で三八年に信仰義認を体験する。これが「第二の回心」である。
だが、その後も聖化の強調が全く衰えないことから、「第一の回心」の方に重きを置く研究者(特にカトリック)も少数ながら存在した。さらに一七六〇年代にカルヴァン派との論争が激化する中で、ウェスレーは信仰義認とキリストの義の転嫁の教えに安住して、聖化や修練の追求を否定する当時の「福音派」を「信仰至上主義者」と批判するようになる。加えてこの時期、ウェスレー神学は、「後期ウェスレー」と呼ばれる独特な進展を見せる。すなわち実生活の諸問題、社会問題、英国全体の文化風習の問題など、神学の活動範囲が広がる。
この経緯を踏まえて、アウトラーは「前期」「中期」「後期」ウェスレーという区分を設け、これが現在では定説となっている。ウェスレー神学における「後期」の独特な発展は、「前期」に回帰したものではなく、「神学者として成熟期」と捉えるのが一般的であって、野呂がこれを「第一の回心」「第二の回心」「第三の回心」という「回心」区分として批判することは(たとえそれに反対であっても)、誤解を招く。その意味で、野呂の清水に対する批判は妥当ではない(二九八頁)。
こうした混乱はさておき、ここで野呂は重要な課題と論議を交えている。「アウトラーにしろランヨンにしろマドックスにしろ、これらのウェスレー神学の研究者たちは、ウェスレーを世界観的に考察しているように私には思えて仕方がない」(二九九頁)。野呂は、アウトラーに始まる最近の研究者たちが、ウェスレーにおけるギリシャ教父の影響を強調するあまり、アルダスゲイトに代表されるような、ウェスレー神学の持つ「主体的・実存的姿勢を見失ってしまった」と述べる。同時に、ギリシャ教父に特有な神秘主義を極力警戒していたウェスレー像も、近年の研究では影を薄くしていると言う。
近年、ウェスレー研究の最大の論議が、アルダスゲイト解釈にあったことは述べた。日本ウェスレーメソジスト学会でも、この問題を取り上げてきた。一般的に、ウェスレーの生涯にわたってアルダスゲイト体験の意義を認めようとする学者は、東方的救済論の中で、メソジストの信仰復興運動を立ち上げた活力のようなものが見失われることを懸念する。だがそこに固執すると、ウェスレー神学の持つ「広がり」を見失う傾向もある。野呂は、「実存」というカテゴリーをもってこの論争に自らの判断を下していることは興味深い。
本書を読み終えて、評者が尋ねてみたいことは、前期ウェスレーと中期ウェスレーに詳しい著者だが、アウトラーを中心に着目されてきた後期ウェスレーの進展(『二百周年記念全集』一巻序文)、特にそれが世界観の変遷ではなく、論争に巻き込まれ、英国の文化世相の実情の中で、「神学者として実存」をかけての変遷であるとしたら、氏が後期ウェスレーをどのように評価するか、である。
日本基督教学会から書評の依頼があった際に、お書きになったものだそうです。
評者ご本人からのお知らせで、今頃になってこの書評の存在を知った次第です。
掲載の許可を藤本先生からいただきました。
***
野呂芳男『ジョン・ウェスレー』(松鶴亭、二〇〇五年)、三四二頁
藤本満(インマヌエル高津教会牧師)
これまでウェスレー研究には二つの大きな波があった。かつて一九五〇~七〇年代に、聖書論、義認論、キリスト論、聖霊論、聖化論、教会論、聖餐論、またウェスレーとカルヴァン、ルター、英国国教会、モラビア派、ピューリタン、神秘主義との関係、と主要題目は博士論文や研究書で扱われてきた。野呂が七五年に出版した『ウェスレーの生涯と神学』は、それらの研究成果を踏まえ、かつ独自の実存的視点や教理史の知識を縦横無尽に用いてウェスレー像を集大成したものであり、もし英訳されていたら、世界におけるウェスレー研究のスタンダードとなっていた。大著の発行から三〇年経過して、ウェスレーに対する熱い思いを再び著されたことは、日本のウェスレー研究を鼓舞することとなった。
第二の波は、一九八〇年代後半から始まった。『二百年記念ウェスレー全集』(刊行中)の膨大な資料に後押しされ、コンピュータによるデータベースが可能になり、新しい展望が開けてきた。また、この時期に、神学的アイデンティティーを失った合同メソジスト教会が、ウェスレー回帰を打ち出したことも、第二波の一因となった。もっとも回帰の流れに乗って、神学者たちが自分の主義主張の「拠り所」をウェスレーに求める傾向もあり、ウェスレーが面白くもなり、また歪みもした。本書九~十章で、著者は最近の動向との対話を試みている。
本書は、三つの部門に別れる。一章でウェスレーの生涯をわかりやすく要約し、二~八章でウェスレー神学を各論的に分析し、九~十章で最近のウェスレー研究の動向と問題点を指摘する。
Ⅰ. 実存主義的解釈
各論において、著者は前作よりも明確に、ウェスレー神学を実存的視点から描くことに努めている。義認の章は、ことさら興味深かった。野呂は、ウェスレーによる「この点(義認)に関して私は、彼(カルヴァン)から髪の毛ひと筋ほども違っていない」との言葉を評して、「おそらくウェスレーは、自分がどれほどカルヴァンから遠くに立っていたかを認識していなかったのではないだろうか」(一五一頁)と解説を始める。
野呂は、宗教改革者たちが義認を「言わばその信者の全生涯を無差別に内に複妙に永遠の面から考える」、客観主義に立っていたのに対して、ウェスレーが義認を「聖化という過程の中の出発点として、その中に含ませ」ることで、「信者が絶えず罪と闘いつつあり、その信者の生活の支配的原則が神の意志に服従しようとの意欲」「主体的な決断」を強調していると説明する。つまり、ウェスレーは、神と信者との関係を「動的な、緊張をもったとらえ方」で考えている。予定論者ならば、「自分の決断とは無関係に設定された必然性の中に、信仰者の安心を見いだそうとするであろう」。しかし、「ここにウェスレー神学の実存的な厳しさがあると言っても良い。これを捨てたならば、ウェスレー神学の持ち味は薄められてしまう」(以上、一五四~六五頁)。また野呂は「ほんとうのキリスト教的な慰めは、神とのきびしい対面そのもののなかからわき出てくるのではないだろうか」(二一六頁)と実存主義的色合いをあざやかに描く。
聖化についても、ウェスレー自身は、それが漸次的に上昇する一つの直線であるかのように教えていた。ウェスレーと聖化の研究で著名なリントシュトレームも、ウェスレーの言葉をそのまま受けて直線的に聖化を説く。だが、野呂は、ウェスレーにとって「上昇する聖化の直線は、手際よくきちんと引かれうるようなものではなく、破れを内包し」、ウェスレーにとって人生の初段階の理解は、「キルケゴールと同じような、きわめて実存的なもの」(一七〇頁)であると指摘している。
時に単純すぎるウェスレーの言葉を鵜呑みにしないで、その全体像からウェスレー神学の「持ち味」を描き、ウェスレー神学の至らなかった点を配慮して解説するところは、研究者の「応用編」らしく、多くを学ばされる。評者は、実存主義のカテゴリーを使わないし、また使えない。このカテゴリーを使うとき、ウェスレー神学の「持ち味」が生かされることは確かである。――著者にとっての実存主義は、「自分を、自分の根底としてすでに与えられてしまっている神の秩序から理解し、そこに生きようとすること」であり、「自分の生形成さえも自分から根拠づけようとする意味での自由な決断ではない」(二〇四頁)。――だが、このカテゴリーを理解しない人には、それはかえって難解な解釈になり得るし、本書に出てくる「前理解」「非神話化」という用語でさえ、次の世代の神学にどの程度通用するのかも考えさせられる。
「キリスト者の完全」の教理においては、もしユングの深層心理学的分析やマルクスの階級分析が当時存在したなら、十八世紀の「ウェスレーが気づいていないような、魂の事情が明るみに出されてくるであろう」と著者は述べる。だが、この教理の核心において、ウェスレーが教えたことは神学的に妥当性があると野呂は記す。ウェスレーは「動機における純粋」「意思の統合性」を語ったが、野呂は、それを「決断という人間の実存的次元の視角」に置き換え、その視角から人間の罪を理解するとき、すなわち、もし「私たちがこの地上の生において、ある瞬間以降、決断をし続けるその方向が、いつも絶えず神に向けられているなら……私たちの決断のすべてが、過ちを除いて汚れのないものになる状態」(一八八頁)が生じてくる。
教理の重要性・正当性をこのように養護しておいて、野呂は反面、ウェスレーの完全論の欠点をも指摘する。それは、上述のような深層心理の角度からの追求ではなく、ウェスレーの完全論が「平盤」であり、「個人差を顧慮していない」という点である。キリスト者の体験を、神の恵みの大海に飛び込み、できる限り潜っていくことにたとえれば(ウェスレー自身もこのたとえを使う)、これ以上深くは潜れないというところに行き着く。その時点で、上を見れば、そこには聖化の始まりであり、下を見れば、それ以上潜れないという完全がある、と野呂は説明する。だが、この距離は、水面から測ってみれば、人によって異なっていて当然であり、また同一個人においてさえ、その深みは徐々に増し加わるはずが、ウェスレーの説明にはそうしたことへの配慮が欠けているという。評者にとっては、これはウェスレーの完全論批判として実に新鮮であった。
Ⅱ. 他のウェスレー研究者との対話
評者にとって最も読み応えがあったのは、第九章に見る、野呂と他のウェスレー研究者たちとの対話であった。氏が対話の相手として選んだのは、
①初代教会史を専門にしながら、六〇年代にウェスレーと東方教父との関連に着目し、その後、ウェスレー研究「第一人者」の立場を譲ることはなかった教会史家アウトラー
②ウェスレーと解放の神学の関連づけからウェスレー研究に着手し、一九九八年に『新創造――今日におけるウェスレー神学』を著したランヨン(米国ドルー神学校で野呂の三年後輩、その後ゲッチンゲンでゴーガルテンとティリッヒの研究で博士号を取得)
③そして、世界的に著名なプロセス神学者カブによる『恵みと責任――今日のためのウェスレー神学』(一九九五年)である。
この二書は、ランヨンが「新創造」、カブが「神の恵みに応答する人間」という、共にウェスレー神学に特徴的なテーマを軸に、その全体像をとりまとめ、なおかつ人権・貧困・女性・環境問題といった現代の諸問題からウェスレー神学の意義を浮き彫りにする、意欲的な取り組みである。アウトラーは別としても、野呂は、ランヨンやカブよりもウェスレー研究・教理史全体に深い造詣を誇る。その彼が二者をどう評価するか。評者は多大な関心をもって読んだ。
カブは、ウェスレーの「先行の恵み」の教理に注目する。堕罪以来、生まれながらの人間には善を選ぶ自由意思も良心もなくなってしまったのであるが、神は先行の恵みとしてそれらを部分的に回復させ、恵みに応答できる存在として、人間をこの世に生かしている。「先行の恵み」こそ、ルターやカルヴァンのように、救いを与える神とそれを信じる人間の関係を排他的に・予定論的には考えなかったウェスレー神学の特徴であり、それが故にカブは自著に『恵みと責任』という題名をつけたことを、野呂は的確に指摘する(二四一頁)。だが、カブは神が聖霊によってすべての人に理性や良心を与えているというウェスレー考えの中に、プロセス思想から来る「神の内在」を巧みに織り交ぜてくる。野呂は、カブの背後にあるホワイトヘッド哲学にまで遡り、カブの解釈が歪んでいく過程を説明する。「カブによると、ウェスレーはちょうどホワイトヘッドと同じように、人間の自由意思を損なわずに完全の聖化まで人間を導いていく、時間の中に内在する神を強く主張した神学者になる」(二四四頁)。
ランヨンは、ウェスレーの救済論が個人だけでなく、社会的視野、さらには宇宙的な次元までも含んでいることを強調した。そもそも、救いは罪の赦しの宣言だけではなく、破壊された人間の中の「神の像」の回復過程であることは、ウェスレーの聖化論に顕著である。そして、これに東方教会との関連づけを与えたのはアウトラーであった。だが、アウトラーが「新創造」を主に個人の聖化に集中させて理解したのに対して、ランヨンは社会的次元に重きを置いているという印象を野呂は抱く(二三四頁)。評者も同感である。当然、ここで聖化論は終末論と結びついている。すなわち、人間の歴史の流れの中で、将来から現在に攻めって来る神の国こそが、聖化を実現していく神の力である。ここで野呂のランヨン評は、評者もまたランヨンを読んで漠然と疑念を抱いていた印象を明確に論理化してくれた。すなわち、ランヨンが終末と結びつけて聖化を語るとき、あたかも「人間の持つ宿命成就的主体性がまるで存在しないかのように、それとは無縁であるかのように、神学において向こう側から人間を捕らえてくる神の働き」(二五七頁)として描いている感が強い。そういう主体的な生き方の選択なしに、信仰義認、そして個人と社会との次元における聖化を語ることは、カルヴァン主義者たちの路線であり、「現代神学の分野で言えば、バルトを延長したモルトマンの路線によるウェスレー解釈と言っても良いかも知れない」(二五九頁)。ランヨンは解放の神学を通してモルトマンとの親交があり、後者は前者を通してウェスレーの聖化を高く評価するようになった(参・『いのちの御霊-総体的聖霊論』)。
野呂のランヨン批判に、実存的思考が反映されていることも事実である。だが、ウェスレーの場合には、終末から社会を変革する神の働き以上に、「個人の信仰体験が深まり、ひとりひとりの完全の追求によって、その人びとのいる社会全体が大きく変化し、そこにこれまでにない宗教的な雰囲気が作り出されることを認め、かつ喜んでいるふしがある」(二七一頁)との野呂の観察は妥当であり、こちらが正統なウェスレー論であると評者は考える。
Ⅲ. 現在のウェスレー研究を二分する論争
最終章に至って、察しの悪い評者は、野呂が近年のウェスレー研究を二分する大きな問題に積極的に関わっていることに気がついた。それは、ウェスレーの福音的回心、アルダスゲイト体験をどう解釈するかである。
ウェスレーは、一七二五年のオックスフォード時代、ア・ケンピスやJ・テイラーなどに触れて、生涯と心を神にささげ、「第一の回心」を体験した。神聖クラブを率い、ジョージアに宣教に赴き、聖くあろうとする自分に絶望し、帰英する。その彼は、入植地でモラビア派から信仰義認を学び、アルダスゲイト街でもたれた集会で三八年に信仰義認を体験する。これが「第二の回心」である。
だが、その後も聖化の強調が全く衰えないことから、「第一の回心」の方に重きを置く研究者(特にカトリック)も少数ながら存在した。さらに一七六〇年代にカルヴァン派との論争が激化する中で、ウェスレーは信仰義認とキリストの義の転嫁の教えに安住して、聖化や修練の追求を否定する当時の「福音派」を「信仰至上主義者」と批判するようになる。加えてこの時期、ウェスレー神学は、「後期ウェスレー」と呼ばれる独特な進展を見せる。すなわち実生活の諸問題、社会問題、英国全体の文化風習の問題など、神学の活動範囲が広がる。
この経緯を踏まえて、アウトラーは「前期」「中期」「後期」ウェスレーという区分を設け、これが現在では定説となっている。ウェスレー神学における「後期」の独特な発展は、「前期」に回帰したものではなく、「神学者として成熟期」と捉えるのが一般的であって、野呂がこれを「第一の回心」「第二の回心」「第三の回心」という「回心」区分として批判することは(たとえそれに反対であっても)、誤解を招く。その意味で、野呂の清水に対する批判は妥当ではない(二九八頁)。
こうした混乱はさておき、ここで野呂は重要な課題と論議を交えている。「アウトラーにしろランヨンにしろマドックスにしろ、これらのウェスレー神学の研究者たちは、ウェスレーを世界観的に考察しているように私には思えて仕方がない」(二九九頁)。野呂は、アウトラーに始まる最近の研究者たちが、ウェスレーにおけるギリシャ教父の影響を強調するあまり、アルダスゲイトに代表されるような、ウェスレー神学の持つ「主体的・実存的姿勢を見失ってしまった」と述べる。同時に、ギリシャ教父に特有な神秘主義を極力警戒していたウェスレー像も、近年の研究では影を薄くしていると言う。
近年、ウェスレー研究の最大の論議が、アルダスゲイト解釈にあったことは述べた。日本ウェスレーメソジスト学会でも、この問題を取り上げてきた。一般的に、ウェスレーの生涯にわたってアルダスゲイト体験の意義を認めようとする学者は、東方的救済論の中で、メソジストの信仰復興運動を立ち上げた活力のようなものが見失われることを懸念する。だがそこに固執すると、ウェスレー神学の持つ「広がり」を見失う傾向もある。野呂は、「実存」というカテゴリーをもってこの論争に自らの判断を下していることは興味深い。
本書を読み終えて、評者が尋ねてみたいことは、前期ウェスレーと中期ウェスレーに詳しい著者だが、アウトラーを中心に着目されてきた後期ウェスレーの進展(『二百周年記念全集』一巻序文)、特にそれが世界観の変遷ではなく、論争に巻き込まれ、英国の文化世相の実情の中で、「神学者として実存」をかけての変遷であるとしたら、氏が後期ウェスレーをどのように評価するか、である。