| ドイツの大学
ドイツの子供たちは4年間(州によって異なる場合あり)の小学校教育を終えた段階(10歳)で、将来大学へ行くか、あるいは職業能力を身につけて就職するかという選択に迫られる。将来の希望進路に合わせて学校の種類を選ばなければならない。ドイツで大学に入るには、Gymnasiumという学校でAbitur(大学入学資格)を取得する必要がある。Gymnasiumというのは日本でいえば、小学校5年生から高校3年生までをまとめたような学校。大学へ行くための一般的なコースで、在学年数は12~13年。大学の入学試験はなく、Abiturを取れば(GymnasiumでAbitur取得試験に合格して卒業すれば)、原則として試験なしで希望の大学に入ることができる。
上記の大学入学までの道のりを経ず、外国からドイツの大学に留学したい場合は、本サイトの(「入学までの流れ」に沿って手続きを踏んでいくことになるが、まずはドイツの大学について簡単に説明しておこう。
ドイツ国内で公的に「大学」と認定されている高等教育機関は2022年3月現在で423校ある(Statistisches Bundesamt
英語のUniversityと同義語ととらえてよく、総合大学のこと。医学系、自然科学系、人文科学系、法学系などさまざまな学部学科を擁しており、基礎研究や応用研究など純粋な「学問」に力点が置かれている。 大学での授業は教授が一方的に講義をする講義形式の科目(Vorlesung)と、小人数でディスカッションを行い、研究発表や論文作成を行うゼミナール形式の科目(Seminar,Übung,Tutorium)があり、これに企業等でのインターンシップが加わる場合がある。 大学で得られる学位は、従来は自然科学、工学、社会科学、経営系の学科ではDiplom、人文科学系と社会科学系の一部の学科ではMagisterが授与されてきた。いずれもいわゆる修士に当たり、その後にDoktor、更にその先に教授資格を得ることができるこうしたドイツの旧来の学位取得コースは、近年の大学改革で大きな岐路を迎えた。1999年に採択された(ボローニャ宣言で、2010年までにすべての学科で、国際的に最も一般的なBachelor/Master(BA/MA)コースに移行することが謳われ、大学改革が行われた結果、現在は一部の例外を除いてBA/MAコースに移行した。 従来のDiplomやMagisterを取得するまでに要する期間は最短でも4年半。しかし4年半で学業を終える学生は殆どおらず、平均すると6年程度はかかり、卒業までの長い道のりは特に近年高い教育行政負担金からも問題となり、「いつ卒業できるかわからない」システムに苛立ちを覚える学生も多かったが、BA/MAコース(学士/修士コース)では、BAは通常3~4年で取得することができ、更に1~2年でMAを取得できる。
日本語にすれば「専門大学」で、ある分野に限定された学部学科で成り立っている。Universitätとはその他の点でも大きく異なる。Fachhochschule(FH)では、純粋な「学問」に力点が置かれるUniversitätとは異なり、より実践面が重視されている。卒業後に就く職業に必要な専門的で高度な訓練や実習を早い時期から行うので、就職に直結させることができる。FHはあくまでも「大学」と位置付けられており、設備もUniversitätと同様充実しており、自治権も保証されている。 大学での授業は講義形式の科目(Vorlesung)とゼミナール形式の科目(Seminar, Übung,Tutorium)があり、学業の後半に置かれるSeminarの内容は実践的な要素が強い。また、職業実習(Praktikum)も授業の重要な1つと捉えられており、入学前の職業実習(インターンシップ)が義務付けられている場合が多い。 FHで得られる従来の学位はDiplom(FH)と、カッコ付きの(FH)でUniversitätと区別されていたが、学位としては同等の価値が認められていた。ボローニャ宣言による大学改革で学位名称はUniversitätと統一され、BachelorおよびMasterとなった。 FHでの最初の学位取得までの期間はUniversitätに比べて一般的に1~2学期(半年~1年)ほど長くなる。これはFHの学業が、より独自性が強く職業能力取得と結びついているためである。就職に有利という利点が働いて、大学の全就学者数のうちFHで就学する学生数の割合は年々増加を辿り、2021年には38.2%に達し、Universitätの就学率(60.5%)との差を縮めている。 出典:datenportal von Bundesministerium für Bildung und Forschung
文字通り、美術、映画、演劇、音楽といった芸術・芸能部門に特化された学科から構成された大学。ここでの修学内容は実技が中心で、芸術家や芸術系の教員を養成することを主眼としており、入学に際しては実技試験や作品製作が求められる代わりに、秀でた才能と技術を持つ場合、一般の大学では必須となっている大学入学資格の有無を問われない場合もある。 音楽や美術系の学科はUniversitätに開設されていることも多いが、Universitätでは理論的、哲学的、歴史的な観点から学問としてアプローチするのに対し、MusikhochschuleやKunsthochschuleでは実技に重点が置かれる。
このサイトではこれらの大学タイプのうち、UniversitätとFachhochschuleについて扱っている。
 ボローニャ宣言 ボローニャ宣言ドイツの大学では卒業までに長期間要すること、ヨーロッパ各国の大学が与える学位がそれぞれ異なり比較が難しいこと、単位制が行われていないために外国の大学で取得した科目の認定に手間がかかることなど、国を越えた大学間の交流に立ちはだかる様々な弊害を取り除き、ヨーロッパの大学間で学位取得のための共通する統一規格を設け、一丸となって国際競争力をつけることを目差したボローニャ宣言が1999年に欧州29カ国の教育相によって採択された。 ボローニャ宣言では、条文の内容が2010年までに実行されることが謳われ、ドイツの大学もボローニャ宣言に沿ってヨーロッパ標準の規格作りという大規模な改革が行われた。例えばドイツの大学での伝統的な学位取得課程であったDiplomやMagisterは、2010年までに全てヨーロッパ統一規格としてBachelor/Masterコースにほぼ移行された。
外国の大学との垣根をなくすために、これまでより短期間で修得できるBA(Bachelor)の設立、外国の大学で修得した単位のスムーズな互換、英語での授業の実施や英語による論文作成、教科選択の柔軟性、大学での外国人向けのドイツ語教育の充実といったことから、ドイツ在留許可の簡略化や修学中のアルバイト規制の緩和といったことにまで改革は及び、ドイツの各大学は「留学生に優しい大学」を目差し、実現している。
大学間交流柔軟化の極めつけがこのソクラテス/エラスムス・プログラム。ヨーロッパではユーロによる通貨統合をはじめとしたあらゆる面での統合が行われ、学術研究、職業実習、スポーツ交流などの幅広い分野でも「ソクラテス・プログラム」の名の下にヨーロッパ諸国の間でのボーダーレスの壮大な交流、交換プロジェクトが2000年より行われている。 このプログラムの一環として、大学など高等教育機関の交流・交換を促進するのが「エラスムス・プログラム(ERASMUS Programm)」。これに参加するヨーロッパの大学間では、幅広く柔軟な単位互換や試験認定制度が実施されている。 学生達は在学期間中の一定の期間(3~12か月)をこのプログラムを使って授業料免除を受けたうえに様々な奨学金制度を利用して、自由にヨーロッパのプログラム参加大学で学び、単位を取得することができる。同時に教職員の交流も積極的に行われている。 ドイツの殆どの大学もこのエラスムス・プログラムに参加しており、1つの大学がこのプログラムによって協定している大学数は、100から場合によっては500校にも及ぶ。エラスムス・プログラムで結ぶ協定は手続きも簡単で、大学間同士で個別に協定を結んでいた従来のやり方に比べ、協定校の数は爆発的に増え、これを利用した留学生の欧州域内での行き来が盛んにおこなわれている。
ドイツの大学では授業料は原則として無料だが、2000年以降の大学改革の流れの中で、授業料導入計画が持ち上がり、一時はドイツの国立大学全体の70%(西側に限れば90%)で授業料が徴収された。 これは、それまで規定在学期間を超える長期在学の学生などに限って徴収されていた授業料が、2004年に「Diplom等最初の学位取得までの課程での学費導入を全国的に禁じる」法律の違法性をめぐって連邦憲法裁判所で争われていた公判の結果、2005年1月に学費導入へのゴーサインが出されたことが発端となっていた。 授業料のかからない州の大学へ学生が集中するという弊害なども起きていたが、その後の選挙による州の政権交代や市民運動などにより、授業料を徴収する州は減り、2012/13冬学期からはバイエルン州とニーダーザクセン州を除き、全国的に授業料は無料に戻り、2013/14冬学期からはバイエルン州でも授業料廃止が承認された。 再びドイツの大学の授業料はタダの時代になったが、2021年現在でバーデンヴュルテンベルク州の大学のみ、EU加盟国以外からの外国人に対して授業料を課している。ドイツの財政状況に余裕があるわけでは決してなく、EU加盟国の財政危機などの煽りや選挙結果によっては、特に外国人学生に対しては再び授業料が導入される可能性はある。
(Erststudiumの規定在学期間/2022)
上述のように、ドイツの大学は外国からの留学生を積極的に受け入れるという趣旨の下、授業での主要な使用言語となるドイツ語の語学力向上をサポートするためにドイツ語コースを併設している。大学併設のドイツ語コースには大きく分けて、 授業並行型ドイツ語コース
ドイツ語試験(DSH)に合格して正規の授業を受けている外国人が、更に語学力のレベルを向上させるために設けられているコースで、正規の授業と並行して受講する。
いくらDSHに合格しても、特に留学開始当初は講義内容を十分に理解したり、ゼミナールでスムーズなディスカッションを行うのはまだまだ厳しい。できるだけ早くこうした授業に適応できる語学力を身につけるために、このドイツ語コースは役に立つ。
コースの内容は大学によって大きく異なる。語学コースが充実している大学では、学科毎に異なった語学コースがあって、自分の専攻分野に則したドイツ語表現を中心に勉強することができる。小規模な大学では、全学共通のドイツ語コースだけしか設けられていない場合も多い。
授業並行型ドイツ語コースはほぼ全ての大学で開設されているが、大学によっては受講対象者を交換留学生など特定の学生に限っていたり、交換留学生以外は受講料を徴収したりするところもある。コースの有無や受講資格、内容の詳細は各大学のホームページ等で調べること。
DSH準備コース
大学の専門課程への入学許可を得るための条件として求められる試験、DSHを受験する学生を対象に行われているドイツ語コースで、学期単位で開講される。このコースの受講生はまだ学部の正規学生ではないので、学部の正規の授業は受けられない。DSHはかなりハイレベルの試験(C1レベル)で、問題形式はドイツのどの大学でも同じだが、それぞれの大学が独自に作成するので、大学毎に問題の傾向は異なっている。
このドイツ語コースは全ての大学に設けられているわけではなく、開設されている場合も内容やシステムは大学によって大きく異なる。受講を希望する場合は、志望大学のドイツ語コースの情報をよく確かめること。
ドイツの大学の多くは初級もカバーしたドイツ語コースを開設している。料金は民間の語学学校に比べて割安だし、その大学のDSHに直結しているのでDSHの準備にも適している。また、大学の施設を使えるなどのメリットも多い。
語学コースはその大学への留学希望者を対象としていることが多いが、大学とは別組織として語学学校のような形で運営されている場合もあり、このような機関では語学学習だけが目的の受講も可能。大学が提供するドイツ語コースの一例を下表に載せておく(2022.5現在)。他にも多くの大学でドイツ語コースを提供している。大学名+"Deutschkurse", "Deutsch als Fremdsprache"などをキーワードに検索すれば、お目当ての大学のドイツ語コースの情報を得ることができるので試してみよう。
|
最新の画像[もっと見る]
-
 やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
-
 やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
-
 やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
-
 やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
-
 やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
-
 やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
-
 やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
-
 やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
-
 やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
-
 やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
やめよう!エスカレーターの片側空け★東京では右側に立とう!(2021.9.23)
2日前
「ドイツ留学相談室」カテゴリの最新記事
 ドイツ留学相談室
ドイツ留学相談室 留学体験記メニュー
留学体験記メニュー 留学体験記 Uni-Lüneburg, Uni-Münster, Uni-Rostock, Uni-Trier, Uni-Würzburg
留学体験記 Uni-Lüneburg, Uni-Münster, Uni-Rostock, Uni-Trier, Uni-Würzburg 「大検」(現:高卒認定)でのドイツ留学
「大検」(現:高卒認定)でのドイツ留学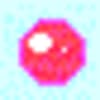 ドイツ語研修便利帳ーホームステイ
ドイツ語研修便利帳ーホームステイ 「ドイツ留学相談室」について
「ドイツ留学相談室」について 「お薦めの場所&お店」メニュー
「お薦めの場所&お店」メニュー お薦めの場所&お店 Wienとその近郊
お薦めの場所&お店 Wienとその近郊 お薦めの場所&お店 (Mainz, München, Münster, Oberhausen, Salzburg, Weimar)
お薦めの場所&お店 (Mainz, München, Münster, Oberhausen, Salzburg, Weimar) お薦めの場所&お店 (Düsseldorf,Essen,Frankfurt,Hannover,Heidelberg,Köln)
お薦めの場所&お店 (Düsseldorf,Essen,Frankfurt,Hannover,Heidelberg,Köln)














