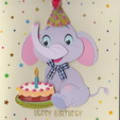2010年6月12日(土)、奥州市水沢公民館(水沢区字聖天85-2)で開催中の水沢盆栽会(桐田斎=ただし会長、会員23人)主催の「さつき・山野草展」に行ってきました。サツキ(皐月)と山野草を合わせて80点ほど展示されていましたが、それらの中にアワモリショウマ(泡盛升麻)が1鉢だけありました。



アワモリショウマ(泡盛升麻) ユキノシタ科 チダケサシ(アスチルベ)属 Astilbe japonica
ショウマとは生薬の升麻のことで、日本ではキンポウゲ科のサラシナショウマの根茎を利用することから、よく似た葉や穂状の花を咲かせる植物にこの名がつけられている。従って、ユキノシタ科チダケサシ属のほかにも同じユキノシタ科の別属にキレンゲショウマ、キンポウゲ科にレンゲショウマやルイヨウショウマ、バラ科にヤマブキショウマAruncus dioicus var.tenuifoliusなど、ショウマと名がつく植物が多数ある。
チダケサシ属は東アジアを中心に約20種あり、日本には6種あるが、山野草として栽培される小型のものにアワモリショウマ、ヒトツバショウマ、ヤクシマショウマ、チダケサシ、アカショウマなどがある。海外では改良が盛んに行われ、多数の園芸品種が作り出されているが、草丈が高いものは鉢植えには向かない。[講談社発行「山野草大百科」より]
特徴:山の谷間や渓谷沿いの岩上に生える多年草。葉は3回3出複葉で、縁には鋸歯をもつ。花茎は高さ50~80㎝となり、茎先に白色の小花を、まるで泡が集まったように穂状に咲かせることから名が付いた。近縁種にトリアシショウマAstilbe thunbergii var.congesta、ヤマブキショウマ、ミヤマヤマブキショウマAruncus dioicus var.astilboides、アポイヤマブキショウマAruncus dioicus var.subrotundusなどがある。花期:5~7月。分布:本州(中部地方以西)、四国、九州。
栽培:日に当てて育て、冬期は簡単な霜除けを施すか軒下などに取り込む。灌水は水切れすると葉先を傷めるので表土の乾き具合を見ながら行う。肥料は春・秋に置き肥するほか、薄い液肥を与える。根づまりしやすいので、植え替えは春か秋に、2年に1回を目安として硬質鹿沼土・軽石・桐生砂の混合土で中深鉢に水はけ良く植え付ける。増殖は株分けか実生。[栃の葉書房発行「別冊趣味の山野草・山草図鑑」より]