戦争とさまざまな画像の関係について考えるための本
編集委員 小笠原 慶彰
『改訂版 写真記録 これが沖縄戦だ』
大田昌秀編、琉球新報社発行・那覇出版社発売
1983年 1,785円
『敵の顔―憎悪と戦争の心理学』
サム・キーン著、佐藤卓巳・八寿子訳、柏書房(パルマケイア叢書)
1994年 4,660円
『戦争がつくる女性像―第二次大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』
若桑みどり、ちくま学芸文庫
2000年 998円
戦時、平時を問わず、さまざまな画像が「戦争」を前提とした国威発揚のためのプロパガンダに活用されてきた。一般市民は、それによって正確な事実を説明され、冷静な判断を求められるのではなかった。作られた虚像に踊らされ、人生を翻弄されたのだ。だが今日、そのような史実を理解し、逆にさまざまな画像を有効に活用して、平和維持に役立てられないだろうか。本号特集の意図は、そこにある。
ところで、今月は6月。それに戦争といえば、まず沖縄を思う。そんな時、本誌4月号にも登場した元沖縄県知事大田昌秀さんが編んだ『写真記録 これが沖縄戦だ』を手にしたい。本書は、表題の
ように写真を多用している。77年の初版を83年に改訂し、その後も息長く増刷されてきた。まだ大手書店には在庫もある。主として米国側撮影の写真を利用しているが、だからといって米国に都合の良い内容になっているというわけではない。とにかく沖縄戦、いや一般市民を巻き込む戦闘の結果をイメージする便よすが
として相当に有効である。
ところで、本書の表紙については、後日談がある。おかっぱ頭の「少女」がうつろな目をして血まみれで座りこんでいる写真である。キャプションにも「少女」とある。だが事実は、当時12歳の少年であった。84年に写真を見た本人が大田に直接申し出た。彼は、息子が皇軍に利用されることを嫌った父親によって「少女」にされていた。そうした努力にもかかわらず、この子は、家族の食料を奪いにきた皇軍兵士に抗い、そのため暴行された。写真は、米軍の治療を受けていた時に撮影されたものであった。その時の傷は、身体障害として残った。それなのに、日本政府は補償を拒否した。そうした事実が本書をきっかけに明らかにされ、マス・メディアでも紹介された。そして今、その男性は「語り部」となり、1千200回を超す活動を続けている。一枚の写真から始まった物語である※。
だが、この沖縄戦の記録を見ていて奇妙な感覚に囚われるのは、子どもや女性、さらに敵兵たる皇軍兵士にさえ親切な米兵の写真が出てくることである。もちろん今では、当時のスローガン通りの「鬼畜米英」などではなかったことは良く知っている。しかし、まだ戦闘が終結していない時期に、すでに親切な兵士の写真を撮影する必要があったのか。あるいは、そういった視覚的なイメージを流布させようとする目的が何かあったのだろうか。
そのことを考える上でサム・キーン『敵の顔︱憎悪と戦争の心理学』(パルマケイア叢書)は、もってこいである。キーンは、人類を敵対人(ホモ・ホスティリス:敵を作り出す存在)と定義している。つまり、自分たちと同じ人間を敵だと思わせることは簡単で、そうなれば殺させることも容易なのである。そのためにさまざまな画像が、戦争あるいは支配を目的として「敵の顔」を作り上げることに利用された。本書では、実際に使われた事例を通して分析を行っている。そこでは「敵の顔」は、全く人間的でない、おぞましい顔として表現された。実像からかけ離れたイメージを作り、「恐るべき敵」に仕上げていく。敵意はイマジネーションによる集団心理の操作なのである。それによって、敵と味方という二元論が世に支配的な思考形式になる。だとすれば、反対に「敵の顔」の実像、それも恐ろしくない実像が流布されれば、敵意は喪失するのか。それが米国側提供写真の撮影意図なのか、それとも大田の編集意図なのか。
いずれにしても、さまざまな画像が、どのようにして「敵の顔」を作り上げていくかを知ることは重要だ。それによって、戦時の敵に限らず平時の敵つまり差別や排除の対象に対して、心底にある差別心や敵意も自覚できる。その自覚は、ひょっとすれば親愛人(ホモ・アミクス:寛容な存在)に向けての自己変革を可能にさせるのではないか、と希望を感じさせてくれる。「パルマケイア」とは、毒の精から変じて薬の精、つまり毒もまた薬になる意であり、本書がそのシリーズに入れられていることは、さまざまな画像も使いようということを暗示しているようだ。
さて、毒もまた薬になるとして、次は、薬と信じて毒を飲むという話である。第二次大戦下、女性はどういうイメージとしてさまざまな画像に登場していたか。若桑みどりさんは『戦争がつくる女性像』で、戦時下に160万部の発行部数を誇った、つまりそれだけ市民に影響を及ぼしていた『主婦の友』を中心とする婦人雑誌の表紙や口絵を分析している。著者は、どこの国でも、戦争中に女性の果たす役割は、以下の3つだという。つまり、第1に「母性」、第2に「補助的労働力」、第3に「チアリーダー」である。事実、表紙や口絵は、子どもを生み育てよ、勤労奉仕に汗を流せ、「戦争に行け」と言い続けよと鼓舞しているイメージなのだ。かくて、戦争中の婦人雑誌は、戦時下女性の役割が巧妙に視覚化し、市民、とりわけ女性に植え付けていった。これはあからさまに「敵の顔」を宣伝するポスターではない。薬と信じて飲んだのが、後になってみれば、じわじわと効いてくる毒であったとわかる完全犯罪仕掛けだったということである。これは相当恐ろしい。
最後に戦争遺跡関連本を考えよう。冒頭述べたようにさまざまな画像を有効に活用して、平和の維持に役立てるとすれば、これらを忘れてはならない。安島太佳由『訪ねてみよう! 日本の戦争遺産』(角川SSC新書2009)や戦争遺跡保存全国ネットワーク(http://homepage3.nifty.com/kibonoie/isikinituto.htm)編『保存版ガイド日本の戦争遺跡』(平凡社新書2004)等は、全国津々浦々の戦争遺跡ガイドブックである。だがこれらは、写真が多用されており、それによって文字からとは異なったメッセージを訴える。戦争とは、莫大なエネルギーと人命の浪費であり、その事実は、ほとんど知られぬままに見事に忘却されるものなのだと。
※注 このエピソードは、大田昌秀『沖縄戦を生きた子どもたち』(クリエイティブ21・2007)に詳しく紹介されている。
編集委員 小笠原 慶彰
『改訂版 写真記録 これが沖縄戦だ』
大田昌秀編、琉球新報社発行・那覇出版社発売
1983年 1,785円
『敵の顔―憎悪と戦争の心理学』
サム・キーン著、佐藤卓巳・八寿子訳、柏書房(パルマケイア叢書)
1994年 4,660円
『戦争がつくる女性像―第二次大戦下の日本女性動員の視覚的プロパガンダ』
若桑みどり、ちくま学芸文庫
2000年 998円
戦時、平時を問わず、さまざまな画像が「戦争」を前提とした国威発揚のためのプロパガンダに活用されてきた。一般市民は、それによって正確な事実を説明され、冷静な判断を求められるのではなかった。作られた虚像に踊らされ、人生を翻弄されたのだ。だが今日、そのような史実を理解し、逆にさまざまな画像を有効に活用して、平和維持に役立てられないだろうか。本号特集の意図は、そこにある。
ところで、今月は6月。それに戦争といえば、まず沖縄を思う。そんな時、本誌4月号にも登場した元沖縄県知事大田昌秀さんが編んだ『写真記録 これが沖縄戦だ』を手にしたい。本書は、表題の
ように写真を多用している。77年の初版を83年に改訂し、その後も息長く増刷されてきた。まだ大手書店には在庫もある。主として米国側撮影の写真を利用しているが、だからといって米国に都合の良い内容になっているというわけではない。とにかく沖縄戦、いや一般市民を巻き込む戦闘の結果をイメージする便よすが
として相当に有効である。
ところで、本書の表紙については、後日談がある。おかっぱ頭の「少女」がうつろな目をして血まみれで座りこんでいる写真である。キャプションにも「少女」とある。だが事実は、当時12歳の少年であった。84年に写真を見た本人が大田に直接申し出た。彼は、息子が皇軍に利用されることを嫌った父親によって「少女」にされていた。そうした努力にもかかわらず、この子は、家族の食料を奪いにきた皇軍兵士に抗い、そのため暴行された。写真は、米軍の治療を受けていた時に撮影されたものであった。その時の傷は、身体障害として残った。それなのに、日本政府は補償を拒否した。そうした事実が本書をきっかけに明らかにされ、マス・メディアでも紹介された。そして今、その男性は「語り部」となり、1千200回を超す活動を続けている。一枚の写真から始まった物語である※。
だが、この沖縄戦の記録を見ていて奇妙な感覚に囚われるのは、子どもや女性、さらに敵兵たる皇軍兵士にさえ親切な米兵の写真が出てくることである。もちろん今では、当時のスローガン通りの「鬼畜米英」などではなかったことは良く知っている。しかし、まだ戦闘が終結していない時期に、すでに親切な兵士の写真を撮影する必要があったのか。あるいは、そういった視覚的なイメージを流布させようとする目的が何かあったのだろうか。
そのことを考える上でサム・キーン『敵の顔︱憎悪と戦争の心理学』(パルマケイア叢書)は、もってこいである。キーンは、人類を敵対人(ホモ・ホスティリス:敵を作り出す存在)と定義している。つまり、自分たちと同じ人間を敵だと思わせることは簡単で、そうなれば殺させることも容易なのである。そのためにさまざまな画像が、戦争あるいは支配を目的として「敵の顔」を作り上げることに利用された。本書では、実際に使われた事例を通して分析を行っている。そこでは「敵の顔」は、全く人間的でない、おぞましい顔として表現された。実像からかけ離れたイメージを作り、「恐るべき敵」に仕上げていく。敵意はイマジネーションによる集団心理の操作なのである。それによって、敵と味方という二元論が世に支配的な思考形式になる。だとすれば、反対に「敵の顔」の実像、それも恐ろしくない実像が流布されれば、敵意は喪失するのか。それが米国側提供写真の撮影意図なのか、それとも大田の編集意図なのか。
いずれにしても、さまざまな画像が、どのようにして「敵の顔」を作り上げていくかを知ることは重要だ。それによって、戦時の敵に限らず平時の敵つまり差別や排除の対象に対して、心底にある差別心や敵意も自覚できる。その自覚は、ひょっとすれば親愛人(ホモ・アミクス:寛容な存在)に向けての自己変革を可能にさせるのではないか、と希望を感じさせてくれる。「パルマケイア」とは、毒の精から変じて薬の精、つまり毒もまた薬になる意であり、本書がそのシリーズに入れられていることは、さまざまな画像も使いようということを暗示しているようだ。
さて、毒もまた薬になるとして、次は、薬と信じて毒を飲むという話である。第二次大戦下、女性はどういうイメージとしてさまざまな画像に登場していたか。若桑みどりさんは『戦争がつくる女性像』で、戦時下に160万部の発行部数を誇った、つまりそれだけ市民に影響を及ぼしていた『主婦の友』を中心とする婦人雑誌の表紙や口絵を分析している。著者は、どこの国でも、戦争中に女性の果たす役割は、以下の3つだという。つまり、第1に「母性」、第2に「補助的労働力」、第3に「チアリーダー」である。事実、表紙や口絵は、子どもを生み育てよ、勤労奉仕に汗を流せ、「戦争に行け」と言い続けよと鼓舞しているイメージなのだ。かくて、戦争中の婦人雑誌は、戦時下女性の役割が巧妙に視覚化し、市民、とりわけ女性に植え付けていった。これはあからさまに「敵の顔」を宣伝するポスターではない。薬と信じて飲んだのが、後になってみれば、じわじわと効いてくる毒であったとわかる完全犯罪仕掛けだったということである。これは相当恐ろしい。
最後に戦争遺跡関連本を考えよう。冒頭述べたようにさまざまな画像を有効に活用して、平和の維持に役立てるとすれば、これらを忘れてはならない。安島太佳由『訪ねてみよう! 日本の戦争遺産』(角川SSC新書2009)や戦争遺跡保存全国ネットワーク(http://homepage3.nifty.com/kibonoie/isikinituto.htm)編『保存版ガイド日本の戦争遺跡』(平凡社新書2004)等は、全国津々浦々の戦争遺跡ガイドブックである。だがこれらは、写真が多用されており、それによって文字からとは異なったメッセージを訴える。戦争とは、莫大なエネルギーと人命の浪費であり、その事実は、ほとんど知られぬままに見事に忘却されるものなのだと。
※注 このエピソードは、大田昌秀『沖縄戦を生きた子どもたち』(クリエイティブ21・2007)に詳しく紹介されている。


















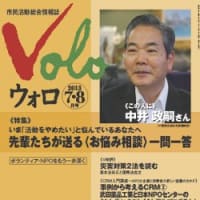
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます