献体について考えるための本
編集委員 小笠原 慶彰
氏家幹人『大江戸死体考-人斬り浅右衛門の時代』
平凡社新書. 1999. 714 円
香西豊子
『流通する「人体」-献体・献血・臓器提供の歴史』
勁草書房. 2007. 3500円+税
アニー・チェイニー著・中谷和男訳
『死体闇取引-暗躍するボディーブローカーたち』
早川書房. 2006. 1600円+税
吉村昭「梅の刺いれずみ青」(『島抜け』新潮文庫・所収)は、明治初期から中期にかけての人体解剖を描いている。表題は、篤志解剖第1号とされる遊女が腕に梅の刺青をしていたことを指している。明治2年のことであった。小説とはいえ、新政府によって西洋医学が認知された後でも、解剖用死体の確保が困難を極めたことがよくわかる。それは日本人の死生観が、たとえ死後であっても身体を切り刻むこととなかなか相容れないためだろうと想像できる。
ところで、江戸時代には、死体に相当無頓着であったらしい。『大江戸死体考』によれば、水辺に土左衛門が漂っていたとか、道端には行き倒れが目に付いたとかで、死体がゴロゴロしていたというのだ。こんな状況だから死体検死の役人も忙しく、すでに何種類もあった検死マニュアルに準拠しながら処理した。だが、いくら死体がゴロゴロといっても、ただ冷ややかに眺められていただけかというとそうでもない。その死体を腑分けするとなると、つまり刃物でもって切り刻むとなると俄然話は違ってきて、強い拒否反応が起きたということのようだ。ところが、それが刑死体の場合は、また違う。まったく物扱い同然になるのだ。この辺りの機微は、とうてい現代の感覚では推し量れない。
たとえば、刑死体で刀剣の様斬りをする据物師という専門家がいた。将軍家や大名家から依頼され、刑死体によって刀剣の切れ味を確かめた。様斬りの注文は頻繁であったが、ある時期から代々世襲の山田浅右衛門が、ほぼ独占していた。山田家は、浪人ながら裕福であった。というのは、死体から胆を取り出して製造する薬も販売していたからである。その人胆丸と称される高価な漢方薬の製造は、明治に至ってようやく禁じられたという。
一方、幕末に刑死体による人体解剖がたびたび許されるようになると、医師と据物師との間で死体の取り合いになっていく。そして明治以後は、様斬りも廃止され、医師が独占して解剖用にのみ利用されていく。だが実際、死体の確保は大変だったらしい。
このような事情を踏まえた上で『流通する「人体」』では、死体を「資源」と捉えて、その流通システムという視点から献体を描いている。帯には「江戸末期から現在に至る『人体』流通システムを追いながら、『善意による無償提供』『自己決定』といったヒト組織利用に関する倫理的根拠が、そもそも資源調達の経済論的帰結であることを描き出す」とある。つまりは「ほしい人がいて、タダででもあげたい人がいて、丸く収まってんだからいいじゃん」っていうことか。だとすると、妙に納得させられてしまうが、引っ掛かるものもある。その奥歯に挟まったものは、「人体標本展」に言及された部分に至って取り除かれる。つまり、「ほしい︱タダであげたい」の関係が「ほしい︱お金を払ってくれるんならあげてもいい」と変形する可能性を示唆してくれるからだ。だが現在の日本では、合法的な死体の利用となると、本人や遺族の意思尊重は当然として、「無報酬」を抜きにはとても賛同されないだろう。
ところで、本人の意思や無報酬とはお構い無しに死体流通ビジネスが半ば公然と存在している国もあるらしい。『死体闇取引』は、アメリカにおけるその実態についてのルポルタージュである。本書冒頭の「死体部位別価格一覧表」には、度肝を抜かれる。たとえばこんな具合である。頭部550ドル~900ドル、脳500ドル~600ドル、肩(片方)375ドル~650ドル、胴体1千200ドル~3千ドル、死体一体4千ドル~5千ドル、各種臓器(一個)280ドル~500ドル等々。
死体は、解剖実習用にだけ用いられるのではない。医療機器メーカーの新製品実演販売用として、骨ペーストや骨ねじの原料用として、地雷防護服の強度実験用として、その他多くの用途が白日の下に曝されている。このような利用は、もちろん本人の意思あるいは遺族の合意に沿っていない。さらにその上、死体の需給関係は、不法あるいは不法すれすれの死体流通によって満たされる。たとえば、火葬場から死体を不法に入手してパーツに切り分けて出荷する業者、解剖実習用に献体された遺体を闇に流して利益を得る人、どこから入手したか等には無関心で医療用の製品に加工する会社、そしてそれらの流通ネットワーク等である。拝金主義の跋扈に唖然とするが、幸い、一部が「闇取引」で、やっと成立しているレベルのようだ。だが、このビジネスが全面合法化したらどうなるのかと思うとゾッとする。
まあ、これはアメリカの話と高を括っていて良いのか。貧困を背景にした途上国での実態も知る必要があるが、水沢渓『ドキュメント遺体は誰のものか︱朝日大学・献体疑惑の真相』(健友館・91年)には、解剖実習用献体を大学がどのように扱っているか、本書が書かれた時点の日本での一つの例がある。献体された遺体を勝手に売買したり、大学の屋上で焼却したり、別人の遺骨や遺灰を遺族に返却したりだというのである。本書の内容が間違いのない事実であるかどうかを検証する必要はなかろう。当の大学を責めるのが目的ではないことに加えて、その大学の解剖学教授であった医師(実名で登場)の証言に基づいているのだから、全くの出鱈目、作り話ではないと判断できるからである。だとすれば、「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」の趣旨に沿った扱い方ではないことだけは間違いないように思える。
いずれにしても篤志献体は「医学・歯学の大学で行われる人体解剖学実習の教材として、自分の遺体を無条件・無報酬で提供する篤志行為」とする言説を支える倫理的基盤は、今のところ確かに存在するようだ。それによって、他の目的での利用や死体流通ビジネスの合法化は、紙一重で阻止されているのだろう。だが、手術手技の研鑽目的での利用が何故認められないのか、報酬を得て遺体を提供することがどうして人倫に反するのか。近世以降の死体への対し方を垣間見ただけでも、献体という仕組みは、実に危うい基盤の上に立っているように感じるのである。
編集委員 小笠原 慶彰
氏家幹人『大江戸死体考-人斬り浅右衛門の時代』
平凡社新書. 1999. 714 円
香西豊子
『流通する「人体」-献体・献血・臓器提供の歴史』
勁草書房. 2007. 3500円+税
アニー・チェイニー著・中谷和男訳
『死体闇取引-暗躍するボディーブローカーたち』
早川書房. 2006. 1600円+税
吉村昭「梅の刺いれずみ青」(『島抜け』新潮文庫・所収)は、明治初期から中期にかけての人体解剖を描いている。表題は、篤志解剖第1号とされる遊女が腕に梅の刺青をしていたことを指している。明治2年のことであった。小説とはいえ、新政府によって西洋医学が認知された後でも、解剖用死体の確保が困難を極めたことがよくわかる。それは日本人の死生観が、たとえ死後であっても身体を切り刻むこととなかなか相容れないためだろうと想像できる。
ところで、江戸時代には、死体に相当無頓着であったらしい。『大江戸死体考』によれば、水辺に土左衛門が漂っていたとか、道端には行き倒れが目に付いたとかで、死体がゴロゴロしていたというのだ。こんな状況だから死体検死の役人も忙しく、すでに何種類もあった検死マニュアルに準拠しながら処理した。だが、いくら死体がゴロゴロといっても、ただ冷ややかに眺められていただけかというとそうでもない。その死体を腑分けするとなると、つまり刃物でもって切り刻むとなると俄然話は違ってきて、強い拒否反応が起きたということのようだ。ところが、それが刑死体の場合は、また違う。まったく物扱い同然になるのだ。この辺りの機微は、とうてい現代の感覚では推し量れない。
たとえば、刑死体で刀剣の様斬りをする据物師という専門家がいた。将軍家や大名家から依頼され、刑死体によって刀剣の切れ味を確かめた。様斬りの注文は頻繁であったが、ある時期から代々世襲の山田浅右衛門が、ほぼ独占していた。山田家は、浪人ながら裕福であった。というのは、死体から胆を取り出して製造する薬も販売していたからである。その人胆丸と称される高価な漢方薬の製造は、明治に至ってようやく禁じられたという。
一方、幕末に刑死体による人体解剖がたびたび許されるようになると、医師と据物師との間で死体の取り合いになっていく。そして明治以後は、様斬りも廃止され、医師が独占して解剖用にのみ利用されていく。だが実際、死体の確保は大変だったらしい。
このような事情を踏まえた上で『流通する「人体」』では、死体を「資源」と捉えて、その流通システムという視点から献体を描いている。帯には「江戸末期から現在に至る『人体』流通システムを追いながら、『善意による無償提供』『自己決定』といったヒト組織利用に関する倫理的根拠が、そもそも資源調達の経済論的帰結であることを描き出す」とある。つまりは「ほしい人がいて、タダででもあげたい人がいて、丸く収まってんだからいいじゃん」っていうことか。だとすると、妙に納得させられてしまうが、引っ掛かるものもある。その奥歯に挟まったものは、「人体標本展」に言及された部分に至って取り除かれる。つまり、「ほしい︱タダであげたい」の関係が「ほしい︱お金を払ってくれるんならあげてもいい」と変形する可能性を示唆してくれるからだ。だが現在の日本では、合法的な死体の利用となると、本人や遺族の意思尊重は当然として、「無報酬」を抜きにはとても賛同されないだろう。
ところで、本人の意思や無報酬とはお構い無しに死体流通ビジネスが半ば公然と存在している国もあるらしい。『死体闇取引』は、アメリカにおけるその実態についてのルポルタージュである。本書冒頭の「死体部位別価格一覧表」には、度肝を抜かれる。たとえばこんな具合である。頭部550ドル~900ドル、脳500ドル~600ドル、肩(片方)375ドル~650ドル、胴体1千200ドル~3千ドル、死体一体4千ドル~5千ドル、各種臓器(一個)280ドル~500ドル等々。
死体は、解剖実習用にだけ用いられるのではない。医療機器メーカーの新製品実演販売用として、骨ペーストや骨ねじの原料用として、地雷防護服の強度実験用として、その他多くの用途が白日の下に曝されている。このような利用は、もちろん本人の意思あるいは遺族の合意に沿っていない。さらにその上、死体の需給関係は、不法あるいは不法すれすれの死体流通によって満たされる。たとえば、火葬場から死体を不法に入手してパーツに切り分けて出荷する業者、解剖実習用に献体された遺体を闇に流して利益を得る人、どこから入手したか等には無関心で医療用の製品に加工する会社、そしてそれらの流通ネットワーク等である。拝金主義の跋扈に唖然とするが、幸い、一部が「闇取引」で、やっと成立しているレベルのようだ。だが、このビジネスが全面合法化したらどうなるのかと思うとゾッとする。
まあ、これはアメリカの話と高を括っていて良いのか。貧困を背景にした途上国での実態も知る必要があるが、水沢渓『ドキュメント遺体は誰のものか︱朝日大学・献体疑惑の真相』(健友館・91年)には、解剖実習用献体を大学がどのように扱っているか、本書が書かれた時点の日本での一つの例がある。献体された遺体を勝手に売買したり、大学の屋上で焼却したり、別人の遺骨や遺灰を遺族に返却したりだというのである。本書の内容が間違いのない事実であるかどうかを検証する必要はなかろう。当の大学を責めるのが目的ではないことに加えて、その大学の解剖学教授であった医師(実名で登場)の証言に基づいているのだから、全くの出鱈目、作り話ではないと判断できるからである。だとすれば、「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」の趣旨に沿った扱い方ではないことだけは間違いないように思える。
いずれにしても篤志献体は「医学・歯学の大学で行われる人体解剖学実習の教材として、自分の遺体を無条件・無報酬で提供する篤志行為」とする言説を支える倫理的基盤は、今のところ確かに存在するようだ。それによって、他の目的での利用や死体流通ビジネスの合法化は、紙一重で阻止されているのだろう。だが、手術手技の研鑽目的での利用が何故認められないのか、報酬を得て遺体を提供することがどうして人倫に反するのか。近世以降の死体への対し方を垣間見ただけでも、献体という仕組みは、実に危うい基盤の上に立っているように感じるのである。


















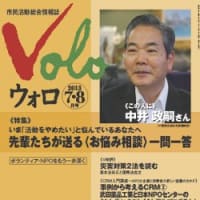
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます