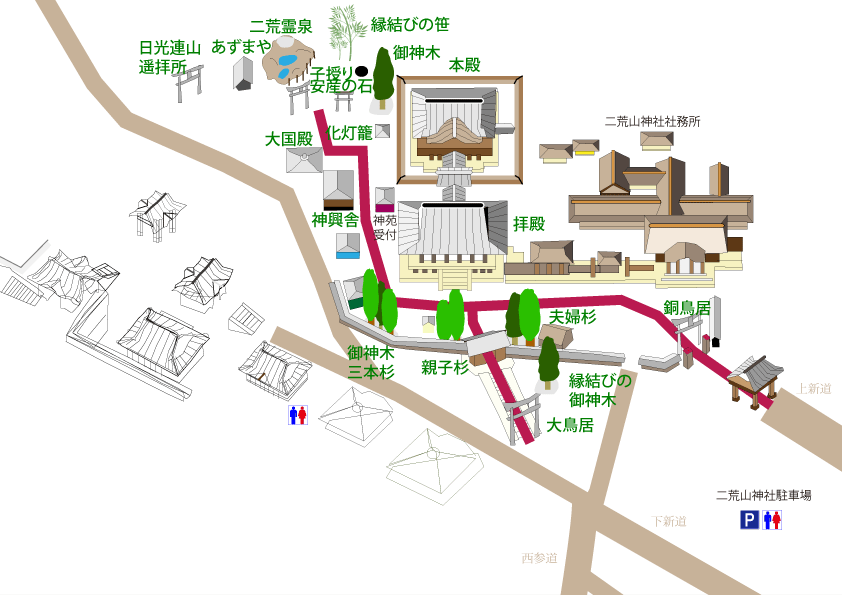147、日光の世界遺産;二社一寺 「二荒山神社・瀧尾神社」



日光二荒山神社の別宮・瀧尾神社
瀧尾神社は、元は今の別所跡(天保2年まで)にあり見事な舞台造りの建物と言う。
日光山の中心として栄えた。
祭神は田心姫命(女峰山の神) 明治の神仏分離までは楼門に空海筆といわれる「女体中宮」の額が架かり仁王像が置かれていたと言う。
本殿背面の扉は女峰山遥拝のもの。輪王寺で行われている「強飯式」も此処が発祥という。 瀧尾神社神興着興祭4月14日 瀧尾神社神興発興祭4月16日 天長2年(825)勝道の弟子そして第1世の瀧尾上人の道珍が書いたと言う「瀧尾山建立草創之記」の霊験談に記される。
弘仁11年(820)弘法大師は日光山に登り、中禅寺を参拝し四本龍寺に帰った。
それから稲荷川に沿って行くと滝があった。 それを「白糸の滝」と名づけた。滝の後ろに亀の形をした山があるのでそれを亀山と名付ける。 亀山の麓に大きな穴があって竜の棲家のようなので大師は穴を大竜穴と名付け庵として住むことにした。
その近くの池の畔に壇を築き修行をしていると池の中から白い玉が浮かび上がった。
問うと「我は天補星」と答えた。 大師はありがたく思い持ち帰り祠を建てて祀った。これが山内にある「小玉堂」。
それからまた呪いを唱えると今度は大きな白球が浮かび上がる。問うと「我は妙見尊星、大師の請いにより現れた。 この峰は女体の神の居られる所だから、その神をお祀り申せ。 我の棲家は中禅寺である」と答える。そこで大師は中禅寺に妙見大菩薩を祀った。さらに呪を唱え神霊の降下を願うと、神々しい天女が雲間より現れた。そこで大師は弟子とともに竜穴の上に堂を建て女神を祀った。
これが今の瀧尾神社(瀧尾大権現)である。
そのときの場所は今は杉林だが 白糸の滝から石段を登りつめた所。
稲荷川を見渡せる高台の景勝の地。天保2年(1645)に社殿を移転し瀧尾上人の住居の別所を建てた。(今の別所跡)
その少し西にある「影向石」が大師が呪を唱え紳姿を拝んだところで、神姿が現れた所が御神木の三本杉の処と言う。
大師は楼門に「女体中宮」と額を書き楼門に掲げ瀧尾に住もうとしたが京に帰らなければならなくなった為、道珍に瀧尾上人として大師の後任となし工事11年12付きに日光山をたったという。
別所は明治後期の取り壊され今は別所跡のみである。
国指定 重要文化財
次回、二荒山神社・瀧尾神社の参道
【小生の主な旅のリンク集】
《日本周遊紀行・投稿ブログ》
GoogleBlog(グーグル・ブログ) FC2ブログ seesaaブログ FC2 H・P gooブログ 忍者ブログ
《旅の紀行・記録集》
「旅行履歴」
日本周遊紀行「東日本編」 日本周遊紀行「西日本編」 日本周遊紀行 (こちらは別URLです) 日本温泉紀行
【日本の世界遺産紀行】 北海道・知床 白神山地 紀伊山地の霊場と参詣道 安芸の宮島・厳島神社 石見銀山遺跡とその文化的景観 奥州・平泉 大日光紀行と世界遺産の2社1寺群
東北紀行2010(内陸部) ハワイ旅行2007 沖縄旅行2008 東北紀行2010 北海道道北旅行 北海道旅行2005 南紀旅行2002 日光讃歌
【山行記】
《山の紀行・記録集》
「山行履歴」 「立山・剣岳(1971年)」 白馬連峰登頂記(2004・8月) 八ヶ岳(1966年) 南ア・北岳(1969年) 南ア・仙丈ヶ岳(1976年) 南アルプス・鳳凰三山 北ア・槍-穂高(1968年) 谷川岳(1967年) 尾瀬紀行(1973年) 日光の山々 大菩薩峠紀行(1970年) 丹沢山(1969年) 西丹沢・大室山(1969年) 八ヶ岳越年登山(1969年) 奥秩父・金峰山(1972年) 西丹沢・檜洞丸(1970年) 丹沢、山迷記(1970年) 上高地・明神(2008年)
《山のエッセイ》
「山旅の記」 「山の歌」 「上高地雑感」 「上越国境・谷川岳」 「丹沢山塊」 「大菩薩峠」 「日光の自然」