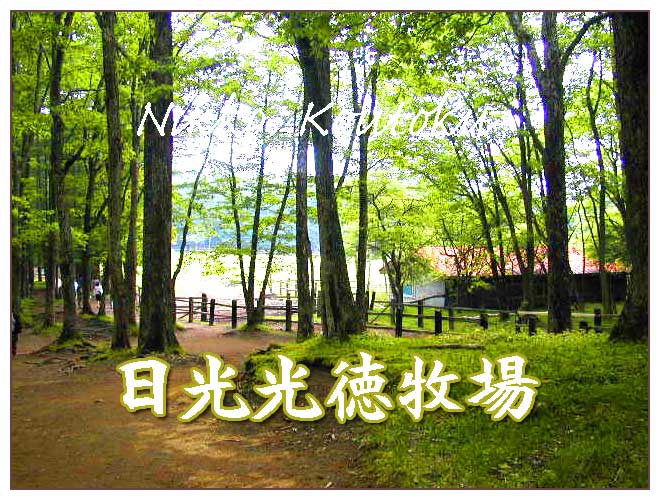世界遺産 日光大紀行(107)日光の自然 「奥日光・泉門池」
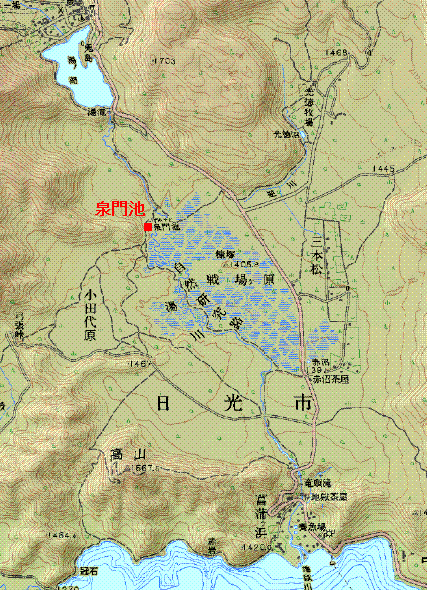

ところで、泉門池と書いて、普通なら“せんもんいけ”などと読みそうであるが、実は、「いずみやど」,または「いずみやどいけ」と読むらしい。 国土地理院の2万5千分の1地形図でも,「いずみやど」と仮名がふってある。
日光の写真集(写真家・秋元満正)「日光に咲く花」、「続・日光に咲く花」では,もっとはっきり書かれている。 「泉門池」全体にはっきりと「いずみやど」と仮名がふってあるし,次のような一文が撮影ノートとして載っている。
『 誰が名づけたか「いずみやど」地図には泉門池とある。これを“いずみやど”と呼ぶように仮名もつけていない。戦場ヶ原周辺で最も静寂な場所。湧き出す清水,繁茂する水草,水中に横たわる倒木,文字どおり自然そのままの光景である 』
或るホームページの識者は泉門池のことを、
『 それは「いずみやど」は「いずみかど」ではなかったのだろうかと言うことである。「や」と「か」は,字体がよく似ており,間違って読まれたのではないかと言う推理である。「いずみかど」ならば,文字通りの読みである。「か」と「や」は,特に手書きの場合に読み間違われることは十分にあり得ることと思う。誰かが「か」を「や」と読み間違えたところ,その言葉の響きの良さと,意味の神秘さのために定着してしまったのではないかと推理した。「泉門池」では,西側の斜面から大量の水が勢い良く湧き出しており,一時的に池に蓄えられた後,急カーブした湯川に流れ込んでいる。文字通り,泉が湧きだしている「かど」なのである。 』としている。
それに対して、小生は単純であり全く異なる考え方をしている。
「いずみやど」の“やど”は“やと”のことで、“やと”は谷戸である。
谷戸とは、「丘陵地の中の森林に囲まれた谷あいの土地で、水が集まりやすいところ」と言う意味で、丘陵地が浸食されて形成された谷状の地形を指す。
栃木県や茨城、福島(小生は福島のいわき市の出身)の言葉は、どちらかと言うと「ズウズウ弁」に近い。 従って、“やと“は”やど“になってしまうのである。
この地は、戦場ヶ原の突端部で、西の外山、東の三岳の山域が迫ってきている谷戸の様な地形で、両山塊は原に立つ門のような感じでもある。
その地形を良く観察すると、両側、つまり湯の湖側、戦場ヶ原からのどちらから見ても、門のような地形でもあり、その地に泉が湧いているのである。
【小生の主な旅のリンク集】
《日本周遊紀行・投稿ブログ》
GoogleBlog(グーグル・ブログ) FC2ブログ seesaaブログ FC2 H・P gooブログ 忍者ブログ
《旅の紀行・記録集》
「旅行履歴」
日本周遊紀行「東日本編」 日本周遊紀行「西日本編」 日本周遊紀行 (こちらは別URLです) 日本温泉紀行
【日本の世界遺産紀行】 北海道・知床 白神山地 紀伊山地の霊場と参詣道 安芸の宮島・厳島神社 石見銀山遺跡とその文化的景観 奥州・平泉 大日光紀行と世界遺産の2社1寺群
東北紀行2010(内陸部) ハワイ旅行2007 沖縄旅行2008 東北紀行2010 北海道道北旅行 北海道旅行2005 南紀旅行2002 日光讃歌
【山行記】
《山の紀行・記録集》
「山行履歴」 「立山・剣岳(1971年)」 白馬連峰登頂記(2004・8月) 八ヶ岳(1966年) 南ア・北岳(1969年) 南ア・仙丈ヶ岳(1976年) 南アルプス・鳳凰三山 北ア・槍-穂高(1968年) 谷川岳(1967年) 尾瀬紀行(1973年) 日光の山々 大菩薩峠紀行(1970年) 丹沢山(1969年) 西丹沢・大室山(1969年) 八ヶ岳越年登山(1969年) 奥秩父・金峰山(1972年) 西丹沢・檜洞丸(1970年) 丹沢、山迷記(1970年) 上高地・明神(2008年)
《山のエッセイ》
「山旅の記」 「山の歌」 「上高地雑感」 「上越国境・谷川岳」 「丹沢山塊」 「大菩薩峠」 「日光の自然」