35、日光の世界遺産;二社一寺の輪王寺 「大猷院の拝殿・相の間・本殿」
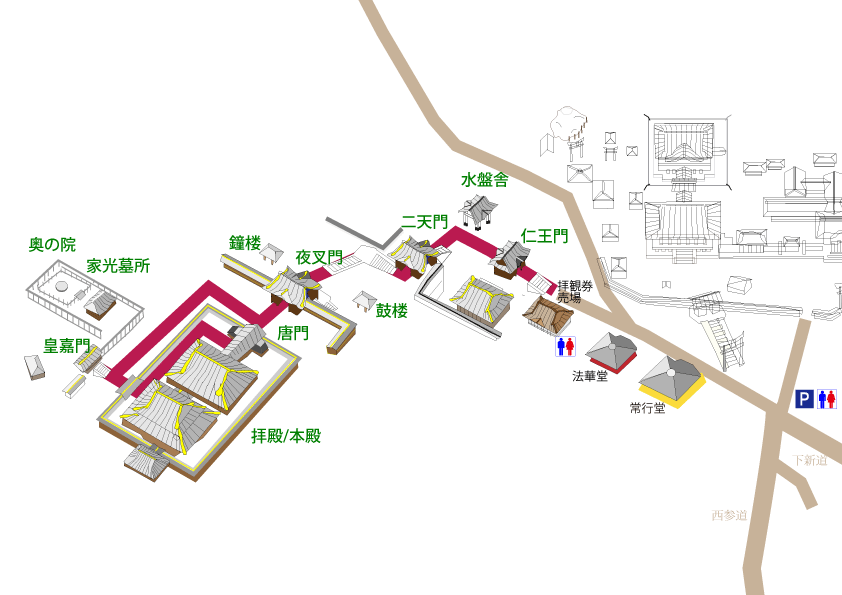


拝殿・相の間・本殿
唐門を背にして内に入ると、まず広々とした拝殿前に上がることができる。
拝殿の奥を見ると、左右は壁になっていて、中央は幅の狭い部屋へと続いている。 これが相の間である。 そして、相の間を抜けると、また部屋の幅が広くなり、本尊が祭られている豪華な本殿となるわけだ。
それぞれの部屋の間には、襖や障子などの仕切りがないので、拝殿から本殿が直に見通せるようになっている。
家光公の命日である4月20日の大法要では、日光山輪王寺の門跡(住職)が本殿へと進み、一般の人たちは拝殿で、亡き家光公を偲ぶことができる。
拝殿は64畳の広さがあり、天井には狩野一門の合作と伝えられる140の竜が描かれている。
小さな円のなかの竜には、違った姿の竜もあるので、1つずつ見てみるのも楽しい。
又、入り口の正面には、幕府の御用絵師だった狩野探幽と、弟の永真(えいしん)の唐獅子(壁絵)も見ることができる。
唐門を含む拝殿・相の間(あいのま)・本殿は、大猷院の中心伽藍で、其々が一体の構造として構成されていて、合わせて1棟が国宝となっている。
建物全体に金箔が多用されていることから「金閣殿」とも呼ばれている。
拝殿は、桁行8間、梁間3間、入母屋造で、正面に大きな千鳥破風、向拝は軒唐破風になっていて、建物全体が黒漆塗りの上に金箔を貼付けられ、彫刻を極彩色、高欄部を朱塗り、開口部を黒に塗るなど色分けし、本殿に比べると若干色調を押さえている。
拝殿内部も悉く金箔を置いた金殿玉楼で、広さは64畳敷という広さで、中央に懸かる天涯は家光の妹(前田利常夫人)、大羽目前の蓮華の花瓶1対は紀州公、鶴亀の燭台は尾張公、釣燈籠はオランダ国王の献上によるものという。
左右大羽目の唐獅子狛犬は、狩野探幽と永真安信の描いたものであり、拝殿内部折上格天井には格子毎に140匹の竜が描かれている。
拝殿と本殿を結ぶ相の間の内部も、拝殿同様結構の極みで、中央にある香炉等の三具足は前田利常の献上になる逸品であり、本殿との境には龍・降龍が描かれている。
次回、「大猷院の拝殿・本殿」
【小生の主な旅のリンク集】
《日本周遊紀行・投稿ブログ》
GoogleBlog(グーグル・ブログ) FC2ブログ seesaaブログ FC2 H・P gooブログ 忍者ブログ
《旅の紀行・記録集》
「旅行履歴」
日本周遊紀行「東日本編」 日本周遊紀行「西日本編」 日本周遊紀行 (こちらは別URLです) 日本温泉紀行
【日本の世界遺産紀行】 北海道・知床 白神山地 紀伊山地の霊場と参詣道 安芸の宮島・厳島神社 石見銀山遺跡とその文化的景観 奥州・平泉 大日光紀行と世界遺産の2社1寺群
東北紀行2010(内陸部) ハワイ旅行2007 沖縄旅行2008 東北紀行2010 北海道道北旅行 北海道旅行2005 南紀旅行2002 日光讃歌
【山行記】
《山の紀行・記録集》
「山行履歴」 「立山・剣岳(1971年)」 白馬連峰登頂記(2004・8月) 八ヶ岳(1966年) 南ア・北岳(1969年) 南ア・仙丈ヶ岳(1976年) 南アルプス・鳳凰三山 北ア・槍-穂高(1968年) 谷川岳(1967年) 尾瀬紀行(1973年) 日光の山々 大菩薩峠紀行(1970年) 丹沢山(1969年) 西丹沢・大室山(1969年) 八ヶ岳越年登山(1969年) 奥秩父・金峰山(1972年) 西丹沢・檜洞丸(1970年) 丹沢、山迷記(1970年) 上高地・明神(2008年)
《山のエッセイ》
「山旅の記」 「山の歌」 「上高地雑感」 「上越国境・谷川岳」 「丹沢山塊」 「大菩薩峠」 「日光の自然」














