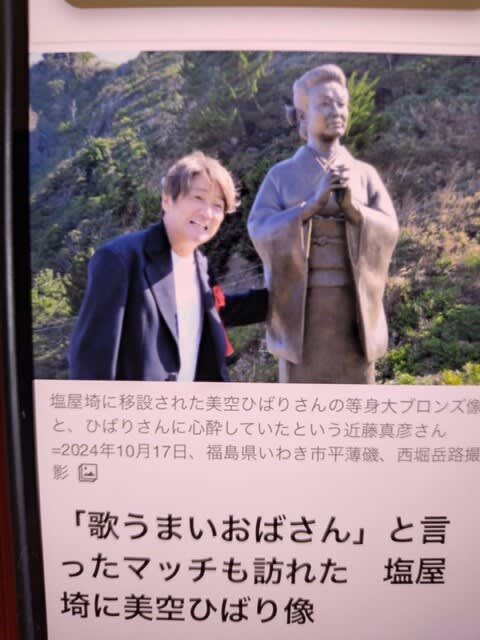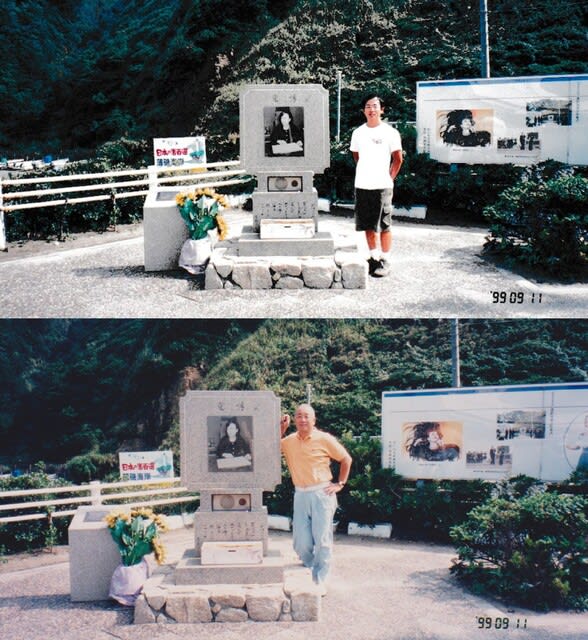1級講師紹介・皇居東御苑散策ツアー 01
SNS発信・皇居東御苑1~22
(youtube・blog・fb・x)
youtubeの番号とblog番号は下記説明文とリンクしてます。ご覧下さい。
SNS発信/皇居東御苑
アップテンポ 江戸城ソング
皆様こんにちは。
私は認定NPO法人「江戸城天守を再建する会」の理事を務めております江澤と申します。
この活動を通じて、皇居東御苑が一般公開されていることをご存じない方が多いという事実、そして訪問者の大半が海外からの観光客であるという現状を知り、大変驚きました。
皇居東御苑は、日本人にとって大変貴重な歴史的・文化的財産です。こうした素晴らしい場所の魅力を、もっと多くの方々に知っていただきたいという思いを強くしています。
そこで今回情報発信の方法として、SNS(YouTube・blog・fb・x)を活用し、それぞれ連携させながらお届け致します。
ぜひご覧いただき、皇居東御苑の新たな魅力を発見していただければ幸いです。ありがとうございます。
皇居東御苑
地図の番号と説明番号を同じくしてます。
]

江戸城天守復元模型 1/30 一般公開
1
和田倉噴水公園
東京都千代田区丸の内にある公園で、皇居外苑の一部として整備されています。
この公園は、1961年(昭和36年)に皇太子明仁親王(後の上皇明仁)と美智子妃(後の上皇后美智子)のご成婚を記念して開設されました。噴水を中心に美しい景観が特徴で、都会のオアシスとして多くの人に親しまれています。
2
大手門入口
大手門は明暦3年(1657年)1月の江戸大火で類焼し、翌年11月に再建された。その後も地震震災の被害、昭和20年の空襲で焼失昭和36年から修復がはじまり42年復元工事が完成した。高麗門は江戸期のものだが修理され、桝形形式の大手門が再建された。
3
算木積み
江戸城の石垣の積み方において「三木積(さんきづ)」とは、石を積む技法の一つで、角の部分に使用される特徴的な積み方を指します。
4
太田道灌
1457年江戸の地は扇谷上杉氏領となり、筆頭重臣の太田道灌はこの地に江戸城を築いて城主となって城下町が出来た。江戸城(千代田城)築城 家紋 丸に細桔梗
5
同心番所
江戸時代は橋の手前にあった。屋根瓦は葵の御紋、反対側に菊の御紋、瓦の紋は(渦を表す火除けのまじない)・(八幡神社神紋)・家紋(蒲生氏郷・山本勘助・宇都宮氏)
6
徳川家紋
徳川家康の家紋として有名なのは「みつばあおい」です。三つ葉葵は、3つの葵の葉が円形に配置されたデザインで、徳川家の象徴的な家紋としてしられています。これは、江戸時代を通じて徳川将軍家の権威を象徴する重要な家紋として用いられました。
7
百人番所
《江戸城本丸への道を厳重に守る警護詰所です。甲賀組、伊達組、根来組、二十五騎組という4組の鉄砲百人組が昼夜交替で勤務していた。各組は、20人の与力と、100人の同心で構成されていた。》江戸幕府に雇用された忍者たちであった。120名 24時間 4交代
8
中之門跡
切り込みはぎと呼ばれる技法で積まれている。・石垣に使われているのは、瀬戸内海沿岸から運ばれた白い花崗岩で西国大名から献上されたもの。・大名が登城する箇所や天守台の主要な部分に徳川の威厳を示すために積まれた。
9
果樹古品種園
上皇陛下のお考えを受けて、江戸時代に食用とされていたニホンナシ、モモ・スモモ
カンキツ、カキ、ワリンゴ、などの古品種が植栽されています。
10
富士見櫓
本丸地区に現存する唯一の櫓で、遺構の中では最も古いものといわれています。
11 松の大廊下跡 全長50m幅4mほどの畳式の廊下に沿った奥に松と千鳥の絵が描かれていたことから松の大廊下と称された
12 茶の木
徳川家康は茶の湯を愛し、その精神を重視していました。戦国時代の武将たちの間では、茶の湯が精神修養や武士道の一環として重視され、家康もその影響を受けていました。
1 3 徳川家
初代徳川家康、2代徳川家忠、3代徳川家光
3代将軍家光の時、1657年明暦の大火天守閣焼失、振袖火事
14 江戸城天守復元模型
家光時代の天守は「寛永度天守」地下1階地上5階
15 天守台
江戸城天守閣は、三度建てられましたが、明暦(1657年)の 大火で焼失した後は、天守台石垣が築き直されただけで、再建されるこ とはありませんでした。
16 桃華楽堂
香淳皇后(昭和天皇の皇后)のご還暦をお祝いして建設 (昭 和41年)された音楽堂です
17 梅林坂
太田道灌が菅原道真を祀った平河天満宮を勧請した際に道真 公 が梅が好きだったことを知っていた道灌が梅の木100本をここに植えたのが梅林坂の始まり目的であった。
18 北桔橋門(きたはねばしもん)
太田道灌が築城した折には、大手門だったといわれています。石垣には工事関係者を記す紋や銘が刻 まれている。
19 二の丸庭園
九代将軍家重の時代の庭絵図面をもとに池泉回遊式庭園
として復元された日本庭園です。二の丸池は、小堀遠州作といわれる
庭園の池水とほぼ同じ位置にあります。
20 ヒレナガニシキゴイ
上皇陛下のご発案によりインドネシアのヒルナガコイと日本のニシキゴイを交配して生まれた。
21 平川門
高麗門と櫓門で虎口を形成している。本来入口の正面に あるはずが変型型をしている。明暦の大火、関東大震災後復元。
22皇居三の丸尚蔵館
皇室が受け継がれた美術品を収蔵館する国立博物館です。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
〒299-5223
千葉県勝浦市部原1928-26
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆