ヤブガラシが目につくようになりました。花は緑色で、咲き始めは蜜の出る部分がオレンジ色で、その後ピンク色に変わります。
ヤヤブガラシはブドウ科の蔓性多年草です。

生態の良く似たものに、アマチャヅルがありますが、こちらはウリ科です。

ヤブガラシは、生長は早く、一晩に数センチも伸び、伸びるにつれて葉も開いてきます。葉は5枚に分かれた複葉で、それぞれに短い葉柄を持ち、その葉柄の反対側から巻きひげが伸びてとっかかるものを探すのか空中をゆらゆらしています。こうして葉と巻きひげは一対となって交互に伸びて、近くの植物に絡みついて覆い被さってしまいます。おまけに地中に縦横に伸びた根茎から、至る所に芽をだして繁殖します。地中で四方八方に伸び、放っておけば薮をも枯らしてしまうというのが名前の由来です。この植物で周りを覆われると、いかにもみすぼらしく見えるので「ビンボウカズラ」とも呼ばれています。

私はヤブガラシ退治には、時として地下茎をたぐって取り除きますが、とても根っこまでは抜き取れないので、大抵は地上部を引き抜きます。慎重にやっても、どうしても途中で切れてしまい、そこから又拡がります。根治することは不可能に思えるのですが、何かよい方法は無いものかと調べていると、面白いサイトを目にしました。
園芸会社のブログですが、”農薬を使わずに、簡単にヤブガラシが駆除出来る” というのです。
【それは、今年6月8日に国立市「やぼろじ」で行われた、矢野智徳さんの「大地の再生講座」での一コマ。下草の風通しを良くする方法を矢野さんが指導していた時。そこにヤブガラシがありました。「この草は、とても素直な草。役目を終えたと思えれば、必ず姿を消してくれます・・・」といって、矢野さんはくるくるとヤブガラシを丸く束ねて、地面に置きました。これでヤブガラシは無くなる、というのです。】
“へぇ-、そんなことで退治出来るの?信じられないが、やってみよう”とヤブガラシを取り外してみたのですが、絡みついているのを外すのは大変です。引っ張れば途中で切れてしまい、とても書かれているようにはできません。南天に絡みついている1カ所をやってみただけでギブアップしました。 ヤブガラシ退治したい方はこちらを参考にあいて、お試し下さい。
こんなヤブガラシでも、昔から薬用に利用されてきました。烏瀲苺(うれんぼ)という生薬名ももっているのです。
薬用として生の葉を使うときは必要に応じて採ります。
・利尿、鎮痛、神経痛、解毒には、煎じて服用。
・腫れ物、虫刺されには、生の葉を潰して汁をつける。
・乳房の腫れや毒虫に刺されたときは、生の根茎を擂り潰して患部に塗布する。
・打ち身、骨折には、生の根茎を擂り潰したものに酢と小麦粉を加えて練り合わせて患部に塗布。
食用としても利用されます。
・若い芽を茹でて水に晒して、アク抜きをしてから調理します。お浸し、和え物、油炒めなどに。
こなんなに有用であるなら、食わず嫌いせずに一度試してみなくては・・・・・モッタイナイ!!
余談ですが、ヤブガラシには、実をつけるタイプと実をつけないタイプがあるそうです。この辺りで見かける花には実はついていないので、関東のヤブガラシは実をつけないタイプのようです。研究によって(大阪市立大学の岡田 博教授)、ヤブガラシには染色体数が2倍体と3倍体があり、2倍体には南西日本型、北西九州型、そして広く日本の関東以南に分布する型の3型があることが判明したそうです。染色体数が多くなると結実しないということは、種なしスイカやヒガンバナでよく知られています。関東のヤブガラシは殆どが3倍体なので、実は付かない(種は出来ず、)実生のヤブガラシを見たことが無いのは、そういうことだったのかと知りました。

















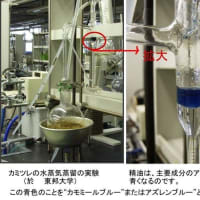

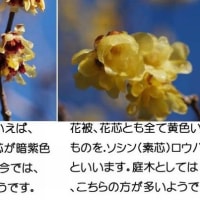
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます