京都新聞 より
「河川改修や湖岸改変、ほ場整備など地形改変が要因とされた種は、ニゴロブナやヤリタナゴ、メダカなど最多の35種に上った。地形改変による湖岸や川底の単調化、水路と田んぼの分断で、多くの種の産卵や生育の場が失われている現状が明らかになった。」記事より。
地形の改変がもっとも影響が大きい。
この記事が重要なことは、琵琶湖における在来魚の減少は外来魚が原因だけではないということを述べているということだ。
地形の改変というのは、生き物の生息する場所そのものに対する改変だから、生き物のすべてにその影響が及ぶ。
たとえば、地形が単調となるから、外来の捕食魚に食べられやすくなる。たとえば、人工的な水位変動の影響が地形改変によってより顕著になる。エトセトラ。
在来魚をもとの状態に戻すには、「地形改変」を改善するということが必要とされるということだろう。ただ、地形改変という意味づけが広範なものなので、生物に関する影響の本質が間違って理解されないかということが、少し気がかりでもある。
「滋賀では琵琶湖の水位操作の影響がニゴロブナなど4種で指摘された。」
ボクの雑文的な理解なのだけれど、生物に関する人間の作用は直線的ではない。また、直接的に作用するものと、」その作用をより大きくするものがあると思っている。
たとえば、水位変動だ。地形をもとに戻しても、水位変動の抑制というか水位の人為的な管理で失われたものがすべて改善されるとは思えない。
水位変動の抑制により影響は、地形が改変されたことでより大きくなったと思うのだが、ニゴロブナ、そしてアユモドキ、湖岸の水位が上昇して、冠水した岸辺に産卵する生物にとって、その行動を前駆する「水位の上昇」という自然現象が存在しなかったなら、産卵行動そのものが抑制されたままなのではないかと考えている。
☆テキスト版
在来魚、最大の脅威は地形改変
琵琶湖・淀川水系 分析で判明
写真
琵琶湖を埋め立てて建設された人工湖岸。これらの地形改変が在来魚の産卵・生育に影響を及ぼしている(草津市北山田町)
琵琶湖・淀川水系の在来魚を脅かすさまざまな要因のうち、河川改修など地形改変が最も広範な種に悪影響を与えていることが各種レッドデータブックの分析で分かった。次いで外来魚の影響が大きく、在来魚保護には両面で対策が求められることが浮き彫りになった。
琵琶湖環境科学研究センターの西野麻知子総合解析部門長が、環境省や滋賀、京都、大阪の3府県のレッドデータを分析した。絶滅危ぐ種などに位置づけられた計42種の記述から、生存を脅かす要因を河川改修▽外来魚▽水位操作▽水質汚濁▽乱獲-などに14分類した。
河川改修や湖岸改変、ほ場整備など地形改変が要因とされた種は、ニゴロブナやヤリタナゴ、メダカなど最多の35種に上った。地形改変による湖岸や川底の単調化、水路と田んぼの分断で、多くの種の産卵や生育の場が失われている現状が明らかになった。
次いで外来魚のオオクチバスとブルーギルに食べられたり、えさや住みかを奪われている種がホンモロコやイタセンパラなど29種あった。
滋賀では琵琶湖の水位操作の影響がニゴロブナなど4種で指摘された。一方で水質汚濁の影響は京都、滋賀ではスナヤツメなど2種にとどまり、大きな危機要因とはなっていなかった。
全魚種とも脅威は一つではなく、外来魚と地形改変など複数が組み合わさっていた。西野部門長は「地形改変で在来魚が減ったところに、外来魚が追い打ちかけている。外来魚駆除に加えて地形修復を進めないと、本当の保護につながらない」と指摘している。
「河川改修や湖岸改変、ほ場整備など地形改変が要因とされた種は、ニゴロブナやヤリタナゴ、メダカなど最多の35種に上った。地形改変による湖岸や川底の単調化、水路と田んぼの分断で、多くの種の産卵や生育の場が失われている現状が明らかになった。」記事より。
地形の改変がもっとも影響が大きい。
この記事が重要なことは、琵琶湖における在来魚の減少は外来魚が原因だけではないということを述べているということだ。
地形の改変というのは、生き物の生息する場所そのものに対する改変だから、生き物のすべてにその影響が及ぶ。
たとえば、地形が単調となるから、外来の捕食魚に食べられやすくなる。たとえば、人工的な水位変動の影響が地形改変によってより顕著になる。エトセトラ。
在来魚をもとの状態に戻すには、「地形改変」を改善するということが必要とされるということだろう。ただ、地形改変という意味づけが広範なものなので、生物に関する影響の本質が間違って理解されないかということが、少し気がかりでもある。
「滋賀では琵琶湖の水位操作の影響がニゴロブナなど4種で指摘された。」
ボクの雑文的な理解なのだけれど、生物に関する人間の作用は直線的ではない。また、直接的に作用するものと、」その作用をより大きくするものがあると思っている。
たとえば、水位変動だ。地形をもとに戻しても、水位変動の抑制というか水位の人為的な管理で失われたものがすべて改善されるとは思えない。
水位変動の抑制により影響は、地形が改変されたことでより大きくなったと思うのだが、ニゴロブナ、そしてアユモドキ、湖岸の水位が上昇して、冠水した岸辺に産卵する生物にとって、その行動を前駆する「水位の上昇」という自然現象が存在しなかったなら、産卵行動そのものが抑制されたままなのではないかと考えている。
☆テキスト版
在来魚、最大の脅威は地形改変
琵琶湖・淀川水系 分析で判明
写真
琵琶湖を埋め立てて建設された人工湖岸。これらの地形改変が在来魚の産卵・生育に影響を及ぼしている(草津市北山田町)
琵琶湖・淀川水系の在来魚を脅かすさまざまな要因のうち、河川改修など地形改変が最も広範な種に悪影響を与えていることが各種レッドデータブックの分析で分かった。次いで外来魚の影響が大きく、在来魚保護には両面で対策が求められることが浮き彫りになった。
琵琶湖環境科学研究センターの西野麻知子総合解析部門長が、環境省や滋賀、京都、大阪の3府県のレッドデータを分析した。絶滅危ぐ種などに位置づけられた計42種の記述から、生存を脅かす要因を河川改修▽外来魚▽水位操作▽水質汚濁▽乱獲-などに14分類した。
河川改修や湖岸改変、ほ場整備など地形改変が要因とされた種は、ニゴロブナやヤリタナゴ、メダカなど最多の35種に上った。地形改変による湖岸や川底の単調化、水路と田んぼの分断で、多くの種の産卵や生育の場が失われている現状が明らかになった。
次いで外来魚のオオクチバスとブルーギルに食べられたり、えさや住みかを奪われている種がホンモロコやイタセンパラなど29種あった。
滋賀では琵琶湖の水位操作の影響がニゴロブナなど4種で指摘された。一方で水質汚濁の影響は京都、滋賀ではスナヤツメなど2種にとどまり、大きな危機要因とはなっていなかった。
全魚種とも脅威は一つではなく、外来魚と地形改変など複数が組み合わさっていた。西野部門長は「地形改変で在来魚が減ったところに、外来魚が追い打ちかけている。外来魚駆除に加えて地形修復を進めないと、本当の保護につながらない」と指摘している。











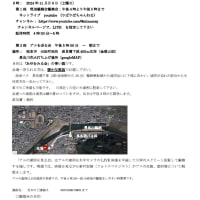














水際地形や水質なんかもマジメに評価研究しなきゃイカンと思います
昨今水質は一般項目でフツーに評価されやすいですが
そういった分析で引っ掛かってこない微量なホルモンとか
薬品化合物って関係ないとは思えないです
とにかく、「直観的に何かを感じ得る」、
顔を水につけるフィールダーの絶対数が不足してると思います
それにしても、問題は高齢化かなあ。
貴兄も現場行っているの?
直観的に形や「なにか」を評価できることと
客観的に評価できること
両方できて初めてプロだと思うんですよね
数値収集ばかりだと視界は狭まるし
現場しか分からないと漁師と変わらない
バランスって大切ですね