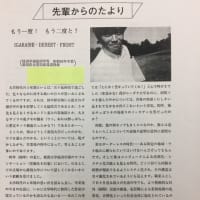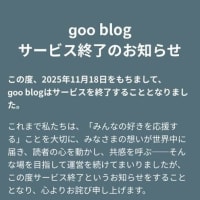●新潟暮らし推進ネットワーク会議
新潟県からの若者を中心とした人口流出は、東京圏への大学進学や就職が主な理由であるとマクロでは分かってはいるが、その対策となると、人気の大学や勤め先を引き抜いて新潟へ移転させることは非現実的であるし、それらは東京圏にあるからこそ価値の高さがあるということでもあり、即座に大きな効果を見込める手法は見出しにくい。そうなると、一人ひとりミクロのレベルで思考に働きかけて新潟へ関心を持ってもらい移住してもらうような取組を積み重ねるより仕方ない。
一人ひとりが何をもって生活の場とすることを判断するのかは正に千差万別となる。ステレオタイプの新潟アピールでは響かない。特に新潟県は県土も広く長く、山あり川あり海あり島もあり、都市的地域から山奥まで、何でもあるので、県として何かを語るときに何でもあることがかえって焦点をぼかしてしまう。地域毎の個別の特徴ごとに移住定住者の需要とのマッチングを図る必要がある。それにしても、県庁には、特に本庁舎に座して仕事をしている立場においては、そのための臨場感を得ることができない。移住定住の促進を県行政としての課題としてときに、地域との連携こそが鍵になるのだ。
そんな問題意識を持っていた着任早々の4月初旬、担当が「新潟暮らし推進ネットワーク会議」を定例開催したいと私の席に相談に来た。前任課長からの引継資料に掲載されてはいたが、あまり深掘りせずに過ごしていたことを思い出した。会議の構成は、民間団体が30、市町村30団体の全て、国機関としては新潟労働局、それに加えて県庁内の関係10課だという。民間団体には、新潟経済活動全般の観点からの経済同友会のほか、住生活の論点で宅地や建築関係の協会、田舎暮らしの関係で農業関係団体、融資の関係で県内金融機関、そして企業創業などの観点から県の三セクであるにいがた産業創造機構、具体の就労情報を持つ中小企業団体中央会となっており、生活者の視点で横串の刺さったようなメンバーでなかなか面白い。
毎年定例開催の会議だというので経緯を踏まえた一定の作法などもあるのだろう。新参者の私が良く知りもせずにあれこれ希望や指示を出しては関係者も困惑するに違い無い。先ずは担当者の開催企画を黙って聞くことにした。会議の概要は、県や市町村、団体それぞれのUIターン促進の取組状況の報告と共有、先進的な取組事例の聴取、今後に向けた意見交換…そんなところだった。年度当初にこうした全体的な情報共有と意見交換を行い、8月頃に動静を踏まえた具体のテーマを設定して実務的に議論するのが通例だという。こうした認識合わせと平行して、都心において移住検討者向けセミナーを会議メンバーが連携して内容により規模を変えるなどして8回程度行うのが年間スケジュールの概略のようだ。
全体会議で足下の移住者意識のトレンドや移住促進に結びついた先進的取組を学び、具体の情報発信となるセミナーの設営や内容を磨き上げていくという仕組みは、目を見張るものではないが、基本としては大切な進め方なので、先ずは例年並みの会議内容で了として作業を進めてもらうことにした。もう少しインパクトがあって実効も上がる方法や内容があるのではと幾つか頭に浮かびはしたが、県庁に戻ってまだ数日。先ずは関係者が一堂に会する「新潟暮らし推進ネットワーク会議」にて参加団体がUIターンの促進についてどのような思惑なのか垣間見ることとしよう。なんていってもUIターンの促進は、現場を持つ市町村や団体の人たちに気分良く仕事してもらってこそ効果の上がるものだ。机上論しか持たない我々県庁としては低い姿勢で丁寧に臨むことが肝要と思った。
(「新潟暮らし推進課6「新潟暮らし推進ネットワーク会議」編」終わり。県職員として11箇所目の職場となる新潟暮らし推進課の回顧録「新潟暮らし推進課7「新潟暮らしセミナー@回帰センター(その1)」編」に続きます。)
☆ツイッターで平日ほぼ毎日の昼休みにつぶやき続けてます。
https://twitter.com/rinosahibea
https://twitter.com/rinosahibea