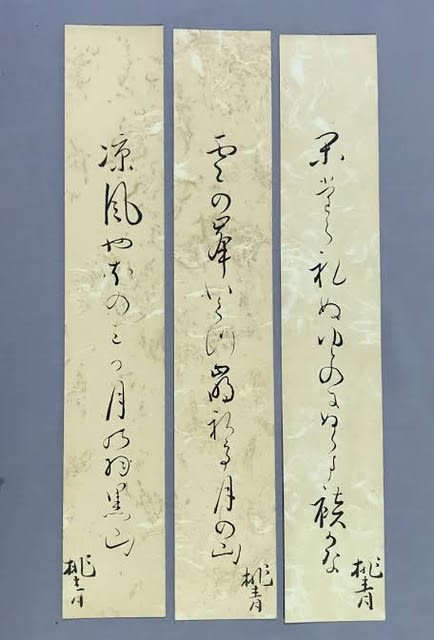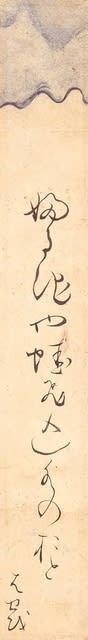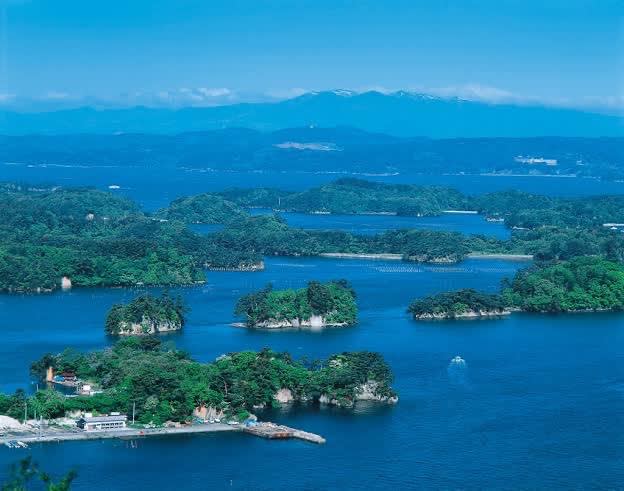__ 一つ前の記事で、伊勢白山道の使う日本語の乱れについて、弾劾しましたが、
私の「リーマン語」非難についての投稿が掲載され、
またリーマンさんの書籍📖を扱う(株)観世音の渡部周編集長からも、メルマガ(有料)の形でご対応を頂いたので、
私の追求の証しとして、ここに記録しておきたい。
(一応、同世代に生きる者として、日本語を乱す輩に注意⚠️訓告して、是正をもとめた証拠を挙げておきたかった。)

まずは、私が投稿した記事のリンク🔗から、
…… この記事に投稿した拙稿が次の通りです。
[実際に掲載された拙稿]
> 2025-02-21 16:11:32 (記事:2025-02-21)
🔴神罰だと思う
> もし、無事のままで済んでいる人でも、
【御本人が気付いていない神罰】を受けておられました。
・ それは、独身に成るということです。
・ 伴侶が居ても、離婚するか、他界されて、独身になる。
…… よく古い読者で、
「うちの家系の霊線は、お役目を終わったから、
わたしは独身を貫き、子孫を作らずに、ミロクの世の中性化に向かっている」と、
自分勝手に判断して、独身を正当している人が少なくないが、ほんとうにそうなのだろうか?
やはり神縁がないと結婚も出産もできないのではないでしょうか。
ですから、ただ単に神縁がないか(神に随う生活をしていない)、
あるいは神罰を受けているということなのではないでしょうか。
私自身もそうなのかなと反省した。
心当たりこそ無いが、あり得ることであり、慎んで省みることである。
さて、私は自分のブログで、リーマンさんの使う日本語が乱れているからといって、公にクレームを発信している。(同世代として責任を感じるから)
これについて、
リーマンさんはともかくとして、リーマンさんを天子(テンゴ)と仰ぐ眷属神は、私の行為を不敬と捉えて漏れなく神罰を下すのであろうか?
眷属神は、人間の命を何とも思わない一途さだと伺っている。
だけれども、日本人として言葉が乱れるのは放っておけない。団塊ジュニアが編み出した「飲食店応対マニュアル」のように、日本語を毀損するような真似はしてほしくない。
神罰があたっても、するべきことなのか。
踏み絵を迫られている心地がする。
_________《引用ここまで》
__ 次に、メルマガについての感想投稿で、リーマンさんの文章に触れています。
[実際に掲載された拙稿]
>2025-02-22 21:21:30 (記事:2025-02-22)
🔴メルマガ感想
コアな読者と、仲間内の符牒(インサイダー情報)でやりとりしたいお気持ちはよくわかります。
が、伝わることが最優先でありましょう。
今回の訂正文を載せたことは、編集長の真摯さが感じられ、徳のあるお方との印象を強くいたしました。
この調子で、リーマンさんの御本の上梓に臨んでいただきたく存じます。
特に、校正にはご注力くださいますように切にお願い申しあげます。
おそらく、出版人としての文責と、リーマンさんの言霊重視の文章との間に齟齬をきたすのは必定だと思います。
リーマンさんの伝えた内容は、学校の「道徳」授業の教科書📕に載せてしかるべきものかと存じますが……
いまの文章では、決してそうならないでしょう。
日月神示や出口なおの御筆先ならば、予言書や神に降ろされた啓示の書として、出鱈目な文章でも何ら問題にはなりませんが、
リーマンさんの言文一致体のブログ記事が、文科省の教科書検定を通るのは難しいです。副読本としても、基準をみたすかどうか怪しいものです。
そこはそれ、販売元の(株)観世音の腕の見せどころでしょう。文学としても通用し、言霊も同時に作用するような稀有な書物を協働して顕現させてください。
リーマンさんのもたらした啓示は、百年や二百年で使い物にならなくなるような一過性の流行り物とは全く次元が違います。
編集長におかせられましては、きっと百年の計をたてて命懸けで臨まれますことを切に希望します。
日々ネットで消耗されるコメントなぞ、何ひとつ後世には遺りません。ただ、リーマンさんの御本は、未来の日本人を励ますために遺ってほしいと思っておりますゆえ。
_________《引用ここまで》
__ この次は、20250301 (土曜日)に、メルマガ(有料)にて、渡部編集長から、「リーマンさんの日本語がオカシイ」とクレームをつける読者について言及があった。
土曜日のメルマガは、編集長の書いた記事を載せることになっている。
有料メールマガジン(月額1250円)だが、伊勢白山道の表の記事では書けない危険な事柄を、コアな読者にお伝えしている。リンク🔗はこちら▼
…… このメルマガ記事に応える形で、表の伊勢白山道コメント欄に投稿した拙稿を次に挙げます。
[実際には、不掲載となった拙稿]
20250301
⚫️メルマガ感想
編集長の「出版人として負うべき文責」について
プロの見解が聞けて嬉しかった。
私は、リーマンさんの文章はオカシイと言っている者の一人だが、15年間は言い続けている。
編集長のお応えをまとめると、
・伊勢白山道の文章の校正は、🖍️「校正技能検定」保持者がおこなっている
・リーマンさんが三歳までは古代インド語しか話さず、記事を書くあるいは質問に返答している最中は、半分入神状態なので、「正確な文法で書けない」のは、情状酌量の余地がある
というお応えでしたが……
たとえば、極貧のうちに神懸りして御筆先を書かされた無学な出口なお刀自や、日月神示を強制的に書かされた岡本天明の文章なら、
「正確な文法で書けない」という非難は、いくら私でもいたしません。
読者は、そーゆートランス状態での日本語の乱れ、誤字脱字は許容範囲であり、そーゆーもの(預言書)だとして本を購入します。
だから、そのトランス時の乱れを言うのだったら、
出版される書籍に、お断りを入れるべきです。
ex. 「著者の入神時の自動書記ですので、日本語としておかしい表現もありますが、どうぞご了承ください」
出版社が、校正という文責を伴うことは当然ですが、
最近は校正担当者のレベル低下も頻繁に見られるようになったのは、日本人として本当に嘆かわしいことです。「編集者あとがき」などに見られる、貧しい日本語には驚かされます。
大手のナチュラルスピリット社ですら、「遍在」と書くべきを「偏在」として、そのまま校正を通している現状です。(スピ系出版社としては、致命的なミス)
私は思うのだが……
「推敲」という作業がおろそかにされているのです。メルマガでも、プロの執筆者なのに、誤字脱字の類いが間々見られるのは何故か?(特に、人名間違いは致命的)
リーマンさんでも、神から降ろされた内容を瞬時に文章に変換したとしても、その出来た文章を日常意識で「推敲」する時間はあるはずです。(日本語がおかしくて伝わらなかったとしたら、何の意味もないからです)
結論として、
私が望むのは、普通の日本文です。
名文や美文を望んでいるわけではありません。(リーマンさんがそーゆー趣味ならOKですが)
リーマンさんの原文を言霊調整するのではなく、校正された正しい日本文に言霊をつけて下さい。
日本語としておかしな処がなければ、リーマンさんの説く内容は、教科書📕に採用されてもおかしくないような根源的な本質をついています。
風俗的にみても、「感謝」や「努力」を日本人に思い出させた功績は巨きいでしょう。
だからこそ、なおさら残念なんです。一読おかしな風情の日本語では、単なるネットカ・ルトの霊能者で終わります。
私も、知識人に紹介する度に馬鹿にされます、「まともな文章もかけない霊能者に凝っているのか♪(冷笑)」と。
_________
…… もうひとつ、ダメ押しで投稿したものも挙げます。
[実際には、不掲載となった拙稿]
⚫️編集長へ
「リーマンさんの日本語がオカシイ」と投稿する人を工作員かと疑っていましたが……
私がもし、工作員ならばずっとこのままにして、リーマンさんの好きに書かせる。
それらのおかしな日本語が、編集者の甘い校正をすり抜けて、上梓される。
そっちの方が、リーマンさん勢力の排除には好都合であることは明らかであろうよ。
どうも、編集長たるもの、そんな甘い読みではこれからの運営が心配ですよ。
それでなくとも、リーマンさんにおんぶに抱っこの経営なんでしょ。読者の富裕層をあてにしないで、メルマガが軌道にのったら、月額を下げる工夫もしてください。
リーマンさんにぶら下がっているから安泰などと夢にも思わないでください、鉄槌は意外と読者の生き霊から下されるでありましょう。
_________

__ いままで、50回どころか100回近く批判し続けた「リーマン語」についての批判投稿が、ようやく陽の目を見たと言ってもいいのではあるまいか。
いままでも、「リーマンさんの日本語がオカシイ」という私の批判は、折々に短く投稿に混ざっていて、実際に掲載されたものも数回はあると記憶している。
ただ、私のブログ記事みたいに本格的に、文法から詳細に指摘した拙稿は、なかなか掲載されなかった。(この点において、リーマンさんの自信の無さには幻滅したものだった)
今回は、正面切ってリーマンさんの「リーマン語」を非難している内容を、キチンとブログ『伊勢-白山 道』のコメント欄に掲載してくれたのが嬉しかった。
まー、私の顔を立ててくださったのかも知れん。
日本語に厳しい私の鑑定眼は、たとえ尊敬するリーマンさんに対しても、微塵も容赦することなく発動したというファクトを記録してくれたのかも知れない。
私の信念と、私自身の整合性はとれていることを現したかった。
まー、リーマンさんに私程度の「作文センス」もなかったことは、返す返すも残念極まりないことである。
あの、素晴らしいブログ内容に較べて、その文章が拙すぎるのは、私のオカルティストとしての経験からすると、まったくもって解せないことなのだ。
ただ、わたしはリーマンさんの同世代(ひとつ年上)なので、「そんな文章じゃダメだよ」と言い続けなければならない。
私たちみたいな年寄りが、日本語を壊してどうするんですか?
伝統を知っている私たちが壊していたら、いったい誰が正しい日本語を守るのですか?
正しい日本語なくして、正しい日本国はあり得ないのです。
わたしは、リーマンさんのような日本語破壊者を許さないが、その日本語も日本国🇯🇵が存続して初めて、その伝統云々を論じられるのである。
いまから15年後、そんな日本語の乱れなど頓着していられない激甚たる変化が音連れようとしているのかも知れない。
だけど、ネット発信が可能である限り、
正しい日本語、美しい日本語を心懸けることは忘れないつもりである。
ブログ『伊勢-白山 道』で、工作員扱いされても、これだけは譲るわけには生かないのだ。
伊勢白山道のコメント欄で、公的な形で掲載されて、多数の読者の目に触れられたのは大変良かった。
まっとうな日本人が多いと思われる「伊勢白山道読者」へは、ちゃんとした形で呼びかけることが出来た。
あとは、それを受け容れられるか、ちゃんとした日本語のレベルがあるのかは、読者次第である。
高学歴の読者は、ほとんどいないと私は見ている。
Fランクの大学卒が多いのかも知れない。というのも、私以外にリーマンさんの変な日本語使いを糾弾した者はいないようだから。(不掲載にされているのかも知れないけど)
ともあれ、なんとも国語力の著しい低下は、このブログ『伊勢-白山 道』でも多々見られるのが遺憾である。
四の五の言っても、国語力は一朝一夕では回復しないものだと言う。(オタキング岡田斗司夫が解説なさっていた、受験勉強で国語の成績を伸ばすのは最も難しい事らしい)
ちゃんとした文章を書けない者(=読解力の無い者)に、いくら言っても、急に改めることは不可能なのだ。
同時代に、アホな日本語しか使えない日本人と巡り合わせたのも、私の宿命なんだろうな。
まず、自分だけでも、正しい日本語を使うことを、肝に銘じることにする。
それが、私の日本人としての意地(使命かも知れん)である。
_________玉の海風