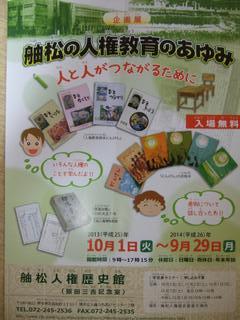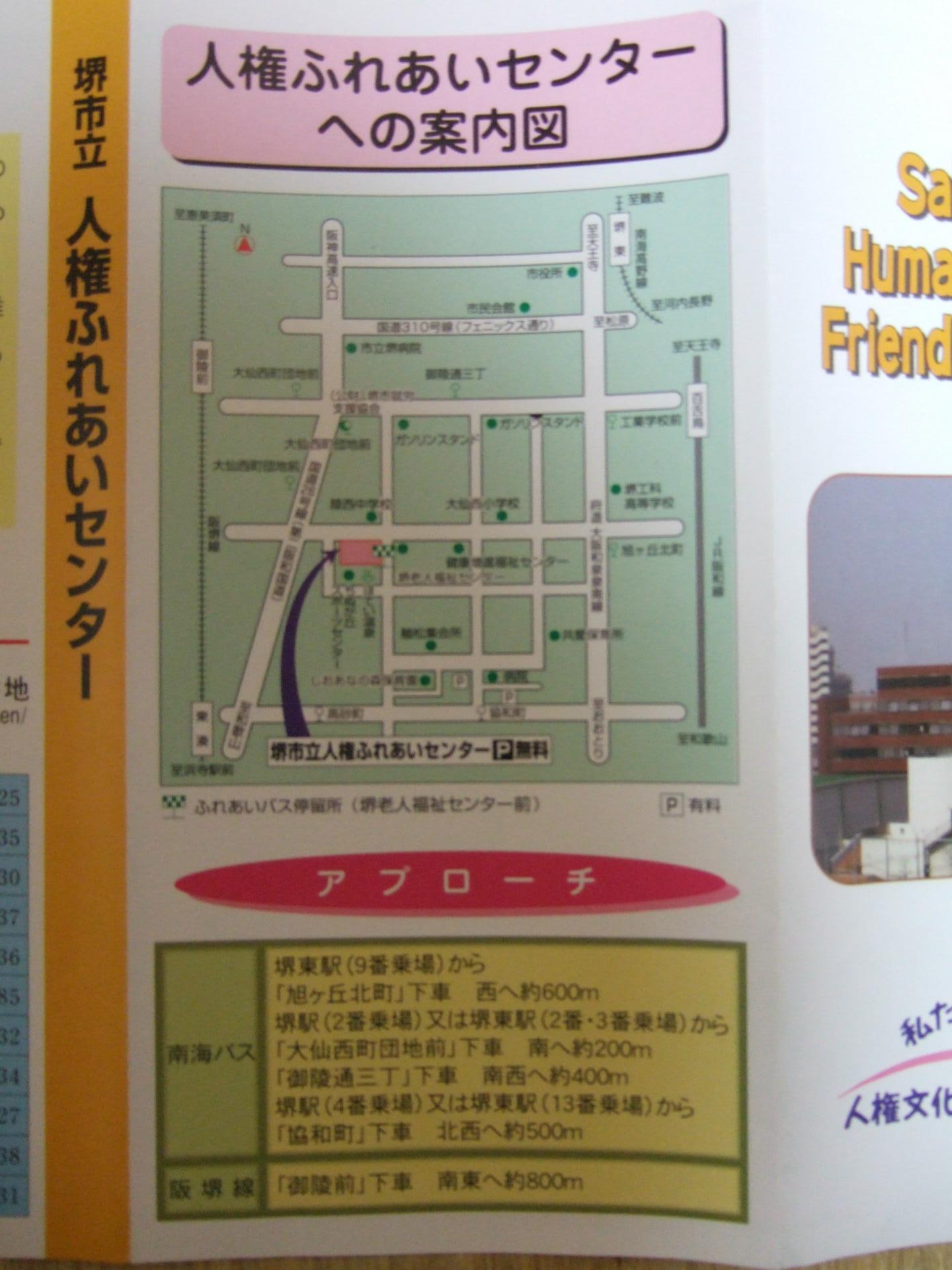明けましておめでとうございます。
さて、1月1日の読売新聞に、中百舌鳥小学校の通学路にて
登校時の見守りをして下さっている阪田幸男さんの記事が掲載されました。
阪田さんは現在90歳ですが、25年もの長い間ほとんど休まず
毎朝子どもたちを見守って下さっています。
読売新聞をご購読の方でまだ阪田さんの記事を読まれていない方は
ぜひ読んでみてください。

中百舌鳥小学校区には阪田さん以外にも何人もの見守り隊の方がいらっしゃいます。
昨年11月末に80歳で見守り隊を引退された松岡さんは中百舌鳥町1丁の踏切で8年間
毎朝子どもたちを見守ってくださいました。
子どもたち一人一人の顔を覚えてくださっていて誰がいつごろ踏切を通るのかまで
ご存知でした。
阪田様、松岡様、地域の見守り隊の皆様、本当にありがとうございます。
子どもたちは地域の方々の温かい気持ちに守られているのだと
あらためて感謝の気持ちでいっぱいになりました。
学校、保護者、地域の方々全てが尊重し合い手を取り合って子どもたちを
育てて行ける中百舌鳥小学校でありたいと心より願っています。
先生・保護者・地域の 皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、1月1日の読売新聞に、中百舌鳥小学校の通学路にて
登校時の見守りをして下さっている阪田幸男さんの記事が掲載されました。
阪田さんは現在90歳ですが、25年もの長い間ほとんど休まず
毎朝子どもたちを見守って下さっています。
読売新聞をご購読の方でまだ阪田さんの記事を読まれていない方は
ぜひ読んでみてください。

中百舌鳥小学校区には阪田さん以外にも何人もの見守り隊の方がいらっしゃいます。
昨年11月末に80歳で見守り隊を引退された松岡さんは中百舌鳥町1丁の踏切で8年間
毎朝子どもたちを見守ってくださいました。
子どもたち一人一人の顔を覚えてくださっていて誰がいつごろ踏切を通るのかまで
ご存知でした。
阪田様、松岡様、地域の見守り隊の皆様、本当にありがとうございます。
子どもたちは地域の方々の温かい気持ちに守られているのだと
あらためて感謝の気持ちでいっぱいになりました。
学校、保護者、地域の方々全てが尊重し合い手を取り合って子どもたちを
育てて行ける中百舌鳥小学校でありたいと心より願っています。
先生・保護者・地域の 皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。