しばらくブログを更新しませんでしたが、最近のバター不足問題を分析していて、データが不足していることに気付き、農畜産物生産量等に関するデータベース構築を行なっていました。
ようやく、新たなデータベースの完成を見ましたので、ブログを続けて行きたいと思います。
一応前回までで、最近のバイター不足の原因と思われることについて考察を行いましたが、乳製品全体の生産動向がどのように推移しているか、農林水産省の牛乳乳製品統計調査のデータを用いて、分析を行なってみましたので結果を報告いたします。
なお、分析方法は米国センサス局の季節調整法X-13を用いて行いました。
◇生乳の乳製品向け処理量生産量の推移について(再掲)
分析期間における乳製品向け処理量は、グラフ上では変動が大きく見えますが、平均的には289千トン±8千トン(2.6%)の周期的な増減変動で推移しています。
生乳は、牛乳等向けに優先的に回されることから、生乳から牛乳等向けの処理量を差し引いた残りが乳製品向けとなるわけですが、牛乳等向け処理量に合わせて生 乳生産量も減少しているにもかかわらず、乳製品向け処理量があまり変わらないのは乳製品総体ではある一定量の需要があるものと思われます。
(グラフをクリックすると拡大したグラフを見ることができます、以下も同じ。)
◇乳製品向け処理量と乳製品生産量との相関について
前回は、生乳の乳製品向け処理量とバター生産量の関係を見て来ましたが、今回は、その他の乳製品について乳製品向け処理量との関係を相関分析してみました。
以下は、その結果です。

この結果から、乳製品向け処理量と強い正の相関を示しているのは、バター生産量(相関係数:0.8085)、脱脂粉乳(0.6820)であり、加糖練乳も正の相関(0.3327)を示しています。
一方、負の相関を示しているのは、クリーム(-0.5902)、全粉乳(-0.4231)、アイスクリーム(-0.3046)となっています。
その他の乳製品は、相関係数が低く生産量も少なく、乳製品向け処理量と関係なく一定量の製品が生産されているものと思われます。
◇全粉乳生産量の推移について
分析期間における全粉乳生産量は、平均的には1,060トン±90トン(±8%)の範囲で変動となっていますが、乳製品向け処理量とは逆の増減(処理量が増えると生産量が減り、処理量が減ると生産量が増える)を示しています。
最近の生産量の動向は、乳製品向け処理量が減少する中にあって、生産量は2013年6月以降増加傾向が続いています。
◇脱脂粉乳生産量の推移について
分析期間における脱脂粉乳生産量は、平均的には12,100トン±1,360トン(±11.2%)の範囲でやや大きく変動し、2008年1月の14,400トンから2014年10月の9,900トンまで減少傾向で推移しています。
減少を年間ベースに直すと54,000トンの減少となりますが、バターと異なりこれだけ大きく減少しても、不足しているという話題にはなっていないようです。
脱脂粉乳という小売商品もあるようですが、バターほど一般的ではなく、ほとんどは製品原料用として使用されているためと思われます。
(参考)バター生産量と脱脂粉乳生産量との関係
生乳は遠心分離するとクリームと脱脂乳になり、クリームからはバターが作られ、脱脂乳から脱脂粉乳が作られます。
したがって、バターの生産量が増えると脱脂粉乳の生産量も増え、逆にバターが減ると脱脂粉乳も減るという関係にあります(決定係数(R2乗):0.8442)。
◇調製粉乳生産量の推移について
分析期間における調製粉乳生産量は、2011年5月、6月を堺に2分されています。
2008年1月から2011年6月の間は、平均的には2,720トン±170円(±6.4%)の範囲で変動しており、2011年6月から2014年10月までの間は、平均的には2025トン±170トン(±8.3%)の範囲で変動しています。
2011年3月の東日本大震災を堺に、需給バランスに変化があったのか、生産体制(施設)に変化があったのか、他のデータ等で検証してみなければ、確かなことは言えません。
機会があったら調べてみたいと思います。
◇バター生産量の推移について(再掲)
分析期間におけるバターの生産量は、平均的には5,800トン±600トン(9.5%)とやや大きな周期変動となっています。
最近では、この変動により、生産が減少傾向となると不足する事態が発生するようになってきています。
◇クリーム生産量の推移について
分 析期間におけるクリームの生産量は、2010年3月と4月を堺に様相が異なり、2008年1月から2010年3月の間は平均的には8,800トン±200 トン(±2.2%)の範囲で減少傾向で推移し、2010年4月から2014年10月の間は平均的には9,400トン±240トン(±2.5%)の範囲で増 加傾向で推移しています。
また、バターと異なり乳製品向け処理量が減少すると生産量が増加し、処理量が増加すると生産量が減少するという逆の関係(相関係数:-0.590)となっています。
バター生産量とクリームの生産量の関係は、バター生産量が増えるとクリーム生産量が減り、バター生産量が減るとクリーム生産量が増えるという逆の関係(相関係数:-0.912)となっています。
(参考)バター生産量とクリーム生産量との関係
バター生産量が増えるとクリーム生産量が減り、バター生産量が減るとクリーム生産量が増えるという、逆の関係(決定係数(R2乗);0.8312)が成り立っています。
原料である生乳(乳製品向け処理量)を遠心分離するとクリームと脱脂乳に分離します。
クリームをさらにチャーニング(クリームを撹拌して脂肪を包んでいるタンパク質の膜を破壊し、脂肪球どうしを結合させ塊にする工程)することでバターが作られます。
元は同じものですから、一方を増やせば一方が減るという関係にあります。
◇チーズ生産量の推移について
チーズの生産量については、国産のチーズと輸入チーズとで作られるプロセスチーズが含まれています。
したがって、乳製品向け処理量とチーズ生産量との関連性は非常に薄い(相関係数:-0.086)ということに注意が必要です。
分析期間におけるチーズの生産量は、2008年1月の10,300トンから2008年10月の9,600トンまで減少した後、2008年11月から増加傾向に転じ、若干の増減を繰り返しながら2013年9月の11,300トンまで増加傾向で推移しました。
その後、再び減少傾向となり2014年10月の10,300トンまで減少しています。
食生活が豊かになるとともにチーズの消費量が増え、生産量も増えてきていましたが、最近、経済が好転している中で生産量が減少していることは若干気がかりです。
家計調査でのチーズ消費量の推移等については、宿題とさせて下さい。
◇直接消費用ナチュラルチーズ生産量の推移について
先に述べたように、チーズには国産チーズと輸入チーズを混合したプロセスチーズがありますが、農林水産省の牛乳乳製品統計ではチーズ生産量の中に含まれている、消費者が直接消費する純国産のナチュラルチーズ分のデータを掲載しています。
分 析期間における直接消費用ナチュラルチーズ生産量は、20010年9月まで大きく増減を繰り返して推移しましたが、2010年10月の1,530トンから 2013年7月の1,950トンまではほぼ一貫した増加傾向に推移し、その後は1,900トン前後の横ばい状態となってきています。
◇加糖練乳生産量の推移について
分析期間における加糖練乳生産量は、平均的には3,000トン±160トン(±5%)程度の変動で、ほぼ乳製品向け処理量の増減と同じ傾向を示しています。
最近の動向は、2013年11月以降減少傾向が続いています。
◇無糖練乳生産量の推移について
分析期間における無糖練乳生産量は、2008年1月の83トン以降減少傾向が続き、2012年1月以降横ばい状態となってきていますが、2014年10月では56トンまで減少しています。
加糖練乳は一定量の需要量はあるが、無糖練乳は需要が無くなりつつあるものと思われます。
◇脱脂加糖練乳生産量の推移について
分析期間における脱脂加糖練乳生産量は、平均的には390トン±30トン(8.8%)の範囲でやや大きな変動を伴う緩やかな減少傾向で推移しています。
脱脂加糖練乳は脱脂乳に砂糖を加えて作られることから、バター生産過程の副次的製品という位置づけと思われます。
◇アイスクリーム生産量の推移について
分析期間におけるアイスクリーム生産量は、2008年の10,500トン前後から2014年10月の12,200トンまで、ほぼ一貫した増加傾向で推移しています。
アイスクリームの生産量が増えるとバター・脱脂粉乳の生産量が減るという逆の関係(相関係数:-0.6222、-0.8031)になっており、クリームとは正の相関(0.7942)になっています。
以上のように元となる原料(生乳)が同じなのに生産される乳製品はそれぞれ異なった動きとなっています。
基本的にはそれぞれの製品の需要によって生産(供給)が決まりますが、もう一つの大きな要素は同じ原料なのにそれぞれの製品向けの価格(乳価)が異なっていることも大きく影響していると思われます。
一例ですが、乳製品向け乳量の最大供給地である北海道における乳価は、2013年のホクレンの価格で、飲用向けは114円40千/Kg、バター・脱脂粉乳等向けは70円96銭/Kg、(生)クリーム向けは75円50銭/Kg及びゴーダチーズ向けは53円/Kgとなっています。










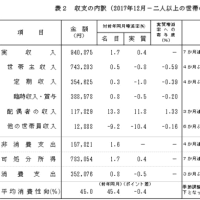
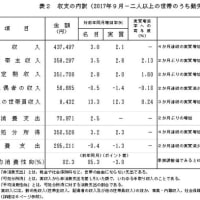
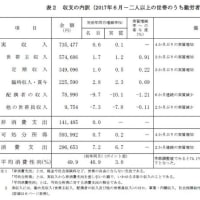







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます