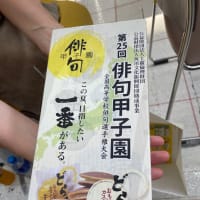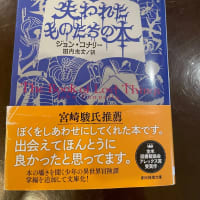今年の目標に(ってもう十月だけど)、ひと月一冊の句集を読む事にした。第一冊目は、瀬戸内寂聴句集「ひとり」。
紅葉燃ゆ旅立つ朝の空や寂 寂聴
第一句にまず驚いた。「空寂」という言葉に憧れる私は、この季語との取り合わせにはっとした。上五・中七と普通に読めば、旅立ちの朝の燃えるような紅葉に高揚する作者の熱が感じられるが、下五の「空や寂」を見て一気にその熱が拡散する思いがした。冷えるのではなく、広がってゆく。
葛城の山懐に寝釈迦かな 阿波野青畝
この句の下五にも驚いた。「葛城の山懐に紅葉かな」なら普通だが、下五に寝釈迦が出て来たら驚く。驚いて読み返すと、改めて寝釈迦を懐に抱く安らかな葛城山の緑が見えて来る。そして懐に抱かれる釈迦の、天上天下唯我独尊と唱えた赤子から、青年となり、出家し、托鉢し、説法し、林の中で入滅した一生が、一瞬に胸に迫って来るのである。
ここまできて、紅葉の句を再読すると、旅立つのは誰なのだろう? という問いにぶつかる。先に逝かれた方への追悼句だろうか? 否、やはりこれは作者の旅立ち、と私は感じる。作者だけではない。命ある者がこの世を旅立つ朝の紅葉は燃えるように赤く、心は空と寂に満ちあふれおそれるものはない。安らかに静かに強く脈打つ赤をこの紅葉は見せてくれる。正岡子規の好きだった赤もこの赤、命の燃ゆる赤、だったのではないだろうか。
<後日、黒田先生から、"旅立つ朝"とは(寂聴先生が)五十一歳で出家得度された日の朝、もう一つのこの世への旅立ちです、と教えて頂いた。がーん。そりゃそうだ! なんで私は分からなかったの?! 姉達の生前葬じゃないけれど、何となく辞世の句が先に出来ちゃったのかな? と思ってた私はやはり愚かもの。だが、この句の紅葉が益々好きになった。季語「紅葉」は私だけの暗号で、私の娘達を意味する。二人とも十一月生れ。紅葉を見ながら二人とも出産したので。>
その他、好きな二十句を写す。
寂庵の男雛は黒き袍を召し
氷柱燦爛訪ふ人もなき草の庵
雛飾る手の数珠しばしはづしをき
子を捨てしわれに母の日喪のごとく
秋時雨烏帽子に似たる墓幽か
ひとり居の尼のうなじや虫しぐれ
ひと言に傷つけられしからすうり
鳥渡る辛い手紙を読みさして
寂庵に誰のひとすぢ木の葉髪
出離へのわが旅清め野火熾ん
標的を朝日まづ射る寒稽古
星ほどの小さき椿に囁かれ
秋冷や源氏古帖の青表紙
雛の間に集ひし人のみな逝ける
鈴虫を梵音と聴く北の寺
老いし身も白くほのかに柚子湯かな
待ち待ちし軀の中まで天の川
骨片を盗みし夢やもがり笛
法臘は十三にして冬紅葉
御山のひとりに深き花の闇