
先週、鹿児島に行って来ました。神戸からだと飛行機であっという間。国宝になった霧島神宮から指宿に南下。砂蒸し温泉は快適でしたね。開聞岳から北上して、鹿児島市。仙厳園はソフトクリーム食べる外人ばっかり。鶴丸城は遺構が少なく残念でした。桜島に渡りました。火山ですねえ。しかし曇りが多く、すかっとしたお山は見れず。薩摩藩の外城である麓は、知覧と出水の武家屋敷。薩摩と大隅国分寺跡も整備され、土から掘り出された隼人塚も驚きました。暖かかったです。
と言うことで、今回はヤッシャ・ホーレンシュタインの演奏です。以前にマーラーの演奏を取り上げた記憶があります。1898年ウクライナのキーウ生まれで1973年に74才で逝去された指揮者ですね。私が音楽を聴き始めたことは、よく名を聞いていました。セラフィムの千円盤で、マーラーの交響曲第4番を買いましたね。マーラーをよく振っていた印象がありました。しかし、没後半世紀がたち、演奏も忘れられているのですか、ほとんど名を聞かなくなりましたねえ。
そんな中、少し前に何を思ったか(失礼)、Veniasから出ていた「ヤッシャ・ホーレンシュタイン・コレクション(43CD)」を買いました。このレーベルは、権利切れの音源などを集めて、演奏家別に激安BOX化して発売していることで知られていますね。私も、いくつかのBOXを買いました。枚数が多いので、それなりの満足感と達成感が得れる?のでありますが、なかなかすべてを聴き通すのは、しんどいのも事実であり、いつのまにか「積どく」になっているのでした笑。
しかし、このホーレンシュタインのBOXを買ったのはなぜか、あまりよく憶えていないのです。これまで、この指揮者を聴いたことはあまりあるわけでもなかったですし、おそらく43枚で4000円ほどや、残部が少ないなどのことに「魅力」を感じたんですかねえ。まあいろいろありますが、ボツボツ聴いていこう、ということになりました。しかし、ほんとにいろんな曲がありますねえ。見ているとほんとに楽しくなります。これがこんなBOXものの魅力ですかねえ。
その中で、ハイドンの交響曲の演奏が4曲ありました。94番、100番、101番、104番です。どれも有名曲です。94番は1929年の録音。でもそれほど聴きにくいこともなかったですが、101、104番はステレオ録音なんで、これを取り上げるということで。オケはウィーン交響楽団です。1957年録音。
ハイドンの交響曲の演奏って、いまや古楽全盛、どころかモダンオケによる演奏なんてもう駆逐されてしまった感があるんですかね。ホーレンシュタインの演奏は、そんなこととはまったく対極にある演奏、つまりモダン楽器による、ゆったりとしたテンポで、実に恰幅のいい、分厚い音とスケールの大きい、堂々としたものであります。逆に、聴いたときは、なんだか新鮮な感覚を持ったのでした。やはりこんな演奏、好きだなあ、と。加えて、この演奏を聴いて、いいなと思ったのですが、それはこの演奏の豊かで深い表現でありました。うーん濃厚な表情ですよねえ。
『時計』では、第一楽章の序奏からゆったりと憂いに満ちた表情。それが主部に入ると一転、快活でダイナミックな演奏となり、とても爽快。第2楽章、4つの変奏曲。まず主題がチャーミングに語られてのち、第一変奏では深い短調での慟哭、第二変奏では、木管が快活に歌う。そして第三・第四でもそれそれの特徴を巧みに表現して、とても心地よいのでありました。第三楽章メヌエット。ハイドンのメヌエットは、派手さはないのですがメヌエットの基本を忠実に履行しながら、とても味わい深いものになっています。このメヌエットは堂々として豪快。そして中間部ではそれぞれの楽器が巧みに歌う。ホーレンシュタインの上手い指揮であります。終楽章。豪快なメヌエットのあと、控え目に演奏。そして、これで終わりのまとめの音楽が展開される。ハイドンの音楽が非常に豊かで、個性あふれるものであることを、とても上手く表現している演奏であります。
ロンドンでも第1楽章、堂々として息の長い深い序奏から、スケールに大きな主部に入り、この心地よさがとてもいい。第二楽章は変奏曲。実に穏やかに愛らしい主題が奏でられていく。第3第三楽章メヌエットも、堂々として元気一杯。そして終楽章、以前にも指摘したが、「さあ、みんなで終わりましょう」的な表情は、ホーレンシュタインもななんだかよくわかっておられますね、と私的には大満足でありました。こんなハイドン、最近ではなかなか聴けませんねえ。
何時までも寒いねえ、と思いきや、急に暖かくなりました。こんな急な温度変化では着る服も悩んでしまいます。昨日も所用で姫路に行きましたが、お城の周辺、暖かく快適でありました。いよいよ春ですねえ。
(Venias VN027 2017年 輸入盤)
と言うことで、今回はヤッシャ・ホーレンシュタインの演奏です。以前にマーラーの演奏を取り上げた記憶があります。1898年ウクライナのキーウ生まれで1973年に74才で逝去された指揮者ですね。私が音楽を聴き始めたことは、よく名を聞いていました。セラフィムの千円盤で、マーラーの交響曲第4番を買いましたね。マーラーをよく振っていた印象がありました。しかし、没後半世紀がたち、演奏も忘れられているのですか、ほとんど名を聞かなくなりましたねえ。
そんな中、少し前に何を思ったか(失礼)、Veniasから出ていた「ヤッシャ・ホーレンシュタイン・コレクション(43CD)」を買いました。このレーベルは、権利切れの音源などを集めて、演奏家別に激安BOX化して発売していることで知られていますね。私も、いくつかのBOXを買いました。枚数が多いので、それなりの満足感と達成感が得れる?のでありますが、なかなかすべてを聴き通すのは、しんどいのも事実であり、いつのまにか「積どく」になっているのでした笑。
しかし、このホーレンシュタインのBOXを買ったのはなぜか、あまりよく憶えていないのです。これまで、この指揮者を聴いたことはあまりあるわけでもなかったですし、おそらく43枚で4000円ほどや、残部が少ないなどのことに「魅力」を感じたんですかねえ。まあいろいろありますが、ボツボツ聴いていこう、ということになりました。しかし、ほんとにいろんな曲がありますねえ。見ているとほんとに楽しくなります。これがこんなBOXものの魅力ですかねえ。
その中で、ハイドンの交響曲の演奏が4曲ありました。94番、100番、101番、104番です。どれも有名曲です。94番は1929年の録音。でもそれほど聴きにくいこともなかったですが、101、104番はステレオ録音なんで、これを取り上げるということで。オケはウィーン交響楽団です。1957年録音。
ハイドンの交響曲の演奏って、いまや古楽全盛、どころかモダンオケによる演奏なんてもう駆逐されてしまった感があるんですかね。ホーレンシュタインの演奏は、そんなこととはまったく対極にある演奏、つまりモダン楽器による、ゆったりとしたテンポで、実に恰幅のいい、分厚い音とスケールの大きい、堂々としたものであります。逆に、聴いたときは、なんだか新鮮な感覚を持ったのでした。やはりこんな演奏、好きだなあ、と。加えて、この演奏を聴いて、いいなと思ったのですが、それはこの演奏の豊かで深い表現でありました。うーん濃厚な表情ですよねえ。
『時計』では、第一楽章の序奏からゆったりと憂いに満ちた表情。それが主部に入ると一転、快活でダイナミックな演奏となり、とても爽快。第2楽章、4つの変奏曲。まず主題がチャーミングに語られてのち、第一変奏では深い短調での慟哭、第二変奏では、木管が快活に歌う。そして第三・第四でもそれそれの特徴を巧みに表現して、とても心地よいのでありました。第三楽章メヌエット。ハイドンのメヌエットは、派手さはないのですがメヌエットの基本を忠実に履行しながら、とても味わい深いものになっています。このメヌエットは堂々として豪快。そして中間部ではそれぞれの楽器が巧みに歌う。ホーレンシュタインの上手い指揮であります。終楽章。豪快なメヌエットのあと、控え目に演奏。そして、これで終わりのまとめの音楽が展開される。ハイドンの音楽が非常に豊かで、個性あふれるものであることを、とても上手く表現している演奏であります。
ロンドンでも第1楽章、堂々として息の長い深い序奏から、スケールに大きな主部に入り、この心地よさがとてもいい。第二楽章は変奏曲。実に穏やかに愛らしい主題が奏でられていく。第3第三楽章メヌエットも、堂々として元気一杯。そして終楽章、以前にも指摘したが、「さあ、みんなで終わりましょう」的な表情は、ホーレンシュタインもななんだかよくわかっておられますね、と私的には大満足でありました。こんなハイドン、最近ではなかなか聴けませんねえ。
何時までも寒いねえ、と思いきや、急に暖かくなりました。こんな急な温度変化では着る服も悩んでしまいます。昨日も所用で姫路に行きましたが、お城の周辺、暖かく快適でありました。いよいよ春ですねえ。
(Venias VN027 2017年 輸入盤)











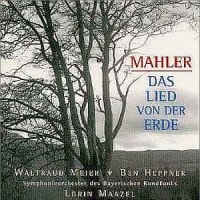
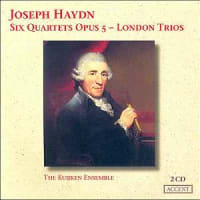
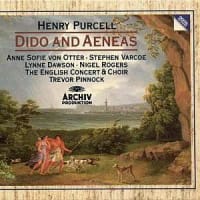











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます