
3月12日は、このブログを初めて7,000日となる日でした。ほとんど意識していなかったんですが、もうそんなになりますか、って感じですかね。7,000日というと19年と少し。まあ、飽きもせず続けてきたこと、その20年の間に私自身、そして家族、世間、いろんな変化がありました。その20年の間、音楽を熱心に聴き続けてきた、聴き続けて来れたことに、感謝しなければならいのだろうと思います。
そんなことをしみじみ思ったのは、その前日の3月11日は、東日本大震災から14年目となる日でした。私に取っても、2012年から18年まで7年間、宮城県の七ヶ浜、名取、石巻にボランティアに行っていたこともあり、そのとき多くの方々と接したこともあり、自分自身が経験した阪神淡路大震災と同じくらいの思いがあるのでした。
その14年目の3月11日の前日にNHKで『感想戦 3月11日のマーラー』という番組が放送されました。震災発生の2011年3月11日の夜、東京墨田区の墨田トリフォニーホールで行われたダイニエル・ハーディング指揮NJPOによるマーラーの交響曲第5番の演奏会をその演奏者や関係者、そして観客が振り返るものでした。震災が発生した日、余震が続き、地震に加えて津波の来襲が報じられ、東京では多くの帰宅困難者があふれる中、観客105人の中、実施されたこのコンサートのことは、これまで聞いたことはありました。
まず、「あの日の団員の精神状態を考えると奇蹟的だった」「あの演奏、あの日のコンサートで、僕らは辛い気持ち、不安なきもち、心の痛みを音に出せることを証明した」という全体的な感想。しかし、開演前は、コンサートの決行を冗談かと思ったとか、やるからにはいい演奏がしなければならないが、東北出身の団員もいる中、こんな状況でできるのか。そしてオケも精神状態を反映して、不安な音だったそうです。しかし、ハーディングは「あのような時だからこそ一人でない、仲間がいることの心強さが必要だ。演奏会を開けば、同僚、観客、そして音楽が側にいることに気づき、けっして一人にはならない」とし、決して勇敢だから演奏をしたのではなかったようです。
演奏は「異様な集中力と緊張感みたいな鳥肌がたつような響きが感じられた。こんな状況の中でとんでもない演奏をするんではないか」「多くの方が東北のことを思って願いを込めて弾いていたと思う」「最初の音からまったく違う音の鳴り方をしていた。一生懸命に何かを表現したい思いが非常に出た」「とてもつらい思いをしている方々のところへ寄り添っているような不思議な気持ちで入り込めた」「楽器を吹くことで気持ちがリラクッスできる。何もしていないと本当に恐かったので、音楽の力で地震を抑えることができるんじゃないか」また、津波で流された現地の思い出を一生懸命かき集めるように演奏した、と。そして、「終わった瞬間、お客さんの拍手とブラボーの声、立って拍手をしてくださる方もたくさんいた…涙をこらえるのが大変でした」
マーラーの5番は、普通の感覚では、葬送行進曲からはじまって、なんだかよくわからないうちに喜びに変わり終わる、とまあマーラーにはよくある不思議な曲に思ってしまう。しかし、この時の演目としては、このマーラーのこの曲の暗から明、苦しみから喜びへ、という図式はよかったと思ったし、マーラーの曲が本当に心に染み込んできたのではないか、と思いました。阪神淡路大震災が起こった日は、家具が倒れたり、食器が割れたりの被害があった程度でしたが、周囲の甚大な被害とこれからの余震への恐怖とで、とても平常心ではおれなかった。この3月11日は、それ以上の動揺があった中での演奏ですから、この日のマーラーが演奏者と観客にとっては何ものにも代え難いものになったろうと思います。
私は、この曲は過去一度しか実演では聴いたことがありません。2011年10月16日倉敷での上岡敏之指揮ヴッパータール響の演奏でした。この当時、私は入院中の母の介護で毎週末岡山に行ってました。このコンサートもそのついでに行こう、と思って券を買いました。しかし、その母は一か月前に亡くなりました。この日は久々に、それも母のいない岡山に行くという、それなりに複雑な気持ちだったことを憶えています。そして聴いたマーラーの5番は、たいそう心に響き、心に入って来る演奏でした。この曲のよさをこのように感じたことはありませんでした。
3月11日のコンサートに、会場の近くに住んでられて、一番速く会場に来られたという女性の方が、この日会場で購入したハーディング指揮のこの曲のCD、ラックに入れてあり毎日目にしているのだが、一度も聴いたことがない、と言われてました。少し違うかも知れませんが、私はコンサートが終わったあと、普通はその曲を違う演奏でも聴くのですが、この日は倉敷から神戸に帰る車の中でもまったく聴く気にならなかったことを思い出しました。
そんなことで、先週末から、マーラーの交響曲第5番を幾度か聴きました。演奏はクラウス・テンシュテット指揮ロンドンPOのセッション録音による全集からのものでした。
そんなことをしみじみ思ったのは、その前日の3月11日は、東日本大震災から14年目となる日でした。私に取っても、2012年から18年まで7年間、宮城県の七ヶ浜、名取、石巻にボランティアに行っていたこともあり、そのとき多くの方々と接したこともあり、自分自身が経験した阪神淡路大震災と同じくらいの思いがあるのでした。
その14年目の3月11日の前日にNHKで『感想戦 3月11日のマーラー』という番組が放送されました。震災発生の2011年3月11日の夜、東京墨田区の墨田トリフォニーホールで行われたダイニエル・ハーディング指揮NJPOによるマーラーの交響曲第5番の演奏会をその演奏者や関係者、そして観客が振り返るものでした。震災が発生した日、余震が続き、地震に加えて津波の来襲が報じられ、東京では多くの帰宅困難者があふれる中、観客105人の中、実施されたこのコンサートのことは、これまで聞いたことはありました。
まず、「あの日の団員の精神状態を考えると奇蹟的だった」「あの演奏、あの日のコンサートで、僕らは辛い気持ち、不安なきもち、心の痛みを音に出せることを証明した」という全体的な感想。しかし、開演前は、コンサートの決行を冗談かと思ったとか、やるからにはいい演奏がしなければならないが、東北出身の団員もいる中、こんな状況でできるのか。そしてオケも精神状態を反映して、不安な音だったそうです。しかし、ハーディングは「あのような時だからこそ一人でない、仲間がいることの心強さが必要だ。演奏会を開けば、同僚、観客、そして音楽が側にいることに気づき、けっして一人にはならない」とし、決して勇敢だから演奏をしたのではなかったようです。
演奏は「異様な集中力と緊張感みたいな鳥肌がたつような響きが感じられた。こんな状況の中でとんでもない演奏をするんではないか」「多くの方が東北のことを思って願いを込めて弾いていたと思う」「最初の音からまったく違う音の鳴り方をしていた。一生懸命に何かを表現したい思いが非常に出た」「とてもつらい思いをしている方々のところへ寄り添っているような不思議な気持ちで入り込めた」「楽器を吹くことで気持ちがリラクッスできる。何もしていないと本当に恐かったので、音楽の力で地震を抑えることができるんじゃないか」また、津波で流された現地の思い出を一生懸命かき集めるように演奏した、と。そして、「終わった瞬間、お客さんの拍手とブラボーの声、立って拍手をしてくださる方もたくさんいた…涙をこらえるのが大変でした」
マーラーの5番は、普通の感覚では、葬送行進曲からはじまって、なんだかよくわからないうちに喜びに変わり終わる、とまあマーラーにはよくある不思議な曲に思ってしまう。しかし、この時の演目としては、このマーラーのこの曲の暗から明、苦しみから喜びへ、という図式はよかったと思ったし、マーラーの曲が本当に心に染み込んできたのではないか、と思いました。阪神淡路大震災が起こった日は、家具が倒れたり、食器が割れたりの被害があった程度でしたが、周囲の甚大な被害とこれからの余震への恐怖とで、とても平常心ではおれなかった。この3月11日は、それ以上の動揺があった中での演奏ですから、この日のマーラーが演奏者と観客にとっては何ものにも代え難いものになったろうと思います。
私は、この曲は過去一度しか実演では聴いたことがありません。2011年10月16日倉敷での上岡敏之指揮ヴッパータール響の演奏でした。この当時、私は入院中の母の介護で毎週末岡山に行ってました。このコンサートもそのついでに行こう、と思って券を買いました。しかし、その母は一か月前に亡くなりました。この日は久々に、それも母のいない岡山に行くという、それなりに複雑な気持ちだったことを憶えています。そして聴いたマーラーの5番は、たいそう心に響き、心に入って来る演奏でした。この曲のよさをこのように感じたことはありませんでした。
3月11日のコンサートに、会場の近くに住んでられて、一番速く会場に来られたという女性の方が、この日会場で購入したハーディング指揮のこの曲のCD、ラックに入れてあり毎日目にしているのだが、一度も聴いたことがない、と言われてました。少し違うかも知れませんが、私はコンサートが終わったあと、普通はその曲を違う演奏でも聴くのですが、この日は倉敷から神戸に帰る車の中でもまったく聴く気にならなかったことを思い出しました。
そんなことで、先週末から、マーラーの交響曲第5番を幾度か聴きました。演奏はクラウス・テンシュテット指揮ロンドンPOのセッション録音による全集からのものでした。












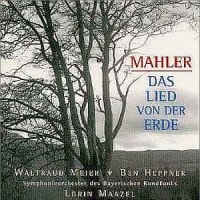
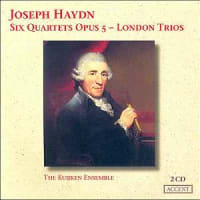
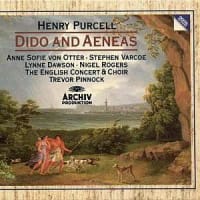










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます