今回のフォーラムでテーマになった納豆は<藁苞(つと)納豆>である.大徳寺納豆などの寺納豆・塩納豆とよばれる麹菌納豆ではなく、納豆菌で大豆を発酵させた糸引き納豆、すなわち我々が今日食べている類のものである.ただ、技術の進歩であのパックに入れられ安く手に入れられるものではなく、ここ京北に昔から伝えられ現在も、以前ほどではないが、家庭で作られている<藁苞>納豆がテーマである.
パネリストの久保功先生は、野菜文化研究センター代表という肩書きで紹介されていたけれど、<木簡広報人>と自称されていて、木簡に書かれていた史実と野菜の歴史・それを支えた人の交流、更に野菜を中心とした<食>の事を話し始められたら止まらない人である.先生の底に流れている考えはゼミナールハウス友の会だより 58号(平成6年1月)に書いておられる;
>グルメだ高級志向だとはしゃぎ廻って、野菜や文化源流への評価と感謝を
>忘れた飽食時代に長屋王は警告のメッセージを送ってきたのかもしれません.
という文章に垣間見える.
そして今回も、野菜の歴史や人の交流、食育などについてお話を聞かせて貰えた.
もう1人のパネリスト、三田邦彦氏は実際に納豆製造会社を経営しておられる立場からの話を聞かせて貰ったが、そのなかで<発生>と<発祥>は違う、と指摘されたのが耳に残った.氏の説明でもその違いはよく分からなかったが( ^_')発祥は歴史を経てのものなのであろう.
今回のフォーラムで取り上げられたテーマに、食育、地域活性化、などもあった.単なる発祥の地云々でなく、藁苞納豆の底に横たわる、歴史、交流、農業、食育などに話が及んだのは、発表者たる長谷川哲善君が実際に京北へ足を運び自ら大豆を栽培して納豆に仕上げた取り組みや、主催者のNPO法人フロンティア協会の徳丸國廣氏の哲学がその基礎にあると思った.
美味しい藁苞納豆を作るには、良質の大豆、無農薬の藁、それに適した気候(平均気温が低くなければならない)などの要素が必要だが、コンバインで収穫される今日、藁を手に入れることが難しいし、また無農薬の稲でないと安心して食べられない(ちなみに藁は熱湯消毒されるが、納豆菌は死滅しない).機械化に適していない.無農薬でお米を育てるのも手間がかかるし、刈り入れも大変だ.こういった問題をクリアーして藁苞納豆が出来るのである.
ここで思うのであるが;
・こういった農作業を都会の自然体験を希望する人たちに場を提供することで都市農村の交流の場に活用できないか?
・こういった活動に都会の子供が参加してくれるのは<食育>に役立つのではないか?
・納豆を煮て寝かすのは<主婦パワー>を活かせないか?(農家の主婦で加工品を作って販売する会社をつくっておられる成功例もある)
・ただこうして手間暇をかけて作った納豆が果たして商業ベースにのるのであろうか?
今回の納豆フォーラムに参加させていただいて、故郷の歴史や文化を思い、先人から何を学び、何を伝承し、何を発信できるか、いろいろな刺激をくれた.そいう意味で僕にはいいフォーラムだった.ありがとうございました.
閑話休題;
ちょっと余談になってしまいますが、納豆発祥の地をキーワードにインターネットをあちこちブラウジングしていたら、納豆発祥の地として石碑まで作っているところもあるという.
こんなのを見ていると、ふと司馬遼太郎さんがその「街道をゆく」<仙台>で、日本三景のひとつ松島を訪れたさい;
-----------------------------------------------------------------
塩釜から舟を漕ぎだしたときは、古人を思い、古歌を思い、心のふるえるような気分
だったにちがいない.そういう芭蕉が、
松島や ああ松島や 松島や
などとノンキなトウサンのような句をつくるだろうか.松島の観光にたずさわるひとたちは、
いますこし芭蕉に対して粛然たる気持ちをもってやってほしいものである.
<途中略>
人の運命は、はかない.そういうかれが、駄じゃれのような句をかれの作として観光客
の目に曝されつづけているのである.李白や杜甫やゲーテは、こういう目に遭っている
だろうか.
------------------------------------------------------------------
と書いておられるのを思い出した、
石碑を作るのは伝承を伝えるにはそれなりの役目もあるのだろうが、何か薄っぺらいもの感じざるを得ない..
それと納豆のことの勉強になる次のサイトを紹介しておきます;
「お豆腐ランド」というサイトにある<納豆横町>というページ
<納得できる納豆の話>
の二つはお勧めです.
パネリストの久保功先生は、野菜文化研究センター代表という肩書きで紹介されていたけれど、<木簡広報人>と自称されていて、木簡に書かれていた史実と野菜の歴史・それを支えた人の交流、更に野菜を中心とした<食>の事を話し始められたら止まらない人である.先生の底に流れている考えはゼミナールハウス友の会だより 58号(平成6年1月)に書いておられる;
>グルメだ高級志向だとはしゃぎ廻って、野菜や文化源流への評価と感謝を
>忘れた飽食時代に長屋王は警告のメッセージを送ってきたのかもしれません.
という文章に垣間見える.
そして今回も、野菜の歴史や人の交流、食育などについてお話を聞かせて貰えた.
もう1人のパネリスト、三田邦彦氏は実際に納豆製造会社を経営しておられる立場からの話を聞かせて貰ったが、そのなかで<発生>と<発祥>は違う、と指摘されたのが耳に残った.氏の説明でもその違いはよく分からなかったが( ^_')発祥は歴史を経てのものなのであろう.
今回のフォーラムで取り上げられたテーマに、食育、地域活性化、などもあった.単なる発祥の地云々でなく、藁苞納豆の底に横たわる、歴史、交流、農業、食育などに話が及んだのは、発表者たる長谷川哲善君が実際に京北へ足を運び自ら大豆を栽培して納豆に仕上げた取り組みや、主催者のNPO法人フロンティア協会の徳丸國廣氏の哲学がその基礎にあると思った.
美味しい藁苞納豆を作るには、良質の大豆、無農薬の藁、それに適した気候(平均気温が低くなければならない)などの要素が必要だが、コンバインで収穫される今日、藁を手に入れることが難しいし、また無農薬の稲でないと安心して食べられない(ちなみに藁は熱湯消毒されるが、納豆菌は死滅しない).機械化に適していない.無農薬でお米を育てるのも手間がかかるし、刈り入れも大変だ.こういった問題をクリアーして藁苞納豆が出来るのである.
ここで思うのであるが;
・こういった農作業を都会の自然体験を希望する人たちに場を提供することで都市農村の交流の場に活用できないか?
・こういった活動に都会の子供が参加してくれるのは<食育>に役立つのではないか?
・納豆を煮て寝かすのは<主婦パワー>を活かせないか?(農家の主婦で加工品を作って販売する会社をつくっておられる成功例もある)
・ただこうして手間暇をかけて作った納豆が果たして商業ベースにのるのであろうか?
今回の納豆フォーラムに参加させていただいて、故郷の歴史や文化を思い、先人から何を学び、何を伝承し、何を発信できるか、いろいろな刺激をくれた.そいう意味で僕にはいいフォーラムだった.ありがとうございました.
閑話休題;
ちょっと余談になってしまいますが、納豆発祥の地をキーワードにインターネットをあちこちブラウジングしていたら、納豆発祥の地として石碑まで作っているところもあるという.
こんなのを見ていると、ふと司馬遼太郎さんがその「街道をゆく」<仙台>で、日本三景のひとつ松島を訪れたさい;
-----------------------------------------------------------------
塩釜から舟を漕ぎだしたときは、古人を思い、古歌を思い、心のふるえるような気分
だったにちがいない.そういう芭蕉が、
松島や ああ松島や 松島や
などとノンキなトウサンのような句をつくるだろうか.松島の観光にたずさわるひとたちは、
いますこし芭蕉に対して粛然たる気持ちをもってやってほしいものである.
<途中略>
人の運命は、はかない.そういうかれが、駄じゃれのような句をかれの作として観光客
の目に曝されつづけているのである.李白や杜甫やゲーテは、こういう目に遭っている
だろうか.
------------------------------------------------------------------
と書いておられるのを思い出した、
石碑を作るのは伝承を伝えるにはそれなりの役目もあるのだろうが、何か薄っぺらいもの感じざるを得ない..
それと納豆のことの勉強になる次のサイトを紹介しておきます;
「お豆腐ランド」というサイトにある<納豆横町>というページ
<納得できる納豆の話>
の二つはお勧めです.










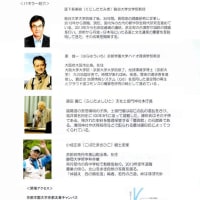
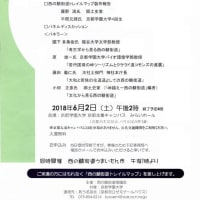
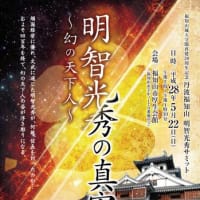


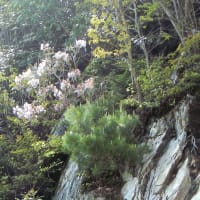


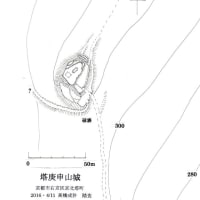

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます