 7月16日(土)
7月16日(土)平成24年のNHK大河ドラマは「平清盛」(マツケン主演)です。

前回2月にも神戸(兵庫)の史跡を少し紹介していますが、この神戸一帯は「平清盛」と平家に縁が深い地なんです。
「福原京」は現在の兵庫県神戸市中央区から兵庫区北部にあたり、平氏の拠点のひとつである貿易港の「大輪田泊(現在の兵庫港・神戸港西部)」に人工島の経が島(経ヶ島)を築き、整備拡張した港を見下ろす山麓に都を置くことが計画されました。
1180年「平清盛」は「高倉上皇」と平家一門の反対を押し切って遷都を強行しましたが、それは宋との貿易拡大によって海洋国家の樹立を目指したためともいわれ、都市整備が進めば平氏政権による「福原幕府」のようなものになったともいわれています。
しかし都造りは途中で頓挫し、たった半年で平安京に還都したため実態としての都は完成せず、建造物群は都落ちの際「源義仲(木曾義仲)」によって全て焼き払われました。

現在は兵庫県神戸市兵庫区福原町という地名があるんだけど、福原町は明治以降に付けられた地名で「福原京」とは直接の関係は無いみたいです。

現在の福原町(柳筋)はソープランドが密集している地区として有名で…以前多くの教え子が入ってた寮がその付近にあったなぁ…

それでは食事に行くついでやブラ~っと散歩がてらにハントした、その他の神戸周辺の源平史跡等をまとめて紹介します。


これは「荒田八幡神社」です。


この地は、池の大納言「平頼盛(清盛の弟)」の山荘があった場所で、治承4年(1180年6月3日)の「福原」遷都のとき「安徳天皇」の行在所…いわゆる皇居となった所です。

これは「荒田八幡神社」の近くにある「薬王山宝地院」です。
「安徳天皇」の御菩提を弔うために弘安2年(1279年)に創建されました。
この辺り一帯が「平頼盛」の山荘だったようです。

これは「熊野神社」です。

「平清盛」が「福原」遷都に際し、「後白河法皇」がご崇敬の厚い紀州熊野権現を皇城鎮護の神として東南に奉鎮したと伝えられています。


これは「祇園神社」です。

「平清盛」は経ケ島を築造の際、ここにあった山寺で海潮を聞きながら計画を練ったと伝えられています。

毎年7月13日~20日まで「祇園祭」があり、その準備がされていました。


15日に教え子と一緒に行って来たので、また別で紹介します。(今回は史跡の紹介のみってことで…)

「牛頭天王由来記」によると869年「京都」では疫病がはやり、 これらの原因は政治で失脚した人々の祟りであるといわれました。
そこで播州「広峰神社」(姫路)に祀られている「牛頭天王(スサノオノミコト)」がこれらの祟りを治めるのに力があるという事が分かり、京都「八坂神社」へ分霊を移す途中、その神輿が1泊したのが神社の起源といわれています。

これは「塞神の碑」です。
「塞神」というのは道祖神で、邪気を払う守り神として村の入り口や道端に祀られました。
また、ここでは道路拡幅に伴う発掘調査で貴族の庭園跡の一部が発見されました。

この交差点は平野…「平清盛」がこの付近に住んでいたからでしょうか?


これは、その平野交差点近くの湊山小学校前にある「雪見御所」の跡です。

1168年「清盛」は「能福寺」にて出家し、約10年間「雪見御所」に移り住みます。
しかし、これは隠居ではなく京にいる一族らを通じて政界ににらみを利かせつつ、港湾施設の整備を着々と進め、宋船の瀬戸内海乗り入れを実現しました。
武士では初めて1167年に太政大臣に任ぜられ、1171年娘の徳子を「高倉天皇」に入内させ「平氏にあらずんば人にあらず」と言われる時代(平氏政権)を築いたのです。


これは「平清盛」が「福原」遷都の際「厳島神社」を勧請し祀った七弁天の一つ「氷室神社」です。
平家が三草山で破れ、「源義経」が鵯越に向かっているのを知り、能登守「平教経」が陣をおいたのもこの辺りといわれています。

「七弁天」の中では“恋愛”に御利益があるらしく、「れんあい弁天」(えんむすびの神)“愛のパワースポット”らしいです。

ちなみに「七弁天」は他に…
・和田神社(あんぜん弁天)
・真光寺(おんがく弁天)
・済鱗寺(べんきょう弁天)
・恵林寺(うんどう弁天)
・兵庫厳島神社(おしゃれ弁天)
・花隈厳島神社(けんこう弁天)
この「れんあい弁天」については由来を後で説明するけど、他のは何が由来なのか調べても分かりませんでした。

(特に由来なんて無いんだろうけどね…
 )
)
俺は、まだ恋愛は二の次かなぁ…まだやらねばならぬ事が多すぎだし、それが成功しなきゃ恋愛どころじゃないもんね。



中にはこのような恋愛成就のためのグッズや企画?がいろいろあるんだけど…場所が不便な所にあるんでね…


ここが何故“恋愛”に御利益があるのか?というと…源平合戦時「平通盛」と愛妻「小宰相」が別れを惜しんだ場所とされ、恋にまつわる言い伝えが多い…らしいです。

では、もう1つ…この付近の「夢野」に伝わる民話を。
はるかな昔「六甲山」のふもとに夫婦の鹿が住んでいました。
二頭の鹿は仲睦まじく暮らしていましたが、ある時、牡鹿(オス)は淡路島の野島に出かけて、そこに住んでいた牝鹿(メス)とすっかり仲良くなってしまいました。
それ以来、牡鹿は来る日も来る日も、海を渡って野島の牝鹿を訪れるようになったので、妻の牝鹿は寂しくてなりませんでした。

ある日、牡鹿は久しぶりに妻のところへやって来ました。
「実はね、昨日の夜、変な夢を見たのだよ。私の背中に雪が降り積もって、そこにススキがいくつも生えているんだ。これはいったいどういうことだろう。何かのお告げだろうか?」
妻の牝鹿は、牡鹿がいつも野島の牝鹿の所へ行くのをやめさせようと思って、ついこんなふうに言ってしまいました。
「それは、とても悪い夢ですわ。背中にススキが生えるというのは、猟師の矢が刺さるということです。それに雪が積もるというのは、肉を塩漬けにされるというお告げです。あなたがこれ以上野島に渡ったら、きっと人間の船に出会って、射殺されてしまうに違いありません。」
こんなふうに夢占いをしておけば、牡鹿はきっと自分の所にいてくれる…妻の牝鹿はそう思ったのでした。
牡鹿はちょっと気味悪く思ったので、しばらくの間は妻の所にいましたが、やはり野島の牝鹿のことが忘れられません。
ある日とうとう妻にかくれて、野島へ出かけてしまいました。
ところが赤石の海を泳ぎ進んで、もうすぐ野島に着くという時になって、運悪く猟師が乗った船と行き会ってしまったのです。
「おう、鹿が海を泳いでいるぞ!」
猟師はそう叫ぶや、弓を構え、矢を射かけました。
矢は牡鹿の背中に突き刺さり、牝鹿の夢占いのとおり、牡鹿は射殺されてしまったのでした。
それ以来、夫婦の鹿が住んでいた野を「夢野」と呼ぶようになりました。
人々は、牝鹿の夢占いが本当になってしまったのを、「夢占いというのは、良い方に占えば良いことが起こり、悪いように占えば、本当に悪いことが起こってしまうものだ。だから夢を悪く考えるものではない。」と語り伝えたそうです。
牡鹿が射殺された辺りの海は、今でも「鹿の瀬」と呼ばれています。
またこの時流れた牡鹿の血が固まって、海の底に赤い石ができ、それが現在の「明石」の地名の元になったとも言われています。
今の「夢野町」はウマの部屋から1、2分の所ですよ。


拝殿の裏に回り…


そこには「氷室稲荷神社」があります。


その更に裏の誰も入らないような所に入って行くと…日本最初の「氷室」があります。
これは「氷室の岩屋」といわれ、仁徳天皇の兄「糠田大中彦皇子」が遊猟の際にこの「氷室」を発見し、「仁徳天皇」に氷を献上したんだそうです。


「氷室神社」からの帰りに絶景ポイント発見


「ポートタワー」もよく見えるよ~



これは「夢野八幡神社」です。
「平清盛」の「福原」新都造営に先駆け、都の守護のために治承元年(1177年)に創建されたといいます。


福原荘全域が展望出来るこの地で“のろし”を上げて新都の位置を測定したと伝えられています。
ちょっと木が邪魔だなぁ。



これは兵庫「厳島神社」です。

ここは俗に「兵庫弁天」または「外弁天」と呼ばれ、親しまれています。

兵庫津築港に尽力した「平清盛」が、平家一族の氏神である安芸ノ国(広島)厳島明神を「厳島神社」から勧請したのが創建の始めです。

ここは「おしゃれ弁天」ですよ。


無人の社務所?で販売してました「おしゃれ弁天」人形です。(¥200)


ここは「湊川公園」です。

園内の「楠木正成」像です。

1336年この湊川で「足利直義」(足利尊氏の同母弟)の軍と戦うも敗れ、弟の「楠木正季」と刺し違えて自害したとされています。


これは「聖徳太子」銅像です…って、どこに「聖徳太子」がおんねん

今までも「馬の銅像」としか認識しておらず無視してたんだけど、「聖徳太子」像があるといわれてる位置には、この馬しか無いじゃんよ。

「聖徳太子」が“廐戸皇子”(うまやどのみこ)といわれてたから「馬」なの?バカにしてない?…って思ったんだけど、帰って調べたら「阪神・淡路大震災」で乗っかっていた太子像は破損しちゃったんだって。

この場所に「聖徳太子」像が建てられた由来として考えられるのは、太子が法隆寺を建立した際、現在の夢野、湊川、会下山一帯が寺領だったからのようです。

これは「願成寺」です。

これは本堂です。
本堂右脇から墓地に入ると奥に…


左から、この寺の開祖「住蓮上人」の墓です。(法然上人の門弟)
そして中央は「小宰相」、右隣は「平通盛」の墓です。
この2人は先程「氷室神社」で紹介しましたね…死後現在に至るまでもこうして夫婦が寄り添って、語り継がれるなんて羨ましいよね。

始めどれが2人の墓か分からなかったんだけど、ちょうど帰って来た?住職さんに教えてもらいました~


これは「湊川神社」の「表門」です。

これは「大楠公御墓所」入口です。(表門から入った後でも墓所へ行かれます)

中の「楠木正成」の墓です。


元禄5年(1692年)に、権中納言「徳川光圀」公(水戸黄門)は、家臣「佐々介三郎宗淳」(すけさん?)を、この地に遣わして碑石を建て、光圀公みずから表面の「嗚呼忠臣楠子之墓」の文字を書き、これに刻ませました。
この墓碑の建立によって、正成公の御盛徳は大いに宣揚されるとともに、幕末勤王思想の発展を助け、明治維新への力強い精神的指導力となりました。
幕末から維新にかけて、頼山陽・吉田松陰・真木保臣・三条実美・坂本龍馬・高杉晋作・西郷隆盛・大久保利通・木戸孝允・伊藤博文等々は、皆この墓前に至誠を誓い、国事に奔走したのでした。


これは「徳川光圀公(水戸黄門)」の銅像です。


光圀公は、水戸藩主を辞して西山荘に隠居した後も、大日本史の編纂を行うなど活躍し、正成公をひたすらお慕いして墓碑「嗚呼忠臣楠子之墓」を建立しました。


これは「宝物殿」(その日は休館日でした)と明治11年のパリ万博で日本館の館長をしていた「前田正名」が持ち帰った日本最初の「オリーブ樹」の1つです。


「楠木正成」を祀った「楠木稲荷神社」もあるんだ…って思ってよく見たら「楠本稲荷神社」でした。


参道を進むと…

正面に「社殿」があります。


「社殿」の左側には「殉節地(楠木正成戦没地)」がありました。(今まで見落としてましたね)


延元元年(1336年)5月25日「正成」が弟「正季」以下一族と「七生滅賊」を誓い殉節した場所と伝えられています。

これは「七度生まれ変わっても“尊氏”を滅ぼす」という想いだったのでしょう…
今回のレポートは如何でしたか?

地元の人しか知らないような小さな寺社でも由縁を調べたりすると、いろんなことが分かりますね。

皆さんも家の近くの寺社に行って調べてみると思わぬ発見があるかも?知れませんよ。

















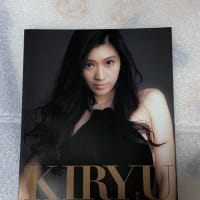




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます