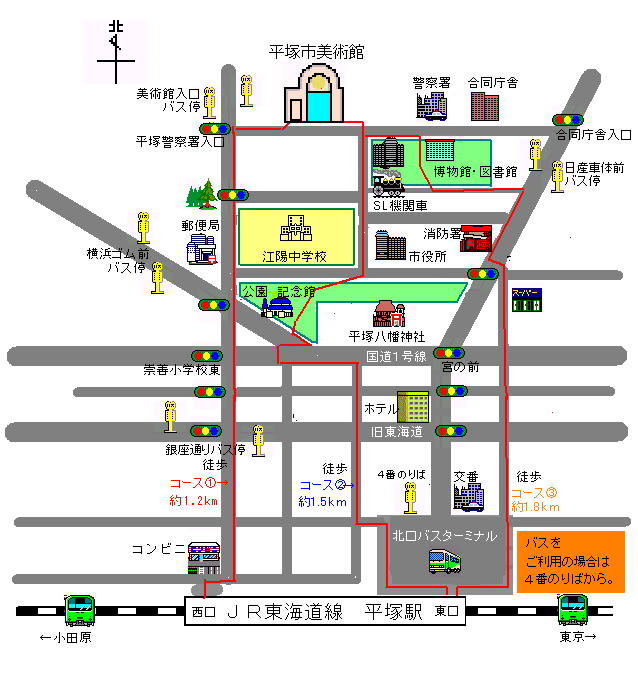ここの「お知らせ」の通り、5月16日(金)には、ここ数年恒例の、写真仲間をお誘いしての「大地沢 ウスバシロチョウ撮影会」の下見のため、町田市の大地沢(正確には相模原市緑区川尻 のようですが、大地沢の方が通りが良いので・・・)に行き、その前に、主として朝露狙いで、裏高尾にも行って来ました。
今日は「速報」のため、撮って出し JPG を単純縮小した画像(RAW 画像を現像時に調整して自分好みに仕上げることを宗とするメカロクにとっては、いわば未完成写真)ですので、いつもよりも小さく、かつ、クリックしても大きな画像は開きません。
1.裏高尾・木下沢 140516
セリバヒエンソウ(芹葉飛燕草)
昨年の4月19日、片岡先生他の「花コミュ」メンバーをお誘いしての「裏高尾ミニオフ会」のときにも、木下沢林道の入口で捉まって、みんなで夢中になった芹葉飛燕草ですが、今回も嵌ってしまいました。

2.裏高尾・木下沢 140516
ヒメオドリコソウ(姫踊子草)
この細かい水滴がビッシリと着いた姫踊子草も、1枚目の芹葉飛燕草の直ぐ近くで撮ったものです。

3.裏高尾・木下沢 140516
水滴 <ムラサキケマン(紫華鬘/ヤブケマン)>
朝露が余り着いていなかった芹葉飛燕草に嵌って時間を費やした所為で、この日の裏高尾での主目的だった筈の水滴写真は紫華鬘くらいで、他には殆ど撮れませんでした(汗)

4.裏高尾・木下沢 140516
サカハチチョウ(逆八蝶/サカハチ)
元々朝露が少なかった上に、5月も半ばとあって太陽高度が高く、谷の底の木下沢でも陽が射すのが早くて、水滴写真は早々に撮れなくなってしまったので、(留まらないため殆ど撮れなかった)薄羽白蝶(ウスバシロチョウ)に出会った後は、昆虫主体にシフトしてしまいました。
この逆八蝶、初めの内は中々近寄らせて呉れなかったのですが、その内に近付いても逃げなくなり、試しに左手指を差し出して見たら、難なく載り移って呉れました。
でも、そのとき持っていた E-M1 に装着していたレンズは BORG 36ED(200mmF5.6)で、どんなに頑張ってもこれで撮るのは無理!(涙)
「逃げるなよ!」と念じながらカメラバッグを置いた場所に急ぎ、E-P5 に装着した TAMRON 90mm MACRO を、右手だけで MZD 60mm MACRO に交換、AF にセットして片手撮りしたものです。
なお、私の汗が余程お気に召したようで、左手から離れず、強制的に草の葉っぱに移しても、また戻って来る始末で、私の左手は30分以上もの間、この子に占領されたままでした(笑)
おまけに、この子を右手で片手撮りしているときに、その右手に小三筋蝶(コミスジ)が留まって、暫くの間は、「両手に花」ならぬ「両手に蝶」の「オオモテ」状態でした(笑)

5.裏高尾・木下沢 140516
ツマキチョウ(褄黄蝶) のオス
「両手に蝶」のときに、目の前の草に褄黄蝶のメスが留まりました。
これは MZD 60mm MACRO で撮るには少し遠かったので、両手に蝶を載せたまま、右手で E-M1 ボディを持ち、左手で BORG 36ED のフォーカスリングを支えての、MF 超望遠撮影と相成りました。
なお、この写真はその後に見掛けた褄黄蝶のオスで、このときは右手の小三筋蝶は飛び立った後で、左手に逆八蝶だけ載せて撮影したものです。

6.裏高尾・木下沢 140516
スミナガシ(墨流し)
逆八蝶/小三筋蝶/褄黄蝶を撮った場所に向かう途中にも墨流しを見掛けたのですが、このときは直ぐに飛び立って遠くの樹に移ったため、BORG 36ED で小さく撮っただけだったのですが、帰る途中、同じ場所に来た時には、同時に最大6頭の墨流しが吸水(ミネラル補給 ?)をしていたので、今度は逃げられないように、BORG 36ED で遠くから始め、次第に近付いて、何枚も撮りました。
ただ、日陰でちょっと暗かったため、ISO 800 でもSS が上がらず(この写真は 1/200sec)、ぶれ写真を量産してしまったのは、今までに撮ったのが2回だけという、私にとっては希少種だけに、何とも残念でした。
帰宅後、チェックしたときに、「ぶれ写真を量産するくらいなら、ISO 1600 の方が良かった!」と思いましたが、後の祭りですね(汗)
なお、「私にとっては」と述べましたが、通り掛かった2組3人の方に「墨流しが居ますよ!」と声を掛けたところ、3人とも「初めて見ました!」と大喜びで撮っていたので、必ずしも私だけではなく、多くの方にとって珍しい蝶なんでしょうね。

7.町田・大地沢(相模原市緑区・川尻) 140516
ウスバシロチョウ(薄羽白蝶/ウスバアゲハ)
木下沢でも、今までに見たことがないほど沢山の薄羽白蝶を見掛け、「今年は薄羽白蝶の当たり年か!?」と思いましたが、大地沢でも同じように、「薄羽白蝶の当たり年」状態でした。
ただ、今までの経験では、大地沢の薄羽白蝶は、木下沢のそれより良く留まり、比較的近寄らせて呉れるという感じがしていたのですが、今年は、ここの薄葉白蝶も中々留らず、時々留まるのは、この子のように草臥れた個体が主でした。

8.町田・大地沢(相模原市緑区・川尻) 140516
ウスバシロチョウ(薄羽白蝶/ウスバアゲハ)
このため、撮影枚数は殆ど伸びず、諦めて帰る途中で、ダイコン(?)の花で吸蜜中の子を発見、25分くらいも付き合って呉れました。

9.町田・大地沢(相模原市緑区・川尻) 140516
ウスバシロチョウ(薄羽白蝶/ウスバアゲハ) の疑似交尾
私が撮っていた25分ほどの間にも数回、オスがアタックして来ましたが、精々10秒くらいで、交尾と見える状態が終わるので、昨年、2時間にも渉る交尾を撮っただけに、「不思議だな!」と思って良く見たら、「交尾嚢」が見え、交尾済みのメスと判明しました。
つまり、既に交尾できない状態になっていたので、アタックしたオスも、途中で諦めたんでしょうね。

今日は「速報」のため、撮って出し JPG を単純縮小した画像(RAW 画像を現像時に調整して自分好みに仕上げることを宗とするメカロクにとっては、いわば未完成写真)ですので、いつもよりも小さく、かつ、クリックしても大きな画像は開きません。
1.裏高尾・木下沢 140516
セリバヒエンソウ(芹葉飛燕草)
昨年の4月19日、片岡先生他の「花コミュ」メンバーをお誘いしての「裏高尾ミニオフ会」のときにも、木下沢林道の入口で捉まって、みんなで夢中になった芹葉飛燕草ですが、今回も嵌ってしまいました。

2.裏高尾・木下沢 140516
ヒメオドリコソウ(姫踊子草)
この細かい水滴がビッシリと着いた姫踊子草も、1枚目の芹葉飛燕草の直ぐ近くで撮ったものです。

3.裏高尾・木下沢 140516
水滴 <ムラサキケマン(紫華鬘/ヤブケマン)>
朝露が余り着いていなかった芹葉飛燕草に嵌って時間を費やした所為で、この日の裏高尾での主目的だった筈の水滴写真は紫華鬘くらいで、他には殆ど撮れませんでした(汗)

4.裏高尾・木下沢 140516
サカハチチョウ(逆八蝶/サカハチ)
元々朝露が少なかった上に、5月も半ばとあって太陽高度が高く、谷の底の木下沢でも陽が射すのが早くて、水滴写真は早々に撮れなくなってしまったので、(留まらないため殆ど撮れなかった)薄羽白蝶(ウスバシロチョウ)に出会った後は、昆虫主体にシフトしてしまいました。
この逆八蝶、初めの内は中々近寄らせて呉れなかったのですが、その内に近付いても逃げなくなり、試しに左手指を差し出して見たら、難なく載り移って呉れました。
でも、そのとき持っていた E-M1 に装着していたレンズは BORG 36ED(200mmF5.6)で、どんなに頑張ってもこれで撮るのは無理!(涙)
「逃げるなよ!」と念じながらカメラバッグを置いた場所に急ぎ、E-P5 に装着した TAMRON 90mm MACRO を、右手だけで MZD 60mm MACRO に交換、AF にセットして片手撮りしたものです。
なお、私の汗が余程お気に召したようで、左手から離れず、強制的に草の葉っぱに移しても、また戻って来る始末で、私の左手は30分以上もの間、この子に占領されたままでした(笑)
おまけに、この子を右手で片手撮りしているときに、その右手に小三筋蝶(コミスジ)が留まって、暫くの間は、「両手に花」ならぬ「両手に蝶」の「オオモテ」状態でした(笑)

5.裏高尾・木下沢 140516
ツマキチョウ(褄黄蝶) のオス
「両手に蝶」のときに、目の前の草に褄黄蝶のメスが留まりました。
これは MZD 60mm MACRO で撮るには少し遠かったので、両手に蝶を載せたまま、右手で E-M1 ボディを持ち、左手で BORG 36ED のフォーカスリングを支えての、MF 超望遠撮影と相成りました。
なお、この写真はその後に見掛けた褄黄蝶のオスで、このときは右手の小三筋蝶は飛び立った後で、左手に逆八蝶だけ載せて撮影したものです。

6.裏高尾・木下沢 140516
スミナガシ(墨流し)
逆八蝶/小三筋蝶/褄黄蝶を撮った場所に向かう途中にも墨流しを見掛けたのですが、このときは直ぐに飛び立って遠くの樹に移ったため、BORG 36ED で小さく撮っただけだったのですが、帰る途中、同じ場所に来た時には、同時に最大6頭の墨流しが吸水(ミネラル補給 ?)をしていたので、今度は逃げられないように、BORG 36ED で遠くから始め、次第に近付いて、何枚も撮りました。
ただ、日陰でちょっと暗かったため、ISO 800 でもSS が上がらず(この写真は 1/200sec)、ぶれ写真を量産してしまったのは、今までに撮ったのが2回だけという、私にとっては希少種だけに、何とも残念でした。
帰宅後、チェックしたときに、「ぶれ写真を量産するくらいなら、ISO 1600 の方が良かった!」と思いましたが、後の祭りですね(汗)
なお、「私にとっては」と述べましたが、通り掛かった2組3人の方に「墨流しが居ますよ!」と声を掛けたところ、3人とも「初めて見ました!」と大喜びで撮っていたので、必ずしも私だけではなく、多くの方にとって珍しい蝶なんでしょうね。

7.町田・大地沢(相模原市緑区・川尻) 140516
ウスバシロチョウ(薄羽白蝶/ウスバアゲハ)
木下沢でも、今までに見たことがないほど沢山の薄羽白蝶を見掛け、「今年は薄羽白蝶の当たり年か!?」と思いましたが、大地沢でも同じように、「薄羽白蝶の当たり年」状態でした。
ただ、今までの経験では、大地沢の薄羽白蝶は、木下沢のそれより良く留まり、比較的近寄らせて呉れるという感じがしていたのですが、今年は、ここの薄葉白蝶も中々留らず、時々留まるのは、この子のように草臥れた個体が主でした。

8.町田・大地沢(相模原市緑区・川尻) 140516
ウスバシロチョウ(薄羽白蝶/ウスバアゲハ)
このため、撮影枚数は殆ど伸びず、諦めて帰る途中で、ダイコン(?)の花で吸蜜中の子を発見、25分くらいも付き合って呉れました。

9.町田・大地沢(相模原市緑区・川尻) 140516
ウスバシロチョウ(薄羽白蝶/ウスバアゲハ) の疑似交尾
私が撮っていた25分ほどの間にも数回、オスがアタックして来ましたが、精々10秒くらいで、交尾と見える状態が終わるので、昨年、2時間にも渉る交尾を撮っただけに、「不思議だな!」と思って良く見たら、「交尾嚢」が見え、交尾済みのメスと判明しました。
つまり、既に交尾できない状態になっていたので、アタックしたオスも、途中で諦めたんでしょうね。