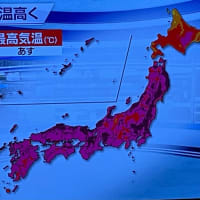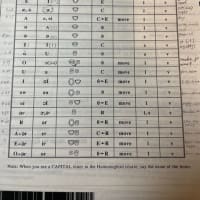2009.11.6.(Fr) 19時過ぎ~22時前
場所: 大阪/西梅田、阪神高速が通り抜けているビル
参加者: 大学図書館の人 4名、元大学図書館のLIS研究者 1名、
公共図書館の人 3名
慶応の原田先生、記録やお手伝いの院生1名
事前のご案内では、幅広いテーマについてお聞きしたいとのことだったが、基本的には情報提供サービス全般について、まずは夢を語るようなものでもいいので。
○3年後、本館のシステム入れ換え。
・2年後に、情報サービスシステムを更新(導入?)
・5年間使うので、7年後まで見据えて。
○集まりの公開可。NDLの活動のアピールにも。
・計16回予定。その他、訪問調査20-30回。
・明日は、利用者
・高校生対象のものは、インフルの学校閉鎖の影響で延期中
#見たいぐらい。
○プロトタイプができたら、ご意見を。
今年度中に作る。
NDLも本気と。
NDLも160項目をまとめている。
・CiNiiが2つくらい作れる予算
■自己紹介+NDLについて
・総合目録は使うけど。
古い資料はお客が要求しない。最近の資料が多い。
・見やすくなっていない。無骨な感じ。一新してほしいなと。
・政令指定都市=大きな図書館だと、NDLに頼むという意識が小さい。
・便利そうとは思わなかった。書誌事項確定は、NDL-OPAC。
CiNiiはよく使う。
・いろいろあって、分かりにくい。組織の大きさの現れも?
・NDLとNIIのサービスの別々さの問題。例えば、書誌とか。
書影、NDLが(スキャンして)提供してくれたらいいのに。国のデータプロバイダとして。
※NDLは、カバーと帯はほかしているとか。
■なんで使う気になれないのか
・仕事の流れに入ってこない。
・最後の砦的な位置付け。
NIIで十分。
・物流経費を誰が払うか。
県立に借りるなら、県立負担=無料
協定があれば、その間は無料
・NDLのサイト(トップページ)は、直感的に使えない。
・広報の問題? ググって上位に出てきたら、それでよい?
公共図書館とか経由で、使うならそれでよいとも言える。
・NDLのサイトが、ググって引っかかっても、それでどうする?
※来られない方に向けてのサービスとしての議論の方向
・NDLが何をしてくれるか知られていない。
NDL-OPACも、では何のため?
・WikipediaやAmazonに出すアイデアも。
・NDLのサービスは、最後の砦 なのか、一般向けサービスなのか。
・NIIの書誌レコードと、何かのコード値での連携もほしい。
・何のために使わすのか。
・リサーチナビ(探し方マニュアル)は、結構いい。
・一般の人は、ネットの向こうは全て同じ。
・本文も見られるように。あるいは、見られないなら、見られるようにガイドする。
・本を探す人向けのサービスは独立して提供?
・個別目録→総合目録 の順序の逆転は?
ゆにかネット(都道府県立+政令指定都市)だけでなく、市町村・県立図書館総合目録は?
「お探しの都道府県は?」というプルダウンボックス付きとか (私)
*)羽田空港のレストラン検索機能からイメージ
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/shops_and_restaurants/
ILLも混じると、現場が耐えられないとか。
"ファーストステップ"になりたいという声はNDLにもあるらしい。
・物流の問題
・ユーザの所在地で、優先する順序を選べるとか。
「乗り換え案内」のように、早さ順・料金順を選べるとか。
・「書誌」とか、「責任表示」とか、「異なりアクセスなんとか」とか、ユーザに分かるわけない。
#終了後、「出版"者"」に噛みついていた私。特に公共図書館(新刊和書が多いところ)だと「出版"社"」でもいいじゃん。「出版社: 鈴木一朗」とか「出版社: ○○研究会」とかでも、分かるでしょ。
目録はユーザのためにある!
#本学さんの仕様書に「OPACの書誌レコード等の各項目名称を表示する時、一般ユーザに分かりにくい用語は極力使わないこと」とでも書こうかしら。
部内会議の議事録に「MLを作成することとなった」と書くのと同じくらい、今さら感とか、わざわざ感があるのだけど。
■プロトタイプ
OPAC、利用者管理、ログインサーバ。
これに貸出管理があったら、図書館システムになるではないか。
これを市町村に配る。
サポートは有料に。
これで、書誌データをハーベストしたら、簡単に(!?)総合目録もできる、とか。
民業圧迫という議論か、価格か。
OSSでも、地元業者がサポートすれば。
大学なら、NIIの WebUIP と、パッケージの併存という例も。
#なんかよさそうやなぁ
■本文データの解像度は?
値段ときれいさのトレードオフだけど、どっち重視?
■本文の表示、見せ方
普通にスクロールとか、ページめくりができればよい。
(変に本をめくるみたいでなくてもよい)
■モバイル、PDA
・携帯で検索はしてて、本文へのリンクをどんどんメールで送れればいい、という声もあったとか。
検索したら、書架まで案内してほしい、という声もあったとか。
・PC版サイトのニュースと、携帯サイトの同時性
・PC版館内OPAC端末で、PCと書架の相対的位置の表示。
#確かに、私もOPACは館内資料へのナビゲーション機能として必要、と言ったことがあると思いますが、そうなっているOPACってどれだけあるだろう。最低限、館内フロア図だと思うけど、出てたかなぁ。
■書誌レコードのエンリッチ
・書影、
+目次・前書き・要約
+本文
・検索結果の表示の仕方、レーティング
■
・画面デザイン、展開の統一感のなさ。
どのページからでもトップページに戻れるよう。
■
・ピタパで払えて便利というアイデア
→ クレジットが使えない人はダメなので、導入ボツになった某KB市立図書館
・名前の問題「登録利用者」→「コピーがほしい方はこちら」とか
やっぱ広報の問題?
*)登録は、年に1回来館しないといけない。
・国会VISAカードでポイント制
・普通のクレジットでも
・一般の買い物サイトでは、支払は、クレジット、振込、コンビニ、着払いとか選べるのに。
*)どこかの公共図書館で、ポイント制を始めたところがあるって言っていたっけ!?
→ポイント制については、別のエントリでも
■リコメンド機能、有効性は?
・NDL-OPACの位置付け、使われ方の問題か。鶏と卵? リコメンドがあれば使われる?
公共のレコードをもらうとか
■在庫中の資料を上位に表示させる機能は?
・あってもいい という意見が大半
・一方、貸出中でも借りて(予約して)もらえるというニーズを摘む結果にならないか。そういう機能を案内する仕掛けも? (私、思いつきで)
■
・思想を感じさせるプロジェクトとなってほしい
■どこから作ってみるべきか
・本文のデジタル化
・想定ユーザ、海外のユーザ、障害者は?
・保存、デジタル化
・まず、書影とか見えるところから
・本文(画像)情報のテキスト化
・ユーザインターフェース。iGoogle のように。
・「政策」(ポリシー?)を明確にしてほしい。
・市町村立を支えるという意識を持っていただきたい。
・ガイドブックを作ってほしい。ムックとかがいいね。
週刊ダイヤモンドで取り上げてもらう。大衆性。
O市立図書館でも、ビジネスに役立つと紹介されると、反響多い。
※写真:10月、新潟市沖から、新潟市街を眺める
場所: 大阪/西梅田、阪神高速が通り抜けているビル
参加者: 大学図書館の人 4名、元大学図書館のLIS研究者 1名、
公共図書館の人 3名
慶応の原田先生、記録やお手伝いの院生1名
事前のご案内では、幅広いテーマについてお聞きしたいとのことだったが、基本的には情報提供サービス全般について、まずは夢を語るようなものでもいいので。
○3年後、本館のシステム入れ換え。
・2年後に、情報サービスシステムを更新(導入?)
・5年間使うので、7年後まで見据えて。
○集まりの公開可。NDLの活動のアピールにも。
・計16回予定。その他、訪問調査20-30回。
・明日は、利用者
・高校生対象のものは、インフルの学校閉鎖の影響で延期中
#見たいぐらい。
○プロトタイプができたら、ご意見を。
今年度中に作る。
NDLも本気と。
NDLも160項目をまとめている。
・CiNiiが2つくらい作れる予算
■自己紹介+NDLについて
・総合目録は使うけど。
古い資料はお客が要求しない。最近の資料が多い。
・見やすくなっていない。無骨な感じ。一新してほしいなと。
・政令指定都市=大きな図書館だと、NDLに頼むという意識が小さい。
・便利そうとは思わなかった。書誌事項確定は、NDL-OPAC。
CiNiiはよく使う。
・いろいろあって、分かりにくい。組織の大きさの現れも?
・NDLとNIIのサービスの別々さの問題。例えば、書誌とか。
書影、NDLが(スキャンして)提供してくれたらいいのに。国のデータプロバイダとして。
※NDLは、カバーと帯はほかしているとか。
■なんで使う気になれないのか
・仕事の流れに入ってこない。
・最後の砦的な位置付け。
NIIで十分。
・物流経費を誰が払うか。
県立に借りるなら、県立負担=無料
協定があれば、その間は無料
・NDLのサイト(トップページ)は、直感的に使えない。
・広報の問題? ググって上位に出てきたら、それでよい?
公共図書館とか経由で、使うならそれでよいとも言える。
・NDLのサイトが、ググって引っかかっても、それでどうする?
※来られない方に向けてのサービスとしての議論の方向
・NDLが何をしてくれるか知られていない。
NDL-OPACも、では何のため?
・WikipediaやAmazonに出すアイデアも。
・NDLのサービスは、最後の砦 なのか、一般向けサービスなのか。
・NIIの書誌レコードと、何かのコード値での連携もほしい。
・何のために使わすのか。
・リサーチナビ(探し方マニュアル)は、結構いい。
・一般の人は、ネットの向こうは全て同じ。
・本文も見られるように。あるいは、見られないなら、見られるようにガイドする。
・本を探す人向けのサービスは独立して提供?
・個別目録→総合目録 の順序の逆転は?
ゆにかネット(都道府県立+政令指定都市)だけでなく、市町村・県立図書館総合目録は?
「お探しの都道府県は?」というプルダウンボックス付きとか (私)
*)羽田空港のレストラン検索機能からイメージ
http://www.tokyo-airport-bldg.co.jp/shops_and_restaurants/
ILLも混じると、現場が耐えられないとか。
"ファーストステップ"になりたいという声はNDLにもあるらしい。
・物流の問題
・ユーザの所在地で、優先する順序を選べるとか。
「乗り換え案内」のように、早さ順・料金順を選べるとか。
・「書誌」とか、「責任表示」とか、「異なりアクセスなんとか」とか、ユーザに分かるわけない。
#終了後、「出版"者"」に噛みついていた私。特に公共図書館(新刊和書が多いところ)だと「出版"社"」でもいいじゃん。「出版社: 鈴木一朗」とか「出版社: ○○研究会」とかでも、分かるでしょ。
目録はユーザのためにある!
#本学さんの仕様書に「OPACの書誌レコード等の各項目名称を表示する時、一般ユーザに分かりにくい用語は極力使わないこと」とでも書こうかしら。
部内会議の議事録に「MLを作成することとなった」と書くのと同じくらい、今さら感とか、わざわざ感があるのだけど。
■プロトタイプ
OPAC、利用者管理、ログインサーバ。
これに貸出管理があったら、図書館システムになるではないか。
これを市町村に配る。
サポートは有料に。
これで、書誌データをハーベストしたら、簡単に(!?)総合目録もできる、とか。
民業圧迫という議論か、価格か。
OSSでも、地元業者がサポートすれば。
大学なら、NIIの WebUIP と、パッケージの併存という例も。
#なんかよさそうやなぁ
■本文データの解像度は?
値段ときれいさのトレードオフだけど、どっち重視?
■本文の表示、見せ方
普通にスクロールとか、ページめくりができればよい。
(変に本をめくるみたいでなくてもよい)
■モバイル、PDA
・携帯で検索はしてて、本文へのリンクをどんどんメールで送れればいい、という声もあったとか。
検索したら、書架まで案内してほしい、という声もあったとか。
・PC版サイトのニュースと、携帯サイトの同時性
・PC版館内OPAC端末で、PCと書架の相対的位置の表示。
#確かに、私もOPACは館内資料へのナビゲーション機能として必要、と言ったことがあると思いますが、そうなっているOPACってどれだけあるだろう。最低限、館内フロア図だと思うけど、出てたかなぁ。
■書誌レコードのエンリッチ
・書影、
+目次・前書き・要約
+本文
・検索結果の表示の仕方、レーティング
■
・画面デザイン、展開の統一感のなさ。
どのページからでもトップページに戻れるよう。
■
・ピタパで払えて便利というアイデア
→ クレジットが使えない人はダメなので、導入ボツになった某KB市立図書館
・名前の問題「登録利用者」→「コピーがほしい方はこちら」とか
やっぱ広報の問題?
*)登録は、年に1回来館しないといけない。
・国会VISAカードでポイント制
・普通のクレジットでも
・一般の買い物サイトでは、支払は、クレジット、振込、コンビニ、着払いとか選べるのに。
*)どこかの公共図書館で、ポイント制を始めたところがあるって言っていたっけ!?
→ポイント制については、別のエントリでも
■リコメンド機能、有効性は?
・NDL-OPACの位置付け、使われ方の問題か。鶏と卵? リコメンドがあれば使われる?
公共のレコードをもらうとか
■在庫中の資料を上位に表示させる機能は?
・あってもいい という意見が大半
・一方、貸出中でも借りて(予約して)もらえるというニーズを摘む結果にならないか。そういう機能を案内する仕掛けも? (私、思いつきで)
■
・思想を感じさせるプロジェクトとなってほしい
■どこから作ってみるべきか
・本文のデジタル化
・想定ユーザ、海外のユーザ、障害者は?
・保存、デジタル化
・まず、書影とか見えるところから
・本文(画像)情報のテキスト化
・ユーザインターフェース。iGoogle のように。
・「政策」(ポリシー?)を明確にしてほしい。
・市町村立を支えるという意識を持っていただきたい。
・ガイドブックを作ってほしい。ムックとかがいいね。
週刊ダイヤモンドで取り上げてもらう。大衆性。
O市立図書館でも、ビジネスに役立つと紹介されると、反響多い。
※写真:10月、新潟市沖から、新潟市街を眺める