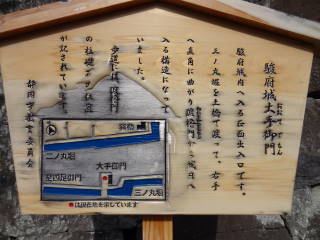2013年12月3日
早朝 6時30分京都到着
その足で 米原行の電車に乗り
安土駅へ行く 一つ手前の近江八幡駅は
あとで戻ることにし 安土駅を降り
一路 安土城跡に向かう 歩くこと30分強
前日、川越で二万歩近く歩いているので
足取りが少し重い 線路に沿う田んぼ道を歩くと
左に 標高199mほどの山が見える
入場料500円取られる


これから 長い階段を登り頂上の天守閣あとを目指す

登り始めてすぐ左は秀吉の館跡 右側が前田利家の館跡

急こう配の階段の左右は 家臣の館跡地が並ぶ

徳川家康の館の跡に立つ お寺

一般公開されていないが 少しだけ拝観

更に 階段は続く右へ直角 左へ直角へと曲がり
ハア~ ハア~言いながらテクテク登る

織田信忠館跡を見ながら 上へと

右に折れ天守閣目指す

あのう積の立派な石垣が出てくる


一気に攻められないように また、直角に曲がる
敵を上から 弓で射るための工夫の石垣

当時は石垣の上に櫓があり 鉄砲などで敵を撃つ
この石段には 階段用の石が不足して
いたるところに 墓石が使われているところが
信長流と言えるとこである
普通であれば ばちが当たりそうで使わないところなれど
一向宗や比叡山焼き討ちをするぐらいの信長は
気にもしないで使用している

やっと 本丸跡地までやってきた
元は 木が生い茂り 木を切って土をどけて
遺跡として出てきたそうです 全部埋まっていたそうです

建物の基礎石として こんな石も出てきたとの事

やっときました

堆積していた土の中から出てきた 基礎石が1.2mおきに
整然と並んでいる

地上6階地下1階(五層七階)高さ33mの木造高層建築は
我が国初めてのものであったと言われています
1579年完成し わずか三年後天正十年六月二日
本能寺の変後 六月十五日 天主 本丸が焼失二の丸は残る
その後、嫡孫秀信が居城していたが 八幡山城築城にともない
1585年(天正13年) 廃城となる

手前の樹は当時は無いので 見晴らしは良かったと想像できる
写真には写らないが 肉眼では遠くに山が見える

琵琶湖を望む展望
当時の琵琶湖はもっと水位があがっていたので
城のまじかまで水に囲まれてたとの事
南側だけが開けていた地形とか

信長が自らの菩提寺として 同じ時期に建てた
総見寺の三重塔 本堂は燃えてしまうが
これは残り 室町時代1454年の建物で
信長が甲賀の長寿寺(甲賀市石部町)から天正三年~四年頃
移築されたとのこと 柱には1454年建立
天文二十四年(1555年)修理の墨書きがあるとのこと

階段下には仁王門があり 位の低い武士はこの門から
登城し総見寺でお参りしてから 信長に挨拶してた

金剛力士像も応仁元年(1467)頭部内側に銘が残っている
ひと通り見たので 同じ階段下る
下に着くと1㎞先に
お城のレプリカがある信長の館に行く 500円払う



天守の5階6階部分だけ再現してある
このあと、テクテクと安土駅まで30分歩く
一駅戻り 近江八幡へ移動する
近江八幡駅から北へ真っ直ぐ小畑まで乗る
このあたりは 古い町並みとお堀と城跡が見どころ
八幡堀から見て回る


琵琶湖に出る 船の流通の要


川沿いに近江商人の蔵が立ち並ぶ

すぐ、荷を出し入れできるための階段




時期が来たらこの船にて遊覧できる
水郷巡り観光船

本願寺八幡別院




透かし彫りの見事な仕事ぶり


近江商人といえば
高島屋 義理の父が近江の国高島出身なので
初代が名を付けた
武田薬品 初代が薬種仲買屋(近江屋喜助)に奉公し
のちにのれん分けで近江屋薬種商を開く
4代目で名前が武田になる
西川産業 蚊帳 畳表などを商う のちに西川の布団になる
伊藤忠 丸紅 住友 西武などそうそうたる企業
町を走る バス タクシー 車体の色は西武と同じ

このマークどこかで観なかったか 使っているリップクリーム

近江兄弟社 昔メンソレータム




今は、ロート製薬の傘下かな

川越に似ている雰囲気

新町通り



尋常高等小学校

このあたりは、明治 大正の文化の匂いがする
北の先にあるロープウェイに乗り八幡山へ行くと
城跡にたどり着く 283mの山に築いた山城である
山崎の戦いの後(秀吉が明智光秀と戦い討ちとったこと)
1585年(天正13年)の紀州攻め、四国征伐で副将格で戦陣に入り武勲を立てた豊臣秀次は8月23日の論功行賞で近江八幡43万石(豊臣秀次は20万石、宿老に23万石)を与えられると安土城の隣地に八幡山城を築き、安土城の建物や城下町を移築することにした。
三谷幸喜監督の映画基になった 「清州会議」が天正10年6月27日
1583年7月16日 織田家の跡継ぎ問題と領地分配の会議が
尾張の国 清州城で行われた
この時の織田家家臣は
筆頭家老 柴田勝家 この会議後信長の妹 お市の方と結婚している
次席家老 丹羽長秀
羽柴秀吉 光秀を討ち取った功労者
池田恒興 桶狭間の戦い 姉川の戦い功労
犬山城の城主
結果は 秀吉が擁立する(三法師)信長の嫡男信忠の子秀信に決まる
これは、来年のNHK大河ドラマ黒田官兵衛(秀吉の腹心)の
策略と言われている
清州会議後 豊臣秀吉は安土城に替わる近江国の国城として
豊臣秀吉自身が普請の指揮をとり、山頂の城郭と麓にある居館
そして安土城から移築した城下町の造営に力を注いだ。
しかし、八幡山は安土山と違い険しい山で
山の斜面を十分活用できず麓の居館が城の中心となった。
今現在、多くが土に埋まっているため 一部の石垣だけしか見えず
今後 発掘調査が進むことにより お宝が出てくるかも。
第三弾は 京都に戻り 明日からは京都の町を散策
京都と言えば ????でしょ
前に京都は書いていますので今回は
歴史から外れ マニア必見!! よだれが出てくるよ!!