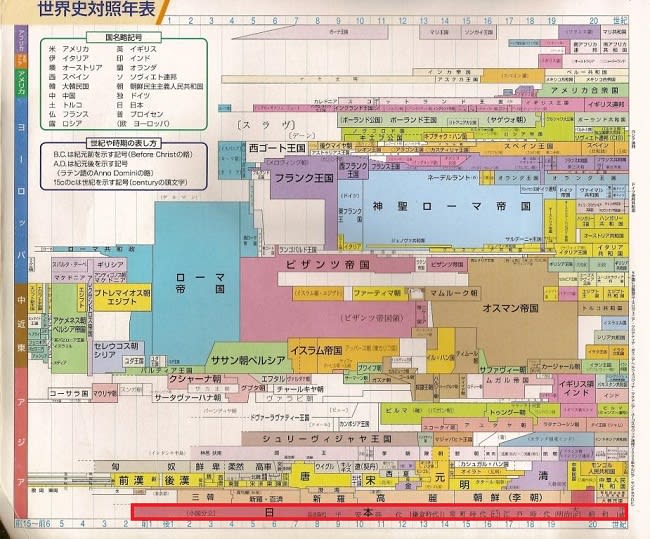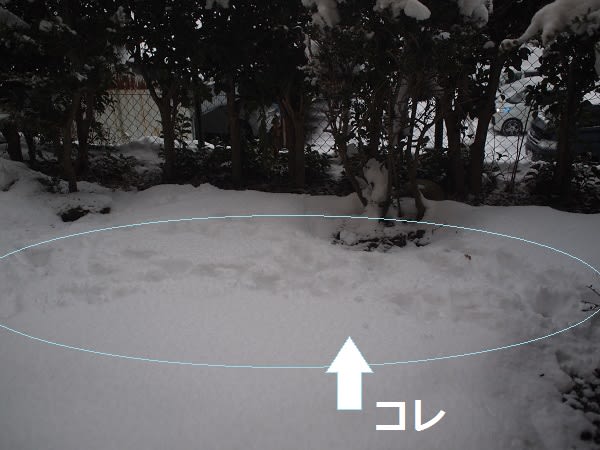昨日、仕事納めでした。
現在わたくし、ムラの託児所に勤めておりまして1歳児クラスの担任をしております。
ブランク長いわ、経験少ないわで四苦八苦の9ヶ月でしたが
これだけは言える
テキトーに仕事したことはない!!
まぁ、そのおかげで夫には抜け殻のような姿を見せてしまっていたし
見るに見かねて食器の洗うのや洗濯物を干すのが私より上手になりましたが
私が担任をする際、心掛けたことは
できるだけ本物を見せる
ことと
変幻可能な玩具をそろえる
事でした。
【本物を見せる】
たとえば、お花や動物の壁面。
保育室などには、たくさん飾られていますが
極論を言うと保育室に張ってある画用紙のくまさんやウサギさんは本当の熊や兎じゃないもの。
「かわいい」と思って満足しているのは大人の感覚だ、と思うのです。
ムラにはちょっと外に出れば本物の草や木や花がそこここにある。
そして生きたカエルやアリやちょうちょやカナヘビや…。(たまにシカや猿も見ますが、コレはちょっと危険 )
)
それに触れて、見て、におって、たまにはなめてみて本物とはこういうものなんだな、ということを五感で知る。
五感で記憶にすりこまれたものはその中のどれかが呼び覚まされるだけで記憶として蘇ります。
そして、それがふるさとの記憶として蘇り、ふるさとを誇りに思い、ふるさとの人々を大事に思う。
先日、お散歩中にしゃくとり虫がいました。
数人の子どもたちといっしょにしゃがんで見ていた。
しばらく見た後、ちょっと「コワイ」と思った子どもが足でグシャッ!と踏み潰した
思わず私と、もう一人の保育者「ぎゃー!!」って叫んじゃいましたよ。
そしたらその子…
「しまった!」って顔をしてうずくまって動かなくなってしまった。
叫んでしまったことで、否定的な感情を受けたのかもしれないけれど、それよりその子はそこで命の火が消えた瞬間を目撃した。
それがある意味ショックだったんでしょうね。
それからは虫や動物の図鑑を持ってきて「にょろにょろ(へび)」や「むー(虫)」を指差しながらとても興味を持つようになりました。
こういう経験って、バーチャルな世界では絶対に経験できないこと。
ゲームでいくら相手を切り刻んでも、この子のように踏み潰したときの感触やつぶれたときの音や分泌物が飛び出た映像ほどの経験はできない。
何より、その時に得られる感情の成長は絶対に得られない。
ある保育所では、危ないから・割れるからといってプラスティックやメラミンの食器などを安易に使わず
陶器の食器やガラスのピッチャーやコップなどを使っている園があります。
当然衛生面のこともありますが、その園は子どもに本物を使わせたい、と思っている。
割れても大丈夫なものを使わせていると、雑に扱ってもいい、投げても大丈夫、という習慣が身につく。
もし投げてしまって割れたら、そこでその子どもは学ぶのです。
投げるとコップは割れてしまうんだ、と。
何より私が懸念するのは、そういう素材を使うことで、保育者である大人の扱いが雑になります。
お子さんのいらっしゃる方は経験があると思いますが、子どもは大人の真似をしたがります。
本当によ~~~~~く見ています。
私が他の保育者に言うのは「片付けにしろ、おもちゃや食器類の扱いにしろ、大人が日々『見せていく』ことが子どもの育ちには大事」だと。
ムラの託児所でも今年から陶器のコップとお皿を使っていますが
子どもは今のところ割っていません。
割ったのは食器洗いで手を滑らせた大人です(笑)。
【変幻可能な玩具をそろえる】
うちのクラスには基本押さえたら音が出るものや、ソフビのなんとかレンジャーとかましてやテレビは置いていません。
チェーンリングや原木積み木、基本図形のみ(○△□)のマグネット、素朴な赤ちゃんのお人形、おままごとセット、ブロック、絵本etc・・・
素材に関しては本当は自然天然のものでそろえたいところですが、そこはまだ力及ばず…。
「見立てによっていろんな物に変わる素材」を置いていると
1.『これがいい!』ってなったときにけんかが少ない。
2.どんな遊びになっても多用できる。
3.想像力次第で遊びが発展する
というメリットがあります。
現にチェーンリングはおままごとではラーメンやうどんになるし、お風呂になると水の変わりに、または女の子の大好きなネックレスにも。
マグネットは貼り付けて図形を楽しむだけでなく、○のものは最近お店ごっこのお金に早代わりしています。
子どもの想像力は無尽蔵。
時々上のクラスの子たちが遊びに来ると、さらに遊びが発展していて「そっか!そういう使い方があったか!」と大人が勉強させられます。
結局のところ、こういう遊びの中で培われる「想像力」は融通性や判断力を養うだけでなく
ひいては人の気持ちを考える際の土台になるのです。
テレビなどの一方的に情報を与えられる媒体は想像力を働かせる間もなく次の映像に移ります。
少なくとも幼児期の脳の発達ではついていけない。
じっくり手で触りながら目で見ながら、これまた五感を働かせながら自分の世界を確立し
それができた暁には他人にも同じように世界があることを知っていくのだと、私は思います。
私も含め、最近は大人も子どもも想像力が欠如している。
今横たわっている問題のほとんどはこの「想像力の欠如」によると思っています。
だから子どものときにどれだけ想像力を養えるか。
これがこれからを担う子どもたちにとっては最重要課題。
そして、それを提供する大人たちの最重要課題。

FBでフォローしている愛知県のレイモンド庄中保育園では定期的に絵画展を開いているらしい。
壁面ではなく、こういうの見せたいなぁ。
愛情料理研究家 土岐山協子の 『料理はしないんだけど料理研究家のブログ』 『いずれ一人で生きていく子ども達へ』〜深い深い愛情を内田美智子先生に学ぶ

自分が生きている周りにはホントにたくさんの支えがあって
脈々とつながれてきた命のリレーがあって
今何も考えずに口に運ぼうとしているそのひと口にもたくさんの人間の汗と努力があり
だから自分は自分ひとりのための命ではなく
自分も誰かの役に立ち、誰かは自分のためになっている。
そういうことを
想像できる人になりたい、そして伝えていきたい。
現在わたくし、ムラの託児所に勤めておりまして1歳児クラスの担任をしております。
ブランク長いわ、経験少ないわで四苦八苦の9ヶ月でしたが
これだけは言える
テキトーに仕事したことはない!!
まぁ、そのおかげで夫には抜け殻のような姿を見せてしまっていたし
見るに見かねて食器の洗うのや洗濯物を干すのが私より上手になりましたが

私が担任をする際、心掛けたことは
できるだけ本物を見せる
ことと
変幻可能な玩具をそろえる
事でした。
【本物を見せる】
たとえば、お花や動物の壁面。
保育室などには、たくさん飾られていますが
極論を言うと保育室に張ってある画用紙のくまさんやウサギさんは本当の熊や兎じゃないもの。
「かわいい」と思って満足しているのは大人の感覚だ、と思うのです。
ムラにはちょっと外に出れば本物の草や木や花がそこここにある。
そして生きたカエルやアリやちょうちょやカナヘビや…。(たまにシカや猿も見ますが、コレはちょっと危険
 )
)それに触れて、見て、におって、たまにはなめてみて本物とはこういうものなんだな、ということを五感で知る。
五感で記憶にすりこまれたものはその中のどれかが呼び覚まされるだけで記憶として蘇ります。
そして、それがふるさとの記憶として蘇り、ふるさとを誇りに思い、ふるさとの人々を大事に思う。
先日、お散歩中にしゃくとり虫がいました。
数人の子どもたちといっしょにしゃがんで見ていた。
しばらく見た後、ちょっと「コワイ」と思った子どもが足でグシャッ!と踏み潰した

思わず私と、もう一人の保育者「ぎゃー!!」って叫んじゃいましたよ。
そしたらその子…
「しまった!」って顔をしてうずくまって動かなくなってしまった。
叫んでしまったことで、否定的な感情を受けたのかもしれないけれど、それよりその子はそこで命の火が消えた瞬間を目撃した。
それがある意味ショックだったんでしょうね。
それからは虫や動物の図鑑を持ってきて「にょろにょろ(へび)」や「むー(虫)」を指差しながらとても興味を持つようになりました。
こういう経験って、バーチャルな世界では絶対に経験できないこと。
ゲームでいくら相手を切り刻んでも、この子のように踏み潰したときの感触やつぶれたときの音や分泌物が飛び出た映像ほどの経験はできない。
何より、その時に得られる感情の成長は絶対に得られない。
ある保育所では、危ないから・割れるからといってプラスティックやメラミンの食器などを安易に使わず
陶器の食器やガラスのピッチャーやコップなどを使っている園があります。
当然衛生面のこともありますが、その園は子どもに本物を使わせたい、と思っている。
割れても大丈夫なものを使わせていると、雑に扱ってもいい、投げても大丈夫、という習慣が身につく。
もし投げてしまって割れたら、そこでその子どもは学ぶのです。
投げるとコップは割れてしまうんだ、と。
何より私が懸念するのは、そういう素材を使うことで、保育者である大人の扱いが雑になります。
お子さんのいらっしゃる方は経験があると思いますが、子どもは大人の真似をしたがります。
本当によ~~~~~く見ています。
私が他の保育者に言うのは「片付けにしろ、おもちゃや食器類の扱いにしろ、大人が日々『見せていく』ことが子どもの育ちには大事」だと。
ムラの託児所でも今年から陶器のコップとお皿を使っていますが
子どもは今のところ割っていません。
割ったのは食器洗いで手を滑らせた大人です(笑)。
【変幻可能な玩具をそろえる】
うちのクラスには基本押さえたら音が出るものや、ソフビのなんとかレンジャーとかましてやテレビは置いていません。
チェーンリングや原木積み木、基本図形のみ(○△□)のマグネット、素朴な赤ちゃんのお人形、おままごとセット、ブロック、絵本etc・・・
素材に関しては本当は自然天然のものでそろえたいところですが、そこはまだ力及ばず…。
「見立てによっていろんな物に変わる素材」を置いていると
1.『これがいい!』ってなったときにけんかが少ない。
2.どんな遊びになっても多用できる。
3.想像力次第で遊びが発展する
というメリットがあります。
現にチェーンリングはおままごとではラーメンやうどんになるし、お風呂になると水の変わりに、または女の子の大好きなネックレスにも。
マグネットは貼り付けて図形を楽しむだけでなく、○のものは最近お店ごっこのお金に早代わりしています。
子どもの想像力は無尽蔵。
時々上のクラスの子たちが遊びに来ると、さらに遊びが発展していて「そっか!そういう使い方があったか!」と大人が勉強させられます。
結局のところ、こういう遊びの中で培われる「想像力」は融通性や判断力を養うだけでなく
ひいては人の気持ちを考える際の土台になるのです。
テレビなどの一方的に情報を与えられる媒体は想像力を働かせる間もなく次の映像に移ります。
少なくとも幼児期の脳の発達ではついていけない。
じっくり手で触りながら目で見ながら、これまた五感を働かせながら自分の世界を確立し
それができた暁には他人にも同じように世界があることを知っていくのだと、私は思います。
私も含め、最近は大人も子どもも想像力が欠如している。
今横たわっている問題のほとんどはこの「想像力の欠如」によると思っています。
だから子どものときにどれだけ想像力を養えるか。
これがこれからを担う子どもたちにとっては最重要課題。
そして、それを提供する大人たちの最重要課題。

FBでフォローしている愛知県のレイモンド庄中保育園では定期的に絵画展を開いているらしい。
壁面ではなく、こういうの見せたいなぁ。
愛情料理研究家 土岐山協子の 『料理はしないんだけど料理研究家のブログ』 『いずれ一人で生きていく子ども達へ』〜深い深い愛情を内田美智子先生に学ぶ

自分が生きている周りにはホントにたくさんの支えがあって
脈々とつながれてきた命のリレーがあって
今何も考えずに口に運ぼうとしているそのひと口にもたくさんの人間の汗と努力があり
だから自分は自分ひとりのための命ではなく
自分も誰かの役に立ち、誰かは自分のためになっている。
そういうことを
想像できる人になりたい、そして伝えていきたい。