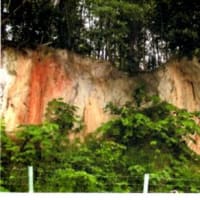平成9月19日(木) 舞洲陶芸館にて
16日の大型台風接近のあとでしたが、青空のもとJR桜島駅に集合、陶芸館に向かいました。 土器作りの一日の始まりです。縄文時代、弥生時代の土器を作りその時代の人の気持ちになってみようと云う訳です。

素地作り(胎土づくり)
 まず、1kgの粘土と300gの砂を前にします。粘土だけで野焼きすると破裂するので、砂を3割ほど混ぜると空気が抜けるので破裂の可能性が低くなるとのことです。ザラザラとした砂と粘土は力一杯錬ってもなかなか混ざりません。うどん作りの要領で、足で踏んだりする人も出てきて、皆、大格闘の上、20分位で、やっと混ぜることができました。
まず、1kgの粘土と300gの砂を前にします。粘土だけで野焼きすると破裂するので、砂を3割ほど混ぜると空気が抜けるので破裂の可能性が低くなるとのことです。ザラザラとした砂と粘土は力一杯錬ってもなかなか混ざりません。うどん作りの要領で、足で踏んだりする人も出てきて、皆、大格闘の上、20分位で、やっと混ぜることができました。
成 形
瓦は先生が朴ノ木で彫り用意して下さった木型で、軒丸瓦の制作です。丸めた粘土を木型の中心に置き周囲に広げ、めん棒を使って伸ばし、叩き、木型からはずします。見事、瓦の出来上りです。
土器は、ひも作りです。粘土をひも状にして、積み上げて形を作っていきます。砂を混ぜたためでしょうか?粘土が硬く、皆、思うように扱えず四苦八苦です。ですが、一歩一歩、形になっていきます。その様子は嬉しいものです。


 軒丸瓦
軒丸瓦
文様付け(施文)
土器の上に、へら、縄、竹串、などで文様を付けたり、粘土で、突帯を付けたりしました。
土偶もいろいろの作品ができました。





乾 燥
 思いを込めた作品を、日蔭で乾かします。軒丸瓦、縄文土器、弥生時代土器、土偶など並びました。力一杯、土に遊ばれました。なかなか楽しい一刻でした。出来上がった作品は陶芸館で預かって頂き、乾かしたあとはいよいよ野焼きです。
思いを込めた作品を、日蔭で乾かします。軒丸瓦、縄文土器、弥生時代土器、土偶など並びました。力一杯、土に遊ばれました。なかなか楽しい一刻でした。出来上がった作品は陶芸館で預かって頂き、乾かしたあとはいよいよ野焼きです。
平成11月7日(木) 浜寺公園内 大阪国際ユースホステル バーベキュー場
土器 野焼き
 夜半過ぎの雨も止み、野焼きには良い天気になりました。野焼きの準備をします。
夜半過ぎの雨も止み、野焼きには良い天気になりました。野焼きの準備をします。
ドラム缶・・ドラム缶を半分に切り、空気穴をあけたもの(今まで何度か使ったものです)炭・・120キロ、送風機、着火剤、レンガ、鉄網、火ばさみ、など用意します。そして、土器です。
設 置
 バーベキュー台にドラム缶をセットします。下段に炭を入れ、上段に、土器を並べます。
バーベキュー台にドラム缶をセットします。下段に炭を入れ、上段に、土器を並べます。
予 熱


 乾燥、膨張させるため。素地作りのとき、砂を混ぜておいたので、空気がその砂粒を通じて出てきます。土器の上に熱を逃さないため、松葉をかぶせました。下段に着火剤で、火を付けます。火力を強めるため、随時、ドラム缶の穴から、燃料を足していきます。炭、新聞、公園で拾った、松葉や松ぼっくりなどです。40分位で松葉から、煙が上がり、燃え始めました。炎が大きくなります。どんどん、燃料を入れ空気を送り温度を上げます。これで、800度くらいです。
乾燥、膨張させるため。素地作りのとき、砂を混ぜておいたので、空気がその砂粒を通じて出てきます。土器の上に熱を逃さないため、松葉をかぶせました。下段に着火剤で、火を付けます。火力を強めるため、随時、ドラム缶の穴から、燃料を足していきます。炭、新聞、公園で拾った、松葉や松ぼっくりなどです。40分位で松葉から、煙が上がり、燃え始めました。炎が大きくなります。どんどん、燃料を入れ空気を送り温度を上げます。これで、800度くらいです。
本焼き

 30分位燃やした後、1時間余りそのままで置いておきます。下段の炭は、炎はなくなっていますが、熱いままです。上段の土器を取り出します。ドラム缶は一段にして、炭を缶の3割ほど入れ上に取り出した土器を改めて並べます。
30分位燃やした後、1時間余りそのままで置いておきます。下段の炭は、炎はなくなっていますが、熱いままです。上段の土器を取り出します。ドラム缶は一段にして、炭を缶の3割ほど入れ上に取り出した土器を改めて並べます。
土器の上に更に炭を置きます。着火です。燃料を入れつつ、温度をあげます。ごうごうと音がします。火の粉が散ります。その間、時々ハンマーで缶を叩きます。なかの隙間をなくすのです。
黒色化

 小さなカンカンにもみ殻をいれます。そこに焼けた土器を入れもみ殻をかぶせて蓋をそます。しばらくおいて、取りだすと、真っ黒になっています。瓦に用いられた方法だそうです。
小さなカンカンにもみ殻をいれます。そこに焼けた土器を入れもみ殻をかぶせて蓋をそます。しばらくおいて、取りだすと、真っ黒になっています。瓦に用いられた方法だそうです。
取出し
いよいよ土器の取りだしです。まだ燃えている炭から土器を出すのは熱く非常に危険な作業でした。一つ一つ取り出される作品に歓声が上がります。少し欠けたりヒビが入っているものもありましたが爆発したものもなく、成功しました。



ドラムの中の作品 並べられた作品 遮光器土偶
火おこし
 古代の火おこしの器具を生徒の一人が作ってきてくださいました。コマを回して数分後、小さな火種が点きました。しかし、なかなかコツがいるようです。
古代の火おこしの器具を生徒の一人が作ってきてくださいました。コマを回して数分後、小さな火種が点きました。しかし、なかなかコツがいるようです。
9月に土をひねり、11月野焼きしました。土と炎と格闘しました。改めて、古代の人々の技術の高さに驚嘆するばかりです。
16日の大型台風接近のあとでしたが、青空のもとJR桜島駅に集合、陶芸館に向かいました。 土器作りの一日の始まりです。縄文時代、弥生時代の土器を作りその時代の人の気持ちになってみようと云う訳です。

素地作り(胎土づくり)
 まず、1kgの粘土と300gの砂を前にします。粘土だけで野焼きすると破裂するので、砂を3割ほど混ぜると空気が抜けるので破裂の可能性が低くなるとのことです。ザラザラとした砂と粘土は力一杯錬ってもなかなか混ざりません。うどん作りの要領で、足で踏んだりする人も出てきて、皆、大格闘の上、20分位で、やっと混ぜることができました。
まず、1kgの粘土と300gの砂を前にします。粘土だけで野焼きすると破裂するので、砂を3割ほど混ぜると空気が抜けるので破裂の可能性が低くなるとのことです。ザラザラとした砂と粘土は力一杯錬ってもなかなか混ざりません。うどん作りの要領で、足で踏んだりする人も出てきて、皆、大格闘の上、20分位で、やっと混ぜることができました。成 形
瓦は先生が朴ノ木で彫り用意して下さった木型で、軒丸瓦の制作です。丸めた粘土を木型の中心に置き周囲に広げ、めん棒を使って伸ばし、叩き、木型からはずします。見事、瓦の出来上りです。
土器は、ひも作りです。粘土をひも状にして、積み上げて形を作っていきます。砂を混ぜたためでしょうか?粘土が硬く、皆、思うように扱えず四苦八苦です。ですが、一歩一歩、形になっていきます。その様子は嬉しいものです。


 軒丸瓦
軒丸瓦文様付け(施文)
土器の上に、へら、縄、竹串、などで文様を付けたり、粘土で、突帯を付けたりしました。
土偶もいろいろの作品ができました。





乾 燥
 思いを込めた作品を、日蔭で乾かします。軒丸瓦、縄文土器、弥生時代土器、土偶など並びました。力一杯、土に遊ばれました。なかなか楽しい一刻でした。出来上がった作品は陶芸館で預かって頂き、乾かしたあとはいよいよ野焼きです。
思いを込めた作品を、日蔭で乾かします。軒丸瓦、縄文土器、弥生時代土器、土偶など並びました。力一杯、土に遊ばれました。なかなか楽しい一刻でした。出来上がった作品は陶芸館で預かって頂き、乾かしたあとはいよいよ野焼きです。平成11月7日(木) 浜寺公園内 大阪国際ユースホステル バーベキュー場
土器 野焼き
 夜半過ぎの雨も止み、野焼きには良い天気になりました。野焼きの準備をします。
夜半過ぎの雨も止み、野焼きには良い天気になりました。野焼きの準備をします。ドラム缶・・ドラム缶を半分に切り、空気穴をあけたもの(今まで何度か使ったものです)炭・・120キロ、送風機、着火剤、レンガ、鉄網、火ばさみ、など用意します。そして、土器です。
設 置
 バーベキュー台にドラム缶をセットします。下段に炭を入れ、上段に、土器を並べます。
バーベキュー台にドラム缶をセットします。下段に炭を入れ、上段に、土器を並べます。予 熱


 乾燥、膨張させるため。素地作りのとき、砂を混ぜておいたので、空気がその砂粒を通じて出てきます。土器の上に熱を逃さないため、松葉をかぶせました。下段に着火剤で、火を付けます。火力を強めるため、随時、ドラム缶の穴から、燃料を足していきます。炭、新聞、公園で拾った、松葉や松ぼっくりなどです。40分位で松葉から、煙が上がり、燃え始めました。炎が大きくなります。どんどん、燃料を入れ空気を送り温度を上げます。これで、800度くらいです。
乾燥、膨張させるため。素地作りのとき、砂を混ぜておいたので、空気がその砂粒を通じて出てきます。土器の上に熱を逃さないため、松葉をかぶせました。下段に着火剤で、火を付けます。火力を強めるため、随時、ドラム缶の穴から、燃料を足していきます。炭、新聞、公園で拾った、松葉や松ぼっくりなどです。40分位で松葉から、煙が上がり、燃え始めました。炎が大きくなります。どんどん、燃料を入れ空気を送り温度を上げます。これで、800度くらいです。本焼き

 30分位燃やした後、1時間余りそのままで置いておきます。下段の炭は、炎はなくなっていますが、熱いままです。上段の土器を取り出します。ドラム缶は一段にして、炭を缶の3割ほど入れ上に取り出した土器を改めて並べます。
30分位燃やした後、1時間余りそのままで置いておきます。下段の炭は、炎はなくなっていますが、熱いままです。上段の土器を取り出します。ドラム缶は一段にして、炭を缶の3割ほど入れ上に取り出した土器を改めて並べます。土器の上に更に炭を置きます。着火です。燃料を入れつつ、温度をあげます。ごうごうと音がします。火の粉が散ります。その間、時々ハンマーで缶を叩きます。なかの隙間をなくすのです。
黒色化

 小さなカンカンにもみ殻をいれます。そこに焼けた土器を入れもみ殻をかぶせて蓋をそます。しばらくおいて、取りだすと、真っ黒になっています。瓦に用いられた方法だそうです。
小さなカンカンにもみ殻をいれます。そこに焼けた土器を入れもみ殻をかぶせて蓋をそます。しばらくおいて、取りだすと、真っ黒になっています。瓦に用いられた方法だそうです。取出し
いよいよ土器の取りだしです。まだ燃えている炭から土器を出すのは熱く非常に危険な作業でした。一つ一つ取り出される作品に歓声が上がります。少し欠けたりヒビが入っているものもありましたが爆発したものもなく、成功しました。



ドラムの中の作品 並べられた作品 遮光器土偶
火おこし
 古代の火おこしの器具を生徒の一人が作ってきてくださいました。コマを回して数分後、小さな火種が点きました。しかし、なかなかコツがいるようです。
古代の火おこしの器具を生徒の一人が作ってきてくださいました。コマを回して数分後、小さな火種が点きました。しかし、なかなかコツがいるようです。 9月に土をひねり、11月野焼きしました。土と炎と格闘しました。改めて、古代の人々の技術の高さに驚嘆するばかりです。
(3班:M・M)