
上の写真は,右が「新・漢語林」,左が「大漢和辞典」(いずれも大修館書店刊)
草かんむり、3画に 4画派・大修館書店が「決断」
漢和辞典で長い間,揺れていた「草かんむり」の画数が,大修館書店が出した「新・漢語林」で三画に変わったそうです。
といっても,普通の人には「草かんむり」は,三画ですよね。
四画なんて‥,とおっしゃる気持ちもよくわかります。
「草かんむり」は「艸」(くさ・ソウ)というのがもとの字です。
これは,「屮」(サ)という字が二つ集まった字です。
「屮」は,地面から若芽がちょっと出ている,という形をあらわしています。
それが少し集まったものが,「艸」なのです。
ですから,「艸」は,「草」そのもののことです。
訓読みの「くさ」,音読みの「ソウ」とも「草」と同じです。
草かんむりは,この「艸」からできているので,四画なのです。
私の漢字検索法「四角号碼(しかくごうま)」でも,草かんむりを含む漢字は「50**」とはならずに,「44**」です。
四角号碼に関する,ちょっとした説明は,ここを見てください。
上の写真を見ていただいてもわかるとおり,草かんむりには三画と四画の二つがあります。
この四画派の最大手が,大修館書店なのです。
まあ,自分が学校で習ったのは三画ですし,漢字に興味を持った人以外は,いまさら四画といわれても,というぐらいじゃないでしょうか。
それが,「諸般の事情を考えて決断したのに残念ながら反響は全くありません(大修館書店の円満字二郎さん)」ということなのでしょう(笑)。
ちなにみ,他の漢字の話を二つ。
「木」がちょっと集まると「林」になります。これが,たくさんになると「森」です。
「屮」も同じように,少し集まったのが「艸」であり,たくさん集まったのは「卉」です。
この「卉」の字は見慣れない字ですが,「花卉(かき:花の咲く草,観賞用の植物)」というふうに使われています。
この「屮」字を上下に二つ重ねます。
これに「斤(おの)」を添えたのが「折」という字です。
つまり,「折」は,おのによって草をばらばらにするという意味です。
でも,そう考えると「卉」の下半分や「折」の左半分は,「屮」が二つで三画です。
ということは,「艸」は三画の草かんむりでもいいってことでしょうか。

いつでも里親募集中
草かんむり、3画に 4画派・大修館書店が「決断」
漢和辞典で長い間,揺れていた「草かんむり」の画数が,大修館書店が出した「新・漢語林」で三画に変わったそうです。
といっても,普通の人には「草かんむり」は,三画ですよね。
四画なんて‥,とおっしゃる気持ちもよくわかります。
「草かんむり」は「艸」(くさ・ソウ)というのがもとの字です。
これは,「屮」(サ)という字が二つ集まった字です。
「屮」は,地面から若芽がちょっと出ている,という形をあらわしています。
それが少し集まったものが,「艸」なのです。
ですから,「艸」は,「草」そのもののことです。
訓読みの「くさ」,音読みの「ソウ」とも「草」と同じです。
草かんむりは,この「艸」からできているので,四画なのです。
私の漢字検索法「四角号碼(しかくごうま)」でも,草かんむりを含む漢字は「50**」とはならずに,「44**」です。
四角号碼に関する,ちょっとした説明は,ここを見てください。
上の写真を見ていただいてもわかるとおり,草かんむりには三画と四画の二つがあります。
この四画派の最大手が,大修館書店なのです。
まあ,自分が学校で習ったのは三画ですし,漢字に興味を持った人以外は,いまさら四画といわれても,というぐらいじゃないでしょうか。
それが,「諸般の事情を考えて決断したのに残念ながら反響は全くありません(大修館書店の円満字二郎さん)」ということなのでしょう(笑)。
ちなにみ,他の漢字の話を二つ。
「木」がちょっと集まると「林」になります。これが,たくさんになると「森」です。
「屮」も同じように,少し集まったのが「艸」であり,たくさん集まったのは「卉」です。
この「卉」の字は見慣れない字ですが,「花卉(かき:花の咲く草,観賞用の植物)」というふうに使われています。
この「屮」字を上下に二つ重ねます。
これに「斤(おの)」を添えたのが「折」という字です。
つまり,「折」は,おのによって草をばらばらにするという意味です。
でも,そう考えると「卉」の下半分や「折」の左半分は,「屮」が二つで三画です。
ということは,「艸」は三画の草かんむりでもいいってことでしょうか。

いつでも里親募集中










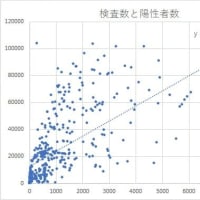
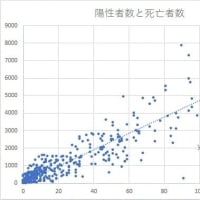
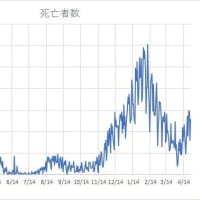


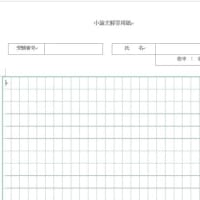


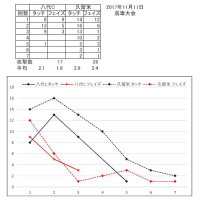


それぞれにキチンと意味があるんですもんね。
姓名判断だと、一画で運勢がかわってしまうから、
草かんむりのつく名前のかたにとっては、
たかが一画、、、だなんて言えないかも!?
やっぱり由来とか語源というものは大事ですよね。
言葉も文字もどんどん簡略化されて、元々の意味がわからなくなっているものも
たくさんありますが。
学校でも、読み書きだけではなく、そういう所から教えた方が
興味を持って覚えられると思うんですがねぇ。
私も漢字自体のもつ意味に興味があるのですが、
草かんむりの由来だとかは知りませんでした。
「四角号碼」というのもおもしろいですね。
漢字の由来をいろいろ見ていくとホント奥深い物だって感じられます。単なる文字ではないとこに興味が惹かれます。
漢和辞典の機能としては3画がベストでしょうから見えない好判断だと思います。
風水なんかでは,漢字の部首の「さんずい」は,四画だそうです。
本来の「水」の画数だそうです。
こういうところの,一画の差は大きかったりして。。。
■うっかりポチ兵衛 さま
そうですよね。
自分でも思うんですけど,語源や本来の意味を一緒に覚えると,なんでも覚えやすくなりますよね。
でも,こういうのって,学校の勉強をしなくなってから,わかるんですよね。
■豚玉そば さま
四角号碼は,大修館書店の漢和辞典の後ろに載ってたのを,めずらしいと思って使い始めたのです。
なかなか簡単で面白いのですが,たぶん流行することは,ないですね(笑)。
■まっちゃ さま
漢字って,由来などがわかれば,とても面白く感じますよね。
やっぱり,単なる文字じゃないからでしょうね。
なにげに見たら「四角号碼」が載っていて,面白そうで使いはじめました。
自分も,諸橋記念館に一度は行ってみたいと思ってます。
それと、茶道の先生の名前に「艸重」先生があり、辞書で調べたことがあります。その先生の親も博学だつたのですね。
自分が漢字に興味を持ったのは中学のときの国語の先生の影響です。
高校のときの先生も影響が大きいですけど‥‥。
高校のときの先生は「落研」の顧問で,日常会話で十干十二支の話などが出てきて,漢字以外にも刺激を受けましたね。