
上の写真は,コンクリートの断面です。
大きな砂利の周りに,砂やセメントがあるのがわかると思います。
コンクリートは,上の写真のように「セメント」と「水」以外に「砂」,「砂利」などを加えて作ります。
これらの材料以外に,もうひとつ重要なものとして「空気」があります。*1
材料の性状や品質については,JIS(日本工業規格)に細かく規定されています。

砂や砂利は,それぞれ「細骨材(さいこつざい)」,「粗骨材(そこつざい)」と呼ばれています。
それでは,これらの材料の比率はどうなっているのでしょうか。
以下に,コンクリート1000リットル(1m3)の量の一例を示します。
※ あくまでも一例です。
このような混ぜ合わせる比率のことを土木では「配合」と呼び,建築では「調合」と呼びます。
そのため,参考書では「配(調)合」などという表記になってます。←ヘンなの。。。
これらの材料の比率が悪いと,コンクリートの品質に大きな影響を与えます。
近年,コンクリートの劣化が社会問題となっていますが,一番の問題は,コンクリート材料のバランスが悪いからだと考えています。
ということで,コンクリートの材料のバランス(配合)について,次回,検証してみます。
*1)空気そのものは,意図しなくてもコンクリートに混ざります。
でもこれは,不要な空気です。
必要な空気は,わざわざ薬剤を使って,1/40㎜~1/4㎜の大きさにして,体積の5%程度混ぜ込んでいます。
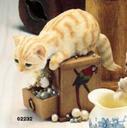
いつでも里親募集中
大きな砂利の周りに,砂やセメントがあるのがわかると思います。
コンクリートは,上の写真のように「セメント」と「水」以外に「砂」,「砂利」などを加えて作ります。
これらの材料以外に,もうひとつ重要なものとして「空気」があります。*1
材料の性状や品質については,JIS(日本工業規格)に細かく規定されています。

砂や砂利は,それぞれ「細骨材(さいこつざい)」,「粗骨材(そこつざい)」と呼ばれています。
それでは,これらの材料の比率はどうなっているのでしょうか。
以下に,コンクリート1000リットル(1m3)の量の一例を示します。
| 体積(ℓ) | 重量(㎏) | |
| セメント | 100 | 316 |
| 水 | 173 | 173 |
| 砂 | 332 | 880 |
| 砂利 | 345 | 914 |
| 空気 | 50 | 0 |
| 計 | 1000 | 2283 |
このような混ぜ合わせる比率のことを土木では「配合」と呼び,建築では「調合」と呼びます。
そのため,参考書では「配(調)合」などという表記になってます。←ヘンなの。。。
これらの材料の比率が悪いと,コンクリートの品質に大きな影響を与えます。
近年,コンクリートの劣化が社会問題となっていますが,一番の問題は,コンクリート材料のバランスが悪いからだと考えています。
ということで,コンクリートの材料のバランス(配合)について,次回,検証してみます。
*1)空気そのものは,意図しなくてもコンクリートに混ざります。
でもこれは,不要な空気です。
必要な空気は,わざわざ薬剤を使って,1/40㎜~1/4㎜の大きさにして,体積の5%程度混ぜ込んでいます。
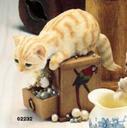
いつでも里親募集中










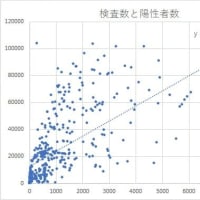
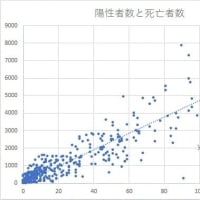
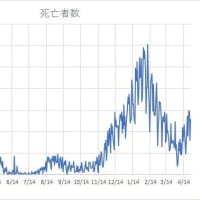


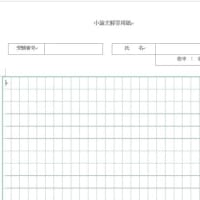


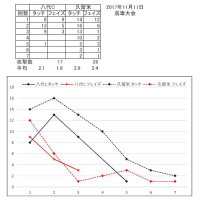







次回が楽しみです。
壁面の装飾用に、わざわざ作ったように見えますよ。
思いました。夫はコンクリートの中性化について知っていました。男の人と女性は知っていることが違いますね
悔しいです。
一体,どういうふうにまとめましょうか‥(笑)。
それは,砂利の周りが角ばっていないからです。
つまり,川や海など,自然にあるそのままの材料を使っています。
今のコンクリートでは,そんな贅沢はやっておりませぬ。
さて,コンクリートの中の空気は,寒いところではとても効果的です。
例えば,寒いところでは,コンクリートに浸み込んだ水も凍ります。
水が凍れば体積が膨張し,限られた空間では,膨張の圧力に変わります。
つまり,コンクリートの中で氷が出来ると,コンクリートは膨張の圧力で,壊れやすくなるのです。
でも,すぐそばにその圧力を緩和する空気の孔があれば,コンクリートは壊れません。
そのためにJIS規格では,空気量も含めて,いろんな決まりを持ってます。
まあそんなもんで,つまり,次回をお楽しみに!!! ということで!
コンクリート打ちっ放しの建物や壁の表面に、この記事の冒頭の写真のように砂利が見えないのは何故なんでしょうか。モルタルなどで表面を仕上げたりもしていないみたいだし…。
もし良ければ教えて下さい。よろしくお願いします。
コメント,ありがとうございました。
問い合わせの内容は,意外と簡単です。
例えば,型枠の中に砂利(粗骨材)だけを入れます。
このとき,砂利(粗骨材)の形はいびつなので,型枠に接っするのはごく一部です。
ここに,モルタルを入れます。
モルタルの粒子は小さいので,型枠に砂利(粗骨材)が接していたところ以外は,モルタルが型枠に接することになります。
その後,型枠をばらします。
すると,型枠に接していたモルタルとごく一部の砂利(粗骨材)だけが見えます。
一見すると,モルタルだけのようにも見えます。
これは,砂利(粗骨材)とモルタルをコンクリートとして同時に入れても一緒です。
まあ,そんなわけで,構造物の表面には,砂利(粗骨材)が見えないのです。
ちなみに何故こんな疑問を持ったかと言うと、昨年新築した我が家は基礎の立ち上がりを打ちっ放し仕上げにしたのですが、コンクリートとゆうものは砂利とセメントと砂と水で出来ているとゆうのをあとから知ったからです。
自分で撥水材は塗りましたが、やはり中性化を遅らせるには、モルタルで化粧したほうが良いのでしょうか?
また質問になりますが、教えていただけないでしょうか?
コンクリートの中の自由に動ける水に触れて,その水が中性化することで段々深い位置まで中性化が広がります。
その水もいっぱいのままより,少ないままより,多かったり少なかったりを繰り返すほうが,中性化は早く深く進行します。
水の多いとき二酸化炭素を含んだ水が,水の少ないとき深部に侵入するようなイメージです。
そこで,水をいっぱいのまま,あるいは少ないままにするための撥水剤は,間接的ですが効果があると思います。
それでも心配であれば,直接的に空気に触れさせない方法を採ればよいと思います。