「芸術は人を癒す」
って、語ったのは誰だったっけ?
ここ数日ぼんやりと考えていた答えを、ふと思い出した。
ルイス・ドメネク・イ・モンタネール
スペインを代表する建築家。
スペイン、バルセロナ、というと日本で有名なのは、アントニ・ガウディだけれど、当時ライバルと呼ばれたモンタネール(実際当時は、モンタネールの方が人気も知名度も上だったようですが…)の建築がまた、すばらしい。
バルセロナにある彼の建築した病院。
サンパウ病院。

ガウディの代表作、サグラダ・ファミリアから歩いてすぐのところにある病院。もちろん、現在も病院としてきちんと機能している。
「芸術は人を癒す」
まさにその思いをぶつけたかのような、建物。
病院とは思えないくらいの、芸術的空間。

私がかつて訪れたときは(病気ではなく観光で、だけれど)
少しも傷んでないカラダと
少しも傷んでないココロでしたが、
ほんの少しだけ溜まった疲れを癒して余りある感動だった。
待ち時間さえ幸せに感じるような、空間。
「癒す」という言葉は、まんざらでもなく、ゆっくりゆったりとした時間で満ちる。

くしくも、ライバルと詠われたガウディが、路面電車にひかれた時に運ばれたのはこのサンパウ病院。
身なりに気を使わなかった彼は浮浪者と間違われ、十分な治療を受けないままこの病院で亡くなったそうです。
「芸術は人を癒す」
あっけなくこの世を去った天才ガウディ。癒えることのない傷でひっそりと息絶えてゆく彼の心は、最期にすこしは癒されたのかしら?
モンタネールの芸術。
それはまさに人を癒す。
少なくとも、私の心を、癒す。
って、語ったのは誰だったっけ?
ここ数日ぼんやりと考えていた答えを、ふと思い出した。
ルイス・ドメネク・イ・モンタネール
スペインを代表する建築家。
スペイン、バルセロナ、というと日本で有名なのは、アントニ・ガウディだけれど、当時ライバルと呼ばれたモンタネール(実際当時は、モンタネールの方が人気も知名度も上だったようですが…)の建築がまた、すばらしい。
バルセロナにある彼の建築した病院。
サンパウ病院。

ガウディの代表作、サグラダ・ファミリアから歩いてすぐのところにある病院。もちろん、現在も病院としてきちんと機能している。
「芸術は人を癒す」
まさにその思いをぶつけたかのような、建物。
病院とは思えないくらいの、芸術的空間。

私がかつて訪れたときは(病気ではなく観光で、だけれど)
少しも傷んでないカラダと
少しも傷んでないココロでしたが、
ほんの少しだけ溜まった疲れを癒して余りある感動だった。
待ち時間さえ幸せに感じるような、空間。
「癒す」という言葉は、まんざらでもなく、ゆっくりゆったりとした時間で満ちる。

くしくも、ライバルと詠われたガウディが、路面電車にひかれた時に運ばれたのはこのサンパウ病院。
身なりに気を使わなかった彼は浮浪者と間違われ、十分な治療を受けないままこの病院で亡くなったそうです。
「芸術は人を癒す」
あっけなくこの世を去った天才ガウディ。癒えることのない傷でひっそりと息絶えてゆく彼の心は、最期にすこしは癒されたのかしら?
モンタネールの芸術。
それはまさに人を癒す。
少なくとも、私の心を、癒す。










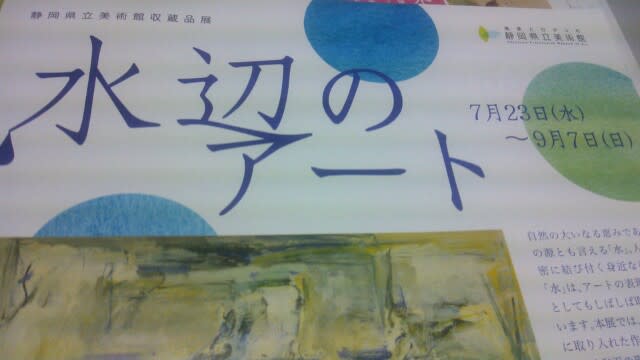 先日行った静岡県立美術館にて、同時開催していた収蔵品展。
先日行った静岡県立美術館にて、同時開催していた収蔵品展。

 [樹花鳥獣図屏風]は県立美術館所蔵で6曲1双の大きな作品。美術館のホームページやポイントカードにも使われています。
[樹花鳥獣図屏風]は県立美術館所蔵で6曲1双の大きな作品。美術館のホームページやポイントカードにも使われています。


