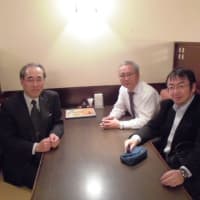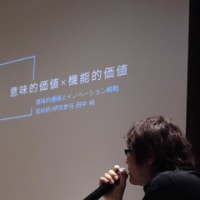三枝匡(さえぐさ ただし)という経営者がいる。
ボストン・コンサルティング・グループの日本人社員第1号を経て、企業再生のプロとして独立(三枝匡事務所を設立)。複数企業の再生を成し遂げた後、FA部品・金型商社「ミスミ」の経営者へと転身し、同社を超優良企業へと生まれ変わらせた人物だ。
日本が誇る数少ない「プロフェッショナル経営者」であり、事業再生請負人の草分けでもある。
私が彼を知ったのは、いまから20年も前になる。当時からコンサルタントや学者、ひいては経営理論のあり方にまで疑問を持っていた私であったが、そのような“虚業”の世界の出身ながら、事業の当事者となってもしっかりと成果をあげている人物がいることを知って、強い関心をもったものである。
さて、本コラムでは、三枝匡氏(以下、敬称略)が実体験から得た、企業改革・活性化を成功させるための理論や、現場を熟知するプロ経営者ならではのポイントを、彼の一連の著作から抜粋し説明していきたい。
なお、最初に、彼の理論は、そのほとんどが、シンプルかつ基本的な考え方で構成されていることを断っておきたい。それは、計画や調査などのペーパーワークよりも、「実践・実行」に重きをおいており、プランニングの精緻さや理論的合理性よりも「実現性」を重視しているからである。
その一方で、戦略の実践・実行の徹底度やその際の組織(責任単位)の考え方、戦略実行の際の障害対策など、実戦的な施策には妥協やスキがないこと、および実戦・実行フェーズにおける人材の能力を最大限に引き出し、牽引していくための(知識や机上の理論では太刀打ちできない)むずかしさが前提として含まれることは覚えておきたい。
さて、まずは、三枝理論のポイントを
1.戦略計画づくりの視点
2.組織づくりの視点
3.改革推進を支えるしくみや制度、リーダーのあり方
4.改革推進のエンジンとなる人材に関する考え方
の4つの切り口から要約してみることにする。
1.戦略計画づくりの視点
●明確なストーリーがあり、論理的にスキがなく、洗練かつシンプルに構成されていなければならない。
(これは、のちに12万部のベストセラーとなった『ストーリーとしての競争戦略』〔楠木健・著、2010年刊〕にも大いに通じるところがある)
●実行段階で骨抜きにならないようにするため、最上位の戦略コンセプトづくりから、現場における実行を支えるシステム・手法・ツールまで(幹だけではなく枝葉まで)、ひとつの体系として徹底的につくり込まねばならない。
●(計画担当者やコンサルタントに任せるのではなく)戦略・計画を実行する当事者みずからが戦略・計画を、頭をふりしぼって創出しなければならない。
→計画者と実行者をわけると、責任があいまいになり、戦略計画自体も魂が込められたものとはならない。また、山あり谷ありの改革プロセスにおいては、うまくいかなくなると責任の転嫁が始まってしまい改革にブレーキがかかってしまう。これは、P.F.ドラッカー教授も、名著『現代の経営』などでくり返し強調している点である。
2.組織づくりの視点:
●商売の基本サイクルであり成果が実感しやすい「創って、作って、売る、のサイクル」(上図を参照)を力強く、豊かに回転させることが「改革の核心」であり、もっとも重要である。これを基本設計思想として事業体(戦略、組織)の再設計が行われなければならない。
●主要経営システム(とくに人材育成・評価制度や測定システムとしての管理会計など)も、この基本サイクルの回転を前提としたものでなければならない。
3.改革推進を支えるしくみや制度、リーダーのあり方:
●(改革プランを策定する)改革タスクフォースメンバーは、そのまま事業部やユニットの責任者となり、自分の組織をけん引しなければならない。
●「気骨の人事」(荒っぽくとも、前例のない思い切った人事)を断行しなければならない。
→人事は従業員への「最大のメッセージ」の1つである。
●説得をいとわない姿勢と毅然とした態度を両立させ、組織全体を巻き込んでいく努力を持続的に行わなければならない。
→全員を巻き込む努力をいとわず、切迫感や危機感をできるだけ共有する。ただし、評論家的な態度を取る者や、新しいやり方に対して根拠のない抵抗を示す者に対しては、断固たる処置を取らねばならない。
4.改革推進のエンジンとなる人材の考え方:
●良質な改革タスクフォースの組成が、よい戦略を見出していくためのポイントとなるゆえ、人選は、改革リーダーみずからが細心の注意と責任をもって行うべきである。
●(プロ経営者が参謀としてCOOなどに就任し)それまでの経営者や事業責任者が続投する場合、当該経営者・事業責任者自身の意識の変革、および嘘のない継続的な姿勢が必須である。
→みずからコミットする気のない経営者・事業責任者がいる組織の改革はきわめてむずかしい。その本気度を見るひとつの指標として、これまでとは発想の異なる、思い切った「気骨の人事」ができるか否かが、ひとつの踏み絵となる。
●経営トップはもちろん、各部門の改革リーダーは「覚悟」を決め、それを人生の貴重なチャンスととらえて、明るく前向きに取りくまねばならない。
→改革を重荷ととらえるか、大きなチャンスととらえるかによって周囲に与える影響が変わってくる。発言や態度がブレたりネガティブなものになると、周囲はそれを敏感に察知し、不安を感じ始め、改革が減速し始める。
.....やはり、これらの中でいちばん興味深いのが、組織変革の核心と位置付けられている、ビジネスの基本サイクルである『創って、作って、売るサイクル』を力強くまわせる組織をつくることであると「断言」している点、および、これを基盤としてさまざまな施策やシステムを組み立てる、という点である。
彼のこのシンプルな組織・経営システム論については、「言い切り過ぎ」と感じるむきも少なくないであろう。しかし、実は「商売をしていることが肌で感じられる」こと、「商売のサイクルが力強く豊かに回転するサイズであること」は、組織づくりの基本中の基本で、つねに意識しておかなければならない最重要事項なのである。
たとえば経営学などで組織論をまなぶ際、しばしば事業部制や機能別組織、SBU(戦略事業ユニット)、マトリクス組織などのモデルをならべて、どれがいい、悪い、といった議論がおこなわれる。しかし、これらのモデルは、あくまでも、三枝が提唱する基本サイクル(事業ユニット)の発展・応用形、あるいはやむをえない次善策ととらえるべきである。
つまり、これらの組織・事業モデルは、たとえば組織が大型化した際、やむなく効率化を図らねばならない、など二次的な目的のための手段なのである。あくまでも、まずは適切なサイズの基本サイクルによって商売の感覚をしっかりと身につけた人材で組織を満たしたあとに導入をはかるべきものである。
別言すると、商売に敏感な組織文化を醸成したうえで、これらの(商売感覚を阻害する)組織形態を導入する、といった順序で注意ぶかく取りかからないと、どんなに精緻な戦略や組織形態を導入したとしても、途端に手段の目的化やお役所化がはじまってしまう、ということでもある。
そして、これこそが、多くの場合、企業を窮地に追いこむ病根なのである。
三枝は、これらを体験的に理解している。商売のサイクルが充実したかたちで回転することで、社員の商売感覚がみがかれ、市場への対応力がたかまり、それが顧客満足度や収益性の向上へ直結することを、実戦を通じて熟知している。だからこそ、あえて、このシンプルな理論を「決定打である」と言い切れるのだ。
さらに言えば、こうしたゆるぎない見識を持ち、それを自在に使いこなして結果を出せることが、真に高度な経営スキルある。逆説的にいえば、コンサルタントのように分析に終始したり、経営手法・技法を設計したり、ロジカルシンキングに長けていたり、というだけでは、経営のプロフェッショナルと呼ばれるには程遠いということでもある。
手痛い失敗を乗り越え、数々の実戦の修羅場をくぐりぬけてきた彼のメッセージが本質的に語りかけているもの、それは「まず、商売の感覚をしっかりと身につけた組織集団をつくれ」ということ、そして「(手段や方法論ではなく)成果に焦点を合わせてすべてを組み立て、実践・実行を第一とする組織づくりを行え」ということなのである。
◆参照文献: ※上から4冊はすべて三枝匡著.
『戦略プロフェッショナル』
『経営パワーの危機』
『V字回復の経営』
『日本の経営を創る』/以上、日本経済新聞社
『ハーバード・ビジネス・レビュー-07年1月号/三枝匡インタビュー』/ダイヤモンド社
*****************************************************
・ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所 代表
・独立行政法人 産業技術総合研究所 研究参与
田 中 純 (Kiyoshi Tanaka)
(淑徳大学オープンカレッジ講師)
〒105-0003
東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル14階
TEL: 03-3975-8171 FAX:03-3975-8171
********************************************************
この記事の一部またはすべての転載を固くお断りいたします。
Copyright (C) 2014Kiyoshi Tanaka All Rights Reserved