長野県は志賀高原の麓まで行ってきました。
今回 車のクーラーが壊れてて 窓開けて走ってたので
雨降って窓開けられなかったら 蒸し風呂だな~~と思いましたが
どうにか 降らないでくれて到着。
伺ったのは 古渡り更紗に魅入られた染織家、田中ゆきひと氏。
以前から その美しい日本茜の色に会いたくて
機会を待っていたのですが このたびようやく工房へお邪魔しました。
じざいやでも 日本茜の色が大好きで
草木染をする作家さんには 必ず 日本茜~~日本茜~~~と
お願いするのですが
日本茜は 採取が困難なのと 深い色を出す技術に手間がかかるので
どうしても 浅い色にしか出来ないことが多いのです。
ところが 田中さんの この色!!


50年近く前に 博物館で出会った一枚の古渡り更紗の裂。
その鮮やかな色が忘れがたく
依頼 試行錯誤、七転八倒をして たどり着いた答えは
「時間を惜しまずに手間隙をかける」こと。
効率を求めることなく じっくりと求める結果を出す・・・・。
ヤマモモで 数回下染めした後に
日本茜を半日ほど煮出した液に浸し染めにして
天日干しにしたら1週間ほど寝かせておく。
そして また茜で染めては寝かす。
繰り返すこと5,6回。布によっては 数十回。
寝かせている内に 色素が繊維に潜って赤味を増す。
完成後も成熟は続き 光沢と透明感の出るのは
染めてから2,3年後だと言います。
もちろん 媒染剤にも 徹底的にこだわり
一切の化学薬品は使わずに
木酢酸鉄 と 灰汁 だけの 有機質媒染で
美しく丈夫に染め上がるいことが草木染の本質と考えているからです。
黒は このヤマモモ、日本茜の上にさらに
ロックウッドで染めた 赤を含んだ妖艶な黒。
染めるのも もちろん大変な作業ですが
その前の 更紗の柄を作ること。
これも また 柄を起こし、木版を作り、布に型押しをしたら
それを蝋で伏せて防染するーーー
更紗の細かい柄を蝋伏せする作業は緻密で根気の要る作業です。
11月には じざいやで 田中さんの個展を行います。
11月までの時間をかけて
じざいやのために 更紗の帯を何点か染めてもらいます。
ぜひ 本当に手間隙をかけた末に生まれる
揺るぎの無い 美しさ、存在感をお確かめください。
個展の前に
いくつかの 帯と着物をじざいやでご紹介していきます。
ご期待下さい!
期待しなくていいけど 今日のさくらこ。
後姿を写す練習を兼ねて。

帯は先週と同じ。やっぱり垂れが長いなぁ。
背中にシワだし。










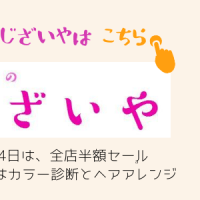










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます