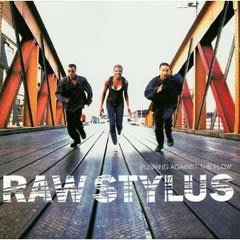ギャラクティックに対するイメージは、元々はオルタナ的テイストを併せ持った強力なジャム・バンドという感じであった。
だが、現在の彼らはニュー・オーリンズ出身ならではの『いなたさ』はそのままに、エレクトロニカ的な要素が強調され、サウンド作りにおいてはより洗練されてきている気がする。
2012年に発表された新作『Carnival Electronicos』はそれを感じさせる作品である。
『Carnival Electronicos』はニュー・オーリンズの祭りである『Mardis Gras Days(マルディグラ・デイ)』をコンセプトに作られた。
マルディグラはリオに並び称される有名なカーニバルで、ハリケーン・カトリーナの影響で規模が縮小されているらしいが、華やかな山車のパレード、その山車から投げられるビーズが有名らしい。
また、このカーニバルの際は音楽と食べ物が街中に満ち溢れ、大層にぎやかだという。
最近は女性の露出が凄いという、うらやまけしからん状況にもなっているらしい。
どんな状況だ?
本作においてギャラクティックのメンバーは結成時の8人から5人になっているが、フィーチャリングMCを含む多くのゲスト・ミュージシャンを迎えている。
楽曲はカーニバルの雰囲気たっぷりの賑やかなサウンドだ。
祭り自体が様々な民族の要素を取り込んでいるだけあり、ここで展開される楽曲も正にごった煮的である。
派手なブラス・バンドとラテン・リズム、ラップ、歪んだギター、泥臭いハーモニカ、深めのエフェクト処理などが渾然一体となっている。
初期のギャラクティックを想像すると全く違う印象を持つサウンドがここにある。
よろしかったらクリックを。
↓
人気ブログランキングへ
だが、現在の彼らはニュー・オーリンズ出身ならではの『いなたさ』はそのままに、エレクトロニカ的な要素が強調され、サウンド作りにおいてはより洗練されてきている気がする。
2012年に発表された新作『Carnival Electronicos』はそれを感じさせる作品である。
『Carnival Electronicos』はニュー・オーリンズの祭りである『Mardis Gras Days(マルディグラ・デイ)』をコンセプトに作られた。
マルディグラはリオに並び称される有名なカーニバルで、ハリケーン・カトリーナの影響で規模が縮小されているらしいが、華やかな山車のパレード、その山車から投げられるビーズが有名らしい。
また、このカーニバルの際は音楽と食べ物が街中に満ち溢れ、大層にぎやかだという。
最近は女性の露出が凄いという、うらやまけしからん状況にもなっているらしい。
どんな状況だ?
本作においてギャラクティックのメンバーは結成時の8人から5人になっているが、フィーチャリングMCを含む多くのゲスト・ミュージシャンを迎えている。
楽曲はカーニバルの雰囲気たっぷりの賑やかなサウンドだ。
祭り自体が様々な民族の要素を取り込んでいるだけあり、ここで展開される楽曲も正にごった煮的である。
派手なブラス・バンドとラテン・リズム、ラップ、歪んだギター、泥臭いハーモニカ、深めのエフェクト処理などが渾然一体となっている。
初期のギャラクティックを想像すると全く違う印象を持つサウンドがここにある。
よろしかったらクリックを。
↓
人気ブログランキングへ