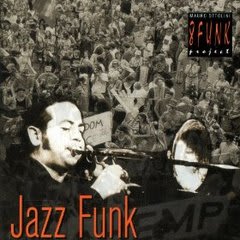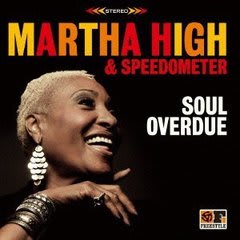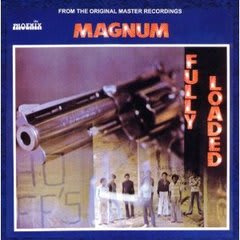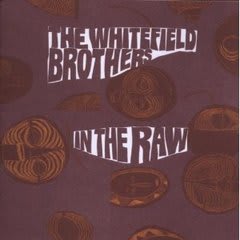今回は、先日のジョージ・デューク死去に寄せて今週の一枚を書きます。
ジョージ・デュークは75年にCBSと契約したあたりからクロスオーヴァーに留まらずファンク、R&Bに急速にシフトしていく。
これは大成功を収め、77年の『Reach For It』はR&B部門4位、総合25位にチャートインしていた。
コテコテの(日本やヨーロッパの)ジャズ・ファンはそれが面白くなかったらしく、アース・ウィンド&ファイアっぽいサウンドを目指した『Follow The Rainbow』発表後のベルリン・ジャズ・フェスティバルでは様々なものを投げつけられ、ステージを降りるハメに陥ったとライナーノーツに書かれている。
今でこそ、とやかく言う人は少なくなったのだろうが、この頃から既にジャズ権威主義みたいなものがムクムクと頭をもたげていたのだろう。
その人の紹介に『○○音大卒』とか『△△に師事』とか、やたら『肩書き』が多いのはクラシックとジャズ系ミュージシャン、と相場が決まっている。
それはさておき、途中にクラーク・デューク・プロジェクトを挟みながら、ジョージ・デュークはチャートの上位に顔を出すアルバムを安定して発表していく事になる。
その中でファンク・R&Bアルバムとして、もっとも完成度が高いと(個人的に)思われるのが83年の『Dream On』。
それと80年の『A Brazillian Love Affair』もブラジル音楽を取り入れているが、傑作と言ってよい。
だが、今回紹介する82年の『Guardian Of The Light』もなかなか捨てがたいのである。
アルバムは何とコンセプト・アルバムになっており、ジャケットには『Musical Fantasy』というオリジナル・ストーリーが曲に沿って書かれている。
(国内盤には和訳が付いている)
生命の結晶『クリスタル』(ムムッ!)を巡るファンタジー作品なのだが、内容は割愛。
当時は『宇宙』からやってきたディスコ戦士が多かったような気がするが、こちらは幻想世界からやって来たらしい。
ファンタジー寄りなのは、彼がジャズ系出身だからだろうか(ある意味リターン・トゥ・フォーエヴァー的な?)
因みに参加メンバーは、ベースにバイロン・ミラーとルイス・ジョンソン!
ホーン・セクションにシーウィンドのジェリー・ヘイ、ラリー・ウィリアムス。
バッキング・ヴォーカルにリン・デイビス、ジェフリー・オズボーン。
ギターのマイク・センベロは、スティーヴィー・ワンダーやハーヴィ・メイソンの作品にも参加しているスタジオ・ミュージシャン。
ドラムのジョン・ロビンソンも同じくスタジオ・ミュージシャンでクインシー・ジョーンズのプロデュース作品(マイケル・ジャクソン含む)に数多く参加している。
ストリング・セクションも入り、なかなかゴージャスである。
ジョージ・デュークはフェンダー・ローズやピアノに加え、ミニ・ムーグやアープ・オデッセイ、コルグのポリシックスなど、当時最新のシンセサイザーを使いまくっている。
もちろんヴォコーダーもだ。時代ですなあ。
ファルセット・ヴォイスを生かしたヴォーカルでも大活躍している。
楽曲はファンタジーなストーリーに合わせて荘厳なテイストもあるが、冒頭の『Overture』のキメまくりなインストからノン・ストップで『Light』に入る辺りでグッと引き込まれる。
それと何といっても『Reach Out』のカッコよさ!
このルイス・ジョンソンのベース・プレイは最高。
そして、ジョージ・デュークお得意のバラード・ナンバーも秀逸で、『Born To Love You』や『Give Me Your Love』などでセンチメンタルなフレーズを堪能できるだろう。
アルバムはジャズ部門17位。R&B部門46位、総合147位を記録した。
よろしかったらクリックを。
↓
人気ブログランキングへ
ジョージ・デュークは75年にCBSと契約したあたりからクロスオーヴァーに留まらずファンク、R&Bに急速にシフトしていく。
これは大成功を収め、77年の『Reach For It』はR&B部門4位、総合25位にチャートインしていた。
コテコテの(日本やヨーロッパの)ジャズ・ファンはそれが面白くなかったらしく、アース・ウィンド&ファイアっぽいサウンドを目指した『Follow The Rainbow』発表後のベルリン・ジャズ・フェスティバルでは様々なものを投げつけられ、ステージを降りるハメに陥ったとライナーノーツに書かれている。
今でこそ、とやかく言う人は少なくなったのだろうが、この頃から既にジャズ権威主義みたいなものがムクムクと頭をもたげていたのだろう。
その人の紹介に『○○音大卒』とか『△△に師事』とか、やたら『肩書き』が多いのはクラシックとジャズ系ミュージシャン、と相場が決まっている。
それはさておき、途中にクラーク・デューク・プロジェクトを挟みながら、ジョージ・デュークはチャートの上位に顔を出すアルバムを安定して発表していく事になる。
その中でファンク・R&Bアルバムとして、もっとも完成度が高いと(個人的に)思われるのが83年の『Dream On』。
それと80年の『A Brazillian Love Affair』もブラジル音楽を取り入れているが、傑作と言ってよい。
だが、今回紹介する82年の『Guardian Of The Light』もなかなか捨てがたいのである。
アルバムは何とコンセプト・アルバムになっており、ジャケットには『Musical Fantasy』というオリジナル・ストーリーが曲に沿って書かれている。
(国内盤には和訳が付いている)
生命の結晶『クリスタル』(ムムッ!)を巡るファンタジー作品なのだが、内容は割愛。
当時は『宇宙』からやってきたディスコ戦士が多かったような気がするが、こちらは幻想世界からやって来たらしい。
ファンタジー寄りなのは、彼がジャズ系出身だからだろうか(ある意味リターン・トゥ・フォーエヴァー的な?)
因みに参加メンバーは、ベースにバイロン・ミラーとルイス・ジョンソン!
ホーン・セクションにシーウィンドのジェリー・ヘイ、ラリー・ウィリアムス。
バッキング・ヴォーカルにリン・デイビス、ジェフリー・オズボーン。
ギターのマイク・センベロは、スティーヴィー・ワンダーやハーヴィ・メイソンの作品にも参加しているスタジオ・ミュージシャン。
ドラムのジョン・ロビンソンも同じくスタジオ・ミュージシャンでクインシー・ジョーンズのプロデュース作品(マイケル・ジャクソン含む)に数多く参加している。
ストリング・セクションも入り、なかなかゴージャスである。
ジョージ・デュークはフェンダー・ローズやピアノに加え、ミニ・ムーグやアープ・オデッセイ、コルグのポリシックスなど、当時最新のシンセサイザーを使いまくっている。
もちろんヴォコーダーもだ。時代ですなあ。
ファルセット・ヴォイスを生かしたヴォーカルでも大活躍している。
楽曲はファンタジーなストーリーに合わせて荘厳なテイストもあるが、冒頭の『Overture』のキメまくりなインストからノン・ストップで『Light』に入る辺りでグッと引き込まれる。
それと何といっても『Reach Out』のカッコよさ!
このルイス・ジョンソンのベース・プレイは最高。
そして、ジョージ・デュークお得意のバラード・ナンバーも秀逸で、『Born To Love You』や『Give Me Your Love』などでセンチメンタルなフレーズを堪能できるだろう。
アルバムはジャズ部門17位。R&B部門46位、総合147位を記録した。
よろしかったらクリックを。
↓
人気ブログランキングへ