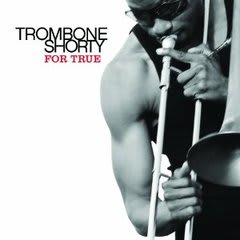激戦を繰り広げた日本シリーズは東北楽天が気迫の勝利を収めて優勝しましたね。
MVPにならなかったとは言え、最後はどうしてもマー君に投げさせたかったんだろうなあ。
今日の仙台はさぞ盛り上がったんでしょうね。
さて、今週の一枚。
連休ってことで、今回はエロジャケ(なぜ?)の紹介を兼ねまして、リチャード・グルーヴ・ホルムズを採り上げましょう。
リチャード・グルーヴ・ホルムズは、ジミー・スミスと並び称されても良いジャズ・オルガン奏者。
あのジミー・マクグリフの師匠にもあたる人である。
ジミー・スミスがヴァーヴでオーケストラを絡めた小洒落たサウンドを展開していた頃に、もっと濃厚でブルージィなオルガンを聴かせていたのだ。
彼は当初はあくまでもファンキーなジャズというスタイルだった。
64年にオーケストラをバックに録音しており、当初アルバムを2枚出すはずだったのだが、セールス上の理由だか流通の問題だかで1枚しか出さなかったらしい。
これは現在、未発表音源を加えて『A Bowl Of Soul』としてエロジャケ仕様で発表されている。

内容は結構良いと思う。
そんな彼がアシッド系やジャズ・ファンク系のファンによって支持されているのは、その後ますますファンキーでブルージィなサウンドに昇華していくからである。
60年代後半から70年代にかけてプレスティッジやグルーヴ・マーチャントで精力的に作品を発表しているのだが、後者での作品は少し前にPヴァインが再発してくれていて、大変あり難い。
で、今回紹介するのは前述の2レーベルに挟まれるように彼が71年にブルー・ノートで残した唯一のアルバム『Comin' On Home』である。
このアルバムの特徴はホルムズのオルガンにウェルドン・アーヴィンのエレクトリック・ピアノを絡めたところにある。
ウェルドン・アーヴィンは7曲中2曲の作曲も担当しており、真っ黒一辺倒ではない都会的なスパイスを提供している。
そして、ベースにジェリー・ジェモットとチャック・レイニー(2曲目のみ)、ドラムにダリル・ワシントン(グローヴァー・ワシントンJrの兄弟)を迎え、ギター、パーカッション2人を加えた、なかなか強力なリズム隊となっている。
特にジェリー・ジェモットのベースが楽曲の全体を引っ張っており、ついつい耳がそちらに釘付けになる。
因みにギターのジェラルド・ハバードは、その後のホルムズの作品に何度かクレジットされている。
そんなリズム隊の上をホルムズのオルガンが縦横無尽に暴れまくるのである。
内容だが、1曲目の『Groovin' For Mr. G』がいきなり強烈なグルーヴをお見舞いしてきて、聴く者はビックリする事だろう。
最初から全開ではないかっ!
この曲だけでも本作を買う価値はある。
にしても、なんでこの曲をフェード・アウトにしたのだっ?
まあワン・コード一発で引き倒してるだけの曲というか、ぶっちゃけジャムってるだけだと思うのだが。
2曲目『Theme From "Love Story"』は映画『ある愛の詩』のテーマ・ソング。
フランシス・レイのセンチメンタルなメロディを軽妙に料理して、ちょっと小粋なカフェの気分。
チャック・レイニーのベースが渋い。
3曲目の『Mr. Clean』はウェルドン・アーヴィンの『Liberated Brother』に収録されている曲だが、発表年次から、こちらの方が初出と思われる。
4曲目『Down Home Funk』もウェルドン・アーヴィンの作品。腰にくるタメの効いたベース・ラインとアフロなパーカッションが印象的。
5曲目『Don't Mess With Me』はパーカッションのジェームズ・デイヴィスの掛け声をフィーチャーした曲。
6曲目『Wave』はアントニオ・カルロス・ジョビンの名曲。
これは超ご機嫌なボッサ。ハバード⇒アーヴィン⇒ホルムズと回していくソロも色気があって良い。
7曲目『This Here』は6拍子の変形ブルース。
このアルバムの後、グルーヴ・マーチャントの諸作品でジャズ・ファンク度がますます高まっていくので、興味のある方はその辺りも是非押えていただきたい。
よろしかったらクリックを。
↓
人気ブログランキングへ
MVPにならなかったとは言え、最後はどうしてもマー君に投げさせたかったんだろうなあ。
今日の仙台はさぞ盛り上がったんでしょうね。
さて、今週の一枚。
連休ってことで、今回はエロジャケ(なぜ?)の紹介を兼ねまして、リチャード・グルーヴ・ホルムズを採り上げましょう。
リチャード・グルーヴ・ホルムズは、ジミー・スミスと並び称されても良いジャズ・オルガン奏者。
あのジミー・マクグリフの師匠にもあたる人である。
ジミー・スミスがヴァーヴでオーケストラを絡めた小洒落たサウンドを展開していた頃に、もっと濃厚でブルージィなオルガンを聴かせていたのだ。
彼は当初はあくまでもファンキーなジャズというスタイルだった。
64年にオーケストラをバックに録音しており、当初アルバムを2枚出すはずだったのだが、セールス上の理由だか流通の問題だかで1枚しか出さなかったらしい。
これは現在、未発表音源を加えて『A Bowl Of Soul』としてエロジャケ仕様で発表されている。

内容は結構良いと思う。
そんな彼がアシッド系やジャズ・ファンク系のファンによって支持されているのは、その後ますますファンキーでブルージィなサウンドに昇華していくからである。
60年代後半から70年代にかけてプレスティッジやグルーヴ・マーチャントで精力的に作品を発表しているのだが、後者での作品は少し前にPヴァインが再発してくれていて、大変あり難い。
で、今回紹介するのは前述の2レーベルに挟まれるように彼が71年にブルー・ノートで残した唯一のアルバム『Comin' On Home』である。
このアルバムの特徴はホルムズのオルガンにウェルドン・アーヴィンのエレクトリック・ピアノを絡めたところにある。
ウェルドン・アーヴィンは7曲中2曲の作曲も担当しており、真っ黒一辺倒ではない都会的なスパイスを提供している。
そして、ベースにジェリー・ジェモットとチャック・レイニー(2曲目のみ)、ドラムにダリル・ワシントン(グローヴァー・ワシントンJrの兄弟)を迎え、ギター、パーカッション2人を加えた、なかなか強力なリズム隊となっている。
特にジェリー・ジェモットのベースが楽曲の全体を引っ張っており、ついつい耳がそちらに釘付けになる。
因みにギターのジェラルド・ハバードは、その後のホルムズの作品に何度かクレジットされている。
そんなリズム隊の上をホルムズのオルガンが縦横無尽に暴れまくるのである。
内容だが、1曲目の『Groovin' For Mr. G』がいきなり強烈なグルーヴをお見舞いしてきて、聴く者はビックリする事だろう。
最初から全開ではないかっ!
この曲だけでも本作を買う価値はある。
にしても、なんでこの曲をフェード・アウトにしたのだっ?
まあワン・コード一発で引き倒してるだけの曲というか、ぶっちゃけジャムってるだけだと思うのだが。
2曲目『Theme From "Love Story"』は映画『ある愛の詩』のテーマ・ソング。
フランシス・レイのセンチメンタルなメロディを軽妙に料理して、ちょっと小粋なカフェの気分。
チャック・レイニーのベースが渋い。
3曲目の『Mr. Clean』はウェルドン・アーヴィンの『Liberated Brother』に収録されている曲だが、発表年次から、こちらの方が初出と思われる。
4曲目『Down Home Funk』もウェルドン・アーヴィンの作品。腰にくるタメの効いたベース・ラインとアフロなパーカッションが印象的。
5曲目『Don't Mess With Me』はパーカッションのジェームズ・デイヴィスの掛け声をフィーチャーした曲。
6曲目『Wave』はアントニオ・カルロス・ジョビンの名曲。
これは超ご機嫌なボッサ。ハバード⇒アーヴィン⇒ホルムズと回していくソロも色気があって良い。
7曲目『This Here』は6拍子の変形ブルース。
このアルバムの後、グルーヴ・マーチャントの諸作品でジャズ・ファンク度がますます高まっていくので、興味のある方はその辺りも是非押えていただきたい。
よろしかったらクリックを。
↓
人気ブログランキングへ