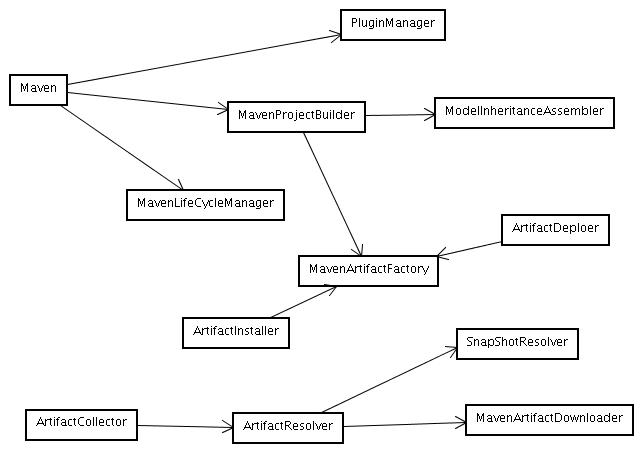Maven2のドキュメントのディレクトリにはaptという謎のフォーマットのドキュメントが置かれています。調べてみるとこれは文書をWikiに似たプレインテキストの形式であるらしい。
このフォーマットの文書をいろいろな形式に変換するaptconvertというツールがhttp://www.xmlmind.com/aptconvert.html
から入手できます。
サポートされている出力フォーマットは一応HTML, LaTeX, PostScript, PDF, RTF, DocBook SGML, DocBook XMLと多岐に渡っています。
確かにxdocよりはずっと楽にドキュメントが書けてよさそうですね。
この手のツールは国際化に関する考慮が不十分なことが多いのですが、aptconvertは出力フォーマットがHTML、DocBookであれば文字コードがSJISの入力を受け付けることができます。XML形式に出来てしまえばあとはどうにでもなる話ですから、実用上はこれで十分でしょう。
ドキュメントも充実していて、すぐに使えます。
このフォーマットの文書をいろいろな形式に変換するaptconvertというツールがhttp://www.xmlmind.com/aptconvert.html
から入手できます。
サポートされている出力フォーマットは一応HTML, LaTeX, PostScript, PDF, RTF, DocBook SGML, DocBook XMLと多岐に渡っています。
確かにxdocよりはずっと楽にドキュメントが書けてよさそうですね。
この手のツールは国際化に関する考慮が不十分なことが多いのですが、aptconvertは出力フォーマットがHTML、DocBookであれば文字コードがSJISの入力を受け付けることができます。XML形式に出来てしまえばあとはどうにでもなる話ですから、実用上はこれで十分でしょう。
ドキュメントも充実していて、すぐに使えます。