11日に、笠間稲荷神社内の「稲光閣」という施設で、小山工業高等専門学校が企画した、笠間城の話を聞いてきました。入場料300円は、資料代だと思ったら、全額笠間稲荷神社に玉串料として奉納すると言っていました。
この学校の生徒の論説を1時間弱に渡って拝聴しました。建築関係の学科ようでした。
漠然と、笠間市の佐白山の山頂に、佐志能神社が鎮座しているなと思っていましたが、これ、笠間城の天守そのもののようで、復元できれば、現存する十三番目の天守閣になるのではという夢のあるお話でした。
ちなみに、現存12基のうち、5つが国宝扱いです。私の知識が古くて、4つかと思っていたんですが、姫路(1951年)、松本、彦根、犬山(1952年)に加えて、松江城が、2015年に指定されています。
論説では、会場に来ていた、笠間市の文化財担当者と共に、現実的には厳しいと結論づけていました。
今回の調査では、佐志能神社の内部を調べて、その築城に関する板書きが出てきたとのこと。この神社は、もともと、この地にあって、笠間城築城の折に移転していて、1873年に笠間城廃城後に復したとなっているので、板書きに書かれた年号は、それより古いものなので、笠間城の記載と言える訳です。
簡単に言うと、1873年に、笠間城天守の上層を取っ払って、一階建てにして神社の拝殿としたとされるようです。板書きには使われている柱の数が記載されていて、現状と異なるために、何らかの施設が付随していた可能性もあるそうです。
この辺は私も詳しくないし、説明は無かったですが、市内にある日蓮宗真浄寺の境内に現存する八幡櫓(現在は七面堂と呼称)と作りはよく似ていたそうなので、モデルにすれば復元は出来るのかも知れません。
この笠間城天守に関する資料は存在せず、複数の絵図等に二階建てで描かれています。二階建ての櫓が2つ以上あったっていうのは、天守って言わないような気がしないでも無いです。
古河城や水戸城は、郭内で一際大きい三階櫓を天守代わりにしていたそうですので。
観光面で、笠間城の門前は南に延びていますが、その南の先に東西の通りにぶつかります。こちらを「門前通り」と呼んでいて、西から進むと東の方向に佐白山があります。つまり、復元できれば、門前から天守が望めるのが絵になるよーというのがあるようです。
笠間城の天守部分以外は見たこと無かったので、これを機会に、城門2つも現存するので、見て回るのも良いと思いました。今回は用事があったんで、次回にですけどね。










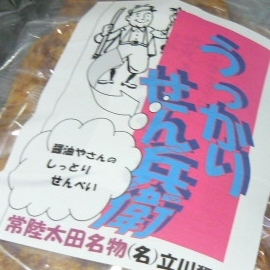




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます