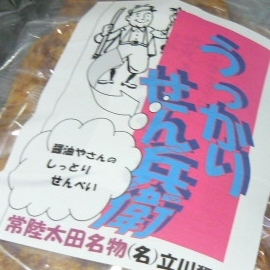結城には、すだれ麩(ぶ)というものがあるらしい。加賀100万石の城下町の料亭でも使われていたようですが、関東では結城、しかも、一件だけだそうです。麩というのは、まず、小麦粉に水を加えて生地を作ります。この後、水を加えて、グルテンと澱粉を分離させ、グルテンの方を使います。これを焼いた物が麩になるそうで、通常は木の棒などに巻き付けて焼くそうです。すだれ麩は、竹の簾の上に生地をのばして、煮固めた物を言うそうです。結城では、保存期間を長くするために塩を加えるのが他と違うそうです。結城と言えば、結城紬や桐たんすですが、こういった伝統食品もあることは、なかなか知られていません。結城土産と言えば高価な物が多いですが、こういった土産も良いですね。
茨城県北部にある常陸太田市は、蕎麦の産地です。市内の史跡、西山荘では、かつて水戸光圀公も、蕎麦を食べていたと思います。特に金砂郷地区には、昔から蕎麦の栽培が盛んでした。その金砂郷地区の在来種を、茨城県農業試験所が品種改良したものが、常陸秋そばで、品種登録は1987年です。名前の通り、茨城県を中心とした地域で、秋に収穫され、それに伴って、PRイベントが盛んに行われます。誕生から20年経ち、認知度も上がり、今では茨城の秋の名物として定着しました。茨城の代表料理、けんちん汁と一緒に食べると美味しいです。
カスミ神栖店で、カード会員のクーポンを使って、198円の中華サラダ(中)が148円で買えました。春雨と刻んだハム、刻んだ胡瓜、刻んだキクラゲなどをごまの入った中華ドレッシングで、あえたシンプルな食べ物です。私の小中学生時代、これは給食でシルバーサラダという名称で出ていたと記憶します。はな垂れ小僧の腕はシルバーアームと言っていました。これが好きでしたね。でも、社会人になって、簡単な調理なのに自分で作ろうとは思わないんですね。この食べ物はドレッシングに合う素材のコラボレーションと言うところがポイントでしょう。よく考えると、これ以外に春雨は滅多に食べませんね。たぶん、昔からあるんで、スローフードに分類してみました。
毎年、11月に、土浦市がレンコンフェアを実施していました。内容はと言うと、市内の協賛店が期間中(場合によっては通年)、れんこん料理がメニューに加わるという物。当然、主に飲食店で、これに触発された旧江戸崎町は稲敷市になっても、6月にカボチャフェアをやっていますが、こちらは盛り上がりが今ひとつ。日曜日休みの店が多すぎるんです。土浦の、このイベントも、高級飲食店が多く敷居が高かった。私は以前は、支店のある蕎麦店(今回は不参加)の本店に行ったら、支店でしかやっていないと言われたことがあります。今年は、霞ヶ浦を囲む自治体の飲食店が加わり、エリアも店舗数も大幅アップの36店舗です。一月では回りきれないでしょうねぇ。でも、これは行くしかないでしょう(笑)。知名度が今ひとつの公式サイトはこちらです。れんこんソングも必見です。
「五家宝」ってお菓子を知っていますか?。茨城県では水戸の「吉原殿中」って行った方がイメージがつかめると思います。まず具体的に、どんなお菓子か。もち米で、餅をつきます。これを薄くのばして、半生に乾燥させ、細かく砕いて煎って、あられ状にします。これを金太郎飴のようにのばして筒状にして適量にカットします。これに黄粉を掛けて完成。発祥の地とされる場所はいくつかあって、まず、吉原殿中の事を水戸の井熊總本家を参照にして確認してください。というより、こちらを見ないと話が見えないと思います。この吉原殿中を真似したという説が、まずあります。つまり、吉原殿中より、後に作られたという説ですが、私はこの説はおかしいと判断します。真似て販売した菓子商が埼玉県の行田や熊谷にあったので、熊谷銘菓になったものですが、五家宝は、吉原殿中に比べて小振りであるというが一般的だそうです。後から作ったものが小振りになる理由は、あまりないですよね。見栄を張って大きくするでしょう。遠慮する理由がありません。江戸に近いのだから物資の不足は、たぶんないでしょう。また、名前の由来がはっきりしません。五家宝である必要がないのです。ただ一説には、「五穀を原料とする」というものがあります。私が信憑性があると思うのが、地名説。上州邑楽郡五箇村(群馬県邑楽郡千代田町)の菓子商が造り、地名を名としたもの。同じく茨城県猿島郡五霞町説もあります。「棒ぼう」は棒状だからです。それが転じて「宝ぼう」になったというもの。同じように名前の由来ははっきりしませんが、埼玉県の加須で誕生したという説もあるようです。鳥海亀吉という人物が1800年頃に開発販売したというもので、これを特に加須五家宝というようです。いずれにしろ加須から、行田、熊谷にかけて発祥したという五家宝には名前の由来が不明瞭です。さて、茨城県の古河でも、五家宝は銘菓として知られています。群馬の五箇、茨城の五霞の間にある、古河でも五家宝が特産この偶然が何を意味するのか。さっぱりわかりません(笑)。古河の場合も加須同様に独立したものかも知れない。私なりのこじつけですが、古河公方から、御公方、五家宝と考えるとしっくり来る。古河で開発され、古河公方にちなんだ名前を付けたものの、東西のごか村の菓子と似ていたので、全部一緒になったのでは?いずれにしろ、水戸の吉原殿中はともかく、五家宝の分布は下総国の西部から武蔵国北部に集中していますので、大元は同じなのかも知れません。続きはいつになるか判りませんが、シリーズで書こうと思います。
茨城には地獄納豆という納豆の原始的な製法があります。煮込んだ大豆を藁苞に包んで、予め地面に穴を掘って余った藁を入れて燃やしたところに放り込み、埋め戻して2~3日放置して掘り起こせば完成するというもの。後から入れた藁苞の方は燃えないようにする工夫が必要みたい。前もって、藁を燃やしておくのは地熱を上げ、藁に付着する納豆菌の生育を促進させる目的があります。かなり臭いも栄養価も強い納豆ができるらしいです。この製法は、全国的に分布しているようですが、「地獄納豆」の呼称は茨城だけみたい。現在では、工場で納豆菌を煮大豆に振りかけて発酵させる手法が採られていて、納豆臭は薄くなっているということで、市販の納豆が嫌いな人は、まず近づけないでしょう。笠間から水戸に掛けての地域では今も作られている農家があるらしいです。一度食べてみたいですね。
山崎製パンの古河工場では、地元茨城限定に、茨城産の特産品を使った製品をいくつか出しています。地産地消なので公式サイトには紹介はありませんけど。その一つが、「レンコン入りゴボウサラダ」という惣菜ドーナツです。レンコンの産地の一つ、かすみがうら市のレンコンを刻んで、ゴボウサラダに混ぜて、パン生地に入れ油で揚げたパン。味は、まあまあですね。マヨネーズの味が強すぎるのと、パン生地に隠れて姿が見えないんで、ゴボウを食っているのかレンコン食っているのか判らないのが残念。原材料を見ても、ゴボウの比重の方が多いようです。これから、レンコンが美味しい季節ですから、アピールとしては評価できると思います。鉾田市のセイミヤウイズで¥138なり。
本日は、那珂湊にお出かけしました。茨城交通主催の町並みハイキングで3時間、市街地を講師の説明を聞きながら散策しました。参加者は10名ほどで那珂湊駅から、町中を散策しました。帰りに、けむし氏の新居にお邪魔し、自家製の「あべ川」をごちそうになりました。那珂湊では、今でも各家庭で、フライパンなどにリングを並べて作るようです。美味しかったです。ごちそうさまでした。それにしても、串に刺すイメージが強かったですが、月見団子のように積み重ねて貰うと壮観ですね。ひょっとして、那珂湊では月見団子も、あべ川なのかな。<写真:けむし氏提供>
くめ納豆の「糸引きそぼろ」を購入しました。¥100なり。内容量50gで、一食分サイズ。通常の、そぼろ納豆に人参と椎茸を刻んだ物が追加され、塩辛さも控えめで、健康志向を追求したのかも。でも、切り干し大根たっぷりに通常のやつの方が食べ応えがありますね。そぼろ納豆の入門には良いと思います。
大洗町に特徴的に分布する鉄板焼きです。具材の入った、緩く水に溶いた小麦粉を鉄板で焼きながら、醤油やソースで味付けたシンプルな食べ物です。もんじゃ焼きに似ているようで似ていない食べ物です。食べ終わった後に鉄板にくっついた焦げ(「せんべい」と呼びます。)を剥がして食べて締めくくります。水溶き小麦粉の中には、身近に手に入る具材が入っています。具材が一種類なら、一色、二種類なら二色というような具合に呼びます。主な物は、ねぎ(輪切りの刻んだ長ネギ)、フシ(鰹節)、ノリ(青のり粉末)、キリイカ(さきいか)が基本ですが、最近では、ソーセージ(魚肉ソーセージ)やベビースター、カレー粉なども登場しています。また、水溶き小麦粉に、黒砂糖だけを混ぜ込んだものを、「くろんぼ」と言います。
なにか情報があればお寄せください。
なにか情報があればお寄せください。