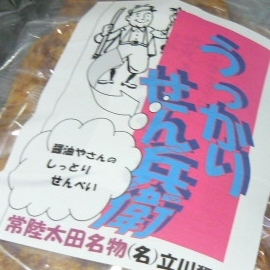エビを串に刺して焼いたものを「鬼がら焼」というみたい。でも、ネットで調べると「鬼がわら焼」というのもある。比べてみても差はないようなので、どちらかが誤記だと思うけどそもそも、名前の由来がわからない。鹿嶋近郊では「鬼がら」なんだけど。
あんこまき(潮来焼き)
この文章を書いている、2006年現在で、50代の方が記憶している。彼らの幼少時代、つまり、1960~1970年頃に隆盛を極めた食文化。潮来から佐原(現・香取市)にかけて分布した。薄く焼いた小麦粉に餡を巻き込んで食したという。
情報募集しています。
この文章を書いている、2006年現在で、50代の方が記憶している。彼らの幼少時代、つまり、1960~1970年頃に隆盛を極めた食文化。潮来から佐原(現・香取市)にかけて分布した。薄く焼いた小麦粉に餡を巻き込んで食したという。
情報募集しています。
大洗町で食べられている焼き和菓子です。碁石のような形状(水戸のオセロ文化を連想します)の団子を、専用の鉄板で焼き、電子ジャーに入れた、店ごとの秘伝のたれに漬け込んで出されます。普通の団子をと異なり、米粉ではなく小麦粉が原材料です。ですから、独特の食感が楽しめます。串に三つ刺さって、黄粉をかける場合もあります。専用の鉄板は、浅型のたこ焼き器と言うような代物で、もはや入手は困難だそうです。焼いているのに非常に軟らかい食べ物です。最近、みつだんごに憧れて、水だんごと言う名前で鉾田市で店を出した人がいます。値段は一本¥50くらいです。
情報があればお寄せください。
情報があればお寄せください。
ひたちなか市の那珂湊地区で販売されている、団子です。静岡の安倍川餅とは別物です。基本的には、大洗のみつだんごと似ていますが、碁石型ではなく円柱型、言い換えるなら、ホタテの貝柱のような形状をしています。材料は、みつだんごと同じ小麦粉です。鉄板の上に、金属のリングを置いて焼くので、この形状になるそうです。蜜と黄粉がたっぷり掛かっています。みつだんごは、黄粉をつけない場合もあるので、こちらの影響を受けたのかも知れません。また、みつだんごと違って製造工程で油が抜けやすいので、さっぱりしているという人もいます。店舗数は、大洗のみつだんご店より数が少なく絶滅寸前です。一本¥50くらい。
情報があればお寄せください。
情報があればお寄せください。
今、大洗の「たらし」を誤って、「たらし焼き」と認知される風潮があります。ここで明確に違う物だという意味で記載しておきます。たらし焼きとは、埼玉県の山間部の郷土料理としても見られますが、茨城県内でも大子など奥久慈地域に分布しています。基本的には「たらし」と同じように、水溶き小麦粉を鉄板で焼きますが、根本的に違うのは、味噌が入るところです。また、葱ではなく、シソかニラが薬味で入ります。こちらは、「もんじゃ」というより、お好み焼きのようにしっかり固まっているようです。平地では、醤油、山地では、味噌が主体になるのは興味深いところです。
昭和40年代~50年代にかけて流行したと考えられます。移動店舗の形態で、細長くお好み焼きを焼き、割り箸の切れ目に挟み込んで、さらに魚肉ソーセージ挟み込んで巻いて販売したといいます。その複雑な工程から、高度成長期に発展していった食物と考えられますが、いつのまにか衰退しました。ひたちなかから、水戸にかけての地域で最近、復活したという情報もあります。
神栖市の一部では、水溶き小麦粉にキャベツやキリイカや干しエビなどの具材を入れ焼いた物を「どんと焼き」と呼ぶそうです。戦前から高度成長期にかけ、全国で「どんどん焼き」と呼ばれる食べ物があったそうです。どんなものかというとお好み焼きの移動販売と呼ばれるもので、子供をラッパや太鼓の音で呼び寄せて販売したみたいです。おそらく、この「どんどん焼き」が土着し、一般家庭に普及したものが「どんと焼き」だと思います。現在では、神栖の一部で「お好み焼き」を「どんと焼き」と呼ぶ地域があります。
鉾田市・鹿嶋市を中心に、年末年始にかけて作られる漬け物です。イワシやサンマを塩漬けしたものに,大根を漬け合わせた強烈な食品です。今ではサンマが主流で、生のサンマを新鮮なうちに、鉈でブツ切りにして塩漬けした物とスライスした大根を交互に重ねて漬け込むのが本来のやり方ですが、内臓や骨を除く場合もあります。千葉県銚子市から旭市にかけて、似たような食品に「塩辛こうこ」というのがありますが、詳細は不明です。12月にはスーパーで出回りますが、自宅で漬ける方々の評判はあまりよろしくありません。
納豆に塩漬けした切り干し大根を混ぜ合わせ、醤油などで味を調えた料理です。別名は、おぼろ納豆、しょぼろ納豆。醤油と塩を入れているのでかなり塩辛い。大根の食感が楽しい。茨城県各地の納豆メーカーや漬け物メーカーが販売しているので、入手は容易です。通常納豆の1.5倍程度の値段です。
秋が深まった頃から霜が降りるまでに原材料のサツマイモを収穫する。収穫されたサツマイモは、蒸して皮を剥きスライスして、一週間ほど寒風の下に日干しする。このサツマイモは通常の品種ではなく、代表的な物は「玉ゆたか」という品種で、普通のサツマイモの調理法では不味くて食べられない。ひたちれっど、いずみ13号などの品種もありますが、これらの苗の入手は不可能(園芸関連の通信販売で入手できる場合がある)。ですから、品種がわかっても、個人で作るのは難しいです。これらの品種は、蒸すことによって、甘みが増し、天日乾燥によって、飴色の独特の形状に仕上がります。スライスしないで、丸ごと干した物を「丸干し」と呼んで、ちょっと変わった食感が楽しめ特に人気があります。その製造工程や外見からは、想像できないくらい美味で高価な食べ物です。茨城県沿岸部、特に東海村、ひたちなか市、大洗町、水戸市、那珂市が特産です。
鹿行地方でも作られています。
鹿行地方でも作られています。