私は以前のブログで、新政権には自民党の仕掛けた時限爆弾がいっぱい待ち受けていると書いた。その一つが日米安保、とりわけ米軍基地の問題である。なかでも、今や焦点となった普天間基地の移設問題は日米関係を考える上で重要なケーススタディとして、新政権だけではなく日本に暮らすすべての人にとって「回答」を求めている。
日米安保条約は日本の戦争放棄=軍隊を持たないという政策の見返りとして、米軍が日本を守るという役割を担うという二国間条約だと思われている。
しかし、実態はその代償として日本は国内各地に米軍基地を受け入れ、ベトナム戦争やイラク戦争、アフガン攻撃など、アメリカが行なう軍事活動の出撃拠点としての役割を担わされているということになる。
出撃拠点は「敵」にとっては、もっとも攻撃すべき対象であり、そのためにさまざまの国の弾道ミサイルや核兵器は日本に照準があわされている。そのことに危機感を抱いていないのは、まさに「平和ボケ」の日本国民だけ。
日米安保は日本を守るものではなく、危険にさらすものに他ならない。
不思議なことだが、アジアに対しては米軍の存在は二重の相反する意味を持っている。一つは米軍の出撃拠点としての懸念の対象だが、もう一方ではかつて侵略の限りをつくした日本を内部から押さえ込む役割で、信頼の対象でもある。
日本政府は在日米軍の存在を取り除こうとすれば、アメリカとの相互信頼関係を維持しつつ、少しづつ日本の真の安全の獲得のための交渉をして、米軍基地を日本の中枢から遠ざけて行くこと、もう一つは過去の歴史を踏まえたアジア各国との信頼と強調を獲得して行くことが肝要である。
普天間基地の移設問題は、そもそもそのための交渉の中から生まれて来た。
歴史は1996年のSACO(沖縄に関する特別行動委員会)にさかのぼる。
本文は以下である。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/saco.html
この中で、三つの移設案の中から、普天間基地の辺野古への移設(ただし沖合設置)が決められている。
このSACO合意は沖縄の基地11ヶ所、面積にして21%の返還がまとめられている。しかし7ヶ所については県内への移設が前提で、その最たるものが普天間基地である。
ヘリポートの移設なのに、なぜか1500メートルの滑走路、しかも2本。これはヘリコプターのためのものではなく、新たな基地(飛行場)建設に他ならない。
SACO合意の背景には、1995年の米海兵隊員による少女暴行事件がある。長い歴史の中のたまたま起こった1件ではなく、何千件、何万件という事件の繰り返しの果てに引き起こされた事件である。
沖縄県民の怒りが頂点に達し、10万人の県民総決起集会などの怒りのうねりの結果アメリカの譲歩として確認されたもののはずだ。
「譲歩」が新しい大規模基地の建設・・。これはおかしい。
日本政府はここで「ノー」と言うべきだった。
岡田外務大臣が掲げた「嘉手納統合案」というのは、このSACOで検討された三案の一つである。ヘリコプターに1500メートルの滑走路は要らない。しかも、この基地を使う米軍海兵隊は外征部隊、つまり他国に攻撃を仕掛けるための部隊である。少なくとも「日本を守る」ための軍隊ではない。
下記のブログによれば、2007年のはじめ普天間にはヘリコプターが1機もいなかった時期もあるという。
http://atsukoba.seesaa.net/article/126373072.html
イラクかアフガンかインド洋か、いずれにしても外国への攻撃のために出かけていた。これが日米安保の本旨にのっとったものと言えるのだろうか。
米軍はこのヘリポート問題を利用して、古い普天間基地から最新鋭の海兵隊基地を獲得しようとしている。沖縄の県民意思とか、民主党の公約とかいう以前に、そろそろこの話は「うまい詐欺だった」のだと認識されても良いであろう。
ケーススタディへの回答は、米軍はこの詐欺的な話を非を認め、普天間基地そのものを、海兵隊にふさわしい米軍の所管する場所に持ち帰りなさいということである。

日米安保条約は日本の戦争放棄=軍隊を持たないという政策の見返りとして、米軍が日本を守るという役割を担うという二国間条約だと思われている。
しかし、実態はその代償として日本は国内各地に米軍基地を受け入れ、ベトナム戦争やイラク戦争、アフガン攻撃など、アメリカが行なう軍事活動の出撃拠点としての役割を担わされているということになる。
出撃拠点は「敵」にとっては、もっとも攻撃すべき対象であり、そのためにさまざまの国の弾道ミサイルや核兵器は日本に照準があわされている。そのことに危機感を抱いていないのは、まさに「平和ボケ」の日本国民だけ。
日米安保は日本を守るものではなく、危険にさらすものに他ならない。
不思議なことだが、アジアに対しては米軍の存在は二重の相反する意味を持っている。一つは米軍の出撃拠点としての懸念の対象だが、もう一方ではかつて侵略の限りをつくした日本を内部から押さえ込む役割で、信頼の対象でもある。
日本政府は在日米軍の存在を取り除こうとすれば、アメリカとの相互信頼関係を維持しつつ、少しづつ日本の真の安全の獲得のための交渉をして、米軍基地を日本の中枢から遠ざけて行くこと、もう一つは過去の歴史を踏まえたアジア各国との信頼と強調を獲得して行くことが肝要である。
普天間基地の移設問題は、そもそもそのための交渉の中から生まれて来た。
歴史は1996年のSACO(沖縄に関する特別行動委員会)にさかのぼる。
本文は以下である。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/saco.html
この中で、三つの移設案の中から、普天間基地の辺野古への移設(ただし沖合設置)が決められている。
このSACO合意は沖縄の基地11ヶ所、面積にして21%の返還がまとめられている。しかし7ヶ所については県内への移設が前提で、その最たるものが普天間基地である。
ヘリポートの移設なのに、なぜか1500メートルの滑走路、しかも2本。これはヘリコプターのためのものではなく、新たな基地(飛行場)建設に他ならない。
SACO合意の背景には、1995年の米海兵隊員による少女暴行事件がある。長い歴史の中のたまたま起こった1件ではなく、何千件、何万件という事件の繰り返しの果てに引き起こされた事件である。
沖縄県民の怒りが頂点に達し、10万人の県民総決起集会などの怒りのうねりの結果アメリカの譲歩として確認されたもののはずだ。
「譲歩」が新しい大規模基地の建設・・。これはおかしい。
日本政府はここで「ノー」と言うべきだった。
岡田外務大臣が掲げた「嘉手納統合案」というのは、このSACOで検討された三案の一つである。ヘリコプターに1500メートルの滑走路は要らない。しかも、この基地を使う米軍海兵隊は外征部隊、つまり他国に攻撃を仕掛けるための部隊である。少なくとも「日本を守る」ための軍隊ではない。
下記のブログによれば、2007年のはじめ普天間にはヘリコプターが1機もいなかった時期もあるという。
http://atsukoba.seesaa.net/article/126373072.html
イラクかアフガンかインド洋か、いずれにしても外国への攻撃のために出かけていた。これが日米安保の本旨にのっとったものと言えるのだろうか。
米軍はこのヘリポート問題を利用して、古い普天間基地から最新鋭の海兵隊基地を獲得しようとしている。沖縄の県民意思とか、民主党の公約とかいう以前に、そろそろこの話は「うまい詐欺だった」のだと認識されても良いであろう。
ケーススタディへの回答は、米軍はこの詐欺的な話を非を認め、普天間基地そのものを、海兵隊にふさわしい米軍の所管する場所に持ち帰りなさいということである。











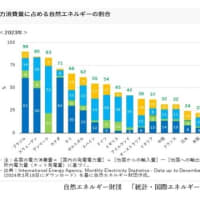


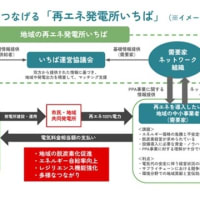






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます