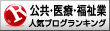午後11時2分。
はやぶさ」は帰ってきた、7年という時間をかけて小惑星イトカワから。その姿は地球の上に立つことはなかったがカプセルというヒナを届けてくれた。そこにはイトカワからのプレゼントがあるはず。
月の石以外、天体からのものはこれがはじめて。
アポロ宇宙船からはTV中継という方法で月面の様子が送られてきた。はやぶさはWEBという方法で多くの人が見守る中、時代の目撃者を作った。
人間が乗り込まず、人間が操縦しない方法で天体間を往復した技術、ましてや天体に降り立ち、物質を採取し飛び立った。そのはやぶさが帰ってきた。
「経済力があり軍事力がある国」の人ではなく「立派な国」の人の勝利。
はやぶさ」は帰ってきた、7年という時間をかけて小惑星イトカワから。その姿は地球の上に立つことはなかったがカプセルというヒナを届けてくれた。そこにはイトカワからのプレゼントがあるはず。
月の石以外、天体からのものはこれがはじめて。
アポロ宇宙船からはTV中継という方法で月面の様子が送られてきた。はやぶさはWEBという方法で多くの人が見守る中、時代の目撃者を作った。
人間が乗り込まず、人間が操縦しない方法で天体間を往復した技術、ましてや天体に降り立ち、物質を採取し飛び立った。そのはやぶさが帰ってきた。
「経済力があり軍事力がある国」の人ではなく「立派な国」の人の勝利。