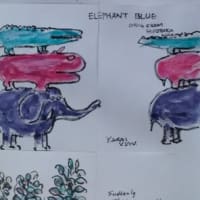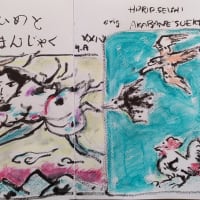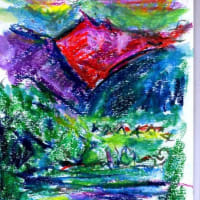朝日記240325 4.(その5)社会的知性としての総合知について報文XVIII (その5)
表紙へ返る 朝日記240325 私が2023年に書いた報文コレクト
朝日記240325 4.(その1)社会的知性としての総合知について報文XVIII (その1)
ーー本文ーー
6.社会的知性への哲学的視点
ラッセルの一元論 Russel’s Monism
ラッセルの一元論 Russel’s Monism
20世紀の最後の十年に、「意識」探求の知的基盤として、人文系と物理系での共通枠組みとして目下容認されている。これは哲学的には、ライプニッツ、スピノザの哲学への接近であり、人文系では形而上学や思弁系哲学への歴史的再評価につながっている。ただし、それはあくまでも物理系との対応を意識したものであり、そのバインダー(「糊」)としては情報信号系の介入が受け入れられている構造といってよい。その意味では観察~信号~対象を一元化したPeirceの三元論への帰着ともいえようか。
物質の本質の問題[1] として
すべてのものごとの 起因的特性[2]は、内的特性[3]の対する外的操作[4]とのunity一体のもとにあると信じたのである。かれは言う、「物理学は数学的である、それはわれわれが物理的世界についてそのように沢山知っているからではない、われわれはほとんど知らないのである;それはわれわれが発見した数学的特性だけである。それを除けば、残りはわれわれの知識は否定的である」— Bertrand Russell, An Outline of Philosophy (1927)
意識の問題を単に解く試み以上にRussellもまた物質の本質の問題を解こうと試みたのである、それは 際限ない繰り返し再帰の問題形式[5]に入る問題である。
(1)多くの科学がそうであるように、物理学は数学をとおして世界を記述するのである。[92]
他の科学がそうであるように物理学はSchopenhauerが数学に「基礎づけられた対象」とよんでいる何かあるものを記述する。経済学はそこに位置付けた資源に基礎をおき、そしてpopulation dynamics人口動力学はそのpopulation人口内での個人的ひとびとに基礎をおきている。
物理学が基礎になっている対象はしかしながら、より多くの数学をとおしてのみ記述されうるのである。[93] Russellの言では、物理学は「しかるべき式がその変化の抽象的特性を与える」ということの記述である。
「それが何を変えるのか、そしてそれが何から、そして何に変わるのか―これに対して物理学は沈黙する。」[48] 換言すると、物理学は物質の外的本質の特性を記述はするが、それらの基盤となっているその内的本質特性は記述しない。[94]
(2) Russellは、物理学は数学的であり、それは、「われわれが発見できる数学的特性でのみ」であるからである。
(3)意識[6]はこれらの物理の内的本質的特性と沢山の類似性をもつのである。
しかしながら、あるひとつの外側からの見通や見解から直接観察できないのである。そしてそれはまた、たくさんの見通し見解からも直接観察されえないのである;想定するに、音楽はそれを聞く経験のあるゆえに鑑賞できるのであり、そして慢性の痛みは痛み経験があるゆえに避けえないことにもなろう。
Russellは、意識は物質[7]の外的本質特性に関係していなければならないという結論を出したのである。 彼はこれらの内的本質性の特性をquidditesクイディティと呼んだのである。 まさに外的本質性の物理的特性が構造を生むように、それに対応し、かつidentical同定的[8]クイディティが生まれるとしたのである。
「意識的こころ」についても、Russelが論議するのは、ひとつのそのような構造のものである。[48][9]
7.寅さんは、この国の民を救ってくれるか。[9]
“Tora-san” versus Immanuel Kant
カントの道徳律、「寅さん」
(2014/9/15)
寅さんは この国の民をすくってくれるか。道徳律について思いを致すカント先生の四つの問いと題して、ブログ掲載の随想そして読者とのコミュニケーション形式のまま掲載する。
~~~~~
先の土曜日の総合知学会での発表は ひとまず、うまく終始し、質疑応答とも手ごたえがありました。 この夏は、がんばってよかったという実感がのこりました。
目的関数のupper boundとすこし理系っぽい副題にしていますが、「超越」と「経験」に焦点を当て、カントの哲学のフレームをつかって、システムを作るときに、人間の皮膚感覚の向こう側に対してどう考えるかという問題にしました。 早い話が 普遍性とか 道徳律をいかに考え、目的に反映するかという哲学的命題に焦点をあてました。
*哲学者は この「向こう側」の思考圏を 物理的な経験を経ない圏として 「超越」と呼んでいます。 早い話、「神」といってしまえばいいわけですが、宗教によってその理念の特徴や違いがあるので ここは 「超越」といっておくのがよいようです。
*科学者はこの「超越」(あるいは「普遍」)とどう知的に向かい合うかという話につながっていって、実生活に意味ある命題を共有すれば よろしいわけですが、ある意味で 平和な日本の現状はこの問題に関して 総じて深刻にならなくても生きていけるという ありがたいところがあります。
*それでも 今回の某新聞社のように 知るということ それを伝えるということの道理に外れていることが わかると われわれは共通に 失望するのはなぜであろうかという思いをいたします。 そのような道理は 日本人は、立派にもっていて それに添うように、生きることを基本にしていることは 疑いのないところです。
これらの道理は ひとが世間をわたっていくうえでもつ ひとつの道徳律のようなもの(「ひととしての道として))ということばで 共有されています。
*もうひと月も前のこの朝日記[10]に 以下のような 四つの設問をあげてみました。これは、カントの「道徳形而上学原論」(岩波文庫)という本のなかで、かれが我々に投げかけた四つの問いですが、再度 引用いたします。(彼は、これを基にして 「実践理性批判」を書いたといいます)
上で、「世間の道理」ということばをあげましたが、「個人の道理」でもかまいません。(これを「格律」とよんでおきます。「俺の生き方はこれだ」と主張する自分がいきるためのベストとおも個人訓です)
~~~~~道徳律について思いを致すカントの四つの問い
第一、ある男性が、あまり見込みがない人生に見切りをつけ 自殺することを考えるとします。
そこで彼は、自殺という行為の格律がよく普遍的法則になり得るかどうかを調べてみる。「自分の生命はこれからさきしばらく延ばしたところで、それは私に安楽を約束するどころか、もっとひどい不幸が私の生を脅かすとすれば、私は自愛の念から自分の生命を断つことを私の行為の格律とする」。
第二、返済見込みのない借金をすることを考える。
「・・・そこで私は、この場合の自愛の不当な要求を普遍的法則の変更に引きなおして、つぎのような形にしたててみよう、―「もし私がこの格律が普遍的法則になるとしたら、いったいどんな事態がおきるだろうか」。
第三、才能があっても挑戦せず、気楽にいきることを考える。
「自分のうちに才能を蔵していて、これを育成しさえすれば、いろいろな方面で有用な人に仕立てることはできる。しかし彼は、自分の気楽な境遇に気をよくして、恵まれた自然的素質の拡張や向上に努めるよりは、むしろ快楽に耽るほうがよいと思っている。それでも彼は、こう自問するのである、―「私は、自然が自分に与えてくれた素質の開発をなげやりににすることを自分の格律としている、そしてまたこの格律は、快楽を求めてやまない性向そのものとよく一致しているが、しかし義務と呼ばれるところのものとも一致するだろうか」
第四、他人とかかわらない人生
「自分が仕合せなところから、ほかの人たちが多大の困難と戦わなければならぬ様子をみても(彼はこの人たちを助けることができるのに)、こう考えるだけであえる、-
「それが私になんのかかわりがあるのか、或いは天意のままに、或いは自力によっていかに幸福であろうとも、私は彼から一物もとりあげはしない。それどころか羨みもしないだろう。 ただ私としては、彼を安泰にするために、或いはまた彼が困窮した際の救助のために、力を致す気持ちはない!」
~~~~~~~
(さて、いかがでしょうか。ここでなぜか、「寅さん」があらわれる)
「おい、そこの若いの、それを言ったらおしまいよ。 手を胸にあって、じーっと考えてごらんよ。 そんなことをしていたら、もう世間さまも相手にしてくれなくなるよ。 幸せになれるはずのおまえさんの芽もそんな考えで、なくなるよ。しっかりしろ!!」と 誰かが言ってくれることで 道理(格律)を しっかりかどうか疑問はのこるにしてもどこか納得して共有していけていると、いいですね。 いまの世でも、 他人とのそういう関わり方は 大事ですが、これが この世の中での規範としてうまく機能しているかどうかでしょうか。
* いま、土曜日の夕方に、たのしみな番組があります。それは「寅さん」[11]の映画シリーズです。むかし マンネリとさんざん新聞で揶揄されたことを覚えていますが、その後、世の支持をえて「偉大なるマンネリ」と書かれ、このごろは だれも揶揄は しません。人のこころのありかたのテキストになっているようにさえおもいます。 そういう意味では きわめて モラルへの共鳴性をもって 共有しているのではないかとおもいます。 ロバート・ギアの西洋寅さんもおもしろいですね。 ということで、 「寅さん」は国民の先生になってしまいました。 これについては あまりまなじりを決して ひとと議論したくはない思いがあります。なぜか ある種の普遍性をそこに見出しているからかもしれません。
それを認めたうえで、「寅さん」は、上のカントの四つの問いへの ベスト・ソリューションをみいだすでありましょうか。 カントの問いは あくまでも その人個人へのなげかけとして設定されています。 ここでは彼ら流のこたえを、ためしにトライしてみます。
寅さんにこたえさせるとどうなるか。宿題として お読みいただいているあなた様に課しましょう。
西側の人たちの答えかたを 想像してかきます;
まず 第一、自殺については 一神教のなかでは 命は神が与えたもので被創造物である人間に権利はないから 神との関係を断絶することになる。バツです。
第二、 自分に返済能力がないのに あるとして偽って借りる。 あらゆる人間権利のなかで 借りなければ生存そのものが危ぶまれるのであれば、それは自然権として矛盾しないことになります。 あきらかに詐欺を意図するものであれば この世の問題として裁判で解決する問題として割り切ることになり おそらくモラルな罪ではなく、法による裁定とはなるとおもいます。 それで済みです。
第三、努力しなくても たのしく生きることができるなら それでなんの問題もない。(ある部分で 戦争もなく、瞬間社会が安定している、幸せな日本でいきるのと似ているようではありませんか) しかし、たとえ 巨富の家庭でうまれた者でも 好き勝手にすごして、自分の才能生涯を安穏に終わることは稀であることを事実がいくらでも教えることであろうとおもいます。 家族からも 他人からも その存在に敬意をもって遇さるることもないことを本人の格律が どうとられるかという課題です。これは日本人の見方であるとおもいます。キリスト教的な見方では、神から与えられた能力(タレント)の最大限の使用を放棄した罪は重いとされます。
第四、隣人愛に悖ることはキリスト教の根本的な背信行為といえましょう。(筆者は この欠如のところに 忸怩たる負い目を持っていることだけを記しておきます)
カントは 個人が自らの規範として努力して持つ格律と、人間が先験的にうけている格率を超えた命令(道徳律)を提起しました。 「いまある」ということと「あるべき」ということのギャップをうめる努力が人間が目指す最高の「善」とします。
かれらの倫理の根底は、旧約以来の 創造主と被創造物との関係ですから、第一義は「世間」ではない。 したがって 善悪は神との関係においてのみ決まる、それを自らの自由意志とそれの判断をささえるの理性をもっているという前提になります。 それゆえ、上の四つは 自分で決めなければなりません。それが 自由意志の本質となります。あとは、それを共存している社会のなかで 実践的なターゲットを共有していく手続きの問題となってきます。
そういう目で 某新聞社の虚偽の報道は それを知っていたうえで 隠していたことで、それ故をもって、意図した犯罪かどうかで裁かれます。 共同社会の平和が脅かされたかどうかという次元に帰すると思います。 報道の自由権における意識的虚偽という点として、道徳律の次元ではなく あくまでも 社会での共存則への刑事犯罪の告発として、成立するかの問題であるということになってしまいます。
道徳律の問題 つまり超越が意味あるのは 基本的価値を共有している立場があるかの相互の信頼感が基本です。 強いていえば 共通の価値をもつ人間であるかどうかの根拠です。(たとえば、キリスト教が西側のパスポートして機能していることはいまも共通です)
しかし現実にはどうなるか、頭のずばぬけてよい、弁の達者な悪者が勝利を収めることもありえます。 ところで、その社会が健全であることは やがて 基本的価値を共有するモラルの欠如ということから、頭のよき悪者の排除へとはたらくかどうかにあるとおもいます。 社会にある人の精神が健全であることが大前提です。
このことは、 同時に 悪しき意図を見抜く 頭脳がどうしても必要であります。
ドイツ観念哲学の系譜のなかで、理性信仰の極みから 想像を絶した結果としてナチスを生んだという、勝者世界からの歴史観で 決着がついているとされています。
また、終戦時 小学生であった筆者が、戦争からの解放を手放しで歓迎したのも事実です。
しかし一方で、実際知である悟性優先で、人類世界がいかに進むべきかが、経済原則のなかでの価値基準が 第一義的価値としています。 人間の存在価値から世界を見直す価値は、いまだに深い傷のなお癒えていないのではないかと思い続けています。
さて、話の括りとして、「寅さん」は どこまで われわれを ガイドしてくれるか 考えてみるのも秋の夜のたのしいの’思いごと’とならないでしょうか。
あまりぱっとした 締めになりませんでしたね。
徒然ことおわり。
(2014/9/15稿)
(ブログ読者からのコメント交流)
====Comments from my friends below===
1.寅さんにこたえてほしいこと (安部忠彦)
2014-09-16
寅さん、大好きです。これまでの人生の分岐点ではいつも、私の心にいる寅さんに「おまいさんだったら、どうする?」と尋ねてきました。でも、それはあまりにも通俗的だと言われそうなので、これまで一度もひとさまに語ったことがありませんでした。別の言い方をするなら、内緒にしてきました。今回の荒井さんの着眼点は実に素晴らしいです。日本人の一般的な思想の代表として寅さんを選んだ慧眼に感服いたしました。
2.honestであるおもいをかたること (あらいやすまさ)
2014-09-16
安部さん、考えることの先がありそうで 希望が持てます。 意見がどこかで異なることがあってもです。いろいろ語ってください。 Discourse me.
3.敬愛する語るべき友S.A氏からの 寅さん論の展開
2014-09-16 20荒井様
寅さんに惹かれて読みましたが、最後に一寸出るだけ、やはりここは寅さんの哲学を展開しなければいけないのでしょうか。寅さんと言えば、すぐ亡くなった友人石井登喜男さんのことを思い出します。昔、石井さんと一緒に名画を見る会をやっていました。仲間に一杯ビデオを持っている人がいたのです。まあ女優さんの美しさを鑑賞する会でしたが(原節子、久我美子、そしてイングリッド・バーグマン)、石井さんは寅さんも好きで、第1作と最終作を見ました。第1作での寅さんは若くて元気で、フレッド・アステアばりのダンスを見せていたものですが、最終作では、持ち歩いているカバンの上にじっと座っている姿が痛々しかったことを覚えています。
確かに寅さんにはこれといった哲学があるとは思えませんが、純粋日本人批判といった、超越的なものを感じますね。
それにしてもカントという人は、ややこしい事を言う人ですね。すべてこの世の中実際ある、いや人間なら実行できることだし、社会を維持しようと思ったら、排除すべきことかもしれないのですが(キリスト教における悪の存在みたいなものですね)、私はどっちかというと実存主義に近く、カントが排除したいものも人間にはある、いやできる、やる自由があると言いたい気持ちがあります。
変な話ですが、毛沢東が言ったという「中国には10億の民がいる。1億や2億が死んでもたいしたことではない」というセリフ案外人間社会の真実かもしれません。カントの様に、まるで結晶の中で、きれいに並んでいる原子ではなく、流体あるいは高分子の様に、つながっているのか、切れているのかわからないのが人間の社会ではないかと思われます。もっと極端に言うと、カオスです。ショートレインジでは、秩序があるように見えて、ロングレインジでは無秩序。そう考えると、これも比喩でしかありませんが、歴史なんてものはブラウン運動で考えた方がいいのかもしれません。
某新聞の問題の根は深いというか、社会の木鐸と言いながら、センセーショナリズム(あるいは特ダネ主義といった方かもしれません)に侵されていること、なんら反省が見られないというのは恐ろしいことです。あれだけ戦時中の行動に反省しているふりをしながら、まったく同じことを繰り返しているとしか思えません。特に、初期の報道で、十分に調査をしなかったと云ってますが、考えられないことです。
そして、これだけ国際的な問題を引き起こしながら(いやどこかでそれを自慢している所もある)反省の色もない。正しい情報ならいざ知らず、誤報とも言っていい記事なのですから。まさにカント的な規範でいうと、やってはいけないこと。でも当人はそれが正義だと信じている。
吉田氏の報道に至っては、歪曲をしても(いやご本人たちは歪曲と思っていなかったのかもしれませんが)、バイヤスのかかった眼で見ているとしか言いようがありません。
こう考えると、哲学もたいしたものだという気がしますが、歴史は残酷です。そのドイツ人が20世紀には2度にわたる大戦争をしたのですから。哲学というのは役に立たないということでしょうか。
そう考えると、日本の戦争は、ひょっとしたら寅さんが軍人だったらやったようなものかもしれませんね。確かに日本の行く末をまじめに考えて、戦争をしたのでしょうが、全部無駄にしてしまった(それにしても、そのことに反省をしていない日本人がいるのも事実)。
長くなりました。ここで止めます。
S.A
4.(尊敬する国際派のATさんから)
2014-09-16
とても興味あるブログです。難解ですので、コピーを取って、時間が有るときに、ゆっくり楽しませていただきます。 いつも勉強させていただいております。
A.T
5.わが畏友のTA氏から
2014-09-17
荒井さんが、寅さんが日本を代表する行動規範であるかどうかについて考察をしていたブログが面白く、ぜひ、本同盟のなかでも、詳細を書いていただきたいものだと考えました。[12] 寅さんの映画は、風景が美しく、マドンナも凛々しく美しく、そして、寅さんの生き方にはカッコよさはないけれど、守るべき規範があり、それを愚直なまでに守る寅さんには強くあこがれました。 正月には、田舎の映画館(自転車で15分)に、寅さん二本立ての上映をしていたので、お年玉を握って、一人で観に行きました。 寅さんを、日本的な俗悪なものとして母が嫌っていたので、内緒で行きました。
寅さんだったら、自殺について、どう答えるか?
返す当てのない借金について、どう答えるか?
もし、あなたが寅さんだったらという話しで、設問に回答すると庶民生活の中にある深みが抉り出されるような気がします。
「年寄りが多い社会になっちまったよ」
「てやンでぇ。年寄りの多い社会を作りたくって、医療や介護を進めてきたんじゃねぇか。年寄に贅沢させろとは言わないが、粗末にしたら罰があたるぞ」
「消費税が8%から10%と、暮らしにくい世の中だよ」
「政府の連中とか、公務員とか飼っとくには、只ってぇわけにもいかねぇだろ。無駄遣いはさせちゃいけないが、頭のいい連中がお国のために、これだけ必要です、って言うんなら、あいよ、と気前よく出してやろうじゃねぇか」
「人口減少が・・・・・」
「中国、韓国とだけは、どうもうまくつきあえないんだが」
「50年前に比べて、わしらは幸せになってるんじゃろうか」
などと、問いかけて、自分の中の寅さんに答えてもらうということで、けっこう遊べるものだなと思った次第です。荒井さんGJです!
6.畏友・安部忠彦さんとの会話
2016-08-18
(安部さんから)みなさんおはようございます。
荒井さんの「寅さんはこの国の民を救ってくれるか」を興味深く読みました。
読後に、私の中に湧いてきた回答は次のような骨格を有しています。
個人の意思決定を、個人だけのレベルにとどめるのか、自分の所属するコミュニティ(家族、地縁・職縁、国籍、地球レベルと並べて、どこまでにするか)まで拡大するのか、人間を超えた概念(神、思想信条、趣味嗜好)まで広げるのか。
まず、ここを定義しなくてはならないということです。
地球に存在するすべての人間との関係性を考慮して個人の意思決定をすべき、とするならことは簡単なのですが、人間を超えたものを含もうとすると、妙なことになります。
神が出てくると、別の神の名においてグルーピングされる別の集団とは、意思決定の方法論は同じでも、戒律というツールが異なることから意思決定のアウトプットは異なることが予想されます。その結果として、集団同士の衝突がありうるわけで、この衝突は、個人レベルの判断としては、「よくないこと」であっても、神を含むコミュニティレベルでは「やらざるを得ないこと」になってしまいます。個人の善悪の感覚と、コミュニティの善悪の感覚が食い違うわけです。
寅さんを、コミュニティの神の位置において、「この場合、寅さんだったらどういう行動をするだろうか」と考える集団は、日本においてはかなり多くの人に支持されそうです。
しかしながら、理屈の上では、寅さんの位置にヒトラー、ファーブル、キリストなどを置き換えると、アウトプット(行動)が異なることが容易に想像されます。
この問題に拘泥すると先に進まないので、ひとまず、回答者はどのレベルの回答をするのかを決めたものとして次に進みます。
公平ということについて、定義をする必要もありそうです。
例えば、一本のジュースを兄弟が公平に分けるとき、二つの方法がありそうです。
(その1)正確に計量して半分に分ける。体重比、水分の必要性などに応じて、最初に分配式を決めて合意しておくことも含みます。
(その2)どちらかが、自分が公平だと思うように分けて、他方に好きなほうを選ばせる。どちらが分ける側になり、選択する側になるかは、じゃんけんで決めればよろしいでしょう。
その1を選べば、その延長線上に科学技術の進歩をもたらすでしょう。
その2を選べば、人間のもつ多様な価値観に気が付き、人間への理解が進むでしょう。
その2について、補足します。
分ける側は、ジュースを瓶から直接飲むことを望み、もう一つ(紙コップとしましょう)で飲むのはおいしさが半減すると思っています。明らかにそれとわかるほどに、紙コップに多く注ぎ、選ぶ側が紙コップを選択するように(それでも、選ぶ側が瓶を選んだら、量のおおい紙コップで我慢するつもり)分けるだろうということです。おいしさという質の問題と量の問題を、どこで等価にするかというのは、面白い問題だと思います。
・・・・・このような調子で、結論は出ているのですが、縷々書いていくと長くなりすぎます。
【結論】寅さん好きの人同士のコミュニティにおいて、行動規範を共有することは容易だと思います。このコミュニティに貢献することおよび依存することを幸福と定義するなら、寅さんは救いになると思います。
【自己採点】この回答は、半分しか明文化されていなくて、論考から結論につながりそうだがつながっていないことから、60点くらいだろうと思います。
自分としては、久しぶりに面白い論考をしたのですが、この面白さはみなさんに上手く伝わらないだろうな、という気がしています。
7.(私荒井 康全から) 安部さん、たいへん、頭の刺激になりました。寅さんは、現実には、こまった人です。むかし、若者からみると、自分の身の回りの生活で、あたりまえで、変わり栄えのしない、もういい加減にしてくれといいたくなるような家族、垣根もひくい隣、なにかがあると行き来する親戚などが転がっていましたね。そのなかで、ひとりくらいは、ひとを笑させておもしろいけれども、これから先どうしようもないような、わかららない存在がありました。 きがついてみたら、そういう基盤が薄くなっていた、あるいは形を変えていたことに気が付いている。終戦が小2で、食糧が不足、なんでも不足、かっぱらい、盗みもあたりまえ、勉強なんか彼方、アメリカ万歳、貧困貧弱日本。るつぼのなかがをかき混ぜているうちに、食えるようになったころに、家族制度も変わってしまった。地域社会も都市化・コンクリート化でどうなったのでしょうか。結構 映画などの定番テーマであったかもしれません。ジュースを分ける話は面白いですね。仕切る人間と仕切られる人間が逆転交差する関係。さまざま多様に見えてきます。ひろしやサクラ・・・、ああ全部役者がそろっていますね。
7.敬愛する友いろはさんから
2022-09-15
2014年9月15日に書かれたgooブログの「あらいやすまさ朝日記」を読みました。寅さんの題にインパクトがあり読み進めました。寅さんの件はよくわかるのですが、カント哲学についての言葉は難しく、その言葉をひとつずつ辞書を引きながら理解を深めようと、その思いに近づいているようで、康全さんが真に言いたいことがどこまで掴めているのかよく分からず、空中分解してしまいます。カントの件で、「カントは「いまある」ことと「あるべき」ことのギャップをうめる努力を、人間の目指す最高の善とする」との文章を読んだ時に、哲学者の河合隼雄に鎌倉時代の明恵上人の研究を勧めたのは梅原猛の助言によることを思い出しました。明恵は「あるべきやうは」という言葉を弟子たちに説き、己にも弟子にも厳しい人だったのだと。人としての根本は洋の東西を問わず、宗教の違いによらず同じ位置に立っているのかもしれないと思いました。
それから、最後の「実際知である悟性優先で、人類世界がいかに進むべきかが、経済原則のなかでの価値基準が第一義的価値なっている。人間の存在価値から世界を見直す価値は、いまだに深い傷を負い癒えていないのではと思い続けている」の一文より、経済優先社会の中で、人としてのあるべき姿を見失ってしまった。それは先の大戦後の社会の現実であることを憂えての発言とうけとめてよいのでしょうか? 日本人は戦後、平和な世の中で確かに幸せに生きてこられたと思っていますが、安倍総理暗殺の報以降、ほんとうにそうであったのかという疑問符が浮き上がってきました。頼るものを無くした空洞な人々がこの国にたくさんいたのではないか。寅さんのフーテンぶりは、経済一辺倒な社会に、それだけではない人の生き方を肯定する役割を果たしていたようにも思います。
8.いろはさんへの返事として (Yasumasa Arai)
2022-09-15
丁寧に思考されていることに脱帽しました。私の意味するところをやさしく、みごとに表現してくださいました。明恵上人をおしえてくれてありがとうございます。大木の枝に座して座禅をしている絵をスケッチしたことがあります。私の文とセットしてまとめたほうがおもしろそうですね。うえのATさんが正月に、母上に内緒で銀貨をにぎりしめて、自転車にのって寅さんの映画をみたというのもおもしろい一文でこれもこれも生かしたいですね。多分たくさんのひとが自分と寅さんというエッセイを投稿してくれるような予感がします。
ありがとう。
[1] Problem of substance
[3] identical intrinsic properties.
[5] problem of infinite regress
[6] Consciousness
[7] matter
[8] identical
[9] 朝日記140915 寅さんは この国の民を救ってくれるか
[10] Google blog名「朝日記」で、公開している荒井康全の公開日誌である。随想「徒然こと」と絵画・動画「今日の絵」を掲載している。最近は、執筆中の論説や翻訳などを試作投稿している。累積アクセス数は110万件(2024/3月時点)である。
[11] 『男はつらいよ』(おとこはつらいよ)は、渥美清主演、山田洋次原作・監督(一部作品除く)のテレビドラマおよび映画シリーズである。主人公の愛称から「寅さん」(とらさん)シリーズとも称される。このシリーズの主人公の名前である。
[12] http://blog.goo.ne.jp/gooararai/e/7fd66bc5818ff62b528c1ab597bd0352