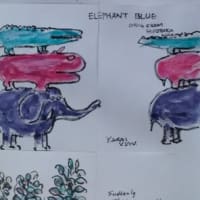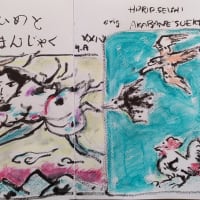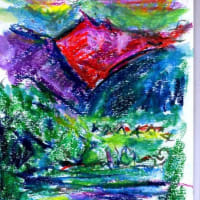朝日記230616 Humeanism ヒューム主義哲学 (その1)
続きへは以下をクリックください;
朝日記230616 Humeanism ヒューム主義哲学(その2)
朝日記230616 Humeanism ヒューム主義哲学(その3)
朝日記230616 Humeanism ヒューム主義哲学(その4)

Translation and Essay
Humeanism ヒューム主義哲学
~Wikipedia, the free encyclopediaから~
Abstract:
Humeanism refers to the philosophy of David Hume and to the tradition of thought inspired by him. Hume was an influential Scottish philosopher well known for his empirical approach, which he applied to various fields in philosophy.[1][2]
In the philosophy of science, he is notable for developing the regularity theory of causation, which in its strongest form states that causation is nothing but constant conjunction of certain types of events without any underlying forces responsible for this regularity of conjunction. This is closely connected to his metaphysical thesis that there are no necessary connections between distinct entities.
Keywords:
Humeanism Causality and necessity Theory of action Practical reason Metaethics[
Bundle theory of the self
概容:これはスコットランドの哲学者デービッド・ヒュームの哲学の概説である。
Humeanismヒューム主義哲学はDavid Humeデービッド・ヒュームの哲学を意味し、彼から起こされたthought(思考)の伝統を指している。
彼はスコットランドの哲学者であり、empirical approach(経験主義的アプローチ)が哲学のさまざまな応用のfields(場)をあたえたという点でよく知られている。このアプローチは、スピノザとカントにおいて決定的な影響を与えている。
大陸の思弁的アプローチと統合され批判主義哲学として金字塔がたてられたのであり、現在も強力なる影響力を与えている。
キーワード;ヒューム主義哲学 起因性と必要性 行動の理論 実践的理性 メタ倫理学 それ自身の束理論
目次;
1.Humeanismヒューム主義哲学
2.Causality and necessity起因性と必要性
3.Theory of action行動の理論
↓
朝日記230616 Humeanism ヒューム主義哲学 (その1)
4.Practical reason実践的理性
5.Metaethics[メタ倫理学
6.Bundle theory of the self それ自身の束理論
おわりに
↓
朝日記230616 Humeanism ヒューム主義哲学(その2)
文献類
↓
朝日記230616 Humeanism ヒューム主義哲学(その3)
朝日記230616 Humeanism ヒューム主義哲学(その4)
============本文 =======
Humeanism ヒューム主義哲学
From Wikipedia, the free encyclopedia
Not to be confused with Humanism.
1.Humeanismヒューム主義哲学
これはDavid Humeの哲学を意味し、彼から起こされたthought(思考)の伝統を指している。
彼は現在も影響力のあるスコットランドの哲学者であり、empirical approach(経験主義的アプローチ)が哲学のさまざまな応用のfields(場)をあたえたという点でよく知られている。[1][2]
philosophy of science(科学哲学)において、彼はregularity theory of causation(起因の規則性理論)を開発したので有名であり、それはcausation(起因性)というものはしかるべきevents(事態)の型でのconstant conjunction(一定共存配置)に他ならないと強調表現した。ここで、その共存配置とは、この配置にたいして底流になにか責任あるいかなる力をも伴わない事態を前提としている。
そしてこのことはno necessary connections between distinct entities. (異なる実体間ではなんら必要な結合が存在しない)というmetaphysical thesis(形而上学的課題)へと密接に結合しているのである。
Hume理論での action(行動)とはbodily behavior caused by mental states and processes (メンタルな状態とプロセスによって起因する身体的行為)としての行動として定義される。ここでのプロセスとはこのために責任をもつ機関からの筋に沿う必要性を伴わないことを前提としている。
実践的理性の理論でのスローガンは"reason is...the slave of the passions"「理性は…情熱の奴隷である」というものである。
それは実践理性の圏域が instrumental rationality (道具的合理性)に限定されており、それはあたえられたa given end(目的結果)を達成するために採用するmeans(手段)に関するものである。
しかし、それはいずれの手段をもってそれが結果につながるかの直接的な理由づけるを否定する。
Humeのmetaethics(メタ倫理学)での位置の中心は is-ought distinction(存在-当為区別)にある。そこで、is-statementsは自然世界についてのfacts(事実)に関する言説であり、ought-statementsをふくまないのである。後者はなにがなされるべきであるかまたはなにが価値がるかについての道徳的もしくはevaluative (慎重評価)された主張言説である。
philosophy of mind(心の哲学)では、Humeはよく知られるようにbundle theory of the self(自己の束理論)の開発者としてよく知られている。
その self(自己)はmental states(メンタルな状態)のa bundle(束)として理解されるべきであり、伝統的概念や、あるsubstance(基質)がこれらの状態に帰して行動するというものではないとするのである。
この位置にあるおおくの人はHumeのこのempirical outlook(経験的外貌)によって当初から影響をあたえた。それは個人次元でのexperience(経験)からの理論に基礎をおかないような対抗理論は失敗することを強調したのである。
しかしHumeの伝統にある哲学者の多くはこの形而上学的制約をはるかに超えていったのであり、そしてHumeの理念からはさまざまなmetaphysical conclusions(形而上学的結論)が引き出されたのである。
2.Causality and necessity
起因性と必要性
Main article: Humean definition of causality
Causality は通常two events(二つの事態)間の関係として理解され、ここではより早い事態がよりあとの事態を引き連れもしくはnecessitating(必然化する)対応責任があるというものである[3]。
Humeのaccount of causality(因果性の勘定法)は現在も影響的であり続けている。かれの最初の設問は起因性関係をどのように範疇化するかにあった。
Humeの観方では、それらはrelations of ideas (観念の関係性)かmatters of fact(事実の物質性)かのいずれに属する。
この区分は Hume's fork.[4](「Humeのフォーク」)として引用される。
Relations of ideas (観念関係性)はexperience(経験)とは関わりなくあたえられるa priori(先見)があるとしてその間でのnecessary connections(必要結合)を含むのである。
Matters of fact,(事実の物質性)の方は、世界がperception(知覚)やmemory.(記憶)を通してa posteriori(後天的)にのみ知り得る世界についての contingent propositions(偶然性提案)に関するものである。[1][5]
Causal relations(起因関係)はmatters of facts(事実の物質性)のcategory(範疇)のもとに収まるのである、Humeによれば、それらが必要であるか、どれかのケースが、ありうるか、ありえないかを事前で知りえないからである。
Humeのempiricist outlook(経験的外見)のためには、causal relations(起因関係)はsensory experience(感覚的経験)に立ち会うことによって学ぶべきものであることを意味するのである。
これに伴う問題としてはcausal relation itself(起因関係それ自体)というものはperception(知覚)には直接にはけっして与えられないというものである。
visual perception(視覚的知覚)を例にあげよう、石が窓のほうに向かって投んできたのをわれわれは知ったとしよう、ひきつづき、その窓は壊れた、だがその投擲がその破壊の起因であることをわれわれには直接に見えないのである。
このことがHumeのskeptical conclusion(懐疑的結論)に導く;厳密にいえば、われわれはcausal relation(起因関係)がここに含まれていることを知らないのである。[1][5]
そのかわり、われわれはearlier experiences(以前の経験)に基づいてまさにそれを仮定する、それらの内容と非常に類似した事態連鎖の経験を所有しているというものである。
この結果は、後事態は、以前事態についての経験的印象から与えられた習慣期待からくるものである。
この形而上学的水準にかんして、この結論はしばしばつぎの課題として翻訳される;起因は事態のしかるべきタイプの一定の結合にほかならないというものである。これはときに"simple regularity theory of causation"(起因性の単純規則性理論)と呼ばれる。[1][5][6]
密接に関係した形而上学的課題はHume's dictum(Humeの言説)として知られている:「もしわれわれが対象をそれ自体のなかで考えれるならば、他のいかなる対象の存在を含む対象というものは存在しない」というものである。[7]
Jessica Wilsonはつぎのような現代的定式化をあたえた:「全体として区分できて、固有のタイプである実体の間での形而上学的必要な結合はあり得ない」[8]
この課題を動機づけるHumeの直観はつぎのものである;experience(経験)は我々にさまざまなobjects(対象)のしかるべきideas(観念)を提供するが、それはまったく異なる観念を同時に提供するかもしれないというものである。
私がある樹木にとまるある小鳥を知覚するときに、私は樹木なしの小鳥を、もしくは小鳥なしの樹木をも同様に知覚していたかもしれない。
これはそれらの essences(基本)がそれぞれには依存していないからである。[7]
Humeの追従者と翻訳者はときどきHumeの言説を起因性の形而上学的基礎としてつかうのである。
この見解について、robust sense(がんこな意味)での起因性関係のいかなるものもあり得ないのである、それは、ある事態が他の事態を必要とすることになるからであって、この可能性をHumeの言説は否定しているのである。
Humeの言説は現代のmetaphysics(形而上学)での論議によく採用されてきた。
それは、たとえば nomological necessitarianism(名目論必要主義)に反対する論議としてであり、可能世界すべてで、それは同じであるというlaws of nature (自然法則)が必要であるという見解である。
これはどのように働くかをみるためには、ケースとして考えよとするのである、つまり塩がカップの水のなかに投入されそして引き続き溶解するというケースである。[12]
これはふたつの事態のシリーズとして記述できるのであり、投げるという事態と溶解するという事態である。
しかし、ふたつの事態は区別できる事態であり、Humeの言説によればそれは他が伴わないひとつの事態が可能であるのである。
David Lewis はかれのprinciple of recombination(再結合原理)を形式化する思考の線に従った:「いかなるものもそのほかのものと共存しうるのである、それはすくなくとも区別できる時空間的位置を占めるならばというもとである。同様にいかなるものも他のものと共存できないともいえる。」[13]
リアリティというはa spatio-temporal distribution of local natural properties(局所的な自然的物性の時空間的な分布)がもっとも基盤的レベルで成り立っているという仮定を伴っていて、この課題は"Humean supervenience"(ヒュームの随伴性)として知られている。
それは自然および起因的関係は単にこのlocal natural properties(局所的自然物性)の分布のうえにsupervene (随伴して)いることを言明しているのである。[14][15]
このヒュームの言説は、the notion of recombination.(再結合の概念)にもとづいての個々のpropositions(提案)やworlds(世界)が可能であるか、あるいは不可能であるかを決定する基礎原理としてひろい応用さえ提供しているのである。[16][17]
上の最後のパラグラフにあるヒューム学派の起因に関するthe reductive metaphysical outlook (演繹的形而上学的相貌)はヒューム自身の位置を事実上反映することに解釈者すべてが同意しているわけではない。
このmetaphysical aspectに反対する人たちがあり、これに代わって、ヒュームの起因性に関わる見解は認識論の場のなかに留まっておること、そこでは起因的関係について知る可能性についての懐疑的位置にあると主張するのである。他にはときに、"New Hume tradition"として参照されているが、かれらはthe reductive aspect を拒否していて、Humeは彼の懐疑的相貌にもかかわらず、起因性についてはrobust realist(がんこなリアリスト)であったとしている。
3.行動の理論
Theory of action
Hume的な伝統での行動についてのもっとも顕著な哲学者は Donald Davidsonである。
機関からの指示を得ないで行動を定義しHumeに従がうと、かれは行動が意図によって起こされる身体的動機であることを保つ。[24]
この意図そのものは信念と願望のことばで説明される。
たとえば、照明のスイッチをオンオフする行為は、一方ではその機関の信念に沿っていて、この身体的運動が明かりをオンになるであろう、そして他方で、明かりへの願望に沿っている[25] 。
Davidsonによればそれはその行動として勘定にいれる身体的行為ではないがそれから続く必然性でもある。
スウィッチを指ではじく運動はその行為の部分であるが、それは電子が電線を流れて明かりが点ずるのと同じである。
ある必然性がその行動のなかに含まれている、それはその機関がそれらを起こそうと意図しないにもかかわらずである。[26][27]
その機関がすることは「それを意図的にするという観点のもとで記述されうる」ということで十分である。[28][27]
そこで、たとえば、明りのスウィッチを点滅することが泥棒に警告をするなら、泥棒に警告することはその機関の行動の一部である。[21]
Davidsonとその類似のHume系理論への重要な反対は起因性に割り当てられた中心的役割りに向かうのである。そこでは行動を定義するに意図によって起因された身体的行為として定義している。
この問題はなりゆきまかせ、もしくは逸脱した起因連鎖として参照される。
起因連鎖がなりゆきまかせなものであるのは次の場合である;意図はそのゴールを現実化するために起こされているが、いつもとは非常に違う意図されなかった道すじでそれがある場合である、すなわちその機関の熟練さが計画された道すじで実行されないことに
よるのである。[21]
たとえばロッククライマーがその下方のクライマーをロープの操作によって殺そうという意図を持ったとしよう。
なりゆきまかせの因果連鎖としては以下である;つかんでいる手を意図的に開くかわりに、その意図が第一クライマーを神経過敏にさせてしまいそのロープがかれの手から滑る、そして斯くして下のクライマーを死に至らしめるというものである。
Davidsonはこの案件を取りあつかう、それはなりゆきまかせの起因性のケースを除外すること、それらは厳密な意味での意図的行為の例ではないので、かれの勘定のそとにおくのである。
しかしこの責任性については非難されてきたのである、それは何がただしい道すじ手段かが明記されていないということがむしろことの困難さを証明しているということであり、それはことの内容が漠然としてしまっているからである。[31][32]