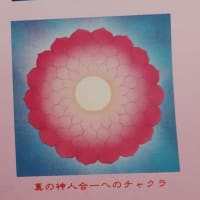1
小説『日本婦道記』山本周五郎著を読みました。山本周五郎( 1903年6月22日~1967年2月14日)、名前は知っていましたが、読むのは初めてでした。
題名の婦道とは、婦人として守るべき道とあり、ちょっと、古臭い話かなと読みはじめたのですが、背景が江戸時代であるのですが、その婦道としての生き方には衝撃でした。現代、この平成・令和の時代では、ちょっと、ありえないかなと思われもしたのですが、このような女性が今の世にも多くいるのだとしたら、いわゆるやまとなでしこという言葉が近いのでしょうか。
「やまとなでしこ」とは、日本女性のしとやかさ、奥ゆかしさ、あるいは清らかさ、美しさをたたえていうことば。か弱さの中に、りりしさがあることを、ナデシコの花になぞらえたもの。やまとなでしこは日本人女性の美称であり、特に、態度や表情が穏やかで、容姿端麗、清楚で言葉使いが美しく、男性を立てるような女性を指す。などとあります。
『日本婦道記』には、十一の物語がおさめられていますが、その中のひとつ。私のふるさと信州でのお話、「糸車」を簡単に紹介いたします。
『糸車』
一
父は依田啓七郎といって、信濃のくに松代藩につかえる五石二人ぶちの軽いさむらいだった、実直いっぽうの、荒いこえもたてない温厚なひとだったが、二年まえに卒中を病んで勤めをひき、今でも殆んど寝たり起きたりの状態がつづいている。十歳になる弟の松之助が、名義だけ家督を継いでいたが、まだ元服もしていないのでお扶持は半分ほどしかさがらない、母親は松之助が三つの年に亡くなって、家族は三人だけであるが、病気の父と幼ない弟をかかえての家計はかなり苦しかった。お高はことし十九になるが、父に倒れられて以来その看護や弟のせわや、こまごました家事のいとまをぬすんで、せっせと木綿糸を繰っては生計の足しにしていた。
(主人公であるお高であるが、お高は実際は依田啓七郎の子ではなく、幼くして依田啓七郎の養女となったのでした。)
二
お高には実の親があった。信濃のくに松本藩に仕えて西村金太夫という、はじめ身分も軽くたいへん困窮していたじぶんに、妻のお梶とのあいだにつぎつぎと子が生れ、養育することにもこと欠くありさまだったので、しるべのせわで松代藩の依田啓七郎にお高を遣ったのである。それからのち、金太夫はふしぎなほどの幸運に恵まれ、しだいに重くもちいられて、数年まえには勘定方頭取で五百五十石の身分にまで出世をした。このように立身して一家が幸福になると、親の情としてよそへ遣った者がふびんになるのは当然のことである、それもその子が仕合せであればべつだが、人をやって尋ねさせてみると依田啓七郎は妻にさきだたれ、お高を貰ったあとで生れた幼弱な子をかかえて、かなり貧しい暮しをしているとのことだった。夫妻は幾たびも相談をしたうえ、それまでの養育料を払ってひきとることにきめ、しかるべき人を間に立てて依田と交渉した。……そのとき初めてお高は自分の身の上を知ったのである、啓七郎はありのままになにもかも語った、そして「松本の家へ戻るほうがおまえのゆくすえのためだから」そう云って帰ることをすすめた。お高は考えてみようともせずに厭だと云いとおした、ついには部屋の隅に隠れて泣きだしたまま、なにを云っても返辞をしなかった。肝心のお高がそんなありさまだったので、間に立った人もどうしようもなく、そのときのはなしは結局まとまらずじまいだったのである。
「お梶どののご病気は、かなり重いようすなのだ」
と、父は暫くして言葉を継いだ、
「ひとめ会いたいという気持もおいたわしいし、おまえも実の子としていちどぐらいはご看病がしたいだろうと思う、意地を張らずにいって来るがよい、ほんの僅かな日数のことだから」
お高は殆んど聞きとれぬほどのこえで「はい」と答えた。そこまでことをわけて云われるのをむげにもできなかったし、重い病に臥している生みの母の、ひとめ会いたいという言葉にもつよく心をうたれた。乳ばなれをするとすぐ松代へ貰われて来たそうで、西村の父母の顔はまったく記憶にはない、もしものことがあれば、生みの母の顔も知らずに終らなければならない、いちどだけお顔を見せて頂こう、そう考えて承知したのであった。
同じ組長屋でもごく近しくしている石原という家の妻女にあとの事をこまごまと頼んで、その明くる朝はやく、松本から迎えに来たという下婢と老僕にみちびかれながら、あとにもゆくさきにもおちつかぬ気持でお高は松代を立った。季節はすっかり春めいていた。遠いかなたの山なみにはまだ雪がみえるけれど、うちひらけた丘や野づらはやわらかな土の膚をぬくぬくと日に暖められ、雪解の水のとくとくと溢れている小川や田の畔には、もうかすかに草の芽ぶきが感じられた。二十里そこそこの道だったが、ひどくぬかるので馬や駕籠に乗りながら三日もかかり、また冬がもどったかと思えるほどひどく冷える日の午後、ようやく松本の城下へ着いた。
(お高の実の母お梶は病気なのではなく、今は裕福な暮しとなり、幼くして別れたお高の現在の暮らしをみて、なんとしても、お高を連れ戻し一緒に暮らすことが出来たらどんなにか幸せなことだろうと思ったのです。)
三
西村の父や兄弟たちは夕食のときひきあわせられた。父は思いのほか若かった。いちばん上の兄は結婚してもう男の子があり、二兄はまもなく分家するとか、むっつりしている三兄は顔もよく見なかったし、四番めの兄は江戸詰めで留守、弟はまだ前髪だちで名をやすのじょうといい、背丈のめだって高いからだつきと、まだ子供こどもした日にやけた赤い頬とに特徴があった。彼はその年ごろの者らしく、ほかの兄たちよりもお高の来ることに興味をもっていたようで、横からしげしげと眺めたり、必要もないのにしきりと話しかけたりした。席は広間に設けられた、かけつらねた燭台はまばゆいほど明るく、大和絵を描いた屏風の丹青も浮くばかり美しかった。幾つもの火桶でうっとりするほど暖まった部屋、贅沢といってもよいくらい品数の多い色とりどりの食膳、そしてなんの苦労もなく憂いも悲しみも知らない親子兄弟の、なごやかに団欒をたのしむありさま、―これが自分のほんとうの家なのだ、ここにいる人たちが自分の生みの親であり、血肉をわけた兄弟たちだ、いま坐っているこの席は誰のものでもなく正しく自分の席なのだ。お高はそう思いながら、できるだけすなおな気持でその室の空気に順応しようとした。けれども燭台は明るすぎ、絵屏風はあまりに美しく絢爛で、いかにもおちつきにくく眩しかった、数かずの料理もいずれは高価な材料と念いりな割烹によるものであろうが、お高にはなにやらよそよそしくて、美味という気持はおこらない、そしてその一つ一つが松代の家のことに思い比べられ、しめつけられるように胸が痛んだ。
切り貼りをした障子、古びた襖、茶色になってへりの擦れている畳や、しみ割れのある歪だ柱、すすけた行燈の光にうつしだされるあの狭い、貧しい部屋のありさまがまざまざとみえる、乏しい炭をまるでいたわるように使うあの火桶ひとつでは、冷えのきびしい今宵はどんなにか寒いことだろう、依田の父と松之助は、いま二人きりであの貧しい部屋のつつましい食膳に向かっているじぶんだ。菜の皿はひとつ、汁椀の着くことさえまれで、漬物の鉢だけが変らない色どりである。いま眼の前にあるゆたかな膳部からみればかなしいほど貧しいものだ、然しそのひと皿の菜をどんなに心こめて作るだろう、また父や松之助がどんなによろこんで喰たべて呉れることだろう。頼んで来た石原の妻女はよく気のまわる親切なひとだった、父の好物もあらまし告げて来たが、今宵はどんなしたくが出来たであろうか、父の気にいるものだろうか、もしかして酒をあがりすぎはしないかしらん。……お高のあたまはこういう考えでいっぱいだった、なにを喰べたかも覚えず、どういう会話がとり交わされたかも知らなかった。そして終るとすぐ自分のために用意されたという部屋へひきこもり、なにか話しかけたそうな梶女にも「疲れているから」と断わって、まだ宵のうちから夜具のなかにはいってしまった。
(お高は、残してきた松代の家の父と弟のことで胸がいっぱいだったのです。)
・続きは次回に・・・・。