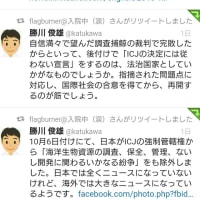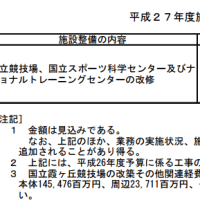日本の大半の学校は、後2日で新年度を迎える。
そんな中、2012年度から新たに採用される中学校教科書のページ数に関して、文部科学省から発表があったのだが・・・。
・中学の教科書分厚く 「脱ゆとり」数学32%・理科45%増(2011年3月30日 日本経済新聞)
・中学教科書検定、平均ページ数25%増(2011年3月30日 YOMIURI ONLINE)
・脱ゆとり、中学教科書24%増 領土問題への言及も増加(2011年3月30日 asahi.com)
・中学教科書検定:ページ数25%増…「ゆとり廃止」反映(2011年3月30日 毎日jp)
・教科書 脱ゆとりでページ増に(2011年3月30日 nhk.or.jp)
ページ数だけで教科書と教育内容の優劣が決まるとは限らないのは自明のことだが、「脱ゆとり」に躍起となった出版社はページ数増という判断に至った模様。
以下、2011年3月30日分 YOMIURI ONLINE『中学教科書検定、平均ページ数25%増』を全文(略
---- 以下引用----
文部科学省は30日、2012年度から使用される中学教科書の検定結果を発表した。
昨年検定の小学教科書に続き、「ゆとり」への反省から学習内容を充実させた新学習指導要領に基づいており、現行(06年度供給)と比べて全体の平均ページ数が25%、数学では33%、理科では45%増えた。
社会では地理、公民の教科書ほぼ全てが竹島問題に触れるなど領土に関する記述が充実した。
理科では「イオン」や「放射線」が復活した。
東日本巨大地震については来春までに加筆されると見られる。
検定合格は9教科計105点。
中学教科書は、指導要領が「ゆとり」のピークだった00年度検定(02年度供給)で小学教科書とともに学習内容を大幅に削減したが、要領を超えた「発展」が登場した04年度検定(06年度同)で増やされ、今回で「ゆとり」から完全に決別した。
全教科でページ数が増え、00年検定時と比べると理科では78%、数学も63%も増えた。
国語では、30年ぶりに常用漢字表が改定されたことを受け、「鬱(うつ)」など追加漢字196字が一覧表で掲載された教科書もあった。
---- 引用以上 ----
中学生の段階で『鬱(うつ)』という感じを書ける子ども達が増えたら、色んな意味で困る人が増えそうだが・・・(汗)
ってのはともかく。
上でリンクを張ってる記事では、2006年度から使ってる教科書とのページ数しか比較してないので、過去に使われてた教科書のページ数についても見る必要がある。
参考までに、文部科学省の中央教育審議会義務教育特別部会(2005年6月18日開催分)の資料に掲載されていたデータを使う。
・義務教育教科書無償給与制度について(2005年6月18日 文部科学省)
上の資料には、小学校で過去に使われてた教科書のページ数なんてのも掲載されてるが・・・。
さしあたっては、2005年6月18日分文部科学省『義務教育教科書無償給与制度について』から、中学校で使われてた教科書の平均ページ数の表を(略

ただし、この表に関しては以下の制限がある。
・ページ数は、表紙と見返しを除いた総ページ数である
・各社全点合計ページ数の平均である
・すべてB5換算している(B5:A5 1:1.2、B5:B5変形版 1:1.04)
・・・という制限を踏まえないと、ページ数増減について思わぬ誤解をしそうだ。
科目と出版社ごとに教科書のサイズが異なるのがいけないんだよ(涙)。
上に紹介した中学教科書平均ページ数の推移を見ると、(2012年度分を含めても)数学のページ数増加が目立つ。
俗に言う「ゆとり世代」以前に中学校の教育を受けた人から見ても、脅威(驚異)のページ数増加だ。
理由としては、数学は他の教科に比べて発展項目や発展問題を盛り込む余地がある(問題を作りやすい)ことか。
後は、以前なら参考書(や教員がダマで使っていた資料のコピー)で扱っていた内容も教科書に盛り込んだ、ってことが想像できるけど・・・。
気になるのは、理科の教科書におけるページ数の増加。
これって、どのくらいのページを実験や観察に割いているんだろうか?
理科は数学と違って、単に紙と鉛筆だけでケリがつく教科じゃないだけに気になる所・・・。
でもさ、ページが増えても、増えた分をどのように教えるかどうかは結局学校側(や教育委員会)の判断だったりするのよね。
裏を返せば、現場で授業をする教員達に余計な負担がかかることを意味するわけで。
無論、授業を受ける生徒達に対しても・・・。
そして、「教科書に盛り込まれた内容を全部教えるべき」なんて言い張る人達も出そうだよな。
現場の負担はそっちのけで。
それはそうと。
教科書の中には、弱視の生徒に対応した拡大教科書(文字を大きくしたり図の配置を変えている)なんてのがあるらしい。
・拡大教科書コストの壁 弱視生徒向け(2010年6月7日 asahi.com)
上の記事では、高校生向けの拡大教科書の普及に関する問題点を説明してるのだが・・・。
拡大教科書を使う生徒達は、普通の教科書より大きい(重い)教科書を持ち歩く可能性が高いのを頭に入れておく必要があるか。
それに加えて、2012年度からは教科書のページ数も増えることを踏まえると、拡大教科書を使う生徒(+家族と教員)にとっては頭の痛い季節になりそうだ。
おまけ:2005年6月18日分中央教育審議会 義務教育特別部会において、苅谷 剛彦氏が行っていた教科書検定制度と教科書無償化に関する発言。
・義務教育特別部会(第19回) 議事録(2005年6月18日 文部科学省)
苅谷氏の発言は、現在の教科書検定制度の在り方について意味深な指摘を・・・。
以下、2005年6月18日分文部科学省『義務教育特別部会(第19回) 議事録』から、刈谷氏の発言部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
【苅谷委員】
私は、先ほどの加藤委員(義務教育中の教科書について無償より貸与を求めていた)と非常に似た考え方です。
これはもちろん基本的には無償制というのがベースになると思いますが、すべての教科について同じ扱いをすべきなのかということについては、議論の余地はあると思います。
それから、検定制度と実際にこの無償制度というものがどういうふうにリンクしているのかということについては、例えば今回の資料の中でも、ページ数はありますが、たしか平成14年度のときにページ数が大幅に減っているときには、相当程度これは無償制度とその検定制度が結びつく形で、多分会社間のページ数の分散が非常に小さかったはずです。
今回、大分発展の内容を入れることになりました。
18年度使用分については、大分会社によるばらつきが増えたと聞いておりますけれども、そういった意味での検定制度とのリンクというのが、行政のそのときどきの考え方で進んでしまうことなのか、それともそこに何らかの歯止めがあるのかどうかというのは、やはり1つチェックポイントとして、まさに国の役割というのは、どこまでがナショナルミニマムなのかという議論の中で、必要だと思います。
その際に、おそらくこれも教科によって、どれぐらいまで厳密にそのことを実現するのかという問題についても、やはり違うと思いますので、先ほども音楽や習字ですか、そういう教科によってどうなのか。
これ、同じ予算額であれば、例えばそこの部分を外したときに、もっと他の充実すべき教科のところでコストをかけることができるのであれば、全教科押しなべて同じような形で考えていくのかどうかというのは、これは有償か無償かという二分法的な考え方ではなくて、多少柔軟な発想というものがあっていいんじゃないかと考えます。
(以下略)
---- 引用以上 ----
教科書検定制度の与える影響ってどのくらいなんだろうか?
そんな中、2012年度から新たに採用される中学校教科書のページ数に関して、文部科学省から発表があったのだが・・・。
・中学の教科書分厚く 「脱ゆとり」数学32%・理科45%増(2011年3月30日 日本経済新聞)
・中学教科書検定、平均ページ数25%増(2011年3月30日 YOMIURI ONLINE)
・脱ゆとり、中学教科書24%増 領土問題への言及も増加(2011年3月30日 asahi.com)
・中学教科書検定:ページ数25%増…「ゆとり廃止」反映(2011年3月30日 毎日jp)
・教科書 脱ゆとりでページ増に(2011年3月30日 nhk.or.jp)
ページ数だけで教科書と教育内容の優劣が決まるとは限らないのは自明のことだが、「脱ゆとり」に躍起となった出版社はページ数増という判断に至った模様。
以下、2011年3月30日分 YOMIURI ONLINE『中学教科書検定、平均ページ数25%増』を全文(略
---- 以下引用----
文部科学省は30日、2012年度から使用される中学教科書の検定結果を発表した。
昨年検定の小学教科書に続き、「ゆとり」への反省から学習内容を充実させた新学習指導要領に基づいており、現行(06年度供給)と比べて全体の平均ページ数が25%、数学では33%、理科では45%増えた。
社会では地理、公民の教科書ほぼ全てが竹島問題に触れるなど領土に関する記述が充実した。
理科では「イオン」や「放射線」が復活した。
東日本巨大地震については来春までに加筆されると見られる。
検定合格は9教科計105点。
中学教科書は、指導要領が「ゆとり」のピークだった00年度検定(02年度供給)で小学教科書とともに学習内容を大幅に削減したが、要領を超えた「発展」が登場した04年度検定(06年度同)で増やされ、今回で「ゆとり」から完全に決別した。
全教科でページ数が増え、00年検定時と比べると理科では78%、数学も63%も増えた。
国語では、30年ぶりに常用漢字表が改定されたことを受け、「鬱(うつ)」など追加漢字196字が一覧表で掲載された教科書もあった。
---- 引用以上 ----
中学生の段階で『鬱(うつ)』という感じを書ける子ども達が増えたら、色んな意味で困る人が増えそうだが・・・(汗)
ってのはともかく。
上でリンクを張ってる記事では、2006年度から使ってる教科書とのページ数しか比較してないので、過去に使われてた教科書のページ数についても見る必要がある。
参考までに、文部科学省の中央教育審議会義務教育特別部会(2005年6月18日開催分)の資料に掲載されていたデータを使う。
・義務教育教科書無償給与制度について(2005年6月18日 文部科学省)
上の資料には、小学校で過去に使われてた教科書のページ数なんてのも掲載されてるが・・・。
さしあたっては、2005年6月18日分文部科学省『義務教育教科書無償給与制度について』から、中学校で使われてた教科書の平均ページ数の表を(略

ただし、この表に関しては以下の制限がある。
・ページ数は、表紙と見返しを除いた総ページ数である
・各社全点合計ページ数の平均である
・すべてB5換算している(B5:A5 1:1.2、B5:B5変形版 1:1.04)
・・・という制限を踏まえないと、ページ数増減について思わぬ誤解をしそうだ。
科目と出版社ごとに教科書のサイズが異なるのがいけないんだよ(涙)。
上に紹介した中学教科書平均ページ数の推移を見ると、(2012年度分を含めても)数学のページ数増加が目立つ。
俗に言う「ゆとり世代」以前に中学校の教育を受けた人から見ても、脅威(驚異)のページ数増加だ。
理由としては、数学は他の教科に比べて発展項目や発展問題を盛り込む余地がある(問題を作りやすい)ことか。
後は、以前なら参考書(や教員がダマで使っていた資料のコピー)で扱っていた内容も教科書に盛り込んだ、ってことが想像できるけど・・・。
気になるのは、理科の教科書におけるページ数の増加。
これって、どのくらいのページを実験や観察に割いているんだろうか?
理科は数学と違って、単に紙と鉛筆だけでケリがつく教科じゃないだけに気になる所・・・。
でもさ、ページが増えても、増えた分をどのように教えるかどうかは結局学校側(や教育委員会)の判断だったりするのよね。
裏を返せば、現場で授業をする教員達に余計な負担がかかることを意味するわけで。
無論、授業を受ける生徒達に対しても・・・。
そして、「教科書に盛り込まれた内容を全部教えるべき」なんて言い張る人達も出そうだよな。
現場の負担はそっちのけで。
それはそうと。
教科書の中には、弱視の生徒に対応した拡大教科書(文字を大きくしたり図の配置を変えている)なんてのがあるらしい。
・拡大教科書コストの壁 弱視生徒向け(2010年6月7日 asahi.com)
上の記事では、高校生向けの拡大教科書の普及に関する問題点を説明してるのだが・・・。
拡大教科書を使う生徒達は、普通の教科書より大きい(重い)教科書を持ち歩く可能性が高いのを頭に入れておく必要があるか。
それに加えて、2012年度からは教科書のページ数も増えることを踏まえると、拡大教科書を使う生徒(+家族と教員)にとっては頭の痛い季節になりそうだ。
おまけ:2005年6月18日分中央教育審議会 義務教育特別部会において、苅谷 剛彦氏が行っていた教科書検定制度と教科書無償化に関する発言。
・義務教育特別部会(第19回) 議事録(2005年6月18日 文部科学省)
苅谷氏の発言は、現在の教科書検定制度の在り方について意味深な指摘を・・・。
以下、2005年6月18日分文部科学省『義務教育特別部会(第19回) 議事録』から、刈谷氏の発言部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
【苅谷委員】
私は、先ほどの加藤委員(義務教育中の教科書について無償より貸与を求めていた)と非常に似た考え方です。
これはもちろん基本的には無償制というのがベースになると思いますが、すべての教科について同じ扱いをすべきなのかということについては、議論の余地はあると思います。
それから、検定制度と実際にこの無償制度というものがどういうふうにリンクしているのかということについては、例えば今回の資料の中でも、ページ数はありますが、たしか平成14年度のときにページ数が大幅に減っているときには、相当程度これは無償制度とその検定制度が結びつく形で、多分会社間のページ数の分散が非常に小さかったはずです。
今回、大分発展の内容を入れることになりました。
18年度使用分については、大分会社によるばらつきが増えたと聞いておりますけれども、そういった意味での検定制度とのリンクというのが、行政のそのときどきの考え方で進んでしまうことなのか、それともそこに何らかの歯止めがあるのかどうかというのは、やはり1つチェックポイントとして、まさに国の役割というのは、どこまでがナショナルミニマムなのかという議論の中で、必要だと思います。
その際に、おそらくこれも教科によって、どれぐらいまで厳密にそのことを実現するのかという問題についても、やはり違うと思いますので、先ほども音楽や習字ですか、そういう教科によってどうなのか。
これ、同じ予算額であれば、例えばそこの部分を外したときに、もっと他の充実すべき教科のところでコストをかけることができるのであれば、全教科押しなべて同じような形で考えていくのかどうかというのは、これは有償か無償かという二分法的な考え方ではなくて、多少柔軟な発想というものがあっていいんじゃないかと考えます。
(以下略)
---- 引用以上 ----
教科書検定制度の与える影響ってどのくらいなんだろうか?