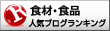◎オクラOkra おくら
アオイ科、ナイル川支流域と言われているアフリカ原産です。 エジプトでは紀元前13世紀ごろの栽培記録が残っており紀元前の古代エジプトで栽培し食べられていたようです。ガーナ共和国で使われているトウィ語「nkuruma(ンクラマ)に由来し英語名Okura(オクラ)から日本でオクラと呼でいます。オクラはアフリカからアジア熱帯地域へ伝播し、重要な野菜として栽培していました。やが17~18世紀にはヨーロッパを経て、新大陸のアメリカへ19世紀頃に伝播しています。明治初期に中近東・中国を経て日本 に伝わっています。ネリと呼んでいたトロロアオイ(中国原産:食用花)の近縁種であったことから別名「花オクラ」とも呼ばれ、オクラに似た花と実をつけます。トロロアオイは、同じアオイ科の植物で、和紙の原料として知られネリは、根を叩いて、水につけておくとできる粘液のようです。
日本では、オクラは主に観賞用で、当初は特有の粘りと青臭さのため、普及しませんでしたがその後の日本へは、品種改良により第二次大戦後にアメリカから持ち込まれ普及し始めています。その当時オクラは、アメリカネリや陸蓮根(おかれんこん)とも呼ばれたりしています。空に向かって育ちます。アフリカでは乾燥オクラをスープのとろみづけに使うなど多くの国で食べられています。
家庭の食卓にのぼるようになったのはアメリカで品種改良したものが日本に伝わり、1960年代から1970年ごろには高度経済成長とともに食生活も大きく変化し、オクラの出荷量は急増の一途で激増していました。
高知県では1971年ごろに、水田転換作物として暖地の特性を生かしオクラを導入し有利な栽培ができることから生産コストが比較的低いトンネル早熟栽培をメインに、5月ごろからの早出し出荷をしています。
オクラは、耐暑性ですが乾燥と低温寒さには弱く日本では四国、九州で主に栽培しています。ハウス栽培、輸入物もあり近年では、ほぼ年中出まわっています。草丈は1.5mほどで成育が早く1日だけの早朝に淡い黄色の花をつけその後若い柔らかい7~8cmの莢(さや)になったものを利用し7~9月を旬としています。主に鮮やかな緑色、切り口がが五角形で、粘りのあるのを特徴としています。
種類として大きく分類すると五角オクラ、丸オクラ、白オクラ、赤オクラ、ミニオクラがあります。
それぞれに特色があります。
◇角オクラは定番で栽培しやすく、葉が小さく、草丈が低く倒れにくくいので、狭い場所でも栽培可能としています。角オクラは、スーパーなどでよく見かけるオクラで断面が星形をしているものが多いですが、六角形から八角形の角オクラもあります。
食べ頃なのは7〜10㎝ほどの長さのもので、それ以上に大ききくなると、実が硬くなってしまいます。初心者でも栽培しやすいほど強くて丈夫であり、収穫の時期になるとたくさんの実を収穫できるでしょう。茹でることで水溶性食物繊維ペクチンの流出しますので固い時は、短時間として粘り気を生かした煮物やサラダ、和え物、揚げ物としています。
◇丸オクラは、断面が丸く角莢オクラに比べ肉厚で柔らかく甘みが強く生食に向いているといいます。多少採り遅れても硬くなりにくいとしています。別名「島オクラ」とも呼ばれ、丸オクラが生まれたのは伊豆諸島にある八丈島で、現在でも多くが八丈島で、丸オクラがメインで栽培しています。
◇赤オクラは鮮やかな色が特徴で、角オクラが10㎝ほどまでが食べごろなのに対し、赤(アントシアニン色素)オクラの場合は20㎝くらいまで大きくなっても柔らかいため、大きな実でも食べやすいのが特徴です。茹でると脱色して緑色になるので色を生かしてスポンジで産毛をやさしくこすり取り刻んで生食・揚げ物がお勧めです。
◇白オクラは薄めの緑色で柔らかく粘り気が強いです。 約50年前に海外から日本にやってきており、歴史がかなり浅く、主に山口県長門市で栽培地域も少ないです。約70年前から栽培する伝統野菜として一説によると海外から持ち帰られたものと伝えられています。白オクラは別名「サラダオクラ」とも呼ばれて、加熱せず、生で多少大きくなっても柔らかくアクが少なくサラダにして食べられます。加熱しないことで、白オクラに含まれている栄養を逃すことなく摂取でき生食に適しています。
◇ミニオクラは一般(角オクラが多い)の幼果の2~4cmの長さで収穫するので小さく柔らかく、ガクまで食べられるようです。主産地は高知県と香川県で通常は業務用として飲食店に添え物、サラダ用に販売していることが多いようです。
主に多くが刻んで生食軽く湯通しして醤油合えに使われますが他にも浅漬け、糠みそ漬け、汁の実、揚げ物、シチュー、炒め物などもよいでしょう。
オクラの栄養成分として
生100g中でエネルギー26kcal、水分90.2g、タンパク質2.1g、脂質0.2g、炭水化物6.6g、灰分0.9g、ナトリウム4mg、カリウム280mg、カルシウム92mg、マグネシウム51mg、リン58mg、鉄0.5mg、亜鉛0.6mg、銅0.13mg、マンガン0.48mg、ビタミンA効力:44μg、ビタミンD:(0)μg、ビタミンE:1.2mg、ビタミンK:66μg、ビタミンB1:0.09mg、ビタミンB2:0.09mg、ナイアシン1.2mg、ビタミンB6:0.10mg、ビタミンB12:(0)μg、葉酸110μg、パントテン酸0.42mg、ビオチン6.6μg、ビタミンC11mg 食物繊維5.0g(水溶性1.4g 不溶性3.6g)を含みます。廃棄率15%です。
茹で100g中でエネルギー25kcal、水分89.4g、タンパク質2.1g、脂質0.1g、炭水化物7.6g、灰分0.8g、ナトリウム4mg、カリウム280mg、カルシウム90mg、マグネシウム51mg、リン56mg、鉄0.5mg、亜鉛0.5mg、銅0.11mg、マンガン0.48mg、ビタミンA効力:44μg、ビタミンD:(0)μg、ビタミンE:1.2mg、ビタミンK:66μg、ビタミンB1:0.09mg、ビタミンB2:0.09mg、ナイアシン1.2mg、ビタミンB6:0.08mg、ビタミンB12:(0)μg、葉酸110μg、パントテン酸0.42mg、ビオチン6.5μg、ビタミンC7mg 食物繊維5.2g(水溶性1.6g 不溶性3.6g)を含みます。廃棄率15%です。
未熟のさやに特記すべき成分としてペクチン、アラバンAraban、ガラクタンGalactanの粘質物(便秘予防)、食物繊維、ビタミンンA:110μg.、C:11mg/100g中を含む。
水溶性食物繊維の「ペクチン」が含まれ、善玉菌のエサとなって腸内環境を整えます。 便秘や下痢などの予防にも効果的です。 また、糖質の吸収を緩やかにして血糖値の急上昇を抑えたり、血清コレステロール値を低下させたりもしてくれます。
特に夏野菜のオクラを七夕に食べると縁起が良いのだとか、 その理由はオクラの切り口が星型で、それを食べることで願いを天に届けるという言い伝えからです。 また、オクラは夏バテ防止の食材としても知られており、これからやってくる本格的な夏を乗り切るという願いも込められています。
宮古島産のオクラは粘りが強いのが特徴で、地元ではオクラ特有の「ネバネバ」を地元の方言で「ムツムツ」と言うことから、JAおきなわが、6月6日を数字の語呂あわせで「オクラの日」として定めています。
完熟の種子は以前炒って珈琲の代用にもして利尿作用があるといわれます。
オクラの一度に食べられる量は、せいぜい10~20g程度ですが、夏野菜として他の野菜と組み合わせて淡色野菜は、一日230g、 緑黄色野菜は120g程度の摂取によって不足がちなカリウム(K)の摂取によく高血圧予防、疲労回復、血中コレステロール低下作用、ダイエット、整腸作用があります。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。