http://news.goo.ne.jp/article/tsr_net/business/tsr_net-5642.html へのリンク
TSR速報:2014年10月1日(水)16:00
2014年9月の「中小企業金融円滑化法」に基づく貸付条件変更利用後の倒産は、15件(速報値:9月30日現在)にとどまった。金融機関がリスケ要請に弾力的に応じるなど実質的な金融支援や、公共工事など景気対策の効果により全体の倒産が抑制され、速報値では8カ月連続で前年同月を下回っている。

2014年9月
負債総額は、158億700万円(前年同月比71.5%減)で、2カ月連続で100億円を上回った。負債額別では、10億円以上の大型倒産が6件(前年同月10件)発生した。
産業別では、製造業が6件(前年同月15件)で最も多かった。次に、卸売業が5件(同9件)、建設業2件の順だった。
従業員数別では、最多が10人以上20人未満の5件(前年同月9件)だった。
2014年1-9月
負債額別 1億円以上5億円未満が最多
2014年1-9月の累計192件の負債額別では、最多が1億円以上5億円未満の90件(前年同期比48.5%減、構成比46.8%)だった。次いで、5千万円以上1億円未満が28件(同48.1%減、同14.5%)、1千万円以上5千万円未満が28件(同28.2%減、同14.5%)だった。
原因別 販売不振が最多
2014年1-9月の原因別では、最多が販売不振の104件(前年同期比47.4%減、前年同期198件)だった。次いで、既往のシワ寄せ(赤字累積)が46件(同41.7%減、同79件)と続く。
形態別 破産が全体の約7割
2014年1-9月の形態別では、消滅型の破産が128件(前年同期比41.5%減、前年同期219件)で最も多く、全体の約7割(構成比66.6%)を占めた。一方、再建型の民事再生法は10件(構成比5.2%、前年同期23件)にとどまった。金融円滑化法に基づく貸付条件変更を利用した企業の中では、業績不振から事業継続を断念するケースが依然として多い。
従業員数別 10人未満が約6割
2014年1-9月の従業員数別では、5人未満が72件(前年同期比35.1%減、前年同期111件)で最も多く、5人以上10人未満も43件(同49.4%減、同85件)だった。この結果、従業員10人未満は115件(構成比59.8%、前年同期196件)で、小規模企業が全体の約6割を占めた。
産業別 製造業が約3割を占める
2014年1-9月の産業別では、製造業が57件(前年同期比44.6%減、前年同期103件)で最多、全体の約3割(構成比29.6%)を占めた。次いで、建設業31件(前年同期比58.6%減、前年同期75件)、卸売業32件(同50.0%減、同64件)、サービス業他25件(同45.6%減、同46件)と続く。












 8月の全国消費者物価指数は、緩やかな物価上昇が続いた。ただ、働き手の給与が物価上昇に見合うだけ増えなければ、消費を冷え込ませ景気を下押ししかねない。国税庁の調査では、平成25年の民間の年間給与は1・4%増にとどまり、今年8月の物価指数上昇率を下回っている。景気の好循環を維持するうえで、企業の賃上げの動きが一段と重みを増している。
8月の全国消費者物価指数は、緩やかな物価上昇が続いた。ただ、働き手の給与が物価上昇に見合うだけ増えなければ、消費を冷え込ませ景気を下押ししかねない。国税庁の調査では、平成25年の民間の年間給与は1・4%増にとどまり、今年8月の物価指数上昇率を下回っている。景気の好循環を維持するうえで、企業の賃上げの動きが一段と重みを増している。 日本文化を海外に売り込む官民ファンドの海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)は25日、第1弾の投資案件の内容を発表した。マレーシアと中国にある日系の商業施設をクールジャパンの発信拠点とする事業など4案件に、最大で計約140億円を投資する。安倍晋三政権が成長戦略の柱と位置づけるクールジャパンの海外展開を加速する狙いで、アニメなどのポップカルチャーだけでなく、日本食やファッションなど幅広い分野の海外での産業化を目指す。
日本文化を海外に売り込む官民ファンドの海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構)は25日、第1弾の投資案件の内容を発表した。マレーシアと中国にある日系の商業施設をクールジャパンの発信拠点とする事業など4案件に、最大で計約140億円を投資する。安倍晋三政権が成長戦略の柱と位置づけるクールジャパンの海外展開を加速する狙いで、アニメなどのポップカルチャーだけでなく、日本食やファッションなど幅広い分野の海外での産業化を目指す。
 「何とか形にできないか」
「何とか形にできないか」 自民党税制調査会(野田毅会長)は24日、内閣改造後の新体制で初の非公式幹部会合を開き、平成27年度税制改正に向けた課題や進め方を確認した。年末に向けては法人税の実効税率の下げ幅や代替財源の捻出策のほか、消費税率10%時の軽減税率の導入の可否など重要課題が山積している。自民党税調では、例年より2カ月前倒しで協議を進め、対応を急ぐ。(今井裕治)
自民党税制調査会(野田毅会長)は24日、内閣改造後の新体制で初の非公式幹部会合を開き、平成27年度税制改正に向けた課題や進め方を確認した。年末に向けては法人税の実効税率の下げ幅や代替財源の捻出策のほか、消費税率10%時の軽減税率の導入の可否など重要課題が山積している。自民党税調では、例年より2カ月前倒しで協議を進め、対応を急ぐ。(今井裕治) 2027年にリニア中央新幹線の開業を目指すJR東海は22日、山梨県の山梨リニア実験線(総延長42.8キロ)で報道陣向け試乗会を行った。最新車両の時速500キロでの走行の様子に加え、11~12月に行うリニアの一般向け体験乗車に向けて新設した発券機や改札機などの設備も公開した。
2027年にリニア中央新幹線の開業を目指すJR東海は22日、山梨県の山梨リニア実験線(総延長42.8キロ)で報道陣向け試乗会を行った。最新車両の時速500キロでの走行の様子に加え、11~12月に行うリニアの一般向け体験乗車に向けて新設した発券機や改札機などの設備も公開した。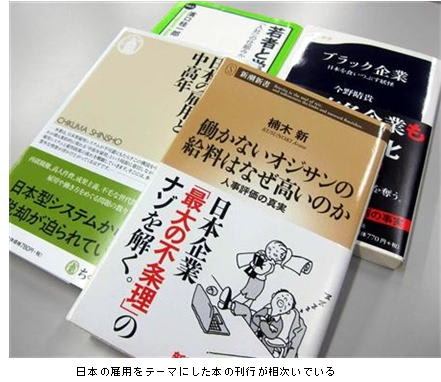 「働かないオジサン」はなぜ生まれるのか-。長時間労働、正社員と非正社員の格差、ブラック企業などさまざまな問題が山積し、中高年が既得権層として指弾されてきた日本の雇用をめぐる論壇。だが近年は、根本原因がかつて称賛された「日本型雇用」の機能不全にあるとするシステム論的な議論が目立つようになっている。(磨井慎吾)
「働かないオジサン」はなぜ生まれるのか-。長時間労働、正社員と非正社員の格差、ブラック企業などさまざまな問題が山積し、中高年が既得権層として指弾されてきた日本の雇用をめぐる論壇。だが近年は、根本原因がかつて称賛された「日本型雇用」の機能不全にあるとするシステム論的な議論が目立つようになっている。(磨井慎吾)